先日ビオトープ作りを行った場所で、
今度は石窯作りのワークショップ。
いい天気に恵まれ、
若くてキレイなお母さんたちを中心に、
今日もたくさんの方にお越しいただき、
楽しく作業することができました。
石窯は当初、
多くの石窯がそうであるように、
耐火煉瓦で作ろう
という話もありましたが、
隣接する屋敷の
大谷石の塀を
バラしてもよいとのことで、
材料となる石は
ほぼ全て現地調達で
まかなうことにしました。
ということでまず、
塀の石をばらす作業。
石塀に石を積む際、
石同士をモルタルで
接着しているわけですが、
それをノミ等で
剥がす作業が必要となり、
これが思いのほか女性に人気。
うまくいけば、
サクッと剥がれる感触が
気持ちよかったようです。

男性陣は、
主に運搬作業。
大谷石は石としては
比重が軽いとはいえ、
長さが90cmあると
さすがにずっしりきます。

こうして石窯に必要な
石を調達。
使う前に、軽く雑巾で
拭きました。

石が用意できたら、
設計図に基づき、
石を耐火モルタルで
積んでいきます。
基本的に、
約90cm×30cm×15cmという
石の大きさを生かして
積んでいったのですが、
それでも時には
ハンパな大きさも必要なので、
その場合はサンダーで切断。
切る作業、
モルタルを仕込む作業、
積む作業、
参加者それぞれが
役割を見つけて、
順調に積み上がっていきました。

夕方、耐火モルタルが品切れ。
途中ですが、
4時を回った時間なので、
今日の作業はここでおしまい。

しかし、
火を焚く炉はできたので、
ガマンしきれず、試しの火入れ。
ちょうど夕方、
肌寒くなってきたので、
暖が採れてよかったです。
ちなみにこの石窯は、
追焚きができる二層構造を
予定しています。
二層目に横たわった石の部分が、
調理室となります。
なのでけっこう迫力のある
石の造形物となる予定。
第二回の石窯作りワークショップは、
少し後になってやろうかという
話になっていましたが、
早く完成型が見たいので、
近々行うことになりそうです。

今度は石窯作りのワークショップ。
いい天気に恵まれ、
若くてキレイなお母さんたちを中心に、
今日もたくさんの方にお越しいただき、
楽しく作業することができました。
石窯は当初、
多くの石窯がそうであるように、
耐火煉瓦で作ろう
という話もありましたが、
隣接する屋敷の
大谷石の塀を
バラしてもよいとのことで、
材料となる石は
ほぼ全て現地調達で
まかなうことにしました。
ということでまず、
塀の石をばらす作業。
石塀に石を積む際、
石同士をモルタルで
接着しているわけですが、
それをノミ等で
剥がす作業が必要となり、
これが思いのほか女性に人気。
うまくいけば、
サクッと剥がれる感触が
気持ちよかったようです。

男性陣は、
主に運搬作業。
大谷石は石としては
比重が軽いとはいえ、
長さが90cmあると
さすがにずっしりきます。

こうして石窯に必要な
石を調達。
使う前に、軽く雑巾で
拭きました。

石が用意できたら、
設計図に基づき、
石を耐火モルタルで
積んでいきます。
基本的に、
約90cm×30cm×15cmという
石の大きさを生かして
積んでいったのですが、
それでも時には
ハンパな大きさも必要なので、
その場合はサンダーで切断。
切る作業、
モルタルを仕込む作業、
積む作業、
参加者それぞれが
役割を見つけて、
順調に積み上がっていきました。

夕方、耐火モルタルが品切れ。
途中ですが、
4時を回った時間なので、
今日の作業はここでおしまい。

しかし、
火を焚く炉はできたので、
ガマンしきれず、試しの火入れ。
ちょうど夕方、
肌寒くなってきたので、
暖が採れてよかったです。
ちなみにこの石窯は、
追焚きができる二層構造を
予定しています。
二層目に横たわった石の部分が、
調理室となります。
なのでけっこう迫力のある
石の造形物となる予定。
第二回の石窯作りワークショップは、
少し後になってやろうかという
話になっていましたが、
早く完成型が見たいので、
近々行うことになりそうです。











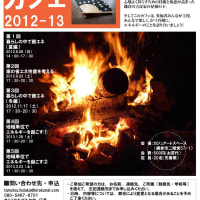









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます