極私的映画論ー観る立場よりー
「メルヘンの闇」
地獄で仏の」菅原文太!
映画「仁義なき戦い」より、
笠原和夫(1927年~2002年享年76歳)の本を読んだ。めちゃ面白かった。ちなみに、菅原文太、深作欣二も既に亡くなっているのだが…。他にも多くの亡くってしまった役者さん達も多くいる。川谷拓三、室田日出男など。 笠原和夫は東映のシナリオ・ライターで最後まで東映という会社、撮影所の座付き?のライターであり、その作品は90本弱になる。1963年頃からヤクザ映画のシナリオを書き始め、1975年の「県警対組織暴力」翌年の1976年「ヤクザの墓場・くちなしの花」でヤクザ映画のシナリオは辞めてしまう。 (なみに1975年製作の「仁義の墓場」深作欣二監督シナリオは笠原ではないのだが…!)これは中々シュールに近く? ただ単にわけが分からないのだが? ラスト近く自殺した女房の骨を噛み砕くシーインは妙に記憶に残っているのだが。余談!
1973年代に「仁義なき戦い」シリーズを深作欣二監督・菅原文太主演で、「~広島死闘編」「~代理戦争」1974年に「~頂上作戦」の4本を書き、彼のヤクザ映画路線は終わる。その後前述の2本はあるのだが…!
笠原和夫のヤクザ映画の脚本は、任侠シリーズ(任侠の美学)と、いわゆるヤクザシリーズ(暴力・破壊の美学)に、分けることが出来るのか? 彼のいわゆるヤクザ映画の初期の作品は、任侠シリーズ系の語りが多い。後期はむしろヤクザ系の語りが多くなる。というか、後期は「仁義なき戦い」シリーズしかないのだが… むしろ任侠系シリーズの方が長く、多くの作品を手がけている。
任侠系シリーズの美学は、仁義を通す。簡単にいえば、古くからある義理人情に厚い親分の縄張りを、新興のえげつない親分が、縄張りを広げる為に、その古くからあるいい親分に横やりを入れ、喧嘩を仕掛け勢力拡大をねらう。それがストーリーの骨組みである。 その古くからのいい親分(当然そこにはその組にお世話になっている一匹狼の侠客がいる)が、新興の親分(組)のえげつない横やりに、耐えるだけ耐えて、堪忍袋の緒が切れ、最後に一匹狼の侠客がその新興の組に殴り込み横やりもなくなり、それまでの極道社会の秩序が回復する。
ただその秩序回復にはある条件が必要になる。
それは死者の介在である。それぞれの組が生き残る為には、お互いに死者を介在させなければ、秩序の回復,安定にまでは持ち込めない。殺し、殺される者,いずれ死者が産出されなければ、秩序は保てない。「~の為に身を捨て」その世界の秩序の安定や回復に向う、そこにヤクザ映画の美学がある。義理のある親分や愛しい女の為に、殴り込みそして死者になる。またその背後で多くの名も無き死者の群れも誕生する。それが任侠系シリーズのヤクザ映画である。「大義の為に身を捨てる」これは高倉健扮する任侠シリーズのパターンであった。それはそれで筋の通った美しさがあった。
笠原和夫・脚本、山下耕作・監督の「博打打ち 総長賭博」ぐらいから、その様な美学が変化してくる。大義があるから,ある程度耐える。が、だんだん耐える意味がなくなって、個々の想いや欲望に即する形で暴力が露出してくる、シチュエーションである。 それぞれの組、あるいは組と組の,また組と組員の大義名分より、個人的な義あるいは想いが優先され,それが更なる暴力を露出させることになる。 これらは、笠原和夫の脚本では、暴力・破壊の美学ということにもなるのか?
これらが顕著に、露骨に表現されてくるのが、何を隠そう「仁義なき戦い」シリーズである。
笠原和夫も深作欣二も菅原文太も川谷拓三もみんな死者に成った。今,文太や笠原や深作という死者を語ることは、映画を語ることと同義になる。彼らは映画を上映する暗闇で永遠に生き続けている。と云えば大げさか?
今回、彼ら死者を偲んで「仁義なき戦い」「仁義なき戦い・広島死闘編」「仁義なき戦い・代理戦争」「仁義なき戦い・頂上作戦」「仁義なき戦い・完結編」の5本を続けてみた。(「・完結編」の脚本はなぜか?笠原和夫から高田宏治に変わる。) 大筋、全体のシチュエーションは先に述べた通りである。が、今回全編を通して見て、気がついたのであるが、何と!この「仁義なき戦い」シリーズ5編中4編のラストシーンが葬儀、火葬場、墓場のシチュエーションなのである。
これはホント今まで全然気がつかなかった。
菅原文太=広能昌三(広能組組長)が訪ひ、焼香をするシーンがある。これは「仁義なき戦い」の第一部で、あまりにも有名になったラストシーンである。拳銃片手に葬式の場に殴り込み、生花や焼香台に拳銃をぶっ放し、喪主である山守組組長に拳銃を向ける。決してこのシーインでは殺しはない。「仁義なき戦い」では珍しく抑えめの演技で、拳銃を了い去って行こうとする。
この菅原文太は鳥肌もので、かっこいい。
二部、三部、完結編でもそれぞれラストシーンは葬式である。その様なシーンをまとめてみた。
第三部「・代理戦争」の火葬場のシーンを観て、死者に成った現実の若者の母親から、これまた現実の美能幸三(元美能組組長)に、「これで息子も成仏できる」「おかげで息子も浮かばれました」と電話があった。と美能幸三から電話があったと 後日談として、笠原和夫が語っている。
いずれ、「仁義なき戦い」シリーズの5作品は、葬式の多い映画である。しかも映画の落とし所でもあるラストシーンにである。
身体でいのちのやり取りをする場に、これまたギリギリでやり場のないいのちが流れ着き、その場で修羅を展開する。挙げ句に多くの死者が産出される。その様な修羅場を潜り抜け,生き残ってきたのが、映画「仁義なき戦い」シリーズの菅原文太扮する、広能組組長の広能昌三である。
このシリーズの菅原文太はヤクザの親分にも関わらず、メチャクチャに優し人に見えてくる。その優しさとは、一般的社会的人間的常識的な枠組みの見せかけの優しさではなく、その様な枠組みでは中々見えてこない、人間存在の闇の側面(地獄・餓鬼・畜生・修羅)を図らずも生きてきた者のみが知りうる優しさである。その優しさは、菅原文太扮する主人公の、何ともいえない葬儀の場面の表情に、よく現れている。
映画館の暗闇は,色々なことを教えてくれる、闇でもある。闇の中で闇の声を聞く。それは、生者が死者の声を聞くことと同義なのかもしれない。死者とは絶対的他者でもある。その様な他者=死者の声を聞くことを通して、生者同士での自から他、他から自へ、あえていえば、他者に対する配慮が必要なのではなかろうか?
映画「仁義なき戦い」のシリーズは、人間臭い人間愛に溢れた映画でもあった。


















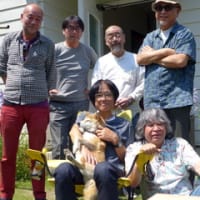








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます