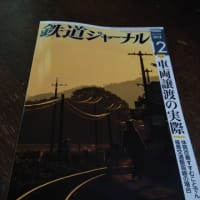さてさて餃子を食べて一休みした後は暑いですが、引続き古跡めぐりを続けます。

「坑尾村公厠」なる公衆トイレ
中華風のデザインでなんとも立派な建物です。
日本の公園とかにある公衆トイレはあまり綺麗じゃないので出来るだけ使いたくない。
ようなイメージがありますが、香港のは家一軒分ぐらいあるんじゃないかというぐらい敷地を使っていて立派。
一角に詰所が作ってあって管理人が常駐していて、意外に綺麗に清掃されていたりします。
かって香港の住宅環境が劣悪で住居にまともにトイレが無かったような時代の影響。
だと書物で読んだことがありますが・・。
ただショッピングモールなどは日本ほどトイレがないし、地下鉄(旧KCR線ではないMTR線)駅は基本トイレが無いので、全体的なトイレ事情としてはちょっと微妙な面も・・・。

次は覲廷書室と併設されている清暑軒
覲廷書室は鄧族という当地の有力者が立てた、科挙を目指す子弟の為の塾のようなもの。
科挙制度が廃止された後は地域の若者の学習施設のように使われていたそうです。
一番最初の聚星樓は合格祈願。こちらは学習塾と子弟の科挙合格対策には力を入れていたようで・・。
科挙というのは古代~近世清朝末期までの中国での公務員試験のようなもので、
合格すれば地位と栄誉があるものの、難易度が高いかなり熾烈なものだったそう。
当時は辺境の田舎だったと思うこの地でも、科挙合格に力を入れていたよう。
また隣りの清暑軒は宿泊施設や客人を迎えるための場所だったそうです。
ただ覲廷書室・清暑軒どちらも1870年に建てられたそうで、既に香港島や九龍半島がイギリス領になった後。
当時の人たちは少し先の地がイギリス領になったことをどう思っていたのか。
前出「観光コースではない香港」書によれば、
1898年に新界地区が英国の租借地となった際、反対運動が起こり英国軍との間で戦闘が起きるも数日で鎮圧。またその反対運動の中心となっていたのが当地の有力者鄧氏だったそうです。
その後イギリス領となった土地は国際都市への道を歩み始め、中華人民共和国建国の頃には大陸からの難民が多数香港に越境。イギリス領となった土地とそうでないところで明暗を分けることになるわけですが、当時の人たちはその後の香港を知ったとしてどう思うのでしょうか。

豪華な装飾の祠のようなものが・・

これまた時代物の中国映画とかドラマに出てきそうな雰囲気?

調理場のようなものも
さて内部を見て回って最奥部の部屋まで来て出口に戻ろうかと思ったら・・・・出口が分からない

どっから入ってきたんだっけ?と出口を探すも・・・唯一の通路の廊下の途中には鉄格子がしてあって南京錠のような鍵がかかっています。
「あれ??さっきはここから入って来たわけじゃないよね・・・ヽ(~~~ )ノ ハテ?」
と思うも出口が見つかな~い。
「ムムッ。もしや閉じ込められたのか
 」
」いくら「生きててもろくなことが無いなぁ」
と言ってもここで閉じ込められて猛暑の中、干からびて死ぬのは恥ずかしすぎるだろう・・・

日本語でもいいから大きな声でも出せば助けが来るかも?
と焦っていたら、なにやら呼び声が・・

内容は分からないけど最後に「嗎」が付いているから疑問文か??
と思っていたら、入口にいた係りのおばちゃんがやってきました。
どうも昼休憩で一時閉鎖するようで見回りに来た様子。
「あらあら言葉分からないの?」のように聞かれたので「分からないです」と言ったら身振りで教えてくれました。
おばちゃんに付いて戻ったら、通路の廊下の横の大きな丸い飾り窓のようなところから、
窓を跨いで隣の部屋に出て出口方向に。「そういえば、来る時はここから来たな・・・」と

なんにしても中華文化4000年の歴史は恐るべしですな

偶然とはいえ、昼休憩(13時~14時)直前に来て入ってよかったです。

ニュータウン開発前の新界地区の光景が偲ばれるような裏通り沿いを歩きます。
この通りは狭いながらバス通りになっているようで、途中にバス停も・・・
写真は香港の郊外で時々見かけるイギリス風?の横断歩道
白黒のポールの上の球にはランプが入っていて点滅しています。

駐停車禁止区域の標識
香港では各所に駐停車禁止区域が設定されていて、区域内ではタクシーやミニバス(自由乗降バス)の乗降も禁止されています。歩道と車道の間に柵があって「乗降させないゾ」という強い意志を感じるような。
ミニバスへの嫌がらせで駐停車禁止区域が増設されている。という話も聞きますが・・・。
ガイドブックの記述で「タクシーは駐停車禁止区域での乗降は出来ない。日本のように交差点などでさっと乗降するのも禁止されている」というのを読んだ覚えが。
webのサイト上で「日本では駐停車禁止区域の取締りが曖昧なのは自動車産業が強い影響か」
と評している文章を読んだことがありますが、その視点は気が付かなかった・・。
日本の道交法は速度制限とか信号が無い横断歩道の一時停止とか、結構ザル法になっている部分がありますが、自動車産業を守る為に敢えて車に甘くして、歩行者保護や事故防止対策をPRするために適宜取り締まっている。という考え方もあるなと。
そう考えると世論の趨勢があるとはいえ、飲酒運転厳罰化とか流れが変っているのかも?と思う面も。

これはMTR(旧KCR)バス
LRT路線の補助的な役割の路線の他に鉄道駅との連絡路線として走っているバス
バス自体はボルボのB10Mという車のよう。
ナンバーの「GM4729」から検索したら
このページ(外部リンク)
がヒットしてわかりました。香港のバス趣味界はやはり凄い。
香港では鉄道よりバスファンが多くてかなりの趣味人口がいて大規模な趣味団体もあるそうです。
さて途中でこの裏通りと別れて山道を登っていきます。
次の見学場所の「屏山鄧族文物館」という資料館に向うわけですが、なんと山の上

暑い中ヒィヒィ言いながら坂道を登ります

ようやく到着
1899年に建てられた警察署の建物を資料館として再整備したそうです。
それにしても街中ではなくこんな山の上に警察署を建てたのが不思議??
消防署の望楼じゃないですが街全体を見渡せるように??

まだこの辺りが農村だった頃の農具や祭礼の道具や様子などが展示されています。
イギリス領になる前の香港の様子が偲ばれるといいますか・・・その頃は単なる農村に過ぎなかったよう。
また日本統治時代の史料もあり、当時の軍票や住民に発行された身分証のようなものも展示されています。
館内は冷房が効いていて嬉しいですね。

資料館の敷地からは元朗方面の高層住宅とその手前の郊外な風景がみれます。

高層住宅を背景に走り抜ける西鐵線の電車
西鐵線は中心部とこの新界西北部を結ぶ路線で130キロ運転を行っていて「香港のつくばエクスプレス」と言いたくなるような雰囲気です。
私はつくばエクスプレスの郊外区間(北千住より先)に乗るよりも前に、こっちの西鐵線に先に乗ったのでつくばエクスプレスの郊外区間に初めて乗った際「香港の西鐵のような路線だ
 」と思ったものです。
」と思ったものです。ここまで概ね一通りの屏山文物経の史跡を見て回りました。
途中には適宜案内看板が設置されていたのと、最初にもらったパンフレットの地図を見ながらだったので特に迷うことなく順調に見て回れました。また最後の資料館も含めて入場料は無料。
ちなみに何処も私以外の見学者は見かないぐらいに空いていました。
LRTの駅だと天水圍~坑尾村~屏山の駅の辺りの裏通り沿い
この経路のLRT路線は99年の旅行の際に乗っている他、前回06年の旅行の際は何回も乗った区間ですが、ちょっと裏通りに入るとニュータウンや中高層ビルではない街並みやイギリス領以前の時代が偲ばれる史跡が点在しているとは知りませんでした。
やっぱり電車に乗ってるだけじゃ面白くないな・・・と思ったりと
次はLRT乗り歩きに移行します
<次回に続く>
2012/8/5 2:05(JST)