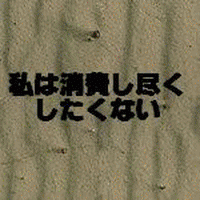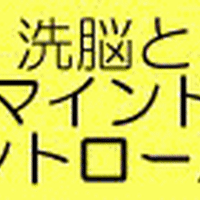ただ、だからといいて、ネット右翼と呼ばれる人たちが言論封殺のために行っている(としか思えない)ことを容認したわけでは決してない。左翼や市民派などと呼ばれた人たちが行ってきた異論を封殺する独善行為は、非難されるべきである。それと同じように、ネット右翼と呼ばれる人たちが行っている、ネット空間を占拠するためとしか思えないような異論封殺行為も容認されるべきではない。
そのように私は考える。このことをここで改めて申し上げておきたい。

以前のエントリー『いわゆる左派・市民派にも、ネット右翼増殖の責任がある!?(1)』に対して、7月29日に犬さんという方からコメントをいただいた。その全文はこちらに。
私はレスを書こうとしたのだが、レス文が長くなりすぎることに気づいた(確か、このブログのコメント欄は、一回に書ける字数が限られている)。それに、レス文は私の考えていたことを改めて表明するのにもいいと思ったので、こうしてレスも兼ねたエントリーという形で書くことにした。
犬さんのご意見には賛同できる部分(「ごもっともです」「それは私も心すべきですね」と思う部分)と、そうでない部分とがあった。
まずは賛同できる部分から。
>リアルにおいて左翼的活動に異を唱えることは非常に危険で面倒です。演説会場に行き反対意見を言い集団リンチされる危険をその辺の市井の人間がそうそう積極的に行うとは思えません。
匿名だから気軽に反論できる。逆に言えば現状においてリアル左翼には、一般人は匿名でないと反論し難いのです。
これはあるかもしれない。
幸いにして、左翼集団による集団リンチの現場を直接見た経験は私にはないのだが、事実上異論を言いにくい雰囲気というのを、いわゆる左翼的集団というのは作り出してきたというのもまだ事実である。
自分たちの信ずる価値観が絶対と信じるあまりに、異論を述べる人に対して非寛容になりすぎた。それがあるかもしれない。それは改められるべき問題であり、現在もなお改善がされていない、あるいは改善が不十分という現状もあると思う(注1)。その問題については、今後も考察していきたい。
理想を言えば、ネットであれ、リアルであれ、実名など身元を発言者自身が明らかにして、その言動に責任が持てるようにするのがいい、ということには違いない。
だが、下手に実名や住所などの個人情報を知られたら、反対意見を封殺しようとする相手から、どんな嫌がらせや危害を受けるかわからない怖さがある。組織の不正を内部告発する場合、身元がバレたらその人の地位や立場が危うくなるという場合もある。論じる話題等、場合にもよるが、このような危険性がまだまだあるのが、残念ながら日本社会の現状である。
だから、「匿名でしか発言できない」という人の存在自体を、私は非難するつもりはない。
>……ネット右翼の態度からみればわかるように、彼らは単純にアンチ左翼思想のネット「右翼」だとレッテル張りしてよい存在ではないと思うのですが。
確かに、それはある。
実際には、「左翼」とか「右翼」とか言われる人たちの中にも、いろんな立場の人がいる。例えば憲法9条に対する立場を見ても、「改憲派」「平和主義擁護派」の人が両陣営に見られるし……。というより、「右翼」「左翼」という言葉自体が、現代社会における意見や立場の違いを表すのには、もしかしたらあまり適切ではないのかもしれない。
では、何故そのような言葉を使っているかというと、正直なところ「便宜上のため」である(注2)。
コメントスクラムや某大手掲示板での晒しなど、気に入らない異論を封殺する相手を萎縮または消耗させることによって、事実上の言論封殺を行っている人たちを表現する言葉として「ネット右翼」という言葉を使わせてもらっている。厳密な定義付けはできていないかもしれないが、議論を展開する上で実に便利な言葉である(注3)。
>そのようなネットだから出来る一般人からの反論に対して、左翼陣営は普通の国民の反論とはとらえず「国民が正しい自分を支持しないはずがない」→「反対勢力の工作だ」→「右翼の反対攻撃」→「ネット右翼」と短絡的にレッテルを貼って満足しているように見えます。
反対意見への短絡的なレッテル張りがネット右翼という想像上の化け物を永遠に生み出しているのではないでしょうか。
この部分については、私は必ずしも同意できない。
中にはそのような人たちも確かにいるだろう。しかし、少なくとも私や私の友好ブログさん、及び読者さんたちは、反対意見をやみくもに排除しないように、出来る限りの努力はしているつもりである。実際は必ずしも十分ではないかもしれないが。
例えば、多くの人たちから「サヨ認定」を受けている(笑)私などは、自他ともに認める「ウヨ」である『気ままにつれづれ』さんとは、意見が異なる場合がしばしばある。が、現在でも相互リンクを結んでいる。また、私が参加している【Under the Sun】でも、参加メンバー全員が必ずしも同じ考え方ではない。【Under the Sun】には、憲法9条擁護を主張する平和主義者や死刑制度反対論者もいるが、もしそのようないい加減なレッテル貼りと異論排除を行うような集団ならば、武力や死刑制度の必要性を否定していない私などは、とうに追い出されているだろう(笑)。
またリンク先の友好ブログ管理人さんの中には、立場は違えど、右派・保守系ブログからの意見をきちんと受け容れている人も少なくはない。
では何が問題なのか?
何故、「ネット右翼」と呼ばれる人たちは嫌われるのか? 私がどうしてもそのような人たちだけは受け入れられないのは何故か?
それは、彼らの主張や考え方よりも、「意見や立場の異なる相手を萎縮・または消耗に追い込むことによって、事実上の異論封殺、言論空間としてのネットの占拠をしようとする」という言動こそが本当の問題なのだ。
「ネット右翼」という言葉の定義付けや使い方が本当に適切かどうか? 彼らの種痘についてどう考えるか? などは議論の余地があるかもしれない。
しかし、以下3つのことは「妄想」でも「想像上の産物」でもない。事実である!
(1)コメントスクラムや某大手掲示板での晒しなどの手段によって、意見や立場の異なる相手を萎縮・または消耗に追い込むことによって、事実上の異論封殺、言論空間としてのネットの占拠をしようとする人たちは、確実に存在する。
(2)そのような人たちによって、ネットにおける言論活動を阻害された人たちもいる。さらにサイト閉鎖や更新停止に追い込まれるなど、事実上ネットにおける言論・表現の場を奪われた人もいる。
(3)さらにひどいのは、ネットにおける影響だけではなく、心に深い傷を負ったり、オフの生活にまで支障が出たり、本来無関係な身内の人間まで傷つけられた人もいる(注4)。
以上3つこそが、私が「ネット右翼」などというレッテル貼りをやめず、さらに「ネット右翼」をどうしても許せない、受け入れられない理由なのだ。
だからこそ、私も篠原某や自称「ネット右翼のカリスマ」、及びそのお仲間連中のような人たちを受け入れることができなかったのだ。他人に対して「反日」だとか「糞虫」「アカ市民」「馬鹿市民」「poor」だとか無礼極まりない言葉を吐く。攻撃的なコメントやTBを送りつける。こちらのミスを大声であげつらい、さらにこちらがミスを認めてから数ヶ月経った今でもそれをネタに罵倒を続ける。このような人たちが、まともな対話や議論を求めているようにはどうしても思えなかったのだ。残念ながら、私もそこをこらえて、そのような人たちと忍耐強く対話できるほど、できた人間ではない。
というか(これまでに私も度々指摘してきたことだが)、それこそアホな左翼がやってきた「集団吊し上げによる異論封殺」と同じではないか! それに私の見る限りでは、そのような人たちほど、他者の批判ばかりで有効かつ現実的な代替案を提示しているようには見えないのだが(注5)。左翼批判をやっている者自身が、左翼がやってきた愚行と同じことをしていて、どうする!?
>ネット弁慶ではありますが、彼らも普通の国民の声の一部なのだと認識しない限り、左翼活動はますます一般社会から乖離するのではないでしょうか。
もちろん、ある意味彼らも「国民の一部」には違いないだろう。「普通の」という部分には、私は少々疑問を感じるのだが(注6)。
もちろん、左翼・市民派側の独善や非寛容さは改められるべきだが、「ネット右翼」側も自分たちの意見を聞いて欲しいというのならば、せめて異論を暴力的な手法によって排除・封殺したり、言論空間としてのネットを占拠しようとするかの如き姿勢は改めていただきたいものである。
でなければ彼ら自身も、いずれベルリンの壁やソ連邦崩壊した後のマルクス・レーニン主義者と同じような末路を辿ることになるかもしれない。「多数と匿名の暴力によって反対者を叩きつぶすという手法が、いつまでも通用すると思うな」と、最後に言っておこう。

*なお、(注1~5)についての注釈は、エントリー本文に入れることはできなかった。エントリー一回分の字数制限にひっかかるためだ。そこで、注釈は本エントリーのコメント欄にて行うということで、ご容赦いただきたい。