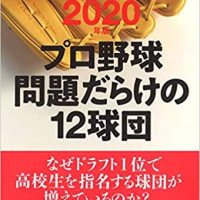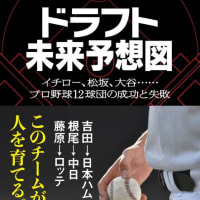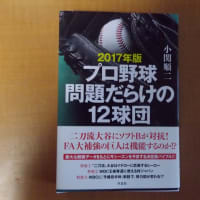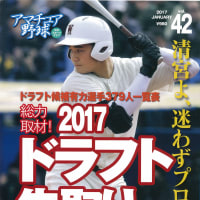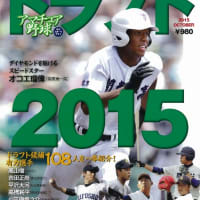◇3月8日(金曜日)/東京ドーム
WBC第2ラウンド
日本対チャイニーズ台北
第1ラウンドでオランダ、韓国と並ぶ2勝1敗でありながら、得失点率で上回りB組をトップ通過した台湾がこの日本戦でも底力を発揮した。
1回裏、2番林哲瑄、3番彭政閔がアッパースイングで一邪飛、一飛を打ち上げたのを見たときはチャイニーズ台北(以下台湾)のバッティングは何も変っていないと思ったが、5回1死後この2人が二塁打、中前打を放って2点目となる追加点をもぎ取ったのを見たときは、技術を超えた執念がモノを言う短期勝負の怖さを見せつけられた思いがした。
日本チームはこの日、1回に2番井端弘和が中前打のあと二盗死、さらに3番内川が左前打のあと二盗を成功させ、1回だけで2つの盗塁を企図して良化の兆しを見せた。こう書くのには理由がある。現在配信中のNumber Web『詳説日本野球研究』にも書いたのだが、09年の第2回大会で日本チームが勝ったときは盗塁が多かったというデータがある。見てみよう。
●第2回WBCでの盗塁数
3/ 5 日本 4-0 中国 盗塁=中島1、片岡1
3/ 7 日本 14-2 韓国 盗塁=イチロー1
3/ 9 日本 0-1 韓国 盗塁=0
3/15 日本 6-0 キューバ 盗塁=青木1、盗塁死=内川1
3/17 日本 1-4 韓国 盗塁=0
3/18 日本 5-0 キューバ 盗塁=片岡1、盗塁死=片岡1
3/19 日本 6-2 韓国 盗塁=城島1、亀井1、片岡1、岩村1、
盗塁死=亀井1
3/22 日本 9-4 アメリカ 盗塁=川崎1
3/23 日本 5-3 韓国 盗塁=片岡1、盗塁死=青木1
3/9、17の韓国戦を見てほしい。日本チームは1つも盗塁をしないまま敗れ、反対に勝った試合では盗塁をしている。とくに14対2で大勝した韓国戦、9対4で大量点を取ったアメリカ戦(各盗塁1個)以外の2~6点差の勝ち試合では2つ以上の盗塁を企図している。
この結果から私は、「盗塁には日本人選手の緊張感を解きほぐす力があるのではないか」と思い始めている。今大会も同様に見て行こう。
3/3 日本5-2中国 盗塁=糸井1、坂本1、盗塁死=内川1
3/6 日本3-6キューバ 盗塁=長野1
3/8 日本4-3チャイニーズ台北 盗塁=内川1、鳥谷1、盗塁死=井端1
勝った試合は盗塁企図数が多く、敗れた試合は少ない。これは12試合に共通して見られる事象である。つまり、試合が膠着状態に入った状況で走者が出たら失敗を恐れず盗塁のサインを出す、そう考えてもいいのではないか。2対3とリードされた台湾戦の9回裏、2死一塁の場面で鳥谷敬が二盗を決め、その直後に井端の同点タイムリーが出たのを見て、より一層そう考えるようになった(日本人選手の一塁走者はリードが大きく、外国人投手のクイックモーションは全体的に遅いので盗塁の成功率は高い)。
逆に日本人選手を“縮こませている”作戦がバントではないだろうか。1アウトを相手にあげる代わりに1点を取りに行くバントほど、日本チームの“貧打の伝統”を象徴するものはない。
台湾戦の3、5回には無死で出塁した一塁走者をバントで送りながら得点を挙げられていない。3回は無死一塁の場面で9番鳥谷敬が初球バントの構えをしたあと2球目をヒットエンドラン狙いのファール、そして3球目を思い直したようにバントをして、という具合にブレまくっている。「慣れないことをして恥をかくより伝統のバント作戦で様子を見よう」という山本浩二監督の縮こまった精神が見えるような鳥谷の打席だった。
投打の技術力を客観的に見れば日本チームがアメリカ以外のチームに敗れることは考えづらい。しかし、過去の大会では韓国に何回も敗れ、今大会ではキューバにも敗れている。その原因となっているのは金縛り状態になるほどの精神の縮こまりである。これを解きほぐすことだけを首脳陣には考えてもらいたい。