明治神宮大会、高校の部の決勝(日本文理対沖縄尚学)は球史に残る名勝負でしたが、大学の部もそれに劣らず見事なものでした。大会前に公開したNumber Web『詳説日本野球研究』には次のような文章を書きました。
「(亜細亜大は)過去4大会で11試合戦い、総得点はわずか32。1試合平均で3点に達しない計算になる。これは亜細亜大がというより、東都大学リーグ全体の傾向で、直近の1部2部入替戦、駒澤対東洋大などは1回戦が3対0、2回戦が1対0(駒澤大が連勝して1部残留)という胃がきりきりするような戦いぶりだった。日常的にこういう守り合いをするからプロで活躍できる選手が多く輩出されるのかもしれないが、日常的な守り合いが度を越した小技の応酬に発展すれば、パフォーマンス能力が低下する危険性もある。全国大会を勝っていない現状を見ればそう考えるほうが理屈に合っている」
補足すれば私はストップウォッチ持参で野球を見るようになってから亜大野球のファンになりました。しかし、ここ数年の亜大野球は“貧打線”と形容したくなる試合が多く、相当物足りないものでした。
この大会は7対0(八戸学院大戦)、4対0(桐蔭横浜大戦、延長10回)、2対1(明治大戦)と初戦以外は接戦続きで物足りなさから脱却できていないように見えますが、1番藤岡裕大(2年・三塁手)、2番北村祥治(2年・二塁手)、3番水本弦(1年・左翼手)、4番中村篤史(4年・中堅手)、5番嶺井博希(4年・捕手)、6番中村毅(4年・右翼手)の上位打線が自分の間合いでボールを捉えていて、打てる気配をムンムン発散し続けていました。こういう打線を見ると物足りなさは感じません。
明大では2番高山俊(2年・中堅手)に魅了されました。道都大戦で3回にソロホームランを打ったときのこと。実はこのとき金澤一希の内角攻めに遭ってバットを2本折っています(ファールで)。そしてホームランを打った球も厳しい内角への134キロストレートでしたが、これをコンパクトなスイングで押し込んで、ライトスタンドに放り込みました。投手陣も1~3年生に逸材が多く、来年以降変らず強そうな戦いぶりでした。
なお、明大対亜大戦では打者走者の全力疾走が目立ちました。「一塁到達4.3秒未満、二塁到達8.3秒未満、三塁到達12.3秒未満」をクリアしたのは亜大5人5回、明大5人7回とハイレベル。また一塁まで5秒以上かけてちんたら走るアンチ全力疾走は1人もいませんでした。東都と六大学の意地と意地がぶつかり合った最高の試合でした。
最新の画像[もっと見る]
-
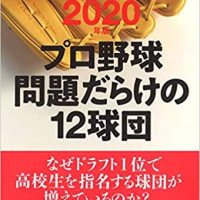 2020年版 プロ野球問題だらけの12球団が出ます
5年前
2020年版 プロ野球問題だらけの12球団が出ます
5年前
-
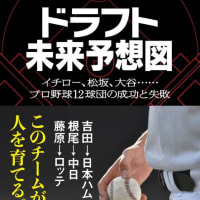 新刊『ドラフト未来予想図』のご案内
6年前
新刊『ドラフト未来予想図』のご案内
6年前
-
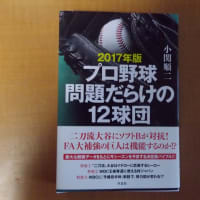 『2017 プロ野球 問題だらけの12球団』が発売されます
8年前
『2017 プロ野球 問題だらけの12球団』が発売されます
8年前
-
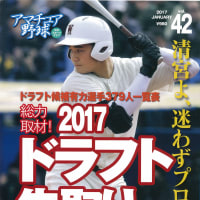 雑誌『アマチュア野球42号』が発売されました
8年前
雑誌『アマチュア野球42号』が発売されました
8年前
-
 ドラフト1位候補の伏兵はこの選手だ
9年前
ドラフト1位候補の伏兵はこの選手だ
9年前
-
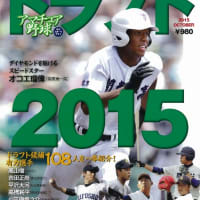 雑誌『アマチュア野球』が発売されます!
9年前
雑誌『アマチュア野球』が発売されます!
9年前
-
 明治神宮大会・大学の部ベストナイン
10年前
明治神宮大会・大学の部ベストナイン
10年前
-
 2年後のドラフト1位候補、山岡泰輔の快投
10年前
2年後のドラフト1位候補、山岡泰輔の快投
10年前
-
 西嶋の超スローボール、健大高崎の機動破壊をめぐる話
11年前
西嶋の超スローボール、健大高崎の機動破壊をめぐる話
11年前
-
 九州の快腕が熊本大会3回戦で姿を消す
11年前
九州の快腕が熊本大会3回戦で姿を消す
11年前










