今日は3月10日。東京大空襲の日。
二度と同じことが起きないことを祈りつつ、
亡くなった方々の霊に祈りを捧げました。
------------
さて、そんな日でもありましたが、
一方、今日で国立大学の合格発表も一段落の様子。
フェースブックなどでは、あちこちから、
お子さんの入試結果のニュースが届きました。
わが家は現在、ひさ~しぶりに入試のない時期を過ごしています。
4人も子どもがいると、いつも誰かしらが
何かしらの入試を控えているような感じで、
春は緊張が抜けない季節でした。
でもここ3年ほどは入試もお休み。
ちょっと感覚が遠のいていましたが、
あちこちから伝わってくる入試の結果に、
合格の嬉しさや、第1志望を逸した悔しさ……
そんな感覚を思い出しました。
お子さんたち、そして親御さんたち、本当におつかれさまでした~!!
合格した方々、ほんとにおめでとうございます。
思いっきり喜んでください!
そして、第1志望には振られてしまった方、
悔し泣きもありだと思います。たとえ男の子でも。
ともかく、本人が自分の感情を
まずはそのまま受け止めてほしいなあ、と思います。
次に進むために。
結果の持つ意味をいちばんよく知っているのは、きっと本人ですよね。
親は当事者ではないし、当事者にはなれない。
一緒に喜ぶのはしやすいけれど、その逆の場合はちょっと難しい。
でも、結果がどうであれ、
「正解は選んだあとの行動で決まる」のだと思います。
第1志望に受かったから幸せ、落ちたから不幸せ……そんなものではない。
悔しさはどうしたってあるけれど、人生がそこで終わるわけじゃない。
その悔しさをどこにどう向けるか、その喜びをどこにどう向けるか。
わが家の子どもたちの入試の結果もそれぞれでしたが、
親ができることは、
いつでも子どもたちがその時できるベストの選択を
してくれることを応援するだけ、でした。
そして、親が幸せを感じるのは、
どこにいても最善を尽くしている
子どもの姿を見ることだと思います。
みなさまに、そしてご家族に、
この春からもたくさんの幸せが感じられますように。
先日送ってもらったパリの桜の写真をシェアしま~す!

更新の励みになります。よろしければクリックをお願いします↓











 。
。
 。
。
 。
。
 みたいなことをしていく上で
みたいなことをしていく上で


 。
。 。
。
 。
。


 。
。 、と思っていました。
、と思っていました。 。
。

 )
)








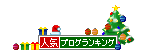


 して、
して、 」と、一時ものすごく心配しました。
」と、一時ものすごく心配しました。

 来年のことを考える、
来年のことを考える、 を始めたい、
を始めたい、 かもしれません。
かもしれません。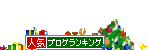
 ⇩
⇩ 」
」
 を
を を、
を、
 。
。 、記憶力とかも、
、記憶力とかも、
