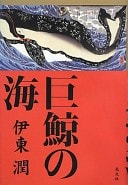
仲間との信頼関係が崩れると即、死が待ち受ける危険な漁法、組織捕鯨。それゆえ、村には厳しい掟が存在した-。江戸から明治へ、漁村で繰り広げられる劇的な人生を描いた連作短編集。『小説宝石』掲載に加筆し書籍化。
1 旅刃刺の仁吉
2 恨み鯨
3 物言わぬ海
4 比丘尼殺し
5 訣別の時
6 弥惣平の鐘
夏の間、鯨は蝦夷地や千島列島で、オキアミをたらふく食べ、一尺を超す皮下脂肪をさらに厚くし、北の海が氷で閉ざされる前に、繁殖のために南に向かう。これを上り鯨と呼ぶ。
上り鯨が太地沖を通過するのは、9月から12月で。北に向かう下り鯨は、3月から4月に通過する。それぞれ冬漕ぎと夏漕ぎと呼ばれ、それ以外の期間は休漁となる。
下り鯨は黒潮に乗っているので瞬く間に通り過ぎてしまうが、上り鯨は逆潮を嫌い、黒潮の強い部分を避けながら泳ぐため、陸岸に近寄ることが多い。紀伊半島の鯨捕りは、そうした寄り鯨を狙うだけで十分に食べていける。
黒潮は太地の4里から5里ほど沖を流れているが、まれに支流が1里まで迫ることがあり、そうした折は、鯨の数も多く大漁の可能性も高まるが、深追いすると黒潮本流に乗り入れる恐れがあり、十分な注意を要する。
小さな帆しか積んでおらず、帆走力の弱い勢子船が、黒潮を脱出するのは至難の業であり、紀伊半島の鯨漁は常に遭難と隣り合わせで行われていた。
太地湾は、東側の燈明崎と西側の鷲の巣崎が、蟹がハサミを広げるように北東に向かって開く、懐の広い湾である。
太地は、紀伊半島南端の潮岬から東北4里、那智の滝で有名な那智勝浦のすぐ南に位置している。それゆえ気候は温暖で、冬でも過ごしやすい。
刃刺(はざし)として勢子船をいっそう任されることが夢だった。刃刺とは、鯨に銛(もり)を打ち込む勢子船の頭(かしら)のことである。
しかも黒潮は、潮岬を通過する辺りが最も速く、一刻(2時間)で60里も流されたという記録さえある。まさに黒潮は海中の大河であり、それが別名、黒瀬川を呼ばれる所以である。
鰹島とは、燈明崎(とうみょうざき)の鼻から北東へ半里ほど行った先にある浅場で、海山の隆起が大きいため、鯨の動きを予想しやすく、網代(あじろ)に追い込みやすい。
銛(もり)は一艘の勢子船に20本ほど積まれている。
これらを使い果たす前に仕留めねばならない。
鯨船に追われたことのない鯨は警戒心が弱い。逆に、命からがら鯨船から逃れたことのある鯨は、過度に警戒心が強く、捕まえるは容易ではない。それゆえ頭(かばち)に銛傷のある鯨は、鯨捕りから避けられる傾向がある。
もおじとは、海面に浮かんでくる水泡のことで、その下に鯨がいる。
鯨は、30分に一回は海面に出て呼吸をせねばならず、もおじの上で待てば、必ず姿を現す。
鯨は、見た目の大きさがさして変わらなくても、生殖能力の発達した成獣か否かで、その気性も力も格段に違う。いかに賢くとも、なぜか鯨は一つの事に気を取られると、すぐに前のことを忘れる。
鯨は苦痛のいななきを上げて逃げ惑うが、すでにその声には、怒りよりも悲しみの色がにじんでいた。遂に駄目押しの柱銛が打ち込まれた。50本ほどの銛を針の山のように突き立てられた鯨は、遂に進退窮まった。その潮声は怒りから悲しみへ、そして死の恐怖へと転じる。むろん潮声といっても、喉仏から出る声ではなく、噴気孔から漏れる音だが、これが息苦しくなると、切迫した調子になるのだ。
鯨の心臓がある腋壺を突き、とどめを刺す剣切りが・・・
しかし鯨を殺してしまっては、沈むこともあるため、持双に掛けるまで、浮いていてもらわねばならない。鯨は鼻弁の開け閉めにより、潜水と浮上を繰り返すが、この鼻弁を切り裂くことにより、二度と海中に潜れないことを覚り、いよいよ観念する。また鼻切りは、鼻弁に紐を通し、持双に結び付けるためにも必要な作業である。
網取り漁法をはじめて8年後の1683年末から翌年の春にかけて、太地だけで座頭鯨を中心とした大型鯨96頭の水揚げがあり、その殷賑喧騒(いんしんけんそう)は言語に絶するほどになった。
当時の大鯨の1頭平均の価値は75両で、96頭だと優に七千両を超える。
現代の価値に直すと、1両を1万円として実に七千万円である。
抹香鯨は群れで生活しており、数十頭で構成される集団が次第に寄り集まり、時には数百頭の群れを成すこともある。
群れで行動している鯨は、子鯨を連れていることが多いため警戒心が強い。
抹香鯨は穏やかな性格で、ほかの鯨に比べて臆病である。
頭部の油のおかげで、死んでからも、しばらくは浮いていてくれる。
オキアミなどを鬚でろ過して吸収する長須、座頭、脊美(せみ)などの鬚鯨類と違い、抹香鯨は、烏賊や蛸を主食とする歯鯨類に属する。
抹香の群れは勝手気ままに烏賊を追っているようにみえても、実際は、雄の成獣が外縁部に散り、雌や子鯨を守るようにして警戒に当たっている。鯱(しゃち)という天敵がおり、警戒を怠ることはない。
鯨が仲間に危険を知らせる場合、海中でクリック音を使う。
雄の抹香鯨は、仲間と雌を争ったり烏賊や蛸を獲ったりする際に、その歯や吸盤で傷つけられることが多く、暗褐色の巨大な頭部には、幾筋も線条の傷が走っている。
五千三百貫(20トン)余の成獣を引き上げるには、百を超える人員を要する。
お宝とは龍涎香(りゅうぜんこう)のことである。
龍涎香とは抹香鯨の腸内から採れる分泌物のことで、主食である烏賊や蛸が消化されず、腸内の分泌液と化合して結石化されたものである。それが麝香(じゃこう)に似た芳香を放つため、高貴な女性たちの垂涎(すいぜん)の的となり、高値で取引された。
ただし龍涎香は、ある程度の大きさになると、糞と一緒に排出されるので、必ずしも腸内に残っているとは限らない。
太地の流罪は、左手首を切り落とされるより過酷である。
流罪とされた者は、三日分の水と食料だけが積まれた小船に乗せられ、黒潮本流に乗せられる。黒潮は遠くアリューシャン諸島まで流れていくが、たいていは、その前に時化(しけ)で転覆して海の藻屑と消えるか、飢えと渇きのなかで死ぬことになる。
恨み鯨とは、子を殺された母鯨や、妻を殺された雄鯨など、鯨船に復仇を遂げようと待ち受けている鯨のことである。
ほかの部分は、すでに硬直が始まっているのに、なぜか乳房は最後まで硬直しない。
それが女の意地のように感じられる。
信夫翁(あほうどり)
そこで表皮、筋、赤肉、内臓、骨などの部位に分けられていく。
分けられた部位は、筋以外のすべてを搾油するため、いったん大釜で煮られる。
しかし、筋だけは、扱いが異なる。
鯨の筋は、弓弦(きゅうげん)として高値で取引されるため、筋師と呼ばれる特殊な技能を持つ男たちが取り付き、慎重に切り取っていく。
「座頭やない。野曾(のそ)や」
野曾とは長須鯨のことである。
長須鯨は日本近海に出没する最大の鯨で、網を2枚同時に破るほどのすさまじい力を持ち、泳速も格段に優れているという。
それゆえ、よほどのことがない限り、野曾を見逃すのが鯨組の定法である。
しかし、たまに流れ着く野曾の死骸からは、同じ大きさで座頭鯨の2倍の脂が取れるため、野曾の流れ鯨は、どこの鯨組でも垂涎の的となっていた。
野曾は俊敏な上、なかなか死なない。
急所が狭く深いため、とどめを刺すのは容易ではなく、鯨の背に乗って、銛か手形包丁を深く刺し込まねばならない。
まれに鯨虱(くじらじらみ)が耳の中まで入り込み、体は健康でも、感覚に不調をきたした鯨がいるという。こうした鯨に率いられた群れは、健康な者も含めて、群れごと陸地に乗り上げることがある。
鯨魚(いお)
鯨は人間同様、基本的に一頭しか子を生まないので、母子の絆は極めて強い。
死米定(しにまいさだめ)とは、仕事中に事故で命を落とした者や、再起不能のなった者の遺族に対する救済法で、現金と扶持(ふち)米が支給される。これにより、沖合衆は安堵して危険な仕事に就ける。
長さ16mほどの小ぶりな鰯鯨
嘉永7年・1854年、アメリカ合衆国との間で日米和親条約が締結されて以来、米国の捕鯨船が近海に出没するようになり、太地では、坊主と呼ばれる不漁が続いていた。
鯨に網を掛けられるのは3回か4回に1回ほどで、さらにその半数には、網を掛けたまま逃げられる。
背美鯨は穏やかでのんびりした性格だが、子連れであれば獰猛な獣と化す。
背美鯨は、体長が15間でも、座頭や抹香の倍くらいの重さがある。つまり全身がずんぐりしている分、その巨大さは、体長だけでは測り難いのである。
鯨の中でも背美鯨の脳は特に大きく、人間以上に読み詰む(深く考える)ことができるという。
黒潮特有の青黒い帯
「黒潮は海の中を流れる大河です。海底に山があれば、支流が生まれます。それが、陸地や海底山にぶつかれば反流になります。それらが錯綜してくれば、海面に渦が浮いてくるのです。」
座頭鯨の雄は、繁殖期に旋律に富んだ歌を歌うと聞いていたが・・・
繁殖地は蝦夷地の北と決まっており・・・
午前に流した二つの遺骸を食った鱶(ふか)の群れが、味をしめて船のあとを追ってきているのだ。
神津島の人々は遭難者の救助に慣れており、焚き火などで体を温めると、衝撃で死んでしまうことを知っていた。それゆえ女たちが身を擦り付けることで、遭難者の体温を戻すという方法を取っていた。
やがて食べ物は赤土から重湯へ、さらに薄粥へを変わっていった。
遭難者に、すぐに米の飯を食べさせると死ぬという島の人々の経験から、そういう食事の順番になっていた。









