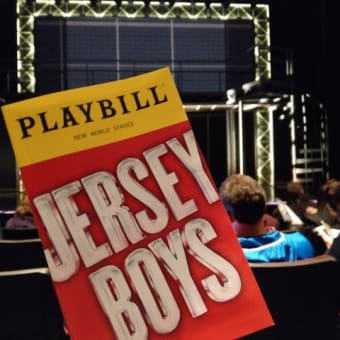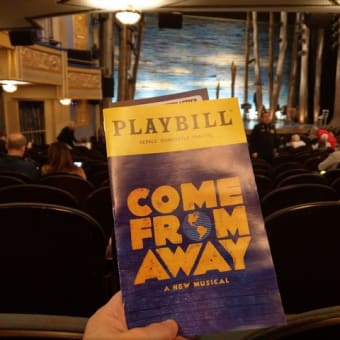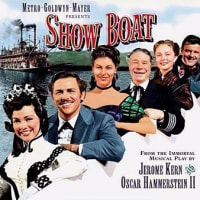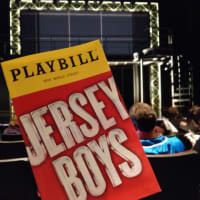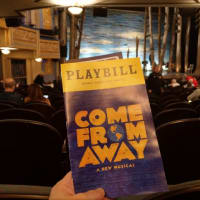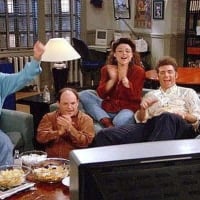美しい英国式ガーデン。
ガーデニングを愛でる大使館職員のジャスティンはアフリカ、ケニアに赴くときも荷物に苗を忍ばせて持っていく。(これって植物検疫上、かなりマズイでしょ!)
美しい花を咲かせるためには雑草も害虫も取り除かなければならない。本来はひとつひとつ手作業で取り除いたものが、最近では薬剤がその代わりをする。しかし、薬剤には環境汚染や人体への有害の恐れが常につきまとう。一方、そうやって咲かせた花々の甘美な蜜を享受する虫も存在する。
この映画は、こんな図式を人間社会に置き換えたドラマだった。
個人的には懐かしくて、どこか気恥ずかしい(?)ストリーだった。そう言えば、先日NHKBSで放送されていた「いちご白書」も懐かしかった。(ま、あれは実際、古い映画なんだけど)
事務的なお役人のレクチャーに噛み付く、儀礼的な場所でも本音で毒を吐きまくる。周囲の顰蹙を買うのも「勲章」みたいなもの。
自分にもそんな時があったな…
ちょっと、見ていて痛々しい(苦笑)
でも、彼女の凛とした話し方が心地よく響く。
テッサは大使館員の妻という、わかりやすく言えばセレブな立場でありながら、スラムへ足を運び、現地の人たちと交流する。政府関係者のパーティには現地の民族衣装のドレスで出かけ、子ども達の作った素朴なモビールを家に飾る。
私も、かつては、淡々と素朴に生きている人たちの生活感がしみた手作りの品物が好きだった。人々が高価なブランド品ばかりに目を奪われるのではなく、こんな「ささやかに」「ひっそりと」存在するものの美しさを感じる心があれば、世界は変わるのに!と思った。テッサの思いも手に取るようにわかった。
でも、私はいつの間にか
「一人で出来ることには限界があるでしょ?青臭いことばかり言っていても何も始まらない!」が口癖のようになった。熾烈な競争社会もジャングルのようなもの。そんな「こちら側のジャングル」で行き抜く術のほうにエネルギーを注ぐようになった。
熱いなぁ彼女…
でも、もっと賢明なやり方はないの?
…なんて、ぼーっとスクリーンを見つめていた私。
テッサは妊娠して臨月が近くなってもスラム街を訪ねることをやめない。スラムにある野戦病院同然のところで出産するという選択をする。しかし、赤ん坊の死産と言う不幸に見舞われる。しかし、気丈にも、隣のベッドで亡くなりかけている現地女性の生んだ赤ん坊に母乳を与え、退院してもすぐに家へ帰らずに、疑惑の場所へ立ち寄ろうと言い張る。
でも、このあたりは彼女の大きな喪失感の表れなんだと思う。
少なくとも、私はそう解釈した。
彼女はいつも、自分の中のぽっかりと空いた所を内から湧き上るエネルギーで埋めてきたような、そんな人だったのだろう。彼女の闘争心がどこから起因するものか、多くは語られていないが。(たぶん…深夜のレイトだったので…見落としてなければ)従兄弟が「ラテンの血」と言ったのと、あとは生まれる子どもにつける予定だった名前に少しの手がかりが隠されていたのかもしれない。
そして、大きな陰謀に気付いた彼女は消されてしまい、そこから、妻の思いを受け継いだ夫、ジャスティンの戦いが始まる。もう、ガーデニングだけに心を砕いているわけにはいかない。妻との愛の日々の思い出に胸をかきむしられながら、執念で巨悪を暴こうとする。
悲劇的な結末ではあったが、テッサとジャスティンの関係が「夫婦愛」から「同志愛」そして「人類愛」へと昇華していく過程に胸を打たれた。
圧倒的なアフリカの大自然。でも、最小限の平穏な空間さえも構築することの出来ない人間の限界。
本当に人を強めるものは何なのだろうか?
登場人物の多さ、プロットの乱雑さも少々気になったが、
自分が「今」、この映画と出会えたことを大事にしていきたいと思った。
最新の画像もっと見る
最近の「Movies」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- JERSEY BOYS (舞台ミュージカル)(127)
- JERSEY BOYS(映画)(43)
- JERSEY BOYS(来日公演)(9)
- JERSEY BOYS(日本版)(18)
- JERSEY BOYS(音楽関連)(30)
- Jerry Seinfeld(36)
- SEINFELD Cast(22)
- BEE MOVIE(40)
- CUTMAN(27)
- Theatre(118)
- Books(33)
- Music(84)
- Movies(111)
- THE PRODUCERS(20)
- CURB YOUR ENTHUSIASM(6)
- New York(49)
- HAIRSPRAY(33)
- SEINFELD(139)
- English(1)
- Unclassified(84)
バックナンバー
人気記事