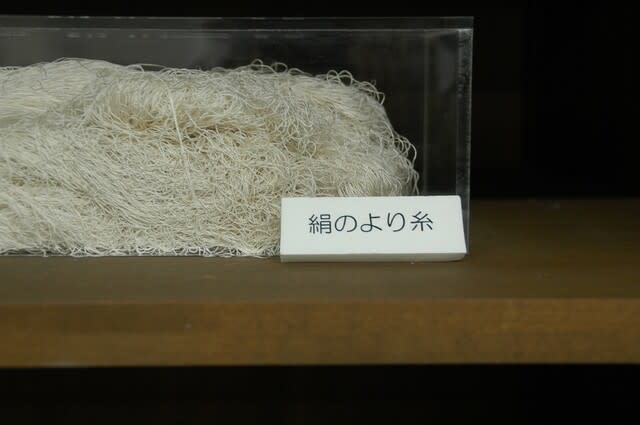その1では、「情報館」に向かう所まででした。
その2は、中の様子です。
入ると、「検温」と「消毒」もう当たり前になってきていますね!
最初に目に付いたのは?
なんだろう? 情報館のスタッフが教えてくれました。
これは、繭の「オス」と「メス」を分けるものみたいです。
どうやって分けるのかなあ~?
疑問は1分後に解決した!(ラジオのコマーシャル風です)
体験してみますか? スタッフから声がかかったので、「はい、ぜひ」
円盤上の四角い所へ繭を乗せて、左側にあるダイヤルみたいな取っ手を回します。
そうすると、回転して奥側に行くと、落ちる繭と落ちない繭があります。
落ちた繭が「メス」との事、でもなんで?
それは卵を持っているので、その分オスより重いので、落ちるようです。
天秤の原理みたいですね! へえ~、そうなんだ、勉強になりました。
(メスは体内に500個ほどの卵を持っている)
人間の手の間隔で重さを判断するのも難しいとの事。
この道具は、清掃センターへ持ち込まれ、職員が「情報館」に「使いますか?」という事で、譲ってもらい、整備したそうです(スタッフ談)
持ち込んだのは、その昔「蚕種屋」を営んでいた、地元の人でした。
「蚕種屋」さんは、メスの繭から卵を取り出し、卵を販売する蚕種業者です。
繭の状態では、オスとメスは、見た目の違いはなく、見分けるのは無理でした。
100年前の大正5年(1916年)に、長野県の「大沢太郎」が考えたもので、
オス、メスを見分ける「繭雌雄鑑別器」です。
これにより、見分けが無理の作業が可能になったようです。
この道具の体験が出来るのは、ほとんどなく、大変貴重との事でした。
これも鑑別器みたいですが、方式が違うみたいです。シーソーみたいなものですね! ガラスケース内に展示されていたので、ちょっと今一の写真でした。
「黄金繭」金色をしています。ちょっとわかりずらいかな?
養蚕に関係するものが展示されていましたね!
高山社て何? と思っている人はいますか?
高山社は、「養蚕の技術を教える学校」みたいな所で、全国から学びに来ていたようです。
蚕を知らない人もいると思いますが..
私も子供の頃は、蚕が苦手でしたね!
蚕の時期になると母の実家へ行き、よく蚕を見ましたが..
なんか「0系新幹線」に似ていますね?
蚕がつぶれると緑色したものが出て、これが嫌でしたね!
「高山社」の模型みたいです。
部屋を暖めるための「火鉢」です。蚕部屋を暖めるものですよ!
蚕は寒さと湿気に弱いそうです。病気にならないための対策だそうです。
これは?
「糸車」みたいですね!
こんなのもありました。
今では、養蚕農家も激減してしまい、蚕を見る機会がないので、こういった道具を見るのもいいですね!
なんか説明がうまく出来ず、わかりずらかったかも知れませんね?
その2はここまでです。