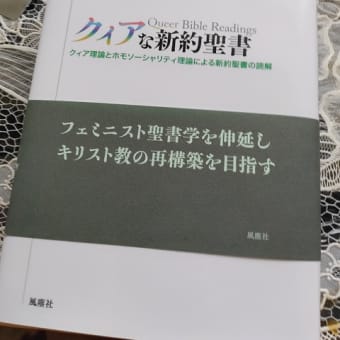韓国は「恨の500年」と言われる。南北への分裂、日本による植民地化、独裁政治、儒教的家父長制による抑圧など歴史的に培われてきた根深い民族感情である。
「うらみ」は「恨」と「怨」がある。これを区別必要がある。「怨」は他人に対して抱く感情。「恨」は自分の内部に積もってしまう情の塊である。
この違いは日常的な実感の中では知り得ない感情である。前回あげた李御寧『恨の文化論』では、次のような整理がされている。
「怨」は復讐すれば晴れる。ところが「恨」は悲しみであり、人間に沈潜する。ただ積もるのである。だから晴れることはない。そういう感情であるが、僕は日本人の悲しみにもそういう面はあると思う。「もののあわれ」であろうが、悲哀に伴うその処理の仕方の違いがあるのではないかと思ってしまう。その違いの大枠が韓国では「死者を許さない文明」として現象化し、日本では「死者を許す文明」となる。そんな違いであるから、日常的な感覚では気にすることもなく、日常を過ごすのである。
李さんは「恨は雪のように悲しく積もる」と表現している。韓国は「恨みながら、500年」生き、蓄積してきたのである。それが冒頭「恨の500年」である。
この民族の心情をそう簡単に理解できるなど軽々しく言うことも出来ないが、僕のような日本人が理解できるのは、僕のような日本人には理解出来ない深い民族感情があるのだと想像することだけである。よく「異文化理解が大切である」などと言うが、それもまた表層なのであり、そのような表層理解が他者理解・異文化理解から遠ざけてしまうことがある。そういう場所で逡巡するほかない、そんな存在状況を見てしまう。
さて、このような「恨」は晴らされることはあるのだろうか。山折さんは崔吉城『恨の人類学』(平川出版1994)から、仮説ではあるがと慎重に、その役目を果たしたのが仏教であったと指摘する。
仏教は、人間の恨みや煩悩を昇華する解脱の道を解くことによって、個人の救いを唱える。この仏教思想が否定的な感情を解決する手立てとなったとするが、それでも解きほどくことができない「恨」を抱えてしまう。そこに韓国の巫俗信仰、シャーマニズムが関わってくる。
これは日本も同様であった。巫俗の宗教儀礼によって、この否定的感情を昇華していたのである。巫俗がお祓いをすることによって、それは(恨も含めて人々の不幸)を納めるのである。
ところが李氏朝鮮の時代(14世紀終わりから)、仏教は廃され、儒教を尊ぶようになる。儒教は現実的な宗教(人々の行動規範を決定する力を持つ)であるため、巫俗と対立して行くことになる。李氏朝鮮になると、巫俗は日陰の存在ではあるが、非業の死を遂げた者への救いをもたらす。ちょうど日本の菅原道真が非業の死を遂げ、鎮魂が信仰に昇華され、太宰府天満宮への信仰となるのを思い出す。
ただ日本と韓国では大きな違いがある。それが仏教である。仏教の慰撫鎮魂が日本では残り、韓国では失われる。さらに儒教の受容も違う。これについては触れられていないが、儒教は日本社会全体に広がったといっていい。これは二宮尊徳の報恩思想に繋がる。韓国では、儒教は官僚などの支配層にのみ広がり、儒教を表看板にしていたのだ。そこに民衆的な巫俗信仰、ネガティブな鎮魂救済が沈潜しつつ力を持つ。そこに「恨」が根付く土台になる。
植民地になったことへの、そこで被害にあった者を思い、その原因でるA級戦犯への「恨」を抱き続ける文化は宿命のようである。ここに「死者を許す文明」(日本)と「死者を許さない文明」(中国と韓国)の緊張と対立の根があると言えるのではないか。