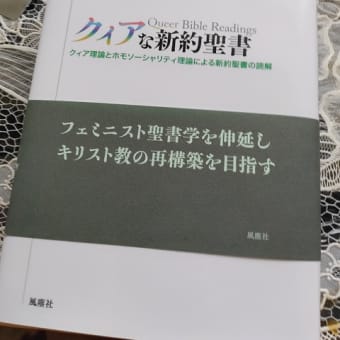今回コロナでも知られた偽陽性であるが、がん検診でも同様偽陽性がある。これはがん検診の不利益であるが、あまり知られない。そもそも統計的に有効かいなかが判断されるので、がん検診で死亡率が低下してれば、がん検診の有効性は認められるが、そのようなデータはない。これは健康診断をすれば、寿命が長くなるという結果が出れば、健康診断に意味があるという話と同じであるが、フィンランド症候群ではそのような有効性がないことが知られている。つまり、なんのために行われているのかよくわからない。
それでも、がん検診も健康診断も推進されている。これは僕の天邪鬼な見方であるかもしれないが、前回あげたように現代社会はリスク社会であるがゆえに、両者を生のリスクと見なす常識が生産され、その対処方法として、科学的手法、統計的処理、予防という概念が自明化されているからである。
さて『子宮頸がんワクチン問題』では、以上のような社会学視角はあまりない。問われているのは、何といっても科学的妥当性の水準で、各種手続きの不透明さである。また副作用の具体的な例がいくつも挙げられている。そこは法律の専門家の専門性、そしてジャーナリストの調査能力が遺憾なく発揮されている。
ちなみに副作用についてであるが、現在もコロナワクチンの副作用については、ワクチンと副作用の因果関係は証明されていないとされているが、これをワクチン後の有害事象とみなせば、ワクチンと有害事象の因果関係を想定できるとするのは合理的と判断するものもいる。なぜなら死亡例をあげれば、ワクチンで死亡したわけではないとすれば、ワクチン接種後から半年、1年とのスパンで1日単位でも1週間単位でも、さらに1ヶ月単位でも死亡数を比較しても変化がないはずである。
ところが明らかに接種後に近い方が死亡数が高い。とすれば、なにがしかの因果関係があると考えるのは合理的である。ただ、死亡の要因、ワクチンの人体の影響は複雑であるから、それら要因を設定し、それぞれの要因の重回帰分析をしなければ、科学的判断には達するわけではないので、そこは不透明であるという科学的結論になる。前回でも指摘したのだが、わからないという結論になってしまう。科学的手法の限界である。
製薬メーカーが中心となってデータを集め、その解釈というか位置づけをするのだが、どうも不明な点が多々出てくる。例えば、ワクチンが感染リスクを低下するとされるが、他の交絡因子についての関連性が考慮されていないことから、発症率をどのように解釈するのか困難である。つまり先にあげた科学的手法の限界があるにもかかわらず、ワクチンの有効性が主張される。
あるいは発展途上国の子宮頚がんでの死亡を研究者は危惧するが、そもそも発展途上国ではバップテスト(つまりは検査であるが)があまりなされないため、栄養や環境衛生を含めると、ワクチンの有効性を主張できるのか疑問がある。栄養状態と環境衛生の向上の方が優先事項であることは、本書で強く指摘されるわけではないが、当然のことであるだろう。
他多々あるのだが、インフォームドコンセントの問題をあげて、次回で最後としようと思う。