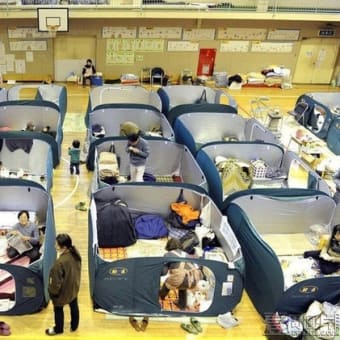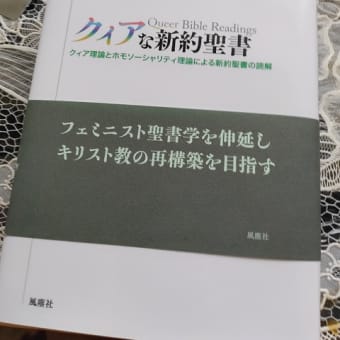先日、若い女性から「何が正しいのか教えてよ」と質問された。
僕の答え「自分で考えなさいよ、それが答え」。
これははぐらかしたのではない。それが本当に答えであると確信している。何が正しいかは、自分が知っている。心が知っている。というのはプラトンの想起説からだが。以下正しい(正義)ではなく、良い(善)で説明。
そういえば、「全ては言語ゲームにすぎない」などと、したり顔で相対主義的な言葉を吐く人がいるが、これは現代哲学ウィトゲンシュタインの言語ゲームの曲解からの言葉なのだろう。これが大衆化すると、「世界はゲームだから」みたいな話になってしまうようだ。
これはプラトンの想起説と、さほど変わらない。問いの仕方が違うのだろうと思う。
プラトンは「善とは何か」と問われたら、善の内容にはなんら答えないが、その善という言葉が心の中にあることは真実であるから、善は存在するとしかいえないと。言語の意味ではなく、言語の形式に着目して、形式として善が使われるということは、その意味を知っているから、あるいはその使われ方を知っているからでしょうと。だから善はあるでしょうと。
ウィトゲンシュタインは変な問いをしているのだと思う。
善という言葉がない世界、架空の民族や国民であろうか、そこで善という言葉を使ったところで、彼らは理解できるだろうかと。そこで善を説明して理解してもらえるだろうかと。善とは何か?という問いが意味を持つのは、どういう状況の時か?
彼は理解不可能であると断言する。なぜなら善という言葉が意味を持つためには、善という言葉の意味(形式でも同じだろう)を持つ世界に生きる必要があるからだ。この生きる世界を言語ゲームと名付けたわけだ。この言語ゲームを共有する人たちが、ひとつの世界を共有するわけだから、それが民族とか国民(これは近代以降ある意味人為的に作られたので、郷土を共有する人という意味で共同体?)ということだろう。
この善という言葉、あるいは冒頭にあげた「正しい」という言葉はいつからあるのだろうかと疑問が生じる。ところが、それ自体が不可能なのだ。なぜなら現在の言語ゲームの中での問いは、この言語ゲーム内の問いであるから、その外に出て、最初(始原)を問えない。あらゆる問いは、現在の言語ゲーム内部にあるからだ。
だから言語ゲームの始原、根拠は不可知。そう、知らないのに、その世界がなぜだか成立する。本当におかしなことだが、それこそ世界というものなのでしょう。
だから冒頭の問いは、何が正しいのか意味内容を問うということは、結局不可知である。だから、とりあえず自分で考えて、暫定的な解答を出すしかなく、暫定であるから、未来には変化することもある。そういうことだ。
そして、意味内容ではなく、言葉の形式に至れば、どのような解答になるのか。「心が知っている」である。