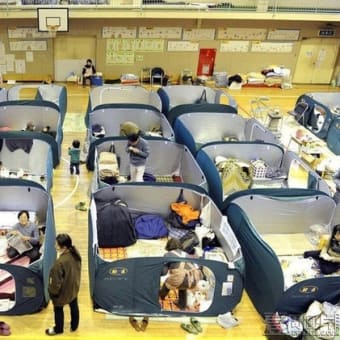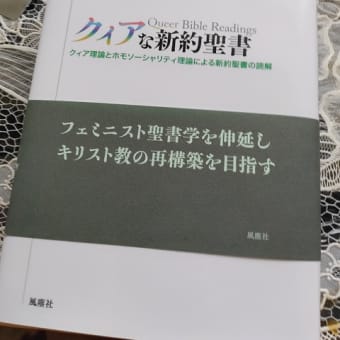前回お金が神の地位を獲得しているメカニズムを、簡単であるけど綴ってみた。
しかしながら、人間の心が求めたということではない。これは社会的なメカニズム・プロセスの結果である。心理学的に説明できるのではなく、社会学的と言っていい。その間にある社会心理学なら接近可能だと思う。
つまりお金が神のように人々を支配するシステムとして君臨するのは、意識ではなく、意識と独立したシステム、人間関係によって作られているということだ。つまり、それが社会ってやつだ。マルクスは関係を重視したが、関係が自律的に運動して、その結果として、お金というシステムがなんだか君臨してしまったのだ。
しかしながら、商品から見るとこのお金という神は神には見えない。なぜなら、それぞれの商品が先にあるのだから。一応断っておくと、物々交換に遡って先にある存在がモノであり、その延長線上で商品が実体化してくる。
商品から見るとお金はあくまで便宜上の手段であることが自明である。お金は約束事にすぎないことを知っている、我々人間も。人間が商品を交換するために作り出したのがお金である。このことに誰もが納得するはずだ。先の意識と社会の違いを組み込んでやると、社会がお金を作ったということになる。
だから、お金を使ってやっているのだから、お金が特権的地位にあるかのように見える。というお金の秘密はネタバレなのである。商品から見れば、自分たちの価値を転倒した存在がお金になってしまう。
神が人間を創ったのではなく、人間が神を創ったと言ったのは、フォイエルバッハだが、神という言葉がなぜ存在するのかの不可思議は置いておいて、商品がお金を創ったにすぎない。お店をやっている人からすると当たり前。お店の商品が売れてお金になるわけだから。「儲かった」と言っても、売るものがなければね。
このようにお金が神であるわけではないし、交換の便利な手段にすぎないと知っていても、人々の行動は違う。やっぱりお金が神のように扱われている。なんせお金があれば、商品を買うことができるからだ。
ここで2つの水準が見出せる。1つはきちんとプロセスをみれば、お金はお金にすぎないと。2つ目には、お金があれば、なんでも買える。だから、僕たちは商品を購入すればするほど、あらゆるものが商品として現れれば現れるほど、2の水準が強調される。
1が意識化したお金の正体出であるとすれば、2は人々の行動によって蓄積された無意識のレベルでのお金の正体。だから行動だけをみれば、お金を崇めているように見える。社会は無意識的であることを意識化した方がいいと考える。