この度細野豪志ブログをホームページ内のブログに移設することになりました。
新しいブログのURLはこちらです。
https://www.goshi.org/archives/category/blog
ブックマークなどの変更をお願いいともに、これからもお付き合いいただきますようお願い申し上げます。
この度細野豪志ブログをホームページ内のブログに移設することになりました。
新しいブログのURLはこちらです。
https://www.goshi.org/archives/category/blog
ブックマークなどの変更をお願いいともに、これからもお付き合いいただきますようお願い申し上げます。
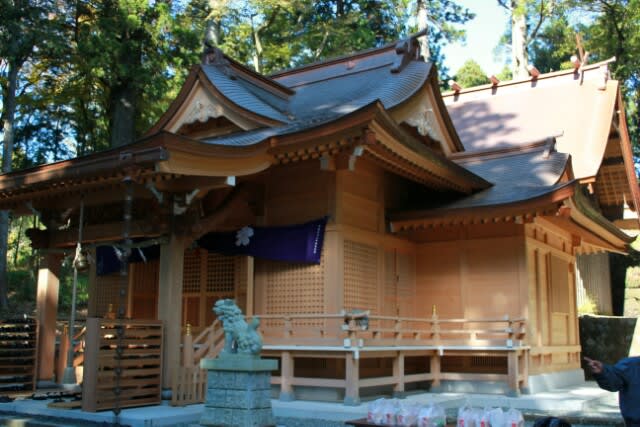

演劇『もう風も吹かない』を見ました。すごいの一言。これまで、『ソウル市民』『冒険王』『火宅か修羅か』『ヤルタ会談』など、いくつかの平田オリザさんの作品を見てきましたが、この作品が一番インパクトがありました。完成度の高い脚本と演出は圧巻でした。
葛藤する海外青年協力隊候補生を演じた役者も良かった。私にもああいう頃が確かにありました。
途中、沖縄まで踏み込んだのには唸らされました。様々な経験をしてきた副所長の「とにかく行ってみることだ」という言葉は、私には若者への応援歌に聞こえました。協力隊の個別の評価は分かれたとしても、私は未来を切り開こうと行動する若者を応援したいと思います。
平田オリザさんの作品の設定では、日本の財政破綻と円の暴落は2025年あたりとのこと。10年前にすでにこの作品を書いていることに驚きます。現状はより深刻になっています。政治家として、財政破綻と円の暴落によって日本の信頼が失墜するのを阻止しなければなりません。帰り際、平田オリザさんから、「しっかり頑張ってください」と穏やかながら厳しいひとこと。その通り。
先日、大阪の天満天神繁昌亭に行ってきました。参議院選挙中、全国で最もにぎわっていた天満橋筋商店街に、もう一度行ってみたいと思っていました。
繁昌亭で行われている寄席も覗いてきました。正直言って、その質の高さに驚きました。東京の新宿末廣亭や浅草演芸場には時々行きますので、寄席の雰囲気には親しんでいるつもりだったのですが、繁昌亭の寄席は雰囲気が大きく違いました。
まずはその盛況ぶり。平日の昼間でもいっぱいになるようです。会場内は飲食禁止。持ち込んだ大阪名物たこ焼きをロビーで食べるはめになってしまいましたが、なるほど会場内は和やかながらも熱気にあふれていて、ものを食べる雰囲気ではありません。当然のように寄席の最中の出入りは禁止。ちなみに、東京の寄席は大阪と比べると、まったりしています。平日は客がまばらな日も多く、会場の中でいなり寿司なども置いていて飲食は自由。噺家の目の前を客が平気で出入りすることもあります。私は、東京の寄席の「ゆるい」感じも嫌いではありませんが、繁昌亭の寄席の熱気には大いに感銘を受けました。関西育ちながら、笑いを大切にする大阪の文化を侮っていました。大阪は、東京に比べると「ええ加減」であるという印象すら覆りました。
寄席の熱気は、2億円以上の寄付を集めてつくられた繁昌亭の設立経緯とも関わりがあるような気がします(開業は2006年。経緯は平田オリザさんが書かれた「新しい広場をつくる」に詳しく書かれています)。天井を見ると、スポンサーである天神橋筋商店街のお店や個人の名が書かれたおびただしい数の提灯が下がっています。大阪商人の心意気の表れと言えるでしょう。繁昌亭の近くには、食い倒れの街らしいふらっと立ち寄りたくなる飲食店がたくさんあります。寄席のお客さんや噺家が商店街に流れ、地域での交流も広がっているようです。
文化振興と言うと固いイメージを持っている人がいますが、文化は街づくりや地域社会と密接につながっています。むしろ、文化が介在しない経済だけのつながりは「金の切れ目が縁の切れ目」になりかねません。天神橋筋商店街の姿は、地域社会を考える上で大きなヒントとなりました。
中曽根康弘元総理は、「政治は文化に奉仕するもの」と発言されています。心したいと思います。

文科委員会での質問が終わりました。高校授業料無償化に所得制限をもうける法案についてです。質疑後に法案は可決されました。高校生の学びを社会が支える仕組みが崩れるのは残念です。
私が問題にしたのは、年収910万円以上(上から2割)の世帯の子どもに充てていた予算を削り、今後は授業料を有料にして、その削った分を年収250万円以下(下から12%)の世帯の子どもに回し、今までの分に上乗せして支給するという仕組み。高校生にもなれば本人は分かりますので、クラスの中で階級ができてしまう懸念があります。低所得者対策には賛成ですが、財源は新たに確保すべきです。ペイアズユーゴー原則は国家の論理。学校に持ち込むべきものではありません。
もう一つは、前年の所得で判断するので、親の失業や死別などの新たな事情が生じた場合に、対応できるか定かでない問題です。学校の設置者である都道府県が判断するとのことですが、個人のリスクを社会でカバーするという理念は薄れたと言わなければなりません。
米英仏などの先進国は、19世紀から戦時中には、高校の無償化を実現しています。もちろん所得制限はありません。貧しくとも、教育にお金をかけたわけです。日本の高校生の年齢は、義務教育になっている国も数多くあります。高校の授業料を「まずは家庭の責任に」という考えに私は賛成できません。

< みらいふくしまプロジェクト >
NPO法人みらいふくしま主催の『古田敦也さんの野球教室』を開催しました。
青空のもと、総勢150近い小学生や保護者の皆様にご参加いただきました。協力を頂いた皆さんに心より感謝申し上げます。
講師の古田さん、鈴木健さんのお二人ともさすがは元プロ野球選手、ウォーミングアップからひとつひとつの指導が行き届いています。

私もユニフォームをお借りし、初めから参加しました。青空の下で思いっきり身体を動かしすことができ、最高の一日となりました。


何より、子どもたちが元気いっぱいに笑顔でグランドを駆け回る姿に励まされました。
やはり、3.11以降、子供を外に出すことを躊躇した方が多く、野球をやる子供も減ったとのことです。挨拶の中で、子供たちと保護者の皆さんにお詫びを申し上げました。
これからも、福島の健康や安全の問題には、政治家として党派を越えて全力で取り組みます。そして、「みらいふくしま」の活動を通じて、様々なスポーツやリクリエーションを通じて、子どもたちが屋外でめいっぱい体を動かせるお手伝いをして行きたいと思います。
福島の未来を背負う彼らのために、私は全力を尽くします。皆さん、是非とも力を貸して下さい。
四号機プールの燃料取出しが間もなく始まります。新燃料を含む1535本の燃料棒を安全な場所に移すことは、廃炉に向けて極めて重要な一歩です。
2011年3月25日、「不測事態のシナリオの素描」(いわゆる最悪シナリオ)を受け取った時のことを思い出します。3.11以降、悪化する事態をあとから追いかけて対応していました。最悪の最悪を想定して対策を打つ。アプローチの転換が必要でした。
日米の大論争の中で、四号機プールに水があることは確認できました。我々が最も恐れたのは、そのプールが空になること。何としても、それだけは阻止しなければならない。プール底部を補強し、注水作業の自動化や不測の事態に備えた決死隊づくりまでやりました。
現場は汚染水をはじめ、数多くの難題を抱えています。対応が不十分なところもまだまだあります。しかし、困難な状況の中で、燃料取り出しについては、当初のロードマップ通り、2013年内に開始するところまでこぎ着けました。この点は高く評価されるべきです。私は、現場の皆さんの頑張りに心より敬意を表したいと思います。そして、これからも彼らを何としても支えていく決意です。
(写真は2012年5月四号機建屋内を視察した時に撮影したものです)
