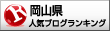手をつなぐ育成会の研修会に参加して
笠岡学園の講演会では、「親をサポートすることが大切」という点が強調されていました。発達障害のある子どもにとって、支援の有無が人生を大きく左右しますが、それは本人だけでなく家族のサポート体制にも大きく依存します。
特に、「困った子」と批判するのではなく、「困っている子」と捉える視点が重要であると感じました。これは、認知症の高齢者支援にも共通する考え方で、本人だけでなく家族の負担を軽減することが、より良い支援につながるという点で一致します。
また、困っている子どもは、どうしてよいかわからずパニックになっていることが多いです。そのため、暴れたりする子どもには対応がなされる一方で、困ったときに固まってしまう子どもは放置されてしまうケースもあるという指摘がありました。この点についても、支援のあり方を再考する必要があると感じました。
さらに、「SLD(限局性学習症)」と「LD(学習障害)」の違いについても学ぶことができました。SLDは医療の診断名として用いられ、LDは教育現場での支援カテゴリーとして扱われています。どちらも知的発達には問題がありませんが、特定の学習分野で困難を抱えるという共通点があります。
この講演を通じて、発達障害児の支援には、本人への直接的なサポートだけでなく、親や家庭環境への支援が不可欠であると改めて実感しました。社会全体での理解と体制づくりが必要であり、そのためには情報発信や啓発活動の重要性が増していると感じています。