飛火野の入り口にある雪消しの沢、という小さな水溜りの向こうに広がるのが飛火野。
向こうに見えているのは春日山と高円山。
そして大きな楠と、イチイガシ。
楠は一本のようにみえますが、実は三本の木なんですよね。
明治41年(1908年)に明治天皇が、陸軍の大演習で臨席された場所に記念に植えられた楠で、樹齢約100年。





飛火野にも藤棚。その下は直射日光を避けようと鹿の群れ。




さらに南へ降りてゆくと、藤棚ではなく、木に藤の蔓が巻きついて、あちらこちらに藤の花。









このあと春日大社へと思っていたのですが、疲れてしまって引き返します。
飛火野から国道を隔てたところにも藤棚。


そこから西へ向うと興福寺です。
五重塔と南円堂


いつものごとく、南円堂の観音様へお経を唱えてお参り。
南円堂の南東にある藤棚ですが、八重の藤のようです。




また南円堂の前の橘の花が咲き、実もなっているようです。
アゲハチョウやミツバチが飛び交っています。
葉にはアゲハチョウの黒い幼虫も見えていますね。






三条通のみやげ物店。



近鉄奈良駅行基広場の大屋根の工事が随分進んで着ました。
行基様がむいているのは東大寺大仏様ということです。


近鉄奈良駅のちかくのミスドで一服。
万歩計を見ると9800歩・・・














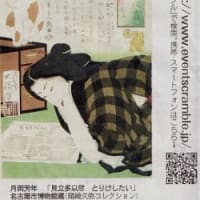
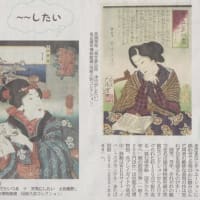





なんか北円堂のライト当ててるのは、見やすいけどやっぱり自然光がいいなと思いました。
藤もちょうどよい時期でいっぱい咲いててよかったです。
次の日京都・狩野山楽 山雪見に行きました。
チケットにもなってる出口のとこにあった山雪さん屏風の右そうの雪の積もった松の枝がうさぎに見えるのなかったですか?
後ろ足もあります。私だけでしょうか?完全にうさぎに見えました。ユーモア入れてはるんやぁと思ったんですが。
やはり慶派も狩野派もすごかったです。
興福寺は自分が訪れたときには長い列やったのに、
帰りに見たときは列なんてなくって・・
日によって、時間によって違うんですね。
京都国立博物館の「雪汀水禽図屏風」、自分は千鳥の隊列に目を奪われ、そこには目が行きませんでした。