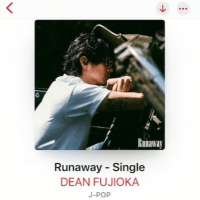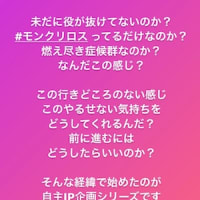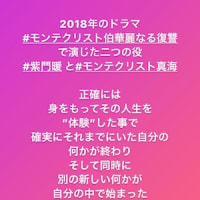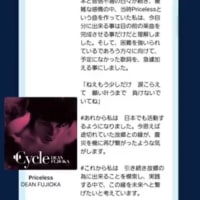梅だけじゃなかったの、2/19日曜日の京都。
「京の冬の旅」2017のテーマは<大政奉還150>。
大政奉還に限らず幕末の歴史にまつわる特別公開がいろいろ。
ただリストアップされているほとんど行き尽くしており。
1月に壬生寺(Good)ともう一カ寺(落胆)に行き、もういいかな〜
と思っていたところへ、TVの「ぶらぶら美術・博物館」をチェック
すると、聖護院が前回の公開内容とかなり違うじゃないですか!
寺社めぐりをしていて仏像ファンの心を曇らせる出来事といえば、廃仏
毀釈と信長の焼き討ちと応仁の乱。特に廃仏毀釈はねぇ〜。
ここ聖護院が皇室ゆかりの門跡寺院で、総本山であったことが幸いして、
今も多種多様な仏像が見られるのは本当にありがたい。

山伏で知られる本山修験宗の総本山。末寺の多くが廃寺となるも、その
仏像や仏具を聖護院が引き継いだことで神仏分離による廃仏毀釈の難を
免れたそうだ。
特に珍しいのが、旧才智院の本尊で今回初公開の「弁才天尊」。
今回は修復後の綺麗なお顔を拝観できた。最近、修復のために古い衣を
除いたところ、作られた当時の鮮やかな彩色が現れたとのこと。
他ではあまり見られない弁才天像だった。

宸殿があるのも門跡寺院ならでは。江戸狩野派・京狩野派の障壁画や、
仏間には修験道開祖の役行者の像、不動明王像など。
他のお寺から移されたというかなり大きな不動明王像があった。
本堂は奥にあり、金庫扉のような頑丈なお厨子に安置されているのは、
智証大師作と伝わる本尊・不動明王立像(重文)、智証大師像(重文)。
御所から移築された書院は、後水尾天皇らしい風雅なこだわりが見られ、
人心地のするほっと落ち着ける部屋という感じ。
1月に行った壬生寺もよかった。
幕末の新選組ゆかりの寺ということで今年公開となっているそうだけど、
本当の特別公開はふだん非公開の、本堂と狂言堂。


本堂に安置されている地蔵菩薩は、本堂再建時に奈良の唐招提寺から移さ
れた大きなお像で、衣の截金文様がきれいに残っていた。
また、国宝「鑑真和上座像」の複製2体を日中共同で製作、そのうちの
1体が壬生寺の本堂に安置され、初公開中。
「鑑真和上座像」は唐招提寺の本物と御身代わり像、それにこの壬生寺
の複製の3つを見たことになる。


もう一つの楽しみは、壬生狂言で知られる狂言堂(重文)の内部公開。
狂言の衣装やお面、小道具などが展示され、若冲が奉納したお面もあった。
前に一度、ほうらくのお皿を奉納した際に狂言を見ようとして、あまり
の混雑に逃げ帰ったことがある。節分会の壬生狂言では積み上げた大量の
皿を落として割る「焙烙割」が有名だそう。
あとは4月と10月。台詞のない無言劇だ。
ナルホド〜、舞台の方から見るとこんな感じなのかというのがわかった。
本当はもう1ついったのだけど、書きたくないので書かない。

お寺を3つ回ったので、いつものように俵屋吉富さんの「京菓子資料館」
でお抹茶と和菓子をいただきました。
「京の冬の旅」2017のテーマは<大政奉還150>。
大政奉還に限らず幕末の歴史にまつわる特別公開がいろいろ。
ただリストアップされているほとんど行き尽くしており。
1月に壬生寺(Good)ともう一カ寺(落胆)に行き、もういいかな〜
と思っていたところへ、TVの「ぶらぶら美術・博物館」をチェック
すると、聖護院が前回の公開内容とかなり違うじゃないですか!
寺社めぐりをしていて仏像ファンの心を曇らせる出来事といえば、廃仏
毀釈と信長の焼き討ちと応仁の乱。特に廃仏毀釈はねぇ〜。
ここ聖護院が皇室ゆかりの門跡寺院で、総本山であったことが幸いして、
今も多種多様な仏像が見られるのは本当にありがたい。

山伏で知られる本山修験宗の総本山。末寺の多くが廃寺となるも、その
仏像や仏具を聖護院が引き継いだことで神仏分離による廃仏毀釈の難を
免れたそうだ。
特に珍しいのが、旧才智院の本尊で今回初公開の「弁才天尊」。
今回は修復後の綺麗なお顔を拝観できた。最近、修復のために古い衣を
除いたところ、作られた当時の鮮やかな彩色が現れたとのこと。
他ではあまり見られない弁才天像だった。

宸殿があるのも門跡寺院ならでは。江戸狩野派・京狩野派の障壁画や、
仏間には修験道開祖の役行者の像、不動明王像など。
他のお寺から移されたというかなり大きな不動明王像があった。
本堂は奥にあり、金庫扉のような頑丈なお厨子に安置されているのは、
智証大師作と伝わる本尊・不動明王立像(重文)、智証大師像(重文)。
御所から移築された書院は、後水尾天皇らしい風雅なこだわりが見られ、
人心地のするほっと落ち着ける部屋という感じ。
1月に行った壬生寺もよかった。
幕末の新選組ゆかりの寺ということで今年公開となっているそうだけど、
本当の特別公開はふだん非公開の、本堂と狂言堂。


本堂に安置されている地蔵菩薩は、本堂再建時に奈良の唐招提寺から移さ
れた大きなお像で、衣の截金文様がきれいに残っていた。
また、国宝「鑑真和上座像」の複製2体を日中共同で製作、そのうちの
1体が壬生寺の本堂に安置され、初公開中。
「鑑真和上座像」は唐招提寺の本物と御身代わり像、それにこの壬生寺
の複製の3つを見たことになる。


もう一つの楽しみは、壬生狂言で知られる狂言堂(重文)の内部公開。
狂言の衣装やお面、小道具などが展示され、若冲が奉納したお面もあった。
前に一度、ほうらくのお皿を奉納した際に狂言を見ようとして、あまり
の混雑に逃げ帰ったことがある。節分会の壬生狂言では積み上げた大量の
皿を落として割る「焙烙割」が有名だそう。
あとは4月と10月。台詞のない無言劇だ。
ナルホド〜、舞台の方から見るとこんな感じなのかというのがわかった。
本当はもう1ついったのだけど、書きたくないので書かない。

お寺を3つ回ったので、いつものように俵屋吉富さんの「京菓子資料館」
でお抹茶と和菓子をいただきました。