「私の病院は、最低限15分に一度の巡回をしています」
もし、このような精神科病院があれば日本指折りの病院か恥を知らない低レベルの病院だ。まず最初に言っておくが、隔離拘束患者の15分に一度の巡回など到底不可能である。
恥ずかしきは、日本医療機能評価機構に評価項目として設定されている(書類を手にしたことがないが、間違っていなければ)ということである。もし、“隔離拘束患者に対して最低限15分に一度の巡回を実施する”という項目が本当に存在するのであれば、その項目の提案者は、無能もしくは虚飾好きの人間だろう。また、その項目を採用した日本医療機能評価機構の存在意義もない。
ある時期、他の第三者機関ともその話をしたことがある。返ってきた返事は、
「どうして不可能なのですか」
という返事だった。いずれも、患者を救済する団体であったり、職員の労働条件を保障しようとするような団体であったが、この程度の反応。現場を把握しなければならないはずの団体がこの程度の“眼”しかもたないのであれば、偽善活動と思われても仕方ない。今即刻解散するべきだ。また、それらの団体が各々の病院長などと馴れ合いになっているのであれば、私はそれも問題にする必要があると考えている(実際なっているが)。
先日、日本医療機能評価機構に、“評価の際、15分に一度の巡回をどのように確認しているか”という旨のメールを送った事もあるが一向に返事がない。メールの後変わったことといえば、ホームページのトップに“自己責任原則について”という説明が付加されただけ(私の記憶では、メールを送る前はそのような項目はなかったと記憶している)の不親切且つ傲慢な対応。
確実に15分に一度の巡回ができているかを確認するには抜き打ちで評価をしにいくしかない。他にも、総室での身体拘束は事実上禁止されているが、これも抜き打ちで評価に行けば、ほとんどの病院は拘束を実施しているのではないだろうか。
改めて第三者機関へ問う。
※隔離拘束患者の巡回に関する問題を考え直すつもりはないのか。そして、第三者機関として、それを平然と受け入れていることに恥じらいを感じはしないのか。
公平をアピールしている第三者機関の瞞着はもう許されない。見栄のみで経営している患者無視の病院経営者も自らの無能さを感じ取れ。
私は、NPOの活動を通して今後も積極的に、精神科を中心とした隔離拘束患者に対する問題に関わっていくつもりである。




 最近ますます面白くない記事になってきて重症ですが、一つずつクリック願いま~す。面倒くさいのはわかってます!!でもお願いします!!!
最近ますます面白くない記事になってきて重症ですが、一つずつクリック願いま~す。面倒くさいのはわかってます!!でもお願いします!!!
最後までご閲覧いただきありがとうございます。拙著本「精神科看護師、謀反」も看護の参考にしていただければ幸いです。
もし、このような精神科病院があれば日本指折りの病院か恥を知らない低レベルの病院だ。まず最初に言っておくが、隔離拘束患者の15分に一度の巡回など到底不可能である。
恥ずかしきは、日本医療機能評価機構に評価項目として設定されている(書類を手にしたことがないが、間違っていなければ)ということである。もし、“隔離拘束患者に対して最低限15分に一度の巡回を実施する”という項目が本当に存在するのであれば、その項目の提案者は、無能もしくは虚飾好きの人間だろう。また、その項目を採用した日本医療機能評価機構の存在意義もない。
ある時期、他の第三者機関ともその話をしたことがある。返ってきた返事は、
「どうして不可能なのですか」
という返事だった。いずれも、患者を救済する団体であったり、職員の労働条件を保障しようとするような団体であったが、この程度の反応。現場を把握しなければならないはずの団体がこの程度の“眼”しかもたないのであれば、偽善活動と思われても仕方ない。今即刻解散するべきだ。また、それらの団体が各々の病院長などと馴れ合いになっているのであれば、私はそれも問題にする必要があると考えている(実際なっているが)。
先日、日本医療機能評価機構に、“評価の際、15分に一度の巡回をどのように確認しているか”という旨のメールを送った事もあるが一向に返事がない。メールの後変わったことといえば、ホームページのトップに“自己責任原則について”という説明が付加されただけ(私の記憶では、メールを送る前はそのような項目はなかったと記憶している)の不親切且つ傲慢な対応。
確実に15分に一度の巡回ができているかを確認するには抜き打ちで評価をしにいくしかない。他にも、総室での身体拘束は事実上禁止されているが、これも抜き打ちで評価に行けば、ほとんどの病院は拘束を実施しているのではないだろうか。
改めて第三者機関へ問う。
※隔離拘束患者の巡回に関する問題を考え直すつもりはないのか。そして、第三者機関として、それを平然と受け入れていることに恥じらいを感じはしないのか。
公平をアピールしている第三者機関の瞞着はもう許されない。見栄のみで経営している患者無視の病院経営者も自らの無能さを感じ取れ。
私は、NPOの活動を通して今後も積極的に、精神科を中心とした隔離拘束患者に対する問題に関わっていくつもりである。


 最近ますます面白くない記事になってきて重症ですが、一つずつクリック願いま~す。面倒くさいのはわかってます!!でもお願いします!!!
最近ますます面白くない記事になってきて重症ですが、一つずつクリック願いま~す。面倒くさいのはわかってます!!でもお願いします!!!最後までご閲覧いただきありがとうございます。拙著本「精神科看護師、謀反」も看護の参考にしていただければ幸いです。











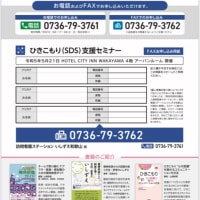

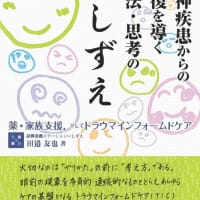

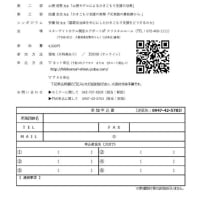
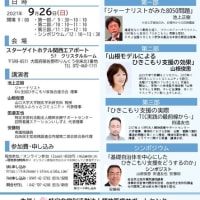
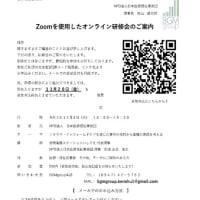
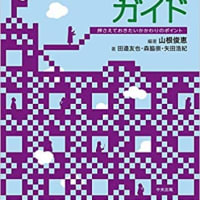
できれば、メールでどういう状況下教えていただけませんか?デスさんはご理解されていると思いますが、もちろん密告などというのではなく、私が多方の精神科の現状を知るという意味でですのでご協力お願いします!
早くからコメントを拝見しておりましたが、お返事をできずにおりました。
学生の受け入れ病院の件ですが、精神科では特に“間違ったこと”を教えられていないのか心配になります。実際、私が学生のとき実習先の病院の主任が、ルールを守れない患者に対し「記録に書くぞ!」と小声で脅しているのを見ました。これは学生時代の話ですが、今でもりえママさんのおっしゃるような現状は、日本中の精神科で散発していると思います。なんとか変えてゆきたいものですが、活動は思うようにいかないものです。
お返事遅くなりました。
私はバイクSR400を一応所有しおりますが、友人の店に預けっぱなしです・・・・
ゆっくりとのりたいのですが、今の職場では時間はありませんね(涙)
私にツッコまれているようでは、プロ失格だと思うのですが、そこの方々はかなりプライドの高い方たちのようで・・・
看護学生ですら鼻持ちならないようです。
詳しくは掛けませんけど、もし私が上司だったら、片っ端から鼻を折ってやるところですわ。
ほぼ完全余談。
バイクも「乗る!」と意気込んで買った刀400(所有10年ちょっと、走行1万キロ弱)を近々売ります。
大型取ってbigバイクを欲しがったら、嫁から「乗れてるの?」(注:「乗るの?」じゃない:マルチ&400以上じゃないとバイクじゃないという嫁談)と言われて断念。
上記のような理由(?)で続かない(確信)のでスレでご容赦を。
偶然ですが、私も精神科時代によく「トラップにやられた」とぼやいていたことがありました。私の集中力不足で、それが生じたこともあったのですが、ゆる看さんでいう雑巾の重ね拭きが“何度も戻って同じところを”拭く上体でないと防げない事故があったりもしました。もちろん、そのミスのおかげで自分が成長した経過もあるのですが、最終的に影響するのは患者であるわけですから、そのトラップの幅は、看護師同士で狭めておく必要はありますね。トラップは狭めるが、重ねぶきはできるだけ大きく。ということですね。
いつもわかりやすい例えです。
PS:またなにか、ピンとくるネタがありましたら、はやめにブログ更新しますね。
もっさんの言われるよう「ここからここまで」は、この重なりを意識するように気をつけてます。また、同僚や後輩にも言っています。
一番事故が起こりやすい部分ですし。
余談ですが、私は「事故」のきっかけを作る行為を『トラップ』と公言しています。
無意識のミスや良かれと思ってやった中途半端な仕事(言われてすることは『作業』、見つけてすることは『仕事』:私の指導者だった人の言葉です)などです。
重なりを意識していないと、「○○してくれているだろう」と都合のいい解釈で『トラップ』に引っかかります。
お話、わかります。単純に、“ここからここまでが、看護助手の仕事でここからここまでは、看護師の仕事。だから、私達には関係がない。”的な発想を持っている人は少なくなかったです。業務の基本的大枠は必要としても、資格を要する業務内容でなければ、状況によっては、助け合いがあってもよいのですが、なかなかそういう発想にはたどり着かないようでした。
ポータブルトイレの話ですが、精神科では、しっかりと訴えることができない人が多いので、看護者側の人間の感情が鈍り、そして麻痺する傾向が多々見られますね。感情育成・コントロールは教育システムがキーだと思っています。ですから、ゆる看さんのようなしっかりと指導できる人に育て上げる教育システムとその配置が必要ではないでしょうか。もちろん、そのような病院はまったくそういう視点に立てていないのが現状でしょうが、ほとんどの精神科はまだ、こういう状況でしょうね。
ゆる看さんのおっしゃるように、トイレ掃除はしますね。私のいた病院では基本的に掃除系統はヘルパー・助手さんがしてましたが、人手によっては看護師もしていました。というか、トイレの掃除をしないというと・・・、便器が詰まってたり、汚れてたりしたらどうするんですかね。精神科では、頻繁に便器が詰まるんですが。タイルの床にべんが落ちてたりもよくありますけどね・・・・。その病院のトイレ、見てみたいです。
助手さんの言葉からして、スタッフのチームワークはうまくいってないんでしょうかね。かなり、看護師が偉くて、助手さんは手伝い的な雰囲気が伝わってきますが。
看護助手に依頼することもあります。便の性状・量などは確認します。
トイレ繋がりの余談(?)ですが、
昔、准看実習の時、「使用後の尿・便器・ポータブルトイレを、綺麗に洗うのも仕事です。汚れが付いたまま使わされる気持ちになってみて。」と言われました。
しかし、助手さんを多く雇用している病院、看護師と看護助手との関係が悪い(看護師or看護助手どちらかが働かない)病院、一部の正看実習先、一部の勘違い看護師&看護学生・・など
「自分達の仕事じゃない」と思っている人がいます。
お尻吹く前に、責任の所在を明確にしたり、マニュアル作り。
「そっちが先かよ!そこまで明文化が必要なのかよ!」
自分(または自分の家族)がイヤなことは、人もイヤと分からなくなる。自分の仕事が増えると感じただけで、それだけで。説明しても不承不承・・ってな感じです。人当たり上手の逃げ上手。
私の思い過ごしかもしれませんが、
准看卒後の座学学習は皆無で、知識・技術の取得はOJTのみの人ほど、「情」を持ち合わせている場合が多い様に感じます。
一般人である私がプロの皆さんの意見交換に飛び込むのは、如何なものかと思っておりましたが、何とかついていけるように勉強しますわ。
ところで嫁さんの病院ですが、何と用便後の清拭をしないんだそうです。
清掃&介護の方たちは、「看護師の仕事なんだし、やると看護師に文句を言われるよ」と言うのだそうですが、肝心の看護師は清拭なんぞやらないとのこと。
それってどうなんですかね?
素人の私から観ても問題大ありなんですが、精神科の閉鎖病棟はこのへんではかなり少ないために、ほぼ満床状態だそうです。
忙しいのも分かる気はしますが、介護士上がりの嫁さんには許せないようで・・・
とりあえず院長に突っ込みいれとけ、と言っておきました。
その存在は必要だと思います。
馴れ馴れしいコメントすみません。
デスさんの登場はいつも心待ちにしているんですよ。なにせ、ブログを始めた当初 から交流がある人なんですから。私の相棒も、「デスさん最近どうしたん?」といってます。早く元気に・・・とせかしても仕方ないですよね。
奥さんの隔離病棟でのお話、早く聞きたいですね。
私はと言うと、相も変わらず家にいるしかない状況で、早く仕事を開始したいのですが、今の会社はもう居場所が無さそうです。
もっさんのブログは意見交換が盛んでとても良い場所になりましたね。
もはや私の出る幕がない気もしますが・・・
いつも、ブログ拝見しております。独特の視点から、独特の論をお持ちのwoainiさんの意見はいつも参考にさせていただいております。また、その看護大学の環境の中ですごされているwoainiさんの人間性もよく見えてきて面白いです。
ご遠慮なく意見交換お願いしますね。
藁の家、木・レンガの家。すごく良いたとえだと思います。評価機構に落ちることで、逆に通ることで周囲の意識がどう変わるかということは、ある意味評価機構の功の部分であるとは思いますね。ふむふむ。
記事を読んでみましたが、精神科のお話って独特ですね。私も授業で受けたりしてますが、まだあんまり「分かった!」という体験はないです。もっと勉強します!と言えればいいんですが、そう言える余裕もないです。残念。なので、マイペースですけど読ませていただきますので、たまには議論に参加させて下さい。
ではでは!
>作>ろうと考えるという思考が必要じゃないん>ですかね。
御意。しかし差し迫った機能評価のために、矛盾を感じつつも当座の藁の家作りに必死です。協力的にかかわっていますが、問題提起もしています・・・。
ダイエーの頃の、城島が工藤投手についてTVで語っていました。ダイエーに居た頃の工藤投手が、城島のサインに頷かず、投げた球をホームランされたそうです。
城島:「サインのところに投げていたら打たれなかったと思います。」
工藤:「打たれると分かっていても、あの時はそこに投げるべきだったんだ。次の回の為に。」といったそうです。
城島:「今になってわかります。育ててもらったことが。」と。
今回の(評価能力に疑問のある)機能評価に落ちたとき、木かレンガで家を造ろうと思いはじめる人が増えるように思います。利用者の視点で、そして、患者さんも職員も好きなウチの病院のスタンスで。
寝ようとTVを見ていたところ、今の職場の看護師のあり方などを考えており、寝られずにおりました。
理想の業務と無駄な業務ですが、基本的には無駄な業務を理想に業務に近づけるべきですよね。しかし、現実は現実することができる立場にある人間が、そのレベルにいるかどうか。実は、そういう実現力のある人間は異端視されているように思います。画期的実現力のある人間が、看護という道一本に絞って改革を行った人間はどれだけいるかですが、ほんの一握りと表現しても大げさではないと思います。
最大のテーマである、「看護の質を落とさず効率的に。」ということに取り組めた人物はどこにいるのでしょう。これが理論化されれば、時代時代の看護理論化に並ぶのではと思っています。
現在の私の病院では、知識や技術に長けた看護師は沢山います。しかし、前述のテーマについては誰一人考えようとしません。幹部クラスでも然りです。
単体としての知識や技術は、前述のテーマにかなうことはないと思っています。これは、ゆる看さんが最後におっしゃっている
「真剣な人々」は、「チームワークでも若干注意が必要なことが多い」
ということにも当てはまると思います。この、「アイコンタクト」が看護の効率性を実現させる一材料であることはいうまでもありません。しかし、いわゆる、「真剣な人」は、そこに議論を持ち込もうとしません。以前の病院の看護長は、まだ理論武装(無駄なものですが、部下には有効な武器でした)程度のものはできていたものですが、これは精神科看護師特有の武器なのでしょうか。今の外科病棟には、そのような理論武装をした看護師すら存在しません。そこには、知識と技術を盾と矛代わりに経験の浅い看護師たちを威圧している看護師には欠けてはならない初歩的な、心構えが欠けてしまったただの人間が存在するのみです。
10年ほど前、いいえ、ほんの5~6年ほど前までは、患者と外に行くことは頻繁でした。利益主義が表にでてきだしたその頃から、すべて利益に繋がらない、リスクの高いことはするなという風潮になりました。すべて利益主義がそうさせたのでしょうが、その仕組みを作った国にも問題がありますし、それをそのまま短絡的に受け入れた経営者側にも問題があると思います。それを評価しようにも、雇われている側は、言うことを聞くしかありません。決められた枠の中で改革を行っていくしかありません。もちろんそこには限界があります。行き着くところは、病院経営の株式化ですが、今は触れないことにしましょうか・・・・・。
絵に描いたもちの食べ方を考えるというよりも、絵に描いたもちをイメージし、実際にもちを作ろうと考えるという思考が必要じゃないんですかね。看護診断・看護計画そのものは否定しませんでしたし、その他の沢山の委員会も私は否定しませんでした。否定されるべきは、その中身であり、与えられたなかでそれをどう変えるかは考える価値のあるものだと思っています。
志半ばで、ご存知のような結果になりましたが・・・・・、仕事は結構楽しかったんですよね・・・・・。今でも、患者さんとの冗談のいいあいが思い浮かびます。
私や、昔の当院を「好き」と言い切れるスタッフの中には、タイトルのようなジレンマが常にあるように感じます。
「看護記録」「機能評価」・・・
みんなで真剣に「絵に描いた餅」(言い切ってしまうのも淋しいですが)の食べ方を考えているような・・
それが、看護の質の低下に影響していると、「真剣な人々」にモチベーションを下げないように気を遣って言ってみても
「やらなければいけないと決まっているんです。」
と言われます。
「御時世」とやらにマインドコントロールされているみたいで・・
10年ほど前は、閉鎖病棟の患者さんとよく遠出の散歩に行きました。隔離室の患者さんとも、病院敷地内を歩く程度の散歩はよく言ってました。今は、その時間が記録やチェック、委員会、マニュアル作成にあてられてしまっています。
あの「ゆるさ」(昔、映画で見た、自然治癒力を高めるような結核のサナトリウムの雰囲気)が療養には必要じゃないのかなと、口にはしています。
「真剣な人々」は、「チームワーク」でも若干の注意が必要なことが多いようです。
往々にして「アイコンタクト」がとれません。
なんとなく理論(のみの)武装の弊害のように感じています。
抽象的で申し訳ありません。
度々のレス、ありがとうございます。詳しく述べることは控えますが、ゆる看さんは、特別な立場にある方とお察しします。
もし、患者の不利益にならない程度(わかりやすく、噛み砕いて説明してくださった体と思いますが)との認識でのものであれば、それは実に的外れな機能となってしまっているように思います。直接的には、患者に不利益になっていないかもしれませんが、無駄な業務(チェックリストへの記入など)の増加で間接的に、看護の質を低下させています。さらに現場の看護師ではありえない感覚が、上層部ではまかり通ってしまい、上部と下部との患者や看護への認識の格差が広がってしまうという状況を生んでいます。
自己評価調査票の内容に関しては、直接は存じませんが、日本医療機能評価機構という立場に対してのそれは、非常に低レベルなものと考え、私個人としては評価しがたい部分があります。
存在継続理由に関しましては、おっしゃるとおり、今後の活動状況しだいでしょうね。
自己評価調査票をまとめたことは評価するとして、存在継続理由は、今後評価機構の方の活動状況でハッキリするのでしょう。
ゆるく自己評価調査票=看護実習要綱のような感じで受け止めてます。
あ、調査能力、と言った方が誤解がないですかね。チェック項目にあることをまともに調査できない機関ってことです。その低い能力であることを前提としてみた場合、機能の標準化ということに関しても、必然的に疑問を抱かざるを得ないでしょう。
たしかに、日本全国の病院機能のの底上げに役立ったことは、評価できますが、評価機構の設立の趣旨など文面で謳っている文句動きの中からはまったく見えてこないのですから、第三者機関を名乗られても不信感を抱かざるを得ませんよね。
>監視能力のない機関が必要あると思いますか?
思いません。監視は一部を除いて不可能だと思います。監視能力のある機関だったとしてもこの基準で、病院の質を決定するとなると、微妙なズレを感じます。病院機能を標準化できるとは思っているのでしょう。
復活は急ぐことありません^^
奥さんが、精神科で勤務ですか!色々お話を伺いたいですねー。
私も直接的には精神科を離れてしまっているので、いろいろな情報をいただければと思います。
まぁ、ぼちぼちいきましょう!
夜勤でも15分に一度としているのに、それをそのまま巡回できていると思っている評価機構が問題でしょう。そのような、監視能力のない機関が必要あると思いますか?全否定するわけではありませんが、第三者機関として公平を称しているのであれば、そのあたりのいい加減さと、メールを無視するような傲慢さは改善すべきですよね。
でも体調はまだダメです。
隔離拘束患者に対する巡回という項目、15分に一度と明記されていたかどうか、失念してしまいましたが、JCQHCのことだからきっと明文化していることでしょう。
我が家の嫁さんがふとしたことから、精神科隔離病棟での介護に就くことになりました。
その状況を見て、また色々と意見交換させていただければと思います。
「15分」ていうのは、いけないと思いつつ笑ってしまいます。
ウチの病院は、5隔離室あります。
日勤では、1名の看護師が担当します。
何分おきと言うのは心がけたことはないですが、午前中などは、意図的に、それ以上患者さんの視野に入る動きをすることがあります。
呼ばれれば行くし(状態次第ですが。当然、訪室が症状増悪させるようなら控えます)、声をかけに行きます。「来るな!」と言われれば行きませんが、攻撃をされるだけなら、メゲズに行きます。
「何か用はないですかぁ?」
「今飲んでいる薬は、どうですか?」
「タバコすうなら、一緒に吸おう。」など。
すると、午後から皆さん落ち着くことが多いように思います。午後の「15分巡回」は、かえってウザがられるか、再燃させてしまうことが多いように思います。
夜勤は、隔離込みで60人前後の患者さんを2人で対応するため、「15」は無理です。しかし、勤務交代直後は、頻回に訪室することがあります。
「居る」と言うことが伝わるだけで、「休養」できることがあるので。
確かにそうですよ。病院によっては、15分に一度のチェック用紙のようなものがあって、そこにチェックを入れていったりしてるようですが、後でまとめ書きをしているようじゃぁしないほうがまし。
今回の記事、かなり気合を入れて書いたのですが、変なところをクリックして全部消えたので一度書き直したんです・・・・・。ちょっと手抜き文章ですが(汗)
巡回したときに何を見て、どう対応するかの方に力を入れようと思っていますが・・・。まぁ自信ないので、もっさんの考えと違ったら意見ください。