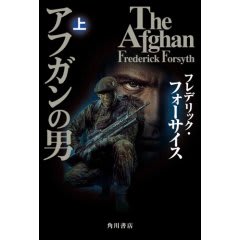
英国人作家フレデリック・フォーサイスの最新作『アフガンの男』(角川書店)を読了。題名どおり物語で重要な鍵となるのが、元タリバーンの司令官だったアフガン男。連帯し西側でテロを起こそうとするアルカーイダはじめ各イスラム過激派と、それを阻止する英米両国の情報部員とのサスペンス。中東に関心のない方でも読みやすい小説だと思う。
長年に亘りフォーサイスは私のお気に入りの作家であり、彼の小説の殆どは読んでいる。だが、この作品は期待外れだった。ベテラン作家だけありストーリーはそつないが、フォーサイス小説によくある最後のどんでん返しが今回は無く、これには拍子抜けした。何よりも強く感じたのは、フォーサイスのイスラム世界の捉え方に疑念を抱いた。いかにイスラム学者ではないにせよ、彼はあまり中東のことをよく判っていないのではないか。元からフォーサイスは英国文化人からも右翼作家、筋金入りのタカ派などと仇名されており、特に最新作には彼の英国ナショナリズムが鼻をつく。
巻末に日本人作家・真山仁氏の解説があった。真山氏もまた学生時代からフォーサイス作品を見ており、小説家になったのはフォーサイスの影響を受けたためと記している。真山氏は今年の4月、ロンドンでフォーサイスとの会見も行っており、インタビューでのフォーサイスの自説は実に興味深かったので、挙げてみたい。
-欧米、中でもアメリカ人の多くは、イスラムの人たちを知ろうとすらしていない。そして、誤った先入観に踊らされる。これぞ悲劇です。まず正しく理解しなければ、問題の本質は浮かび上がってきません。
全く反論の余地も無い正論である。そのフォーサイスのイスラム観は以下の通り。
-千年前、西洋人に文化や技術を教えたのはアラブ人です。それが今から5百年ほど前に、完全に逆転してしまう。以来アラブ人は、恨みと妬みの歳月を今に至るまで持ち続けることになる訳です。さらにイスラム教という、キリスト教的発想では理解出来ない宗教が絡み、彼らの憎悪は増幅されていきます。石油という大きな天の恵みを得たにも係らず、アラブは先進国になり損ね、もはや何も出来なくなっていた。結局は欧米人の搾取に耐えるしかなかった。そんな不条理が長年蓄積された憎悪のマグマとなり、9.11という形で爆発したのです。
フォーサイスは小説を書く際、綿密な取材をすることで知られる作家だが、上記の解釈ならば、英国人の彼もイスラムを正しく理解しているか、甚だ疑問である。まず、アラブが5百年ほど前、西洋に完全逆転されてしまうというのは間違いだ。アラブは既に十字軍時代からテュルク(トルコ)系のセルジューク朝に支配され、5百年前はオスマン帝国の支配下にあった。当時のオスマン朝は逆転どころか最盛期であり、第一次ウィーン包囲(1529年)をやってのけている。この包囲は“神風”により辛うじて守られた元寇の様に、冬将軍の到来でウィーンの陥落だけは免れたものであり、逆転より失点が相応しい。
それまで地中海でトルコ艦隊にヤラレ放題だった西欧が、レパントの海戦(1571年)の大勝利で転機を向かえたとの見方が一般的だが、依然オスマン帝国の軍事的優位は続く。オスマン帝国は敗戦の6ヶ月後、再び大艦隊を編成、ヴェネツィア領土を奪うほどだった。ただ、レパントの海戦後、西地中海の制海権を無くしており、逆転の始まりになったのは事実である。
トルコの衰退を決定的に印象付けたのは第二次ウィーン包囲(1683年)であり、加えて台頭するロシアの脅威に悩まされることになる。この間アラブはトルコと共存しており、西洋との戦も殆どトルコ人や元キリスト教徒子弟のイェニチェリの役割だった。アラブもトルコも十字軍を忘れた訳ではなかったが、アラブ人が西洋に恨み妬みを再認識するのはむしろ近代に入ってからではないか。かつての野蛮な西洋が優位に立ったのだから。
フォーサイスはアラブ人の恨みと憎悪を指摘し、私もそれは間違っていないと思う。だが、同時に西洋人も劣らずイラスム世界に対し憎悪を抱いていたのではないか。十字軍の敗北とそれに反撃するオスマン朝の台頭は屈辱と脅威だったのは明らか。戦後に植民地を手放す羽目になったことも、憎しみを拡幅させるのに十分過ぎる。日本のマスコミが知日派と持ち上げるロナルド・ドーアなる英国人学者も、昨年夏私と交わしたメールで、日本のナショナリズムの背景は西洋諸国への恨みと記していた。
その②に続く
◆関連記事:「アヴェンジャー」
「テロリズム-まず憎悪ありき」
「アラブが見た十字軍」
よろしかったら、クリックお願いします


長年に亘りフォーサイスは私のお気に入りの作家であり、彼の小説の殆どは読んでいる。だが、この作品は期待外れだった。ベテラン作家だけありストーリーはそつないが、フォーサイス小説によくある最後のどんでん返しが今回は無く、これには拍子抜けした。何よりも強く感じたのは、フォーサイスのイスラム世界の捉え方に疑念を抱いた。いかにイスラム学者ではないにせよ、彼はあまり中東のことをよく判っていないのではないか。元からフォーサイスは英国文化人からも右翼作家、筋金入りのタカ派などと仇名されており、特に最新作には彼の英国ナショナリズムが鼻をつく。
巻末に日本人作家・真山仁氏の解説があった。真山氏もまた学生時代からフォーサイス作品を見ており、小説家になったのはフォーサイスの影響を受けたためと記している。真山氏は今年の4月、ロンドンでフォーサイスとの会見も行っており、インタビューでのフォーサイスの自説は実に興味深かったので、挙げてみたい。
-欧米、中でもアメリカ人の多くは、イスラムの人たちを知ろうとすらしていない。そして、誤った先入観に踊らされる。これぞ悲劇です。まず正しく理解しなければ、問題の本質は浮かび上がってきません。
全く反論の余地も無い正論である。そのフォーサイスのイスラム観は以下の通り。
-千年前、西洋人に文化や技術を教えたのはアラブ人です。それが今から5百年ほど前に、完全に逆転してしまう。以来アラブ人は、恨みと妬みの歳月を今に至るまで持ち続けることになる訳です。さらにイスラム教という、キリスト教的発想では理解出来ない宗教が絡み、彼らの憎悪は増幅されていきます。石油という大きな天の恵みを得たにも係らず、アラブは先進国になり損ね、もはや何も出来なくなっていた。結局は欧米人の搾取に耐えるしかなかった。そんな不条理が長年蓄積された憎悪のマグマとなり、9.11という形で爆発したのです。
フォーサイスは小説を書く際、綿密な取材をすることで知られる作家だが、上記の解釈ならば、英国人の彼もイスラムを正しく理解しているか、甚だ疑問である。まず、アラブが5百年ほど前、西洋に完全逆転されてしまうというのは間違いだ。アラブは既に十字軍時代からテュルク(トルコ)系のセルジューク朝に支配され、5百年前はオスマン帝国の支配下にあった。当時のオスマン朝は逆転どころか最盛期であり、第一次ウィーン包囲(1529年)をやってのけている。この包囲は“神風”により辛うじて守られた元寇の様に、冬将軍の到来でウィーンの陥落だけは免れたものであり、逆転より失点が相応しい。
それまで地中海でトルコ艦隊にヤラレ放題だった西欧が、レパントの海戦(1571年)の大勝利で転機を向かえたとの見方が一般的だが、依然オスマン帝国の軍事的優位は続く。オスマン帝国は敗戦の6ヶ月後、再び大艦隊を編成、ヴェネツィア領土を奪うほどだった。ただ、レパントの海戦後、西地中海の制海権を無くしており、逆転の始まりになったのは事実である。
トルコの衰退を決定的に印象付けたのは第二次ウィーン包囲(1683年)であり、加えて台頭するロシアの脅威に悩まされることになる。この間アラブはトルコと共存しており、西洋との戦も殆どトルコ人や元キリスト教徒子弟のイェニチェリの役割だった。アラブもトルコも十字軍を忘れた訳ではなかったが、アラブ人が西洋に恨み妬みを再認識するのはむしろ近代に入ってからではないか。かつての野蛮な西洋が優位に立ったのだから。
フォーサイスはアラブ人の恨みと憎悪を指摘し、私もそれは間違っていないと思う。だが、同時に西洋人も劣らずイラスム世界に対し憎悪を抱いていたのではないか。十字軍の敗北とそれに反撃するオスマン朝の台頭は屈辱と脅威だったのは明らか。戦後に植民地を手放す羽目になったことも、憎しみを拡幅させるのに十分過ぎる。日本のマスコミが知日派と持ち上げるロナルド・ドーアなる英国人学者も、昨年夏私と交わしたメールで、日本のナショナリズムの背景は西洋諸国への恨みと記していた。
その②に続く
◆関連記事:「アヴェンジャー」
「テロリズム-まず憎悪ありき」
「アラブが見た十字軍」
よろしかったら、クリックお願いします





















あれだけコテンパンにやったのに、また経済大国になってきた黄色人種は、本当に気に入らないでしょうね。
英国が西洋で最も反日国なのを、日本の文化人はあまり触れませんね。
英国のメディアは何かあれば、第二次大戦中の捕虜虐待を取り上げ、フォーサイスの上記の小説でも旧日本軍の侵攻のことが書かれています。その理由をフランスの学者ジャン・ピエール・レーマンは、「日本と戦った英国は多くの兵士が捕虜の恥辱を受け、おまけに植民地も失ったが、米国のように原爆で仕返しもしていない。そのフラストレーションが常に残っている」と書いていたとか。
もっとも小説『鷲は舞い降りた』には、英国人のボーア戦争時での民間人(オランダ系白人)捕虜への惨い扱いが載っていました。
http://blog.goo.ne.jp/mugi411/e/f9436966adf2bc811154f0fff88046e9
同じ黄色人種でも植民地で協力した中国人は、まだ恨みがないかもしれません。ただ、かなり昔読んだ英国人の本の冒頭に、乾隆帝の時代、派遣された英国使節が叩頭を求められたことが書かれてあり、これがアヘン戦争に繋がったと思います。