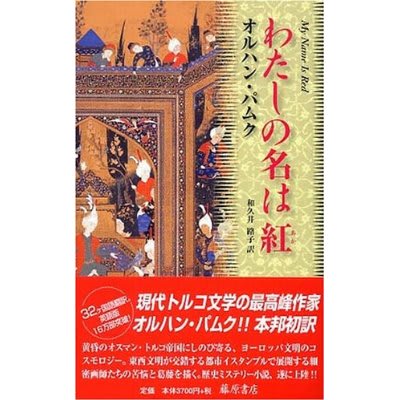
久しぶりに本格的な外国文学を読んだ気がする。『わたしの名は紅(あか)』(オルハン・パムク著、藤原書店)がその作品で、昨年の『トルコ狂乱』に続き、読了したトルコの歴史小説はこれで2作目となった。パムク氏は2006年度ノーベル文学賞受賞者だけあり、ストーリー展開は見事なだけでなく、作品に描かれた16世紀末のトルコ社会は興味深い。
物語は1591年の冬、オスマン帝国の都イスタンブルが舞台。折りしもトルコの衰退の兆しが表面化してくる時代である。時の皇帝で第12代ムラト3世は翌年のイスラム暦千年目(※622年のヒジュラからの陰暦)に向け、その在位と帝国の威容の誇示のため、祝賀本の制作を元高官で細密画を知るエニシテに命じた。その祝賀本を巡る細密画家たちを描いた異色作こそが、『私の名は紅(あか)』なのだ。その細密画師の1人が殺害されたところから、物語は始まっている。
建前こそイスラムは偶像崇拝厳禁で、人物画や動物画を描くことは厳禁されている。しかし、実際には中東に限らずイスラム諸王朝ではミニュアチュールと呼ばれる細密画が発達し、宮廷文化として花開いた。イスラム世界の細密画は中国の影響も受けていることが、素人目にも分かり、この物語にも蒙古人が中国画の手法を伝えたと書かれていた。イスラムが勃興してから細密画が誕生したというより、マニ教の開祖マニが中国に行って、現地の画法を学んで帰国したというイランの伝説からも、イスラム以前から中東世界で絵画は広く受け入れられていたのだ。
細密画は絵単独で描かれるのではなく、教典や詩文の挿絵として作成されるものが大半であり、細密画の名称どおり実に細かい描き方をする。極細の線を出すため、リスの尾の毛で作られた筆を使ったり、米粒や髪の毛にまで絵の描ける名人までいたことが小説に見える。この種の名人は中国にもいたはずだが、そのような細かい手作業の結果、老齢になる前に失明する絵師までおり、視力を失うことが名人の証と見なされたそうだ。老いても視力がある絵師は凡庸と思われたため、人前では盲目を装う者までいたらしい。
中国の影響を受けたにせよ、細密画の中心というか発祥はやはりイランで、イランの名人の画法はイスラム世界全般に影響を与えた。トルコの細密画工房もイランの画法を学んでおり、画でイランを超えたいという意気込みがあったことが伺える。
トルコの細密画の題材でよく使われたのがイランの詩人ニザーミーのロマンス叙事詩。『ホスローとシーリーン』『ライラとマジュヌーン』『ハフト・パイカル』(七王妃物語)などの叙事詩は細密画家たちの創作欲を刺激した。特に『ホスローとシーリーン』(※トルコ語ではヒュスレヴとシリン)の物語は好まれ、主人公のホスローが水浴する美女シーリーンを見初めるシーンは、よく描かれていた。便利なことにネットでもその画像が公開されている。
叙事詩のような真面目なテーマばかりでなく、密かに春画も描かれていたようだ。やはり、この手の絵はイラスム世界にもあったのだから、人間性は東も西も変わりない。絵師によっては写実性を求めるためか、動物の性器を描いた者もいたそうだ。
興味深いことに、イランやトルコの細密画師たちは己の作品に署名や工房名も記さず、画風だけで作者が分かるように描いたそうだ。個人の作品よりも工房室全体で創作したと考えている節があり、西欧のようにサイン入りの画やスタイルを確立することを卑しんでいたという。その感性は昔の日本の絵師にも通じる所があって面白いが、少なくともオスマン帝国全盛時代までは中国画は学んでも、欧州の絵画技法を取り入れようとはしなかった。十字軍時代の野蛮な西欧人を忘れていなかったのか。
工房に弟子入りした見習い修行はかなり厳しいものだった。少年の頃から名人と呼ばれる親方について絵画を学ぶのだが、師匠が折檻するのは当り前で、何かしくじれば足の裏を鞭で打ったり、定規で叩いたりする。見習いに粗相がなくとも、親方や先輩の気紛れで八つ当たりや殴られたりすることも。弟子には美少年もいて、親方の寵愛を受ける者がいたことが知れるが、あからさまには書かれてないにせよ、現代なら未成年への性的虐待に当たるだろう。工房の親方は絶対的存在であり、逆らうことなど考えられないのだった。
雪の降るイスタンブルの9日間の出来事を描いた小説らしく、読者も登場人物と同じく雪の積もった陰鬱な路地裏を歩いている気分にさせられる。細密画師が主要登場人物にせよ、作品全体が絵画的であり、著者自身、7歳から22歳までは画家になることを考えていたそうだ。何故、パムク氏が22歳で作家に転向したのか理由は不明だが、日本語版序文に「近代のトルコの絵画があまりにも西洋絵画の影響にはいってしまった」の言葉がある。「大多数の今日のトルコの画家のように」「いささか「模倣的かつ真摯的」でない立場に陥るであろう…」とも語っていた。
その②に続く
◆関連記事:「狂気の愛―ライラとマジュヌーン」




















