
奄美大島で行われた「はじめての自然系」フォーラムの開催について書いています。その後、リュウキュウアユ関連の集まりは沖縄でも、また、鹿児島市、名瀬市(奄美)での行われました。それぞれ、北部ダム工事事務所(国)、日本魚類学会、鹿児島県、が主催者となりました。特定の生物の保護をめぐってそれぞれの組織が、公開の発表会を開いたのは余り前例はありません。その先駆けとなったのが「リュウキュウアユフォーラム」でした。

リュウキュウアユのすむ川は濁っていた。上流域の樹林は根こそぎ伐採され山は丸裸になっていた。奄美大島は過去にも大規模伐採の時代があった。先の大戦後、荒廃した鉄道網再建の枕木材として、大量に伐採された。私が初めて奄美大島を訪ねた1987年は、戦後40年を経て樹林が再生して「切り頃」を迎えた時期だった。
こんなに森を切って大丈夫なのか。不安は的中する。90年9月17、18日、島の近くを通った台風19号は豪雨を伴い、大量の土砂を含んだ大水は役勝川沿いの集落を襲った。その時私は被災した川沿いの旅館に滞在していた。森林伐採、水害、やがて始まるだろう災害復旧の河川工事を思い暗然とした。それは、川の自然を損ない、リュウキュウアユを絶滅に追い込みかねない事態だった。
その1年前、私は、84年に鹿児島県にアユの保護を求めたアユ研究の先駆者、当時京都大学におられた川那部浩哉教授に助けを求めていた。川那部教授は、奄美大島に全国の研究者、専門家を集め、シンポジウムを行うことを提案された。テーマは「奄美の宝」。島の自然の貴重性をまず人々に知ってもらわなければならない。
10月20日、世界自然保護基金日本委員会(現WWFジャパン)、淡水魚保護協会、奄美振興研究協会の三財団の共催で「リュウキュウアユフォーラム」が開催された。参加したパネラーは12名。シンポジウムは、奄美の自然の貴重さについて、専門家が奄美の人々に直接語った最初の機会となった。リュウキュウアユの存在も広く知られるようになる。
そして、愛媛大学の水野信彦教授が会場で紹介した、自然と共存した河川工事は可能だという「多自然型河川工法」は、その後の災害復旧工事に取り入れられることとなった。
首の皮一枚で、リュウキュウアユは絶滅を免れたのかもしれない。しかしまだ、安心していられる状況ではなかったのだ。











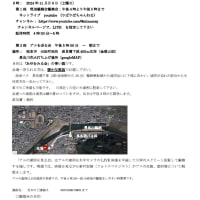














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます