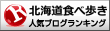地口行灯
地口行灯
 地口行灯(じぐちあんどん)とは。
地口行灯(じぐちあんどん)とは。
駄洒落の一種である言葉遊びであり、
ことわざ、有名な芝居の台詞、格言などを似た音に置き換えた地口を作り、
地口に合わせた滑稽な画を描き、祭り用の行灯に仕立てたものである。
(特別展図録「地口行灯の世界」・足立区立郷土博物館 より)
「千住のまつり」の時期になると、北千住(東京都足立区)を彩る地口行灯。
お祭りの時以外でも、北千住を歩くと時々、軒先で見かけます。
調べてみると、地口行灯は北千住だけでなく、文京区の根津神社、浅草、
多摩地区といった東京都下や埼玉県、千葉県、茨城県でも
見られることがわかりました。
なんと、私の出身地、埼玉県日高市でも、
地口行灯は確認されているとのこと。
(えーっ、全然気が付かなかった。 )
)
また、意外にも、秋祭りの時に北千住の街をたくさんの地口行灯が飾られるようになったのは、
平成15年(2003年)からとのこと。
なんか気になって、調べているうちに、
「へー」と思うことが結構出てきて面白いので、
ほんのちょっとですが、この興味深い「地口行灯」について、
私の勉強をかねて、記事にしてみました。
次回は「地口行灯」のレポートです。
よろしくお付き合いくださいませ。 吉田絵馬屋No.28
吉田絵馬屋No.28
【地口】えんま下の力持ち
【元句】縁の下の力持ち
赤い波線が1本見えるが、本来は朱系と青系の二色の波線が描かれ、
この波線を瓶垂れ霞(かめだれがすみ)と呼ぶ。
今年は朱系1本。
(こういうのも行灯を見る楽しみなのかも。)
 参考文献
参考文献
特別展図録 「地口行灯の世界」 足立区立郷土博物館
次回に続く≫