1月20日(火) 「そして、星の輝く夜がくる」(真山仁著)
被災地の子供が心の奥に抱える苦しみと向かい合う「わがんね新聞」、福島原子力発電所に勤める父親を持つ転校生を描いた「“ゲンパツ”が来た!」、学校からの避難の最中に教え子を亡くした教師の苦悩と語られなかった真実を描いた「さくら」、ボランティアと地元の人たちとの軋轢を描く「小さな親切、大きな……」、小野寺自身の背景でもある阪神淡路大震災を描いた「忘れないで」。そして、震災をどう記憶にとどめるのか? 遠間第一小学校の卒業制作を題材にした「てんでんこ」の六篇を収録。阪神大震災を経験した真山仁だからこそ描くことのできた、希望の物語。
1月23日(金) 「茗荷谷の猫」(木内実著)
茗荷谷の一軒家で絵を描きあぐねる文枝。え庭の物置には猫の親子が棲みついた。摩訶 不思議な表題作はじめ、染井吉野を造った植木職人の悲話「染井の桜」、世にも稀なる効能を持つ黒焼を生み出さんとする若 者の呻吟「黒焼道話」など、幕末から昭和にかけ、各々の生を燃焼させた名もなき人々の痕跡を掬う名篇9作。
1月28日(水) 「フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ」(E・L・ジェイムズ著)
グレイの豪邸を初めて訪れたアナに差し出された、二通の契約書。それには秘密保持義務と、彼とつきあう女性が守るべきさまざまなルールがそれぞれ定められていた。食事、服装、エクササイズの方法から、信じられないようなセックスの詳細まで。普通の恋人同士になることを夢見ていたアナは大きなショックを受け、苦悩する。それでも彼女はグレイを拒むことはできなくて…。
<フィフティ・シェイズ>は三部作あり、全世界で1億部も売れてるとのこと。映画化もされ2月に公開されるということで購入して読んでみたが……。
1月31日(土) 「限界集落株式会社」(黒野伸一著)
「限界集落」、「市町村合併」、「食糧危機」、「ワーキングプア」、「格差社会」などなど日本に山積する様々な問題を一掃する、前代未聞! 逆転満塁ホームランの地域活性エンタテインメント!!
起業のためにIT企業を辞めた多岐川優が、人生の休息で訪れた故郷は、限界集落と言われる過疎・高齢化のため社会的な共同生活の維持が困難な土地だった。優は、村の人たちと交流するうちに、集落の農業経営を担うことになる。現代の農業や地方集落が抱える様々な課題、抵抗勢力と格闘し、限界集落を再生しようとするのだが……。
ルールは変わった!
老人、フリーター、ホステスに犯罪者? かつての負け組たちが立上がる!!ベストセラー『万寿子さんの庭』の黒野伸一が、真正面からエンタテインメントに挑んだ最高傑作! 地方書店発のベストセラー待望の文庫版を電子化!!新しい公共がここにある!
NHKで5回に渡ってのドラマ化で放映されているのもいい。そして、「続・限界集落株式会社」も出版されてるので読みたい。
2月9日(月) 「日御子」(帚木蓬生著)
代々、使譯(通訳)を務める“あずみ”一族の子・針は、祖父から、那国が漢に使者を遣わして「金印」を授かったときの話を聞く。超大国・漢の物語に圧倒される一方、金印に「那」ではなく「奴」という字を当てられたことへの無念が胸を衝く。それから十七年後、今度は針が、伊都国の使譯として、漢の都へ出発する。(上巻)
漢へ赴いた針のひ孫の炎女は、弥摩大国の巫女となり、まだ幼い女王の日御子に漢字や中国の歴史を教える。成長した日御子が魏に朝貢の使者を送るとき、使譯を務めたのは炎女の甥の在だった。1~3世紀、日本のあけぼのの時代を、使譯の一族9代の歩みを通して描いた超大作。傑作歴史ロマン小説!(下巻)
物語は灰(はい)から圧(あつ)、針(しん)、江女(こうめ)、朱(しゅ)、炎女(えんめ)、在(ざい)、銘(めい)、治(じ)に至る九代の歴史を繋ぐことで進んでいく。
”あずみ”一族の三つの掟「人を裏切らない」「人を恨まず、戦いを挑まない」「良い習慣は才能を超える」が、様々な人に影響を及ぼしてる様子が伝わってくる。著者は悪字を修正している所が気になったが納得! 卑弥呼→日御子、邪馬台国→弥摩大国他。
第2回歴史時代作家クラブ賞作品賞受賞、帚木蓬生の素晴らしい世界を味わうことができた。
2月10日(火) 「仕事。」(川村元気著)
「私と同じ年の頃、何をしていましたか?」
大人になってからのほとんどの時間、僕らは仕事をしている。
だとしたら僕は人生を楽しくするための仕事がしたい。
そこで仕事で世界を面白くしてきた12人に訊ねた。
山田洋次:批判する頭のよさよりいいなぁと惚れ込む感性が大事です。
沢木耕太郎:僕はあらゆることに素人だったし素人であり続けた。
杉本博司:やるべきことは自分の原体験の中にしかないんです。
倉本聰:世間から抜きん出るにはどこかで無理をしないといけない。
秋本康:時に判断を間違えるのは仕方ない。大切なのは、間違いを元に戻えもす力だ。
宮崎駿:何いwかでも自分の肉眼で見る時間を取っておく。作品を見ることは違うんです。
糸井重里:仕事は人間の一部でしかない。だから、どうやって生きていくかを面白くやれ。
篠山紀信:世界をどうにかしようなんて、おこがましい。大事なのは受容の精神です。
谷川俊太郎:人類全体の無意識にアクセスできる仕事であればいいんじゃないかない。
鈴木敏夫:最近はみんな丁寧に物をつくるから完成したときには中身が時代とズレちゃう。
横尾忠則:自分が崩落していく感覚の先に新たな道を見つけることも多いと思います。
坂本龍一:勉強とは過去の真似をしないためにやるんです。
彼らが僕と同じ年の頃、何を想い、何を考え、 どう働いていたのかを。
2月12日(木) 「アルピニズムと死」(山野井泰史著)
日本を代表するアルパインクライマー、山野井泰史が考える「山での死」とアルパインクライミング。かつて「天国に一番近いクライマー」と呼ばれた男はなぜ、今も登り続けていられるのか。
「より高く、より困難」なクライミングを志向するアルパインクライマーは、突き詰めていけば限りなく「死の領域」に近づいてゆく。そんななかで、かつて「天国にいちばん近いクライマー」と呼ばれていた山野井泰史は、山での幾多の危機を乗り越えて生きながらえてきた。
過去30年の登山経験のなかで、山で命を落とした仲間たちの事例と自らの生還体験を1冊にまとめ、山での生と死を分けたものはいったい何だったのか、を語る。




















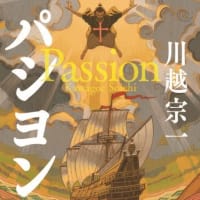

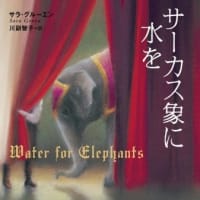
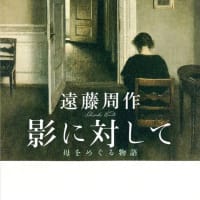

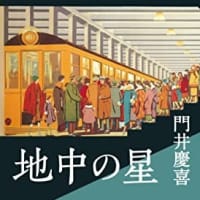
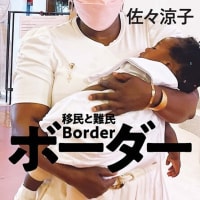
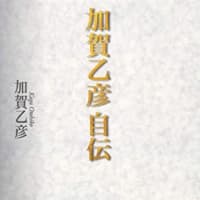
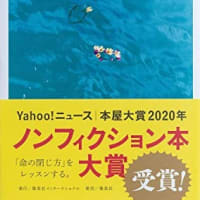
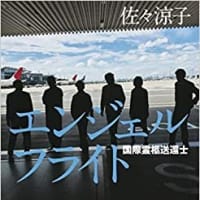
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます