実はこの工場にもある。ここに工場が引越してきてから前にあった古いのをバージョンアップして作った。作る前に神様だか霊だかが見える霊媒師的な人を呼んでこの土地を見てもらったら7人の神様だか霊だかがいると言われた。
そしてどうやったかは知らないが場所を決め、工事業者はこれ専門ではないが、来てもらった祠が作られた。それからと言うもの、年に2回か3回位だったと思うけど、線香を立て、神のお金を燃やしたりしている。
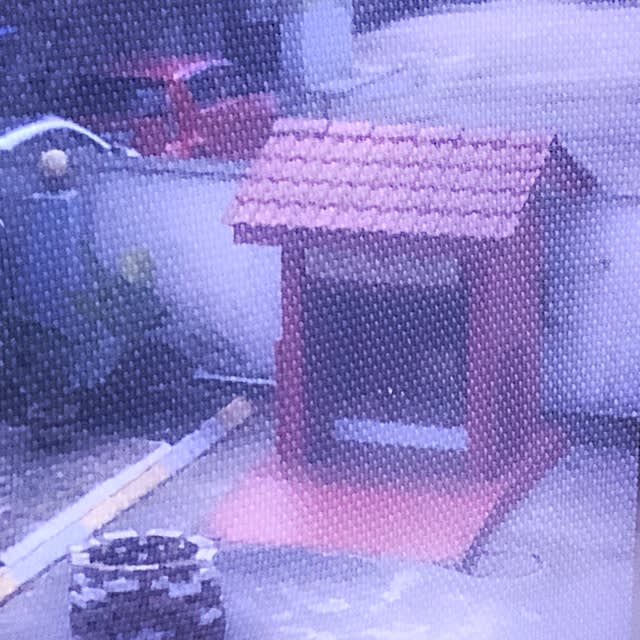
それが今日もあった。
最初に線香を上げてそれから紙を燃やす。参加者はチャイニーズに加えてネパールやミャンマーの仏教徒とインド系を加えたヒンドゥー教徒。うーん? この習慣は仏教系なのか? それとも宗教より土着信仰的な何かなのか?
まあいいか、で終わりにする。
が、全く違うポイントが気になる。
この祠、どこのも必ずコンクリートで出来ている。日本だとこの手の物はだいたい木で作ると決まっている。お地蔵さんの入った祠とか家の仏壇、大きな物ではお寺や神社は巨大な川崎大師のようなのを除けばだいたい木造。
コンクリートで作ってしまうとなんだか味気ないしご利益が薄そう。
マレーシアのチャイニーズがお盆に使う道具類、ボンボリとか色々はほとんどプラスチック製。中国で作られて運んで来られる安っぽいプラスチック。日本だと宗教関係の物はもちろんプラスチックも使われるけれどあれほどあからさまにプラスチック丸出しは無いと思う。
日本人は伝統的な何かを考える時には昔には無かった材質はそぐわないと感じるけれど、マレーシアはそれが全然ない。昔いた台湾もそうだった。形は古式でも材質までは古式にはしないらしい。こだわるポイントがかなり違うらしい。

















