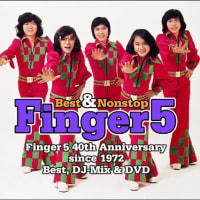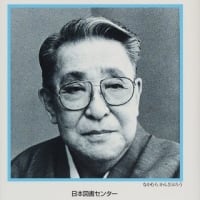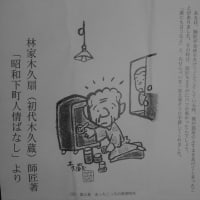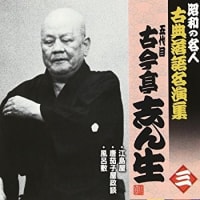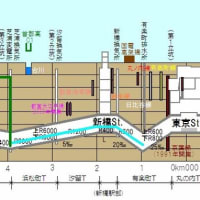歴史的仮名遣 

(絵上:藤原定家)
★出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 より
歴史的仮名遣とは、現在の発音によらず語の本来の形によって表記を決定する日本語の仮名遣のことである。「旧仮名遣」と呼ばれることもある。
現在でも歴史的仮名遣を使用する人が存在する。その中には、歴史的仮名遣を正仮名遣(正かな)と呼ぶ人もある。
【歴史】
現在は歴史的仮名遣(旧仮名遣)と呼ばれる表記も、平安時代の中期まではだいたい発音通りのものだったと推測される。
時代が下るに従って、日本語の発音は変化した。そのため、語の表記と発音とにはしばしばずれが生じ、同音でも異なる表記がありうる様になった。
その時、ある一つの表記を正しいものと看做し、それとは別の表記を誤りと決定する必要が生じ、仮名遣が出現する事になった。
鎌倉時代初期には、発音と表記とにずれが生じ、既に表記が混乱した状態にあった。そのため、藤原定家は、古い文献を渉猟した上で「を・お」「え・ゑ・へ」「い・ゐ・ひ」の区別について論じた。
これに行阿が補正・増補を行なって定家仮名遣が成立した。江戸時代まで、定家仮名遣は正式なものとして、歌人の間などに普及した。
しかし、定家らの調べた文献は十分古いものではなく、すでに仮名遣の混乱を含んだものであった。また、いくつかの語については、アクセントに基づいて表記が決定されたため、誤った仮名遣が「正しい」とされた場合があった。
江戸時代になって、契沖は、万葉集などのより古い文献を調べ、定家仮名遣とは異なる用法が多く見られることを発見し、それを改訂して復古仮名遣を創始した。
その後、本居宣長らによって理論的な改訂がなされ、更に明治以降の研究によって近代的な表記法として整備され、太平洋戦争敗戦直後まで一般に使用された。この復古仮名遣を普通、歴史的仮名遣と呼ぶ。
明治維新前後以来、国語の簡易化が表音主義者によって何度も主張された。表記と発音とのずれが大き過ぎる歴史的仮名遣の学習は非効率的である、表音的仮名遣を採用することで国語教育にかける時間を短縮し、ほかの学科の教育を充実させるべきである、と表音主義者は主張した。
これに対して、森鴎外や芥川龍之介といった文学者、山田孝雄ら国語学者の反対があった。民間からの抵抗も大きく、戦前は表音的仮名遣の採用は見送られた。
敗戦直後の混乱のさなか、GHQの招聘したアメリカ教育使節団の勧告もあり、民主化政策の一環として政府は表記の簡易化を決定、国語審議会の検討による「現代かなづかい」を採用、内閣告示で実施した。以来、この新しい仮名遣である「現代かなづかい」に対して、歴史的仮名遣は「旧仮名遣」(旧かな)と呼ばれる様になった。
【批判】
この国語改革に対しては、批評家・劇作家の福田恆存が『私の國語教室』を書いて、「現代かなづかい」の論理的な矛盾を衝き、徹底的な批判を行なった。
「現代かなづかい」は、表音的であることを標榜するが、一部歴史的仮名遣を継承し、完全に発音通りであるわけではない。助詞の「は」「へ」「を」や、「ず・づ」の区別は歴史的仮名遣の規則そのままであるし、「え」「お」を伸ばした音の表記は歴史的仮名遣の規則に準じて定められたものである。
また、福田は「現代かなづかい」の制定過程や国語審議会の体制に問題があることを指摘した。その後、国語審議会から「表意主義者」4名が脱退する騒動が勃発し、表音主義者中心の体制が改められることとなった。
その結果、昭和61年に内閣から告示された「現代仮名遣い」では「歴史的仮名遣いは、我が国の歴史や文化に深いかかわりをもつものとして尊重されるべきである」と書かれる様になった。
【現状】
既に多くの日本人が新しい仮名遣で教育を受け、歴史的仮名遣を使用する日本人は少数派となった。一部に国語改革の見直しと歴史的仮名遣の復権を主張する人は残るものの、歴史的仮名遣そのものに生理的な違和感すらも覚える日本人は少なくない。
しかし、俳句・短歌の世界では歴史的仮名遣が使用されることもまだまだ多い。また、最近では、若合春侑氏が歴史的仮名遣による現代小説を発表し、注目された。
【参考】
上代特殊仮名遣
万葉仮名
許容仮名遣
このうち・・・
許容仮名遣(きょようかなづかい)とは、歴史的仮名遣の規範からは外れるが、広く使用されていたために一般の使用が許容されていた仮名遣のこと。
*許容仮名遣の例
「用ひる」(正しくは「用ゐる」)
「或ひは」(正しくは「或いは」)
「せうゆ」(醤油:正しくは「しやうゆ」)
「どぜう」(泥鰌:正しくは「どぢやう」)

06.06.05