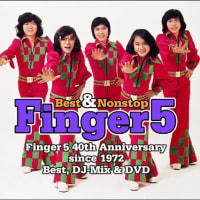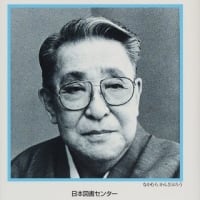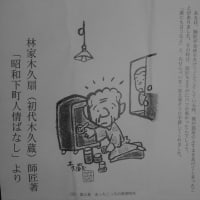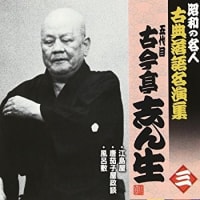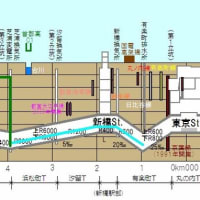そうめんの由縁 
ガキの頃よく「アーメン、ソーメン、冷や素麺」なんて言って遊んだが、暑いときの素麺は堪えられない。
今年もそういう時期が到来したようだ。
お古い川柳に…
●素麺は皿から脾胃(ひい)へ引き続き …とある。
昔の素麺は食べやすいように長さを切りそろえるようなことはしてなかった。だから長いまま、煮たそうだ。そのため、噛まずに飲み込むと、皿から胃袋まで連綿と一続きになる。その状況を詠んだもの。

素麺流し
それではいつ頃から切りそろえて短くなったものか、それは知らない。
実にくだらない話だが、「いつから細長くなったのか?」は分かる。 以下の通り。
◆そうめんはいつから細長くなったのか?
鎌倉時代になると禅宗が伝来し、民間レベルで大陸との交流が盛んになった。遣唐使廃止以来の(ちょうど延喜式の頃から)四百年の平安の眠りを醒ますように、大陸の新しい技術が入ってくる。
1.まずは油をつけて伸ばす技術。麺が長く細くなった。
2.次に挽き臼の伝来。小麦の細粉を製粉するようになり、製粉過程でできるグルテンがよく熟成して麺の腰が強くなった。
3.最後に鉄製農具の普及。小麦の生産が飛躍的に伸びた。この3つの大きな変化によって今日の素麺が誕生するのである。
室町時代には、この新しい麺の製造法が全国に普及。麺食の流行に刺激を受け【こんとん】を細く切って麺状にする「切りめん」が現れる。(★こんとん:刻んだ肉を小麦粉に包んで蒸したもの。平安時代、宮中の節会〈せちえ〉などに供せられた。また、餡を包んだ小麦団子を煮たもの。 ←広辞苑)
これが後に「うどん」と呼ばれることになる。つまり、小麦粉を練った後、油で細く伸ばして乾燥させるものが素麺、細く切った生の麺が「うどん」となっていく。
形が変われば呼び名も変わる。索麺(さくめん)が「さうめん」と音便化したのか、素麺(スーミエヌ)という中国語が「ソーメン」と‘なまった’のか。【素】は精進物の意味を表わし、引出物やお供物として使われるそうめんにピッタリの名称である。

これまでの【索麺】にかわって書物に【素麺】の字がで出てくるのは、南北朝時代の「庭訓往来」という書物からである。
ちなみにこの書物、武士や庶民が使う子供用の教科書なのである。いかにそうめんが普及していったかが知れよう。

11.08.06 (06.08.10)