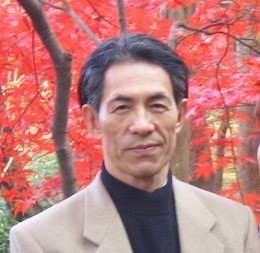写真は、戸建の内覧会で撮影したバスルームです。ここでご覧頂きたいのは、窓にかかっているブラインドです。このブラインドは買主が付けたわけではなく、標準装備として、既に付いていました。こういうのを見ると、気を使ってるな、と好感が持てます。
写真は、戸建の内覧会で撮影したバスルームです。ここでご覧頂きたいのは、窓にかかっているブラインドです。このブラインドは買主が付けたわけではなく、標準装備として、既に付いていました。こういうのを見ると、気を使ってるな、と好感が持てます。
戸建の場合、バスルームの窓は、通常、曇りガラスになっていますが、周りが暗くなって、中で明かりを点けますと、外からどう見えるのか、気にはなります。また、バスルームは、通常、1階部分の側面に置かれますので、余計注意が必要となります。
また、ビューバスを売りにしているマンションのお部屋もあります。ゆったりと外の景色を見ながら、お湯に浸かる、考えただけでも気持ちが癒されます。でも、時間と共に環境も変わります。今まで、何も無かった隣の敷地に高層マンションが建ってしまう、こんなこともあります。
以上のようなことを考えますと、バスルームには、写真のようなブラインドを付けておくのが安心かな、と思います。モデルルームに行ったり、お部屋の内覧会に行かれる際には、バスルームの窓に標準装備として、ブラインドが設置されているのかもご確認下さい。そして、設置されてなくて、これでは気になる、という場合には、ブラインドの設置を売主に要望してみて下さい。(811)
 写真は、58階建てタワーマンションの23階の南向きの部屋です。写真を撮った時刻は午後2時、廊下の向こうのリビングの窓には、太陽がサンサンと輝いています。でも、ドアが開いている手前右側の洋室は、窓があるのですが、夜のように暗いです。この洋室に入ってみますと、照明を点けなければほとんど見えません。
写真は、58階建てタワーマンションの23階の南向きの部屋です。写真を撮った時刻は午後2時、廊下の向こうのリビングの窓には、太陽がサンサンと輝いています。でも、ドアが開いている手前右側の洋室は、窓があるのですが、夜のように暗いです。この洋室に入ってみますと、照明を点けなければほとんど見えません。
タワーマンションの場合は、ほとんどが内廊下となります。内廊下側の上の屋根は空いているのですが、高層のため、下の方の階では、廊下側の部屋までは、ほとんど太陽の光が差し込んできません。廊下側の洋室は、子供部屋になることが多いと思います。昼でも夜のように暗い部屋は、子供には、ちょっとカワイソウな気もします。
パンフレットでもモデルルームでも、このような状況はなかなか把握出来ないと思います。内廊下型のターマンションでは、下層階の廊下側の部屋の採光につきましては、注意が必要となります。このような暗い部屋を作らないために、採光を考えて設計しているタワーマンションもあります。(710)
 新築のマイホームを購入して、雨漏れや構造的など大きな欠陥があった場合には、引き渡し後最低10年間は、瑕疵担保補償が法律的に定められていて、買主の請求によって売主は補修を行うことが義務付けられています。それでは、中古住宅を購入した場合はどうなるのでしょうか?
新築のマイホームを購入して、雨漏れや構造的など大きな欠陥があった場合には、引き渡し後最低10年間は、瑕疵担保補償が法律的に定められていて、買主の請求によって売主は補修を行うことが義務付けられています。それでは、中古住宅を購入した場合はどうなるのでしょうか?
中古住宅も欠陥に備える保険がありますが、売主の任意加入となっています。買主個人は直接入れないので、売主が保険に加入しているかどうかを確認することが大事となります。一般的に、保険付きの物件は割高になる傾向にありますが、保険付きとなりますと、保険会社が品質検査をしていることになりますので、保険と合わせて安心感はあります。ただ、この場合でも、新築の条件とは異なり、補償が法律的に定められていないので、保険の期間や条件などは確認しておかなければなりません。
個人間の中古住宅売買でも瑕疵保険に加入することはできます。但し、保険法人に登録している住宅検査会社にあらかじめ物件を検査してもらうのが条件となります。登録会社は住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページで調べられます。新築でも中古でも、欠陥が出てしまって、売主に連絡せずに、別の業者に補修を依頼してしまった場合には、保険金は出なくなりますので、注意が必要となります。(31)
 写真は、マンションの内覧会で和室の畳表(たたみおもて)を少し押してみたところです。畳表が畳床(たたみどこ)にしっかりと張られていませんので、畳表を押すと写真のように沈んでしまいます。手前の畳表はしっかり張られています。内覧会では、畳表が畳床にしっかりと張られているかもチェックして下さい。畳を踏むと、都度沈むのも気持ちの良いものではありませんから。写真ぐらい押して沈んでしまうと不具合として指摘すべきです。
写真は、マンションの内覧会で和室の畳表(たたみおもて)を少し押してみたところです。畳表が畳床(たたみどこ)にしっかりと張られていませんので、畳表を押すと写真のように沈んでしまいます。手前の畳表はしっかり張られています。内覧会では、畳表が畳床にしっかりと張られているかもチェックして下さい。畳を踏むと、都度沈むのも気持ちの良いものではありませんから。写真ぐらい押して沈んでしまうと不具合として指摘すべきです。
畳は、芯となる畳床、表面の畳表そして周りの帯状の布である畳縁(たたみべり)とから構成されます。畳床の厚さは、15~60㎜、そして畳表の種類はいぐさ、樹脂、和紙の3種類です。戸建てでもマンションでも、使われている畳のサイズは、ほとんどが850㎜×1700㎜です。(931)
 一戸建ての売買契約時に、買主として入手すべき建築図書(図面や書類)はどのようなものがあるでしょう。売買契約書や重要事項、平面図や立面図、これらは一般的に売主が買主に渡しています。しかしながら、家の地盤の状態や骨組みは見えないので、これらが分かる資料も買主は保管しておくべきです。内覧会で家を検査する以前に、買主が入手しておくべき建築図書が揃っているかを確認しておいた方が良いでしょう。図書が揃っていなければ、売主に対し、提出するように要求すべきです。以下に、その内容を記します。
一戸建ての売買契約時に、買主として入手すべき建築図書(図面や書類)はどのようなものがあるでしょう。売買契約書や重要事項、平面図や立面図、これらは一般的に売主が買主に渡しています。しかしながら、家の地盤の状態や骨組みは見えないので、これらが分かる資料も買主は保管しておくべきです。内覧会で家を検査する以前に、買主が入手しておくべき建築図書が揃っているかを確認しておいた方が良いでしょう。図書が揃っていなければ、売主に対し、提出するように要求すべきです。以下に、その内容を記します。
1.一般的に配布される建築図書
・売買契約書関連(需要事項説明書等)
・確認申請及び確認済証
・地積測量図、配置図、各階平面図、立面図、電気設備図
・仕様書(外装、内装、設備にどういう材料を使ったかを書いたもの)
2.一般的に配布されていないケースが多い建築図書
・ 地盤調査報告書:地盤についての調査結果です。中に、考察があること。
・ 地盤改良報告書:地盤を改良した場合、その内容について書いたもの。
・ 矩計図(かなばかりず):家の断面詳細図。
・ 構造図:各階別に家の骨組みの状態を示したもの。
・ 壁量計算書:建物の風及び地震に対する強さを示したもの。
・ 構造計算書:建築基準法では3階以上は構造計算することになる。
・ 給排水設備図:給排水管の位置を示したもの。土中なので図面は大事。
・ 外構図:庭の状態を示したもの。
2の建築図書の内容は少し専門的になりますが、家の品質を証明する貴重な資料ですので、大事に保管して下さい。(3219)
 写真は、マンション内覧会で洗面所の洗面台の下の扉を開けて、給水管の継ぎ目のナットを写したものです。よく見て頂くと、ナットの部分に割れ(矢印部分)があるのが分かります。極めて稀ですが、このような不具合も潜んでいますので、内覧会では、隅から隅まで、特に水周りは充分なチェックが必要となります。
写真は、マンション内覧会で洗面所の洗面台の下の扉を開けて、給水管の継ぎ目のナットを写したものです。よく見て頂くと、ナットの部分に割れ(矢印部分)があるのが分かります。極めて稀ですが、このような不具合も潜んでいますので、内覧会では、隅から隅まで、特に水周りは充分なチェックが必要となります。このナットでは、締め付けが不十分ですから、継ぎ目から漏水してくることが心配されます。また、時間が経てば、このナットが割れて、そこから水が流れ出してしまうでしょう。特に、マンションでは、漏水は大問題となります。漏水しますと、水は下の階に流れていきますので、被害が広がってしまうからです。
写真のようなナットの不良は極めて稀ですが、漏水は恐いので、内覧会では、洗面所そしてキッチンの下は扉を開けて、水を暫く出して、パイプの接続部などから漏水はないか、ナットがちゃんとしてるか、懐中電灯を当ててしっかりとチェックして下さい。(83)
 写真はマンションの内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、リビングに付けたホスクリーン(室内用の物干し)です。ホスクリーンは、天井にソケットを取り付け、そこにポールを差し込みます。オプションでホスクリーンを付ける場合には、なるべく陽のあたるところと考えがちなので、どうしても、写真のように窓側寄りの天井に付けることになります。そうなると、リビングの生活動線の激しいところに洗濯物が干されることになります。
写真はマンションの内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、リビングに付けたホスクリーン(室内用の物干し)です。ホスクリーンは、天井にソケットを取り付け、そこにポールを差し込みます。オプションでホスクリーンを付ける場合には、なるべく陽のあたるところと考えがちなので、どうしても、写真のように窓側寄りの天井に付けることになります。そうなると、リビングの生活動線の激しいところに洗濯物が干されることになります。
私は、リビングの天井にホスクリーンを設置することをお勧めしません。理由は、リビングに洗濯物は干したくないと思うし、また、ホスクリーンを付ければ、ポールを外しても天井にソケットは残るからです。ホスクリーンを付ける場合には、生活する際の見栄え、生活動線に影響が少ないこと、風通しの良いところ、このような点を考えて、位置を考えた方が宜しいでしょう。ホスクリーンを使う時は、雨だったり、夜だったり、陽が射すかどうかはあまり関係ないケースもあるでしょう。(8131)
 写真は、マンションの内覧会で撮りました。撮った部分は、キッチンのシンクの下の開き戸の丁番です。ご覧頂きたいのは、赤い矢印が付いているところです。こんな小さなものなのですが、これが大きな働きをします。これはセーフクローズダンパーと言います。セーフクローズ、要するに、バネの力を使って、扉のぶつかりを和らげる装置です。これが付いているだけで、扉を開けて閉めるときには、枠とのぶつかり音もなく、ゆっくりとやさしく閉まってくれます。ですので、高級感も出るし、気分も和らぎます。
写真は、マンションの内覧会で撮りました。撮った部分は、キッチンのシンクの下の開き戸の丁番です。ご覧頂きたいのは、赤い矢印が付いているところです。こんな小さなものなのですが、これが大きな働きをします。これはセーフクローズダンパーと言います。セーフクローズ、要するに、バネの力を使って、扉のぶつかりを和らげる装置です。これが付いているだけで、扉を開けて閉めるときには、枠とのぶつかり音もなく、ゆっくりとやさしく閉まってくれます。ですので、高級感も出るし、気分も和らぎます。
このマンションでは、感心なことに、このセーフクローズダンパー付きスライド丁番が、キッチンだけでなく、洗面所の棚、クローゼット、玄関収納等の扉に使われていました。結構、このような観音扉を閉めるときの音は気になるものです。また、このような衝撃音は壁を伝わって隣りの家にまで響いてしまうこともあります。特に、戸境壁に面して洗面台などが取り付けられている場合には、引き出しを閉めた際のぶつかり音が隣戸へ伝わりやすくなります。
そのような状況を防ぐためにも、このセーフクローズダンパーは、小物ですが大事な役割をします。モデルルームへ行った際には、細かい点ですが、クローゼットやキッチン、洗面台の扉が、このようなダンパー付き丁番になっているかもご確認下さい。このセーフクローズダンパーは後付けも出来ますので、ホームセンターで購入して、自分でも付けられます(02)