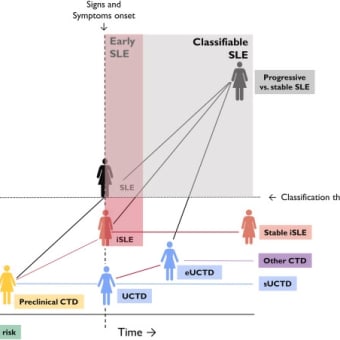アカルボースによる門脈ガスと気腹症をともなった良性の腸管気腫症の症例報告
Intern Med 2015; 54: 1733-1736
α-グルコシダーゼ阻害薬は腸管気腫症 (pneumatosis intestinalis: PI) と関連することが報告されている。著者らは α-グルコシダーゼ阻害薬(アカルボース) で加療されており、急性腹症を呈した 73歳男性について報告する。CT では PI の他、肝内門脈ガスと気腹症 (pneumoperitoneum) を認めた。観察目的に腹腔鏡を行ったところ、管腔臓器の穿孔や腸管壊死は認めなかった。患者は α-グルコシダーゼ内服を中止した上で保存的に加療され、軽快した。本症例は α-グルコシダーゼ阻害薬による PI に門脈ガスと気腹症を合併した例の初めての報告である。
1. 背景
腸管気腫症 (pneumatosis intestinalis: PI) は腸管の壁にガスが貯留する稀な病態である。PI は良性のものもあれば、敗血症にともなうものもあり、死亡することもある。PI の病態生理は不明だが、機械的な障害、細菌による障害、呼吸のメカニズムの障害などが考えられている。PI に門脈ガスをともなうと高い死亡率と関連することが示されている。
過去 10年で 2型糖尿病の治療に用いられる α-グルコシダーゼ阻害薬が PI 発症に関連することが示されている。
今回、著書らは、門脈ガスと気腹症をともない腸管壊死と紛らわしい α-グルコシダーゼであるアカルボースによると思われる PI の症例を報告する。
2. 症例提示
2型糖尿病の 73歳男性がアカルボース 50 mg 1日3回を服用していた。既往症に、2型糖尿病 (網膜症あり、腎症あり)、高血圧症、脂質異常症、虚血性心疾患、繰り返す尿路感染症がある。
患者は当日朝からの繰り返す嘔吐と便秘を主訴に救急外来を受診した。胸痛、腹痛、下痢、発熱、排尿時の不快感はなかった。
バイタルサインは正常だった。身体診察では、腹部全体に圧痛があり、腹膜刺激症状はなかった。腸音を聴取し、直腸診では異常を認めなかった。
血液検査では、白血球数 21000/μL、CRP 10 mg/dL と高値で、急性腎障害 (Cre 2.1 mg/dL) を認めた。他に pH 7.3 の代謝性アシドーシスと乳酸高値 (4.43 mmol/L) を認めた。
立位胸部 X線写真では横隔膜下に free air を認めた。胸腹骨盤部 CT では回腸および上行結腸に腸管気腫症と肝内門脈ガスを認めた。上腸管動脈とその分枝は開存していた。わずかな気腹症も認めた。
身体所見、血液所見、画像所見から探査目的の腹腔鏡を行う方針とした。腹腔鏡では腸管壊死などの病態は認めなかった。腹腔鏡後は外科病棟に入院の上で管理した。入院中はバイタルサインは安定しており、輸液と抗菌薬 (タゾバクタムピペラシリン) 投与を行った。アカルボース投与は中止した。炎症マーカーはゆっくりと低下し、正常化した。腎機能は輸液後に正常化した。尿培養からタゾバクタムピペラシリンに感受性の大腸菌を検出した。経口摂取を再開し、腹部所見は認めなくなった。入院 10日目に自宅に退院した。
3. 議論
腸管気腫症は 1730年に Du Veroni によって最初に小腸または結腸の壁内にガスがある病態として報告された。60以上の原因が報告されているが、15%は原発性または特発性である。
腸管気腫症の病因の主な説は 3つある。ひとつは管腔内圧が上昇すると、粘膜上皮を介して腸管壁内にガスが侵入するというものである。もうひとつは粘膜上皮下層にクロストリジウムや大腸菌などの発酵菌が侵入し、ガスを産生する結果、粘膜上皮下にガスが蓄積するというものである。最後のひとつは、肺胞が破れて縦隔内に漏れたガスが後腹膜を通って腸管壁内に侵入するというものである。
剖検からは腸管気腫症全体の罹患率 (有病率の間違いか?) は 0.03%と報告されている。一方、CT が使用されるようになり、腸管気腫症の罹患率は 0.3%だと報告されている。
腸管気腫症は無症状で良性の経過をたどるものから、腸管虚血など生命を脅かす重篤なものまである。腸管気腫症と診断された患者のおよそ半数は保存的に治療することができる。さらに、腸管気腫症はかつては外科的治療の適応と考えられていたこともあったが、腸管気腫症にともなうものの場合、腸管壁内の気腫が破裂したことによるもので良性の経過をたどるものがあることが報告された。これらの観察結果は外科医に対して緊急手術を行うべきか否かについてのジレンマを生む。
代謝性アシドーシス、APACHE II スコア高値、血清乳酸値 >2.0 mmol/L は予後不良の予測因子であると報告されている。最も悪い予後と関連するのは門脈ガスである。門脈ガスを認めた場合、91%の貫壁性の腸管感染症、72%の死亡と関連する。
腸管気腫症の部位も重要かもしれない。小腸に腸管気腫症を認めた場合は、貫壁性の腸管感染症と死亡の頻度が高いことが示されている。
Wayne らは PI を管理し、不必要な腹腔鏡検査を避けるためのアルゴリズムを提案している。このアルゴリズムでは、喫煙歴、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、冠動脈疾患、末梢動脈疾患の既往の有無、身体所見における腹痛の有無、乳酸アシドーシスの有無からなる血管疾患のリスクスコアで、患者の血管疾患のリスクを評価する。陽性的中率は 100%、陰性的中率は 96%だったと報告されている。
最近、α-グルコシダーゼの使用が PI 発症と関連すると報告されている。この現象については、α-グルコシダーゼによって吸収阻害された炭水化物を細菌叢が発酵 (fermentation) に利用し、ガスを産生するという病態生理が提案されている。さらに、自律神経障害をともなう糖尿病患者では蠕動障害 (peristaltic dysfunction) により、腸管内圧が上昇し、ガスが腸管壁内に侵入しやすくなる。
文献検索すると、α-グルコシダーゼ阻害薬 (赤留ボース、ボグリボース、ミグリトール) による PI の症例報告は 30件以上あった。しかし、α-グルコシダーゼ阻害薬による PI で気腹症と門脈ガスをともなう症例の報告は本件が初めてである。
α-グルコシダーゼ阻害薬投与開始から PI 発症までの期間は 7日から 12年間の幅がある。興味深いのは、ほとんど全ての報告が日本からであることである。これは日本の糖尿病患者の 1/3 近くが α-グルコシダーゼ阻害薬を処方されているのに対し、欧米ではあまり処方されないことと関係があるかもしれない。
実際、ボグリボースの売り上げの 98%、アカルボースの売り上げの 34%は日本での処方である。
α-グルコシダーゼ阻害薬による PI はα-グルコシダーゼ内服を中止し、保存的治療すれば 28日以内に完全に回復する。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26179526/