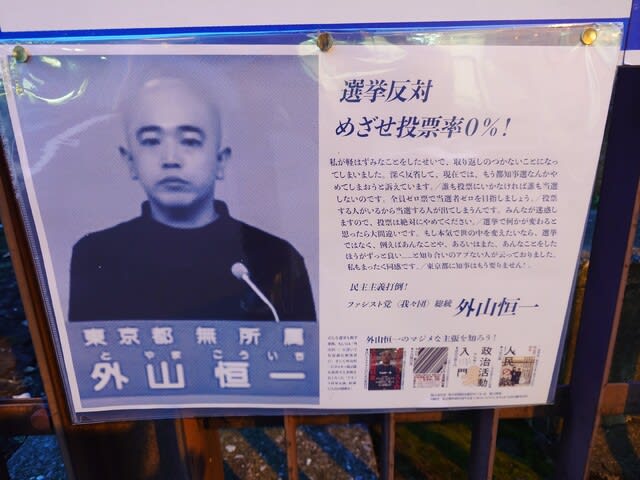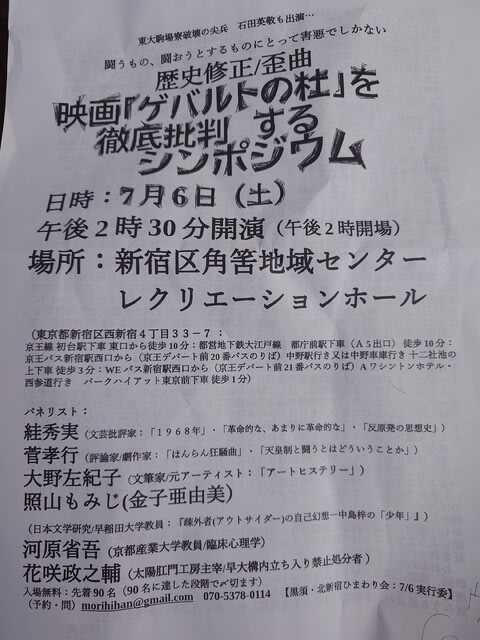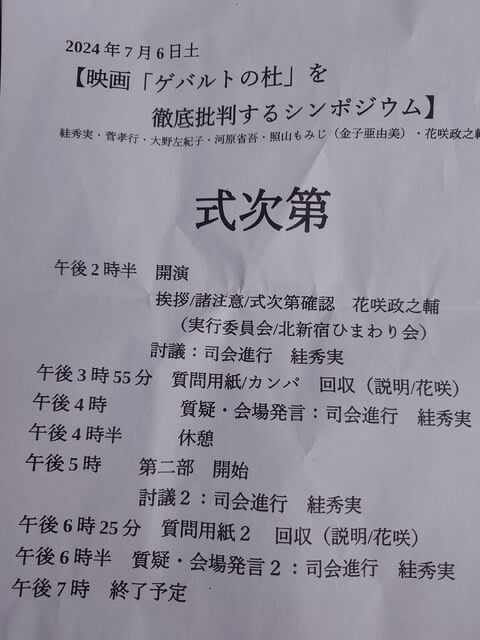八月に入り猛暑が続いている。ちょうど前回のブログを書いてから、色々予定が重なり今後も年末に向けて忙しく、なかなか落ち着いて文章を書いている時間が取れず、八月に突入してしまった。時間がない時ほど、時間の使い方がまずくなる典型である。
読書としては、井上究一郎訳『失われた時を求めて』がやっと7巻に突入した。「ソドムとゴモラⅡ」を読み進めている。『失われた時を求めて』を読んでいると、やはり「近代」の「底」、それも「無-底」を観させられている気がして、その「無-底」がプルーストの場合、マルクスでいうところの「下部構造」となっているように読める。どうしようもなさと言おうか、アルベルチーヌとのやり取りを見ても、グダグダとどうでもいいことが延々と描かれており、このグズグズが「近代」を形作っているのだろう、というモチベーションで、僕はこの「物語」をどうにかこうにか読んでいるという状態を保っていると言えそうだ。そしてそのグズグズの中に、「ドレフュス事件」への登場人物たちの距離が見えるようにも書かれている。これが印象的だと思う。前に「泡沫候補」について書いたが、もしこの小説?に別名を付けるとしたら、「泡沫候補」なのかもしれない。最初「泡沫」と書こうとしたが、そういう「はかなさ」が言いたいのではなく、民主主義や資本主義、近代の「無-底」を書いている小説という意味では、その「底」に没落して「根拠」をなすテクストという意味で、『失われた時を求めて」はまさしく、最早取り戻せぬ、「失われた時」の時代としての「底」の時間性を、ある種の遂行的次元でテクストにした小説といえるのかもしれない。とにかく、このブログ自体のタイトルのきっかけともなったテクストなので、終わりまで読んでいくのだが、まだ今からかなりの「長篇」を読むくらいの分量が残っている。
「パリ・オリンピック」が開催されているようだが、テレビをほとんど見なくなった関係上、オリンピックの競技もほぼ見ていない。どこかの待合室でテレビが流れているときなどに見かけるだけで、その時に一部の競技の結果を知る程度だ。そのような中でネット上ではオリンピックにおける「トランス女性」についての意見が、様々出されていた。特にSNS上の議論というのは、昨今は特に深まらないばかりか、自分たちにとって「適切」か「不適切」かの意見の応酬になって、「プロセス」として議論する過程がほとんど失われている。そこでいろいろ議論してもしょうがないと思いつつ、昔、若い人に「トランス女性」が、「女性競技」に出たら「不公平」だという議論を投げかけられたことがあるのを思い出した。
その時のやり取りを約めて言うと、トランスジェンダーの存在論的問題を、そのような「不公平」感に還元することは間違っているし、そもそも「トランス」とは、そのようなルールを「なんでもあり」にするという「越境-トランス」の問題ではなく、また流行りの「ハック」のようものでも当然ありえず、その〈あなた〉の抱く仮定上の「不公平」感でトランスジェンダーに憎悪を向けるのは間違っているという話をした。僕自身は昔ここでも書いたように、「性」というのはジャック・デリダのいう「差延」のことだと思っているので、「性」自体が常に既に「トランス」な存在であるわけで、「男女」という二元論的性差さえも、「トランス」という遂行的次元を前提にしなければ成り立たないと思っている。二元論的「男女」も一方の「性」がもう一方の「性」に「トランス」できる可能性を排除したら、存在しなくなるのだ。そしてこのような一方の性からもう一方へという比喩的な表現は本来は正確ではなく、「性」それ自体がその中に必ず「移行」それ自体の可能性を憑依させていることが重要なのである。
さて、その時はデリダのことまでは説明し切れなかったので、ある程度相手の話を引き受けて、少し「経済的」な問題で逆に質問をしてみた。仮に君のいう「不公平」感にある程度の説得力が宿るとして、例えばオリンピックの場合は、経済的に不利な地域、資本主義的に力が弱い国家からオリンピックに出てきている国の選手のことを、どう考えるのかを聞いた。
メダルの個数を競争し、喜々としてネットに日本のマスコミまでもが記事を張り付けているわけだが、それを見ると恐らく特定の競技以外は、アフリカ大陸の諸国はメダル獲得という意味での成績は振るわないはずだ。メダルを多く獲得しているのは、ほとんど「列強」としての「先進国」であろう。このような「出来レース」としての「不公平」をどう考えるのか、という質問をしてみた。もしこれが「不公平」ならば、オリンピックの競技は、「国民=国家」別の区分ではなく、「所得」区分で競技をし、「所得」に応じてハンディキャップを設定することで、その結果を是正すべきではないか。とにかく「先進国」が「出来レース」的にメダルを取り、それを当然だと考えていること自体の「不公平」に、君も含めた多くの人が抗議しないのはなぜなのか、と。この「不公平」に抗議しずらいのは、経済的格差は「経済的競技」として公正にでき上がった秩序だからだという偏見から来ているのであろう。アフリカ大陸の諸国が「所得」の関係上、オリンピック競技で不利になるのは、自由主義経済的には資本主義経済という「公正な競技」の中ででき上がったものであり、「自然」なものだと考えられているからである。一方、「性」の「トランス」は「不自然」のものとして、「不公正」と見做されてしまう。しかし、ここに働く判断の恣意性こそ問題だろう、と。
このような話をすると、議論の相手は一応納得をした。したものの、結局はどういう意味で納得したのかを本当の意味では確認できない。また、こういうまぜっかえしのような議論は根本的な議論にはなり得ない。やはりきちんと、資本主義批判から、フェミニズムの問題もオリンピックの問題も考えざるを得ないのだ。そしてその議論のプロセスで結論が出なかったとしても、話し合う必要がある。基本的人権を毀損する「不公正」を自然化しているそのシステムとしての資本主義を批判することなしに、オリンピックなど見ても無駄だろう。「国民=国家」別のメダル獲得数で何位になったと言い合っている状況では、「トランス」に対する差別も、「所得」による差別も自然化されてしまい、全く見えなくなってしまう。
それにしても、SNSを見ていても近頃は自分たちに「適切」か「不適切」かという基準で、バッサリ何事も裁断している意見をよく見る。コンプライアンスを批判している人や、相当に知識がある人も、同じように自分にとって「適切」か「不適切」かという基準で事態を判断しているように見える。最早そこには、これまで積み重ねられてきた「表象批判」などなかったかのようである。その意味では、「不適切」を主題にしたドラマは、時代的だったのかもしれない。