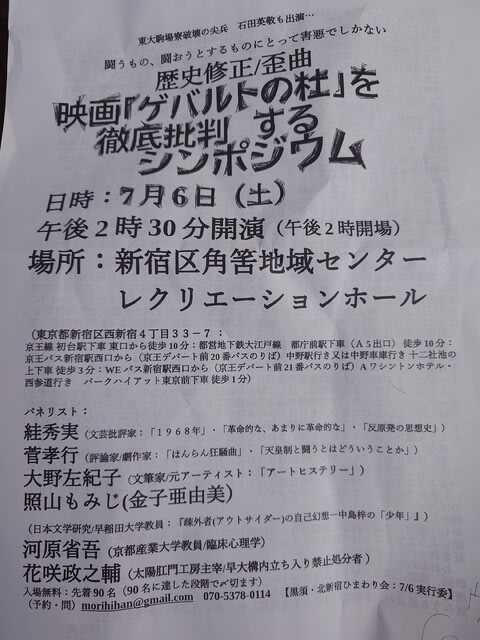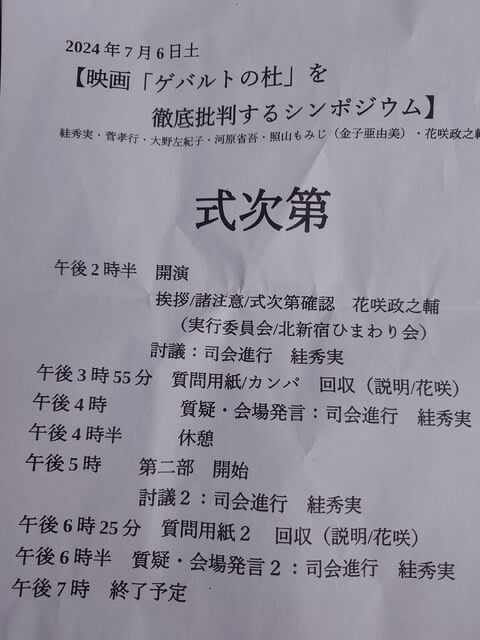この頃忙しく、ブログの記事に書けるような読書ができず、また、書く時間はあったのだと思うが、書いている時間を考えると気もそぞろになるほどには他にやることもあり、ブログの更新が一か月以上の空白となった。ただ、今日はアメリカ大統領選挙で、ドナルド・トランプがカマラ・ハリスを破り、「当確」を出したというのもあって、少し書いてみようと思った。
日本の衆議院選もよくわからない形で終わり、自民党が敗れたのか野党が勝ったのかもさっぱりわからない。ニュースや新聞を見ても、破れたはずの自民党が政権運営を続けており、また、野党までも自民党の補完勢力のように、それは意図せざるものも含めて、なってしまっている。要は「何も変わらない」ということなのだろう。ただこの何も変わらない、というのは、まさしく何も変えたくないという意志の表れとして解釈した方が良いのかもしれない。「トランプかハリスか」という問いも、この衆院選と全く同じで偽物の問として、何も変えたくないという人びとの願望のスクリーンになっている。ツイッターでグレタ・トゥーンベリが、乱暴に要約・解釈すれば、トランプであろうがハリスであろうが、それは相対的な差異に過ぎず、どちらも打ち倒すべき敵(資本主義としての「システム」)である、と文書を提示していたが、それが真実だろう。トランプが大統領になった場合、あるいは日本でも排外主義者や差別主義者が為政者になった場合、喫緊の問題として直接的に「当事者」の命が危険にさらされることとなる。これは批判されるべきであり、これからのトランプにはその問題が大いに存在する。しかしながら、選挙でトランプを選ぶということは、あるいは日本でも選挙では大敗したはずの自民党が政権を担当し続けるということは(しかも野党もこぞって自民党を補完し)、人々が現状を変えたくない、あるいは自らの立場をこれ以上悪くしたくないという、意思の現れなのだろう。そういう意味も含めて、結局ハリスだったとしても、トランプと「変わらない」ともいえる。
今日、若い人たちとデヴィッド・グレーバーの本を読みながら、グレーバーがいうように、剰余価値を生み出すという意味での「生産性」が乏しいと見做される「ケア労働」がないがしろにされる現実と、マイノリティがないがしろにされる現実を重ねつつ、剰余価値の生産が大きいとされる金融資本主義下でのエリートの労働と「ケア労働」を比較して議論をした。「エッセンシャルワーカー」とも呼ばれ、インフラをメンテナンスし、介護や医療や清掃、農業、畜産、漁業、食料品販売、輸送、教育といった、社会を維持するに欠かせない「ケア労働」が剰余価値を生まないものとして軽視される一方、剰余価値を莫大に生産するとされる金融資本主義で封建的資本主義的なエリートの労働、経営者、サブスクでの地代資本主義、それらに携わる人々が、「ケア労働」の数百倍の収入を得て「尊敬」されている。社会をケアしメンテナンスする、あるいは教育のように再生産を促す労働は、剰余価値を多く生まないと軽視されるのである。だからこそ、人々は早々にインフラや教育を民営化し、大学の学費値上げのように、教育への公的支出を切り詰め、例えば能登半島地震のように、剰余価値を生まないとされる地域は打ち捨てられ、「棄民」されるのだといえるだろう。それに対してグレーバーは、そのような地代資本主義やサブスク的封建資本主義、金融資本主義では不可視になってしまう「ケア労働」に重点を置くだけで、世の中の無駄な労働の多くは削減され、現状での富の不平等も軽減されるはずだという。もっと言えば、「価値」への眼差しが根本から変わるのではないかともグレーバーは予想しているのである。そして、その議論では、そのような「ケア労働」やそこに関わる「当事者」への「配慮」の問題が、「ポリコレ」や「コンプラ」として反動的に反発を買っている問題に繋がっているということにも話が及んだ。よく言われる「ポリコレ」や「コンプラ」のおかげで表現の自由の範囲が窮屈になり、「マイノリティ」への「配慮」が、逆に民主主義に不平等を招き寄せているという主張である。しかし、本当に人々の生活を窮屈にしているのは、そのような「ケア労働」や「マイノリティ」や「当事者」に対する「配慮」によって引き起こされているのだろうか、と。
おそらくは、「ポリコレ」や「コンプラ」が窮屈さを生んでるのではなく、むしろ「サブスク」が人を封臣としてヴァーチャルなデジタルの「土地」に縛り付け、そこから年貢(会費・使用料)をとり続けているからこそ、その「支配」が人々に窮屈さもたらしているはずなのだ。しかしながら、人はそのような「サブスク」の「支配」に対して、価値を生み剰余価値を生むエリートの労働として賞賛するよう仕向けられている。そのため人はその対極にある「ケア労働」を益々価値のないもの、あるいはそれが世の中の自由主義経済・封建資本主義を阻害するものとして敵視するようになり、マイノリティへの「配慮」を垣間見ると、そこに不自由と窮屈を見てしまうのだ。そういう意味で、ほとんどの人は経営者や資本家という封建領主の領地を防衛するため、体よく使われているともいえるだろう。自分を苦しめて土地に縛り付ける封建領主を、むしろ解放者として賞賛し続けるようなシステムになっているのである。だからこそ人々は何もいわず水やライフラインが民営化されるのを眺め、質を低下させながら料金が上げられても文句を言わないのだろう。何故ならインフラは生産性が低いからである。だが、その結果、自分たちは益々生活基盤を奪われて「窮屈」になっているにもかかわらず。
こう考えるとハリスのように、マイノリティや性的少数者に対する「配慮」を掲げる候補者が敵視されるのも「当然」となる。しかし問題は、だから「ケア労働」や「配慮」に関する問題を人びとに啓蒙すれば、その封臣たちは本当の敵に気付き、トランプやイーロン・マスクといった封建領主的経営者や資本家という真の敵を倒すのかというと、そうはならない。何故なら、ケアやマイノリティへの「配慮」を説き、啓蒙するハリスもまた、資本主義という搾取構造は変えたいとは思っていないからだ。結局は変えたくないのである。そうなれば、その窮屈さから解放してくれると思っていたハリスのような「善良な」民主主義者たちが、結局は搾取を容認する資本主義を全く変えるつもりがないとわかれば、少数派を気にする候補者よりは、ありもしない嘘の「大衆」という存在に自信を取り戻させると、嘘でも言ってくれる、嘘つきである改革者という名の経営者たちを、人は嘘でも信じたいとなるのは、わからなくはない。要は、「善良な」ハリスもまた嘘つきだからである。
これはアメリカ大統領選だけではなく、先ほどの日本の衆院選でもいえる。結局自民も野党も同じ嘘つきなのだ。自民党の搾取構造を批判し選挙で政権にダメージを与えても、野党がそれを補完して、選挙などなかったような日常を作り上げようとする。選挙が終わったとたんに、野党は、変えるつもりはなかったんだ、そんな極端なことは言うつもりはなかったんだ、という形で言い訳を始め、何も変えないように動いていく。そして自分たちはより良い資本主義を作っていくんだと、自民党と五十歩百歩のことを言い始めるのだ。だったら選挙など無意味だろう。この嘘つきの慢性化は、本当の意味で「ポストトゥルース」的であるといえる。益々代表制は信頼を失っていき、封建制、絶対君主制に近づくのではないかと思う。そういう意味でトランプだけではなく、ハリスもまた陰謀論的かつ、修正主義者の側にいるといえるだろう。「啓蒙」と「陰謀」は、本質的には区別はできない。これは重要なことだ。
経営者という君主による「解放」を夢見るという意味では、『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』を読んだ方がいいのかもしれないが、やはり思うのは、資本主義自体を批判し、代表制自体の問題化を考える政治的なイデオロギーが必要だということだ。それは相対的にマシなハリスが選ばれればいいということではない。その相対的にマシなものを選ぶという免罪符が、トランプを活気づけ、マイノリティを追い込む資本主義を持続可能にしているからである。
日本の衆議院選もよくわからない形で終わり、自民党が敗れたのか野党が勝ったのかもさっぱりわからない。ニュースや新聞を見ても、破れたはずの自民党が政権運営を続けており、また、野党までも自民党の補完勢力のように、それは意図せざるものも含めて、なってしまっている。要は「何も変わらない」ということなのだろう。ただこの何も変わらない、というのは、まさしく何も変えたくないという意志の表れとして解釈した方が良いのかもしれない。「トランプかハリスか」という問いも、この衆院選と全く同じで偽物の問として、何も変えたくないという人びとの願望のスクリーンになっている。ツイッターでグレタ・トゥーンベリが、乱暴に要約・解釈すれば、トランプであろうがハリスであろうが、それは相対的な差異に過ぎず、どちらも打ち倒すべき敵(資本主義としての「システム」)である、と文書を提示していたが、それが真実だろう。トランプが大統領になった場合、あるいは日本でも排外主義者や差別主義者が為政者になった場合、喫緊の問題として直接的に「当事者」の命が危険にさらされることとなる。これは批判されるべきであり、これからのトランプにはその問題が大いに存在する。しかしながら、選挙でトランプを選ぶということは、あるいは日本でも選挙では大敗したはずの自民党が政権を担当し続けるということは(しかも野党もこぞって自民党を補完し)、人々が現状を変えたくない、あるいは自らの立場をこれ以上悪くしたくないという、意思の現れなのだろう。そういう意味も含めて、結局ハリスだったとしても、トランプと「変わらない」ともいえる。
今日、若い人たちとデヴィッド・グレーバーの本を読みながら、グレーバーがいうように、剰余価値を生み出すという意味での「生産性」が乏しいと見做される「ケア労働」がないがしろにされる現実と、マイノリティがないがしろにされる現実を重ねつつ、剰余価値の生産が大きいとされる金融資本主義下でのエリートの労働と「ケア労働」を比較して議論をした。「エッセンシャルワーカー」とも呼ばれ、インフラをメンテナンスし、介護や医療や清掃、農業、畜産、漁業、食料品販売、輸送、教育といった、社会を維持するに欠かせない「ケア労働」が剰余価値を生まないものとして軽視される一方、剰余価値を莫大に生産するとされる金融資本主義で封建的資本主義的なエリートの労働、経営者、サブスクでの地代資本主義、それらに携わる人々が、「ケア労働」の数百倍の収入を得て「尊敬」されている。社会をケアしメンテナンスする、あるいは教育のように再生産を促す労働は、剰余価値を多く生まないと軽視されるのである。だからこそ、人々は早々にインフラや教育を民営化し、大学の学費値上げのように、教育への公的支出を切り詰め、例えば能登半島地震のように、剰余価値を生まないとされる地域は打ち捨てられ、「棄民」されるのだといえるだろう。それに対してグレーバーは、そのような地代資本主義やサブスク的封建資本主義、金融資本主義では不可視になってしまう「ケア労働」に重点を置くだけで、世の中の無駄な労働の多くは削減され、現状での富の不平等も軽減されるはずだという。もっと言えば、「価値」への眼差しが根本から変わるのではないかともグレーバーは予想しているのである。そして、その議論では、そのような「ケア労働」やそこに関わる「当事者」への「配慮」の問題が、「ポリコレ」や「コンプラ」として反動的に反発を買っている問題に繋がっているということにも話が及んだ。よく言われる「ポリコレ」や「コンプラ」のおかげで表現の自由の範囲が窮屈になり、「マイノリティ」への「配慮」が、逆に民主主義に不平等を招き寄せているという主張である。しかし、本当に人々の生活を窮屈にしているのは、そのような「ケア労働」や「マイノリティ」や「当事者」に対する「配慮」によって引き起こされているのだろうか、と。
おそらくは、「ポリコレ」や「コンプラ」が窮屈さを生んでるのではなく、むしろ「サブスク」が人を封臣としてヴァーチャルなデジタルの「土地」に縛り付け、そこから年貢(会費・使用料)をとり続けているからこそ、その「支配」が人々に窮屈さもたらしているはずなのだ。しかしながら、人はそのような「サブスク」の「支配」に対して、価値を生み剰余価値を生むエリートの労働として賞賛するよう仕向けられている。そのため人はその対極にある「ケア労働」を益々価値のないもの、あるいはそれが世の中の自由主義経済・封建資本主義を阻害するものとして敵視するようになり、マイノリティへの「配慮」を垣間見ると、そこに不自由と窮屈を見てしまうのだ。そういう意味で、ほとんどの人は経営者や資本家という封建領主の領地を防衛するため、体よく使われているともいえるだろう。自分を苦しめて土地に縛り付ける封建領主を、むしろ解放者として賞賛し続けるようなシステムになっているのである。だからこそ人々は何もいわず水やライフラインが民営化されるのを眺め、質を低下させながら料金が上げられても文句を言わないのだろう。何故ならインフラは生産性が低いからである。だが、その結果、自分たちは益々生活基盤を奪われて「窮屈」になっているにもかかわらず。
こう考えるとハリスのように、マイノリティや性的少数者に対する「配慮」を掲げる候補者が敵視されるのも「当然」となる。しかし問題は、だから「ケア労働」や「配慮」に関する問題を人びとに啓蒙すれば、その封臣たちは本当の敵に気付き、トランプやイーロン・マスクといった封建領主的経営者や資本家という真の敵を倒すのかというと、そうはならない。何故なら、ケアやマイノリティへの「配慮」を説き、啓蒙するハリスもまた、資本主義という搾取構造は変えたいとは思っていないからだ。結局は変えたくないのである。そうなれば、その窮屈さから解放してくれると思っていたハリスのような「善良な」民主主義者たちが、結局は搾取を容認する資本主義を全く変えるつもりがないとわかれば、少数派を気にする候補者よりは、ありもしない嘘の「大衆」という存在に自信を取り戻させると、嘘でも言ってくれる、嘘つきである改革者という名の経営者たちを、人は嘘でも信じたいとなるのは、わからなくはない。要は、「善良な」ハリスもまた嘘つきだからである。
これはアメリカ大統領選だけではなく、先ほどの日本の衆院選でもいえる。結局自民も野党も同じ嘘つきなのだ。自民党の搾取構造を批判し選挙で政権にダメージを与えても、野党がそれを補完して、選挙などなかったような日常を作り上げようとする。選挙が終わったとたんに、野党は、変えるつもりはなかったんだ、そんな極端なことは言うつもりはなかったんだ、という形で言い訳を始め、何も変えないように動いていく。そして自分たちはより良い資本主義を作っていくんだと、自民党と五十歩百歩のことを言い始めるのだ。だったら選挙など無意味だろう。この嘘つきの慢性化は、本当の意味で「ポストトゥルース」的であるといえる。益々代表制は信頼を失っていき、封建制、絶対君主制に近づくのではないかと思う。そういう意味でトランプだけではなく、ハリスもまた陰謀論的かつ、修正主義者の側にいるといえるだろう。「啓蒙」と「陰謀」は、本質的には区別はできない。これは重要なことだ。
経営者という君主による「解放」を夢見るという意味では、『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』を読んだ方がいいのかもしれないが、やはり思うのは、資本主義自体を批判し、代表制自体の問題化を考える政治的なイデオロギーが必要だということだ。それは相対的にマシなハリスが選ばれればいいということではない。その相対的にマシなものを選ぶという免罪符が、トランプを活気づけ、マイノリティを追い込む資本主義を持続可能にしているからである。