
2024/10/15 tue
前回の章
結局今までのやり方でゴリに彼女を作るのは難しいんじゃないのかと考えていた俺たちは、新たなアイデアを練っていた。
しかし飲み会以外、どうやって異性とゴリを絡ませたらいいのか分からない。
紹介という手もあるが、酒が入って陽気になれるからこそ、ゴリにもチャンスができるのではと思う自分がいた。
「ゴリ自身が変わらないと難しいんじゃないかな」と、大沢史博。
「いや、ありのままのゴリを好きになってくれる子じゃないと意味がないでしょ」と、二ノ宮裕二。
確かに無理して自分を変えさせても、あとで反動がくるだろう。
ゴリが自分で駄目な部分に気付き、変えようとする分には構わない。
俺たちがあれこそ言うのもおかしな話なのである。
「今度は僕が飲み会の話持ってくるからさ。もう一度それで様子を見てみようよ」
「何か当てでもあるの?」
「僕の彼女が東村山に住んでいるから、そっち系の友達集めさせてやるのもいいかなと」
「場所はどこで?」
「所沢辺りがいいんじゃない」
そんな訳で、また『CPL』主催の飲み会が決定した。
ちょうどこの頃俺は、夢だったプロレスラーのプロテストに受かり、気分は上々だった。
元々痩せていた俺は、無理して毎日吐くまで食料を胃袋に詰め込み、頑張って体重を増やしていた時期でもある。
当初、「レスラーになりたい」と知り合いに言うと、百人が百人とも大笑いされたものだ。
それぐらい俺は細かったのである。
一年経ち、二年経ち、徐々に俺の身体は大きくなっていった。
それと比例するように俺を笑う者も少なくなっていく現実。
辛かった分、結果が出た時の喜びは何とも言いようのないものだった。
うまく行けばテレビにも映り、一躍有名にという淡い思いもある。
そんな状況下の中、『CPL』二ノ宮裕二の彼女主催の飲み会が始まった。
今回のメンバーは俺、ゴリ、大沢、二ノ宮の四名。
相手も二ノ宮の彼女を含む四名。
いい子がいればいいが……。
ゴリの指先は、今日も真っ黒けだった。
その事に触れて注意したところでゴリ自体聞き入れないので、誰一人口に出す者はいない。
「はじめまして~、二ノ宮の彼女の冨岡文江です。今日はよろしくね~」
俺たちより一つ年上だという二ノ宮の彼女。
『金の草鞋を履いて、一つ上の女房を見つけろ』というが、なかなか明るく気さくでいい彼女そうだ。
文江さんの揃えた面子は、ごく普通な感じの子ばかりだった。
果たしてゴリがこの中で気に入る子がいるのか?
「誰か気に入った子いる?」
小声で囁くと、ゴリはぶっきらぼうに「いねえなあ」と呟く。
まったく偉そうに……。
何様のつもりでいるのだろうか。
ゴリメインでやろうと思ったが、ここは普通に楽しんだほうが良さそうだ。
実はこの日、俺は徹夜で飲み会に来ていた。
俺のプロテスト合格を喜んだアルバイト先の社長が、非常に喜び、お祝いに朝まで飲みに連れていってくれたのだ。
本来なら家でゆっくり寝ていたいところだが、前からこの飲み会の約束をしていた為、無理して来たのである。
乾杯を済ませると、料理が運ばれてきた。
適当に摘みながら、俺は隣の子に話し掛ける。
「仕事は何をしてるの?」
「私? アパレル関係」
「へえ、そうなんだ。よく業界の事分からないけど、色々大変なんでしょ?」
「そうだね。立ちっ放しだし。岩上君は何をしてるの?」
「俺? う~ん、今度ひょっとしたらテレビに出るかもしれないね」
まだこの頃、プロレスは世間でも人気のあったジャンルである。
放送時間も夕方ぐらいに放映されていた。
「え、ウソ! 何をしてる人なの?」
テレビという言葉が利いたのか、興味津々で聞いてくる女。
「何をしてるか、当ててみて」
「何だろう?」
盛り上がっているところに店員が、「すみません、相席よろしいでしょうか?」と声を掛けてきた。
「構いませんよ」と言うと、三人組の女性グループが頭をペコリと下げてテーブルの隅に腰掛ける。
なかなか可愛い子が相席になったなあ。
「ねえ、何をしてるの? 教えてよ~」
三人組に気を取られていると、隣の女が好奇心旺盛な顔で聞いてくる。
「プロレスだよ。プロレス……」
自信満々に答えると、その女は急に呆れ顔で「な~んだ」と吐き捨てるように言った。
当然カチンとくる。
「何だよ、その態度は?」
「だってプロレスって八百長でしょ?」
「んだと、おいっ!」
人が真剣に打ち込んでいるものを簡単に『八百長』のひと言で済ませやがって……。
「まあまあ、落ち着いて落ち着いて」
二ノ宮が仲裁に入る。
ここで怒ったら二ノ宮の顔を潰す事になるし、俺はとりあえず引く。
「プロレスって八百長のくせに野蛮でさ。私、プロレスって大嫌い」
「私も~」
「私も嫌だな~」
二ノ宮の彼女の文江さん以外、すべての女がムカつく台詞を連発してくる。
「ちょっとあなたたちさー、いい加減にしなさいよ」
慌てて文江さんも間に入ってくる。
「だってテレビ出るかもなんて言っといて、プロレスでしょ~?」
「おい、コラッ!」
人が黙ってりゃあいい気になりやがって……。
「ほら、すぐに怒鳴れば済むと思ってる人種でしょ?」
「舐めてんのか、おい」
自分が一生懸命やってきたもの。
すなわち崇高なものである。
それをこうまで言われたら、頭に来る。
「ほんと野蛮よね~。だから私、プロレス嫌い」
「見て、あの顔。血管がピクピクして血が噴き出しそう。やーねー」
楽しいはずの飲み会が、一気に修羅場と化した。
何で俺がここまで言われなきゃいけないんだ?
こいつらがプロレスの何を分かるって言うんだ?
あまりの悔しさで目に涙が浮かんできた。
「あれ、ひょっとして泣いてるの? 馬鹿みたい」
「おい、おまえらいい加減にしろよ」
二ノ宮や大沢が、馬鹿女どもに注意しだす。
「だって馬鹿みたいじゃない」
もう我慢の限界だった。
「男の尊厳を簡単に踏みにじるな、このドブスがっ!」
俺はテーブルを持ち、力一杯持ち上げ叩きつけた。
「信じらんな~い……」
テーブルの上にあった料理の皿ごと、ドブス目掛けて叩きつけたのだ。
頭から焼きそばを垂らし、身体中様々な料理が引っ掛かっている。
「信じられないなら、とっとと帰れ、このドブスが」
三人の女は半べそ状態で居酒屋から逃げていく。
まだ怒りの収まらない俺は、荒い息を立てながら正面を睨みつけていた。
すぐ店員が駆けつけて、俺たちは当然の事ながら出入禁止となる。
店を追い出された。
うな垂れて歩く俺の肩をゴリがポンと叩いてくる。
「ありゃあ、あの女たちが悪いよ。岩上は悪くない」
「そうそう、いくら何でもあれは言い過ぎだもん」と、二ノ宮まで慰めてくれる。
問題は彼女の文江さんだ。
彼女に思い切り恥を掻かせてしまったのだから……。
「すみませんでした、文江さん……」
「しょうがないよ。あの子たちのほうが悪いもん。注意しても全然聞かなかったしね。気にしないで、岩上君。そうだ! また飲み直ししよ、ね?」
本当は徹夜明けで眠くて仕方なかったが、酒をたくさん飲みたい気分だった。
それに自分の友達より、こちら側についてくれた文江さんの心意気が素直に嬉しかった。
あと、途中から相席で座った三人組の女性。
彼女らにも大変失礼な事をしてしまった。
俺が店の人間に怒られている内に先に行かれ、まともに謝れなかったのも気掛かりである。
感情的になると、いつだってあとで後悔が押し寄せてくるものだ。
冷静沈着でいられる事の大事さ。
俺は、その部分をもっと噛み締めねばならない。
みんな気まずかった酒を飲み直ししたかったのか、文江さんを筆頭にすぐ近くの居酒屋へ入る事にした。
週末のせいかどこの店も混んで、待ちができている。
俺たちが入った店も、待たないと入れない状況だった。
他の待っている客をボーっと眺めていると、先ほど相席になった女性三人組がいた。
思わず、お互い顔を見合わせて「あっ!」と言い合う。
「先ほどは本当にすみませんでした。洋服とか汚れませんでしたか?」
頭を下げながら、三人組に謝ると、「そんな気にしないで下さい。俺たち横で聞いてただけですけど、あれはどう見ても女の子のほうが悪いし、酷いと思いますよ」と暖かい言葉を掛けてくれた。
「良かったら、先ほどの非礼もあるので一緒に飲みませんか?」
正直な気持ちで言うと、向こうも笑顔で応えてくれた。
こちら男性陣は変わらず俺とゴリ、大沢に二ノ宮。
女性陣は文江さんに、相席だった女性三名が加わり、今度は楽しいお酒を飲めそうだ。
「まずお互い自己紹介しておいたほうが良くないですか?」と、俺が言うと、女性陣三人組も快く紹介をしてくれた。
「俺は梅田和子って言います。こちらが宗岡さくらさん。こっちが小沢杏です」
正直な自分の好みを言えば、一番落ち着いた雰囲気のある美人な宗岡さくらだった。
こちらの自己紹介も済ませると、乾杯をして笑顔で飲み始める。
俺たちが二十歳なのに対し、梅田和子は二つ上の二十二歳。
宗岡さくらは三つ上の二十三歳。
小沢杏は俺と同じ年だった。
さり気なく宗岡さくらのそばへ行き、話し掛けようとすると、小沢杏が笑顔で話し掛けてきた。
「さっきちょっと聞いただけなんですけど、レスラーの方なんですか?」
「いやいや、まだテストに受かっただけで、練習生ってだけだよ」
「でも、すごい身体してますよねー。私…、筋肉のある男の人って好きなんですよ」
「嬉しいですね」
「ちょっとだけ触っていいですか?」
「え、構わないけど……」
本当に俺の事がタイプなのか、ベタベタと身体を触りだす杏。
こんな風にこられると、可愛く感じる。
うまくいけば、このままおいしい展開になれるかもしれない。
しかし、宗岡さくらも気になる。
隙を見て彼女のほうをチェックすると、うまく場に溶け込む事のできないゴリに優しそうな表情で話し掛けていた。
ゴリもまんざらでない様子で、ニヤニヤと鼻の下が伸びている。
まあゴリが彼女をこれで気に入るのなら、俺は黙って見守ろう。
そんな気持ちでいた。
リーダー的存在の梅田和子が話し掛けてくる。
「あなた、硬派っぽいよね。結構モテるでしょ?」
「そんな事ないっすよ~」
「またまた~。杏なんて、かなりタイプでしょ?」
「やだー、先輩ったら~」
女性二人に挟まれ、至福の時を過ごしていると、一人あぶれた大沢がつまらなそうにしている姿が目に入った。
たまには俺だって自分自身楽しみたい。
杏、和子との会話を楽しんでいると、大沢が焼酎のボトルを手に取りラッパ飲みしているのが分かった。
マズいなあ~……。
過去大沢がベロベロに酔うと、いつもロクでもない目に遭わされる。
警察が来た事も三回あるし、気付いたら地元の不良に囲まれていた事だってあった。
そのぐらい酒乱になり、他の関係ない人間にまで絡みだすのだ。
「おい、大沢! いい加減にしとけよ」
ボトルをひったくるようにして奪う。
「大丈夫、もっと飲みたい」
「駄目だよ。おまえ、過去にあれだけ酔って問題起こしてきたんだぞ」
「今日は大丈夫だから」
そう言うと大沢は俺からボトルを奪い返し、またラッパ飲みでゴクゴクとやりだした。
俺も徹夜で疲れ、先ほどの件で苛立っていたのもあり、いちいち大沢を監視するのが面倒臭くなってくる。
杏や和子と楽しく会話を続けていると、目の据わった大沢が隣にちょこんと座ってきた。
ジッと杏の胸元に視線を集中させている。
「な、何ですか……」
恐る恐る杏が尋ねると、大沢は人差し指を突きたて「ワンプッシュ」と杏の乳首目掛けて突きだした。
「やだー、この人、信じられない!」
杏が両手で胸を隠しながら、怒り出す。
当たり前だろう。
いくら酔っているといっても、やっていい事と悪い事がある。
大沢はその反応に対し、ニヤニヤ笑いながらまだちょっかいを出そうとしている。
「おい、大沢。おまえ、いい加減にしろよ」
しょうがないので、少し低い声を出しながら強めに注意した。
「ワ、ワンプッシュ……」
まったく懲りない大沢。
嫌がる杏の胸をまた指で突こうとしている。
「ちょっと本当にやめてよ!」
杏が本当に怒り出した。
俺は見るに見かねて大沢の胸倉を掴む。
「おまえさ…、本当にいい加減にしろよな」
大沢はいじけた表情になり、どこかへ行ってしまう。
あまり友達をこのような扱いするのは好きじゃないが、彼の場合異常な部分があるのでしょうがない。
杏と和子に挟まれ楽しい時間を過ごしながら、いつの間にか大沢の事などすっかり忘れていた。
たまにゴリのほうを盗み見ると、宗岡さくらと仲良く酒を飲んでいる。
二ノ宮と文江さんのカップルは真剣に何か話し合っていた。
数杯酒を飲み、いい感じで酔いが回ってきた頃。
俺たちの方向に、ヤンキーチックなパンチパーマの男が向かってくるのが見えた。
どう見てもこちらを睨んでいる。
「おい、おまえらよ~」
パンチ男が、いきなり怒鳴りつけてきた。
何をトチ狂っているのだろうか?
するとあとから大沢が、パンチ男の仲間らしき人間に腕を掴まれた状態でこちらに歩いてくる。
「こいつの連れかよ、おい?」
アゴをしゃくりながら偉そうな態度のパンチ男。
大沢がまた何かやらかしたのか?
「何だよ、一体?」
仕方なく俺は立ち上がり、パンチ男に近づく。
「この野郎がよ、俺たちの連れの女の乳首を『ワンプッシュ』とか抜かしながら、いきなり触りやがったんだよ。どう落とし前つけんだよ、あっ?」
「……」
確かに言い返す言葉がなかった。
大沢の馬鹿め……。
とりあえず女の子だけは逃がさないとマズい。
俺は文江さんに小声で「女の子、連れて逃げてくれ」と囁く。
奥からパンチ男の連れがゾロゾロとこちらに向かってきた。
こんな事態を巻き起こした大沢本人は、酔っているので涼しい顔をしている。
文江さんが杏たちと一緒に逃げるのを確認してから、俺はパンチ男に話し掛けた。
「すまない。こいつ、ベロベロに酔っていて迷惑を掛けたみたいで……」
「おいおい、何だその謝り方はよ?」
気付けば俺たちは二十名以上の集団に囲まれていた。
どう見ても暴走族の集まりのようだ。
こちらの面子はゴリと二ノ宮、それに酔っ払った大沢。
かなりヤバい状況である。
「ゴリ…、俺が連中をどかすから、一気に走って逃げろ。いいな?」
すぐ後ろにいたゴリにしか聞こえない声で言う。
「ん…、ああ……」
チャンスは一度しかない。
「おら、何をゴチャゴチャ抜かしてんだ、おい」
パンチ男が俺の胸倉を掴んだ瞬間だった。
左腕でパンチの頭を押さえ下に押し、右腕で思い切り背中をぶっ叩く。
相手の胴体に両腕を回し、両手でガッチリとクラッチを組むと、一気に持ち上げた。
プロレス技でいうパワーボムの体勢である。
遠慮せず、畳の上目掛けて叩きつけた。
もちろん背中からちゃんと受身が取れるようにであるが……。
<iframe style="width: 100%; height: 752px; display: block; visibility: unset;" src="https://www.tiktok.com/embed/v2/6852152207056309506?lang=ja&referrer=https%3A%2F%2Fblog.goo.ne.jp%2Fadmin%2Fnewentry%2F&embedFrom=oembed" name="__tt_embed__v87235338459272220" sandbox="allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-scripts allow-top-navigation allow-same-origin"></iframe>
自分のした行為がどれだけ理不尽か理解している。
自分たちが連れている女の乳首をいきなり触られたのだ。
怒りは相当なものである。
逆の立場でも同様に怒るだろう。
大沢のした行為はそれほど洒落にならないものなのだ。
しかしまずはこの窮地を脱しなければいけない。
周りの人間が怯んだのを確認すると、俺は一歩前に出てデカい声で言った。
「次にやられてえ奴はどいつだ!」
普通じゃ、あんな事をやらないというような大技をワザと目の前で見せたのだ。
当然相手は後ずさりする。
その隙にゴリと二ノ宮、大沢を外へ逃がした。
あとは俺がいつ逃げるタイミングを掴むかである。
目を剥き出しながら、相手を威嚇した。
あとちょっとで階段だ。
俺は方向転換し、一気に階段を駆け下りた。
「コラッ! ちょっと待てや、おいっ!」
「ふざけやがって!」
「殺してやるよ。おらっ!」
様々な罵声が背後から聞こえるが、一目散に階段を駆け下りる。
向こうも何をされるか分からないから、すぐに飛び掛っては来られないのだろう。
外へ出ると、先ほど逃がした杏たちがいて、「タクシー捕まえといたから早く乗って!」と大声で近づいてきた。
すぐそばでタクシーが停まっていて、後部座席にゴリと二ノ宮の姿が見える。
大沢は?
慌てて窓から中を覗き込むと、二人の膝枕の上で横になって寝ていた。
あれだけの騒ぎを起こしておいて呑気なものだ。
「君たちは……?」
「私たちは大丈夫。早く乗って! みんな、先に乗ってるから」
俺は手帳を破り、乱暴に電話番号を書くと「ありがとう。あとで連絡する」と言い残してタクシーの助手席へ乗り込んだ。
徹夜しながら酒を飲み、馬鹿な女連中に怒ってテーブルのちゃぶ台返しをして、店を出入禁止。
また飲み直して今度は乱闘騒ぎ。
さすがに体力も限界に来ていた。
そこへタクシーの揺れが加わる。
俺は一気に吐き気を覚えた。
「あ、あの~……」
一旦車を停めてもらおうと声を掛けたが、運転手は不機嫌そうな表情で黙ったまま運転をしている。
「す、すみません……」
もう一度声を掛けても、運転手は返事をしない。
嫌な客を乗せてしまったものだと思っているのだろう。
それにしても態度のなっていない運転手である。
そんなに嫌なら客として乗せなければいいのに……。
つまらない事を考えている内に、そろそろ限界がきた。
俺は咄嗟に窓を開け、外に向かって静かにゲロを吐く。
吐きながら、すごく楽に感じる自分がいた。
あの子たちはうまく逃げられただろうか?
二ノ宮の彼女である文江さんも。
その辺が気掛かりである。
非常に気の利く子たちだ。
あんな乱闘騒ぎの中、外でタクシーを捕まえて待っていてくれたのだから。
今度、キチンとお礼をしなきゃいけないな……。
俺はゲロを吐きながらそんな事を考えていた。
ちょっとして後ろから、「うわっ!」というゴリの声が聞こえてきた。
俺は極度の眠気から目を閉じると、深い眠りへ一気に引きずり込まれた。
目を覚ますと昼近くになっていた。
頭がガンガンする。
そういえばタクシーの助手席からゲロを吐いてからの記憶がまったくない。
みんなはどうしたのだろう……。
女性陣の事が気に掛かっていたので、二ノ宮に電話をしてみた。
「おはよう。昨日は大変だったね~」
思ったより二ノ宮は元気である。
自分とその彼女が組んだ飲み会があんなハメになったというのに、ひと言も俺を責めようとしない。
「二ノ宮の彼女の文江さんとか、大丈夫だった?」
「ああ、文江はあの三人の子たちと、あれから別のタクシーを捕まえて逃げたから問題ないよ」
「それは良かった……」
「あ、そうそう。あの三人組がまた僕たちと逢いたいって、文江に言ってたみたい。電話番号教えてもらったみたいだから、今度聞いて、岩ヤンに教えるね」
「何だかホッとしたよ。あのまま何のお礼もできないっていうのが一番嫌だからね」
「今日、文江は仕事だから、夜か明日ぐらいにまた聞いとくよ」
「悪いけど頼む。それと本当にすみませんでしたって伝えておいて」
「そんな気にしないで」
二ノ宮は笑いながら言う。
「そういえば、昨日タクシーに乗っている途中で寝ちゃったから、記憶がないんだけどさ。二ノ宮、状況覚えてる?」
「う~ん、僕も家に着く間に寝ちゃったからなぁ。よく覚えていないんだよね」
「そっか…。じゃあ、ゴリにでも聞いてみるよ。文江さんに本当ごめんなさいって言っといてね」
二ノ宮との電話を切り、次はゴリに掛けてみた。
「おう岩上か。昨日は参ったよ」
電話に出るなりゴリは、いきなりマシンガンのように喋りだした。
「俺と二ノ宮が後ろで大沢を乗せていて、暑かったから窓を開けたんだ。夜風が頬に当たって気持ち良くてさ。つい、俺も寝ちゃったんだよ。そしたら頬に水滴がついたから、『ん、雨か……』って目を開けたら、おまえが窓からゲロを吐いているじゃねえかよ。俺、慌てて『うわっ!』って窓閉めたけどさ」
「ははは、悪い悪い」
俺のやった行為はとても酷いものだ。
しかしゲロを掛けた相手がゴリというのもあって、あまり罪の意識を感じなかった。
前回俺がゴリのを掛けられているし……。
「悪いじゃねえよ、まったく」
「いいじゃねえかよ。前におまえだって俺にゲロ掛けたんだし」
「そういえば昨日、俺が話していた宗岡さくらって子いたじゃん」
「ああ、彼女がどうした?」
「いや、ああいう子いいなあと思ってさ」
ゴリと宗岡さくら……。
ハッキリ言ってつり合わない気がしたが、好きだという気持ちが芽生えるのは悪い事じゃない。
それに『CPL』当初の目的であるゴリに彼女を作ろうという目的意識にも繋がる。
あの三人組の中で、俺自身も宗岡さくらを気に入っていた。
ゴリと話をしていなければ、俺が口説きたかったぐらいである。
しかしゴリが気に入っているのだ。
ここは潔く身を引こうじゃないか。
それが『CPL』会長としての役目でもある。
「うん、あの子、気遣いもできて本当にいい子だよな。ああいう子、彼女にできたらすげー幸せだぜ」
ゴリのテンションを上げようと、俺も必死に自分の気持ちを隠しながらフォローした。
「そうだよなあ」
「あ、そういえばさっき二ノ宮に電話したらさ。彼女の文江さんに、俺らとあの三人組がまた一緒に飲みたいって言ってたらしいよ?」
「え、ほんと?」
「連絡先は文江さんが知っているから、二ノ宮があとで聞いとくって」
「またあの子と逢えるのか~」
「いいチャンスじゃないか。ゴリ、気合い入れろよ!」
「いくつくらいなんだろ」
「俺らの三つ上って言ってたから、二十三歳でしょ」
「えっ?」
驚いた声を上げるゴリ。
「どうした?」
「三つ上? じゃあ、いいや……」
「おまえさ……」
「だって俺、年上好きじゃねえもん」
「……」
さっきまでいいって絶賛していたのは誰だ。
この男の理不尽ぶりには、ほとほと愛想が尽きる。
「おまえさ~……」
「しょうがねえじゃん。俺、年上好きじゃねえもん」
一度も彼女ができた事がないくせに、何をこの男は自惚れているのだろうか?
頭の構造がまったく理解できない。
出されたおかずを素直に食ってろと言いたい。
「三つしか変わらないだろうが! それにまだ付き合うとかそんな段階でもないのに……」
「俺はあの三人組との飲み会はいいや。年下のほうが好きだから」
「勝手にしろ、馬鹿!」
こうして『CPL』は俺の独断により、潰す事が決定した。
先日の電話での口論により、ゴリとしばらく会う機会はなかった。
俺は俺の道を行けばいい。
全日本プロレスのプロテストに受かった俺に、合宿の日が近づきつつあった。
あんな奴の彼女を作る為に時間を割くぐらいなら、トレーニングに没頭しないと……。
それからの俺はコンディション作りに励み、日々ストイックな生活を送っていた。
所沢乱闘事件の張本人である大沢から、何度も謝りの電話があり、最初は怒っていたが仕方なく許してあげる事にした。
合宿前日に大沢から電話があり、「この間のお詫びも込めて、明日から合宿に行く岩ヤンの祝賀会をしたい」と申し出があった。
気持ちは嬉しいが、明日からプロの合宿である。
そんな甘い世界ではない。
日々鍛錬しているトレーニングが、まるで通用しないかもしれないのだ。
「悪いけど、さすがに時期が悪いよ」と断ると、大沢は「ちょっとの時間でいい。そうじゃないと俺の気持ちが済まないよ」と懇願してくる。
「明日から大変な世界に行くんだし、地元の人間で華やかに送り出したいじゃん」とも言ってきた。
ここ最近ストイックな生活をしているせいで酒など飲んでいない。
それで大沢の気持ちが納まるのなら、ちょっとぐらいいいかと感じた。
「じゃあ、ちょっとの時間ならいいよ。面子は誰が来るの?」
「まだ二ノ宮ぐらいにしか声を掛けてないけど…。あ、ゴリにも声掛けとくよ。とりあえず駅前のいつもの居酒屋に七時集合でいいでしょ?」
「まったく…。明日があるから俺はすぐに帰るからね」
「分かってるって。形だけお祝いしたいだけなんだから」
中学時代から一緒につるんできた仲間である。
内心大沢の心遣いが嬉しかった。
明日に響くといけないから、酒の量は考えないとな……。
時間が来て、俺は駅前の居酒屋へ向かう。
大沢と二ノ宮は先に到着して中で待っていた。
「あれ、ゴリは?」
「あいつ、冷たいんだよ」
「何で?」
「岩ヤンの祝賀会だからって言っているのに、『俺は眠いからいいよ』って電話切りやがった」
あの野郎……。
イライラしたが、明日から地獄のような場所へ行くのである。
今は出来る限りニコニコしていたい。
「岩ヤンからゴリに電話してみれば違うんじゃない?」
「えー、いいよ。来たくないんなら、来なきゃいいよ」
「まあまあ、そんな事言わないでさ。僕も一緒に誘ってみるから」
二ノ宮と二人で電話ボックスへ行き、ゴリの家に電話を掛けてみた。
「あーもしもし」
ゴリ独特のダミ声が聞こえる。
本人が出たようだ。
「おまえさ、今日は俺の祝賀会なんだよ。ちょっとぐらい顔出せよ」
「仕事終わって眠いんだよ」
「それは分かるけど、俺、明日から地元をしばらく離れるんだぞ?」
「そうかもしれないけど、眠いんだよ」
「眠いってまだ七時じゃねえかよ」
「今日は疲れているんだよ」
この男に友情などひと欠片もないのだろうか?
「おまえさー……」
「眠いもんは眠いんだよ。じゃあな」
ガチャン……。
ゴリの電話を切る音が無情に鳴り響く。
あのクソ野郎が……。
イライラしながら席へ戻り、仕方なく野郎三人で寂しく乾杯をした。
しばらくみんな、ゴリの愚痴ばかり言っていた。
「だいたいあいつはさ、感謝ってもんが足りないんだよ」
「いや、感謝というよりも、誠意ってもんがない」
「う~ん、誠意というより、頭が悪いだけなんだよ」
「でもさ、俺にひと言、『明日頑張れよ』ぐらい言っても罰当たらねえぞ」
「そりゃそうだ」
「ゴリのあの妙な自信は、一体どこから来るのかね?」
「あいつ、今までに何人の女にフラれてきた?」
「う~ん、何人ぐらいだろ」
「ちょっと整理してみるか」
俺たちはゴリのフラれた歴史を振り返ってみた。
まず、彼の伝説が始まったのが、社会人になった十八歳の寒い冬の日だった。
俺とゴリが、近くのファミリーレストランで食事をしていた時の話である。
「なあ、か、岩上……」
俺が大好物のハンバーグを口一杯に頬張っている時に、タイミングも見計らず自分勝手にゴリは声を掛けてくる。
知らない人が聞いたら、すごいダミ声に聞こえるだろう。
「何だよ、ゴリ。いつもいつも間の悪い時にばっかり、話し掛けてきやがんなあ」
「ああ、わりーわりー」
本当に格好というかポーズだけ謝るゴリ。
左手で頭をポリポリ掻きながら不満そうな顔をしている。
「…で、どうしたんだよ?」
「そ、そろそろさー…。今、働いている所を辞めようと思ってさ」
「いきなり何だよ。何かあったのか? それとも不満でも?」
ゴリは食事中にも構わず、キャビンマイルドを口にくわえて火を点けだす。
すごい勢いで鼻から真っ白の煙を吐き出し、続け様に二本続けて吸う。
俺が不思議そうに見ていると優越感を感じたのか、何故かいやらしい笑みを薄っすら浮かべ、得意気な表情になる。
「俺らがよー、お互い就職してから、半年以上経つだろ?」
「そうだな…、ひょっとしてゴリ、もう今の仕事飽きたのか?」
「違うよ。そーじゃねーよ。ただ俺が今の会社入った時、『大型ルーキー』だって散々もてはやされたろ?」
確かこいつが今の印刷会社に入社した当時、俺と会う度「俺は大型ルーキーと呼ばれている」とか、よく自慢していたっけな。
まあ昔からの付き合いだから、うまい具合におだてられているか、勝手に都合良くそう解釈しているだけかもしれないとは思ってはいたが……。
「半年経って、もうルーキーじゃなくなったから辞めるとか言うんじゃないだろうな?」
「そんなんじゃないよ。今の凸版印刷での俺のやるべき事は終わったと感じてね。次に俺を必要とする会社に行くのもいいんじゃないかなと思ってるんだ」
「その新しい所から誘いか何かきたのか? うちに働きに来て欲しいとか?」
「違うよ」
「じゃあ、何で?」
「自分を試してみたいんだ」
明らかにゴリの台詞には嘘が混じっていた。
本来の気持ちを堂々と言っている訳ではないぐらい、こいつと長い付き合いの俺にはすぐ理解できた。
一体今の会社を辞めたいと言っている原因は何なのだろう。
「もう少し考えてみたら? 急いで会社を辞める必要性は何もないと俺は思うけどな」
「いや、このままでいいのかと自分自身、色々考えたんだ」
「じゃー、いちいち俺に相談する意味無いじゃん」
「相談じゃない」
「じゃー、何だよ?」
「報告だ」
ドッと全身に気だるさを覚えた。
ゴリと話す時は、よほどの忍耐力と辛抱強さが必要になってくる。
何故彼はゴリと呼ばれ、こうも理不尽なのだろうか。
彼を理解するには膨大なエネルギーがいる。
「多分、今の会社の歯車の一部分になるのが嫌なんだろうな」
ゴリが歯車という言葉を使うのは、間違っているような気がした。
「じゃあ勝手にすればいいじゃん」
「まあそう言うなって。今日はさ、ある話があるんだよ」
彼は昔からそのような時、必ずといっていいほど俺に協力を求めてきた。
「いいよ、別に聞きたくない」
「いいから聞けって、岩上」
ゴリのアクセント一つで、俺にはだいたい何を言いたいか予想がつく。
「だいたい何を言いたいか当ててやるよ。女関係で何かあったんだろ?」
「ん…、ああ…、やっぱ分かるか?」
図星をつかれた時のゴリはすぐに「ん…、ああ…」と話す前に必ずといっていいほど切り出す。
基本的に全部女がらみだと思っても間違いない。
「あー、これでもおまえとは、長い付き合いだからな」
「おまえには叶わないな」
「とりあえずいいから、話してみなよ」
しばらくゴリは黙っていた。
こういう時は大抵これから話す話を出来る限り頭の中で一生懸命に美化させているはずだ。
自分なりの間をとって静かにゴリは話し始める。
「俺の今の仕事のシフトは知ってるだろ?」
「隔週おきの日勤夜勤の繰り返しだろ。もちろんそのぐらいは把握してるよ」
「ああ、それで一週間ごとに俺が朝六時の電車に乗って会社に行くんだけどさ。日勤の時は乗る時間帯から車両からいつも同じ訳よ」
「…で?」
「いつも所沢から田無まで行くんだけど、途中の駅、小平の駅で俺と同じように同じ時間で同じ車両に乗ってくる女がいるんだ」
もう話が全部見えたようなものだった。
ゴリは通勤途中で一週間おきにいつも会うその女に恋をしてしまったのだろう。
「俺がチラッと見ると、向こうも俺を見てんだよな…。それで目が合うと向こうは視線を逸らすんだよ」
ん…、何やら面白い展開になってきそうだ。
俺の予想を裏切る面白そうな出来事の匂いがプンプンしてきた。
ここは出来る限りゴリを乗せて気分良く喋らせるに限る。
「へー、どういうつもりだろうね、その子」
「いや…、多分だけどさ…。いいや、やっぱやめとこう……」
「おいおい何だよ、そこまで話してもったいぶるなよ」
「ひょっとして、俺に気があるんじゃねーかと思ってさ」
危なく吹き出してしまうところだった。
十八年間、彼女のかの字すらできた事の無い男が、どこからその自信は出てくるのであろうか。
普通に考えたら、仕事の通勤で同じ車両、同じ時間に乗るのは当たり前のような気がするが……。
「よく俺のほうを見ているような暖かい視線を感じるんだよね。乗る駅は違うけど、彼女も俺と同じで田無の駅で降りるんだ。何か感じるものがあるだろ?」
俺には何も感じる事はなかったが、せっかくゴリが異性に対して重い腰を上げたのだ。
ここは乗せて頑張らせるしかない。
「へー、もしそうならゴリから誘っちゃえよ」
「えー、でもさー……」
俺はゴリの顔に迫り、マジマジと目を見て話す。
「いいかい、ゴリ…。例えばだけど、自分のタイプじゃない女から『好きです』って、いきなり告白されたとするよ……」
「俺は付き合わないなー」
「今はそんな事を聞いてるんじゃないって。その場合、全然タイプじゃなくても、自分自身の気持ちはどうだよ。嫌な気分になるか?」
「うーん、そりゃー、好きって告白されて気分を害す奴はいないだろ」
「…だろ?」
「ああ……」
もう一押しだ。
自分の中に眠る意地悪な人格が、ゴリの調子をのせようと口を軽くさせる。
「女だって一緒だよ。タイプじゃない奴に告白されたとしても、ムカつくとか思う訳ないだろ。やっぱり嬉しいはずだよ」
「い、いやー。この場合はちゃんと、彼女も俺のほうを見て……」
「だったら尚更だろ。きっと向こうはおまえが誘ってくるのを待ってるんだよ」
「そ、そうかな……」
「絶対にそうだって!」
「そ、そうかな……」
「きっとそうだよ!」
今まで一人で色々考えていたのだろう。
俺に話した事で急展開になったもんだからゴリは戸惑っている様子だ。
背中を押せ。
もう一息だ。
「いつ誘うんだ?」
「え、いつって……」
「結構その女っていい女なんだろ? モタモタしてると他の男に盗られちゃうぞ。いいのか、それで?」
「い、いい訳ないだろ」
「じゃー、早速、明日電車から降りたら誘っちゃえよ。今週はちょうど日勤だろ?」
「そうだけど……」
「明日金曜日だから、言わないと十日ぐらい間が空くぞ。その間に彼氏とかできてもいいのか? こういうのは早目早目が勝負なんだって。鉄は熱い内に打てって言うだろ?」
「俺は別に鉄じゃねーよ」
「馬鹿だなー、あくまでも例えだろ。例え」
「そ、そうか……」
「じゃ、明日に早速決行だな」
「待ってくれよ」
「待てないよ。俺にできる事あったら協力するから頑張りなって」
「ん…、ああ……」
俺のマシンガントークで、ゴリはその気になりつつあった。
「じゃあ明日、決行だぞ?」
「そ、そうだな……」
俺たちはそこで別れ、明日に備える事にした。
翌日の金曜日。
俺は普通に会社に行き定時を待って、寄り道もせずに真っ直ぐ家に帰った。
この頃はプロレスラーを目指していた訳でなく、普通のサラリーマンをしていたのだ。
当時は今みたいに携帯電話という物が無い時代だったので、自宅の電話で報告を待つしか方法がない。
果たしてゴリはちゃんと彼女を誘えたのか。
いや…、あいつの性格じゃ、声すら掛けられなかったのかもしれない。
他にする事がなく、ぼんやりと窓の外を眺めていると白いものが宙を舞っていた。
雪だ。
関東で雪が降るのは珍しい。
ひょっとしたら、これが最後の雪になるかもしれない。
俺は頭の中に一面の銀世界を思い描いた。
いい気分に浸っていると、自宅の電話がけたたましく鳴り出す。
受話器を手に取り耳に当てると、何やら相手は小声でブツブツ言っているが、よく聞き取れなかった。
「もしもしー? 岩上ですけど。もしもし…、もしもし?」
「寒いよー」
「へっ?」
「寒いよー」
「ゴリか?」
「ああ…。か、岩上。外は…、す、すげー寒いよ……」
「少し事情を言ってくれよ。話が全然見えない」
「いやー、今日さー。朝の電車で彼女に声を掛けたんだよ」
「おぉっ! それで、それで?」
勇気を懸命に振り絞ってゴリは話し掛けたのだろう。
それだけでも今までと比べたら格段な進歩だ。
「田無の駅に着いた時に捕まえて、『今日仕事終わったら話しあんだけど』ってハッキリ言ってさー。彼女にこの駅の改札で待ってるけどいいかなってね」
「それで相手は何て答えたんだ?」
「『はい、分かりました』って」
「いちいちダミ声で女の真似までしなくていいよ。それにしても、やったじゃん、ゴリ」
「ま、まーね」
こいつもやる時はやるもんだ。
今までにない頑張りに驚きを隠せない。
待てよ、喜ぶにはまだ早い……。
今話している出来事は、今朝の会話なのだ。
時計を見ると六時を回っていた。
さっきゴリが言った『寒いよー』という台詞を思い出すと、まだ彼女はその待ち合わせ場所に来ていない事になる。
ようするにゴリは雪の降るこの寒空の下で一時間ほど、待ちぼうけを食っている訳だ。
「まだ彼女は来てないのか?」
「当たり前だろ。来てたらワザワザ岩上なんかに電話するかよ」
相変わらずムッとするような言い草だ。
しかし今、ここで俺がムッとして突っ込んでも意味がない。
今の発言の借りはまた今度、お返ししてやればいいだろう。
「そんなに怒るなよ。待ってるって言っても、まだ、たったの一時間だろう?」
「あ、ああ……」
「じゃあ、たぶん残業かなんかで遅くなってんだろ。ところで今朝、どんな風に誘ったのよ。変な事言ってない?」
「変な事なんか言わねえよ。田無の駅で声掛けて、前から気になってたんだけど、今日、仕事終わったら少し時間とれないかなって言ったんだよ」
「へー、意外と正攻法だな」
「そしたら分かりましたって言うから、ここの駅の改札で待ち合わせにしたんだ」
実際その通りに誘ったのなら、ゴリにしては上出来だ。
「中々やるじゃん。あと少し頑張って待ってなよ。たださ、今、駅の公衆電話からだろ? 改札の傍でちゃんと待ってたほうがいいんじゃないの?」
「何でだよ?」
「だってもし彼女が改札に来て、おまえの姿が見えなかったら、すぐにそのまま帰ってもおかしくないだろ?」
「ああっ。岩上、電話切るぞっ」
俺の言葉にゴリは慌てて反応し、電話を切った。
それから一時間後俺がテレビを見ていると、突然自宅の電話が鳴った。
受話器を取る時に窓の外を見ると、雪はさっきよりも降りが酷くなっていて地面が白くなりつつあった。
「はい、もしもし岩上ですが……」
「まだ来ねえよー」
電話の相手はゴリだった。
雪の降る中、外で二時間……。
ゴリの声はかなり弱々しくなっていた。
「どっかでコーヒーか何か飲んでて、彼女が来たのを見逃したんじゃないの?」
「そんな事はねーよ。俺、ずっと改札の所で待ってたから」
二時間……。
何て言っていいか微妙な時間だ。
返答に困る。
「おまえ、本当に彼女と今朝、約束したのか?」
「ああ、したよ」
「ほんとかー?」
「ほんとだよ。じゃなきゃ、こんな雪の降る寒い日にわざわざ二時間も待たねえよ」
確かにゴリの言う通りだ。
ここまでゴリが気合い入っている以上、俺は友達として元気付けてやらないといけない。
そんな使命感に駆られた。
「じゃあ、せっかく二時間も待ったんだ。まだ頑張って待ち続けろよ。な?」
「でも寒いよー」
「何、寝言言ってんだよ。待つのが嫌ならとっとと帰ればいいだろ。これはおまえと彼女の問題なんだから。寒いぐらいなんだよ。気合いで吹き飛ばせよ」
「き、気合いで暖かくなるなら、今すぐそうしてるよ」
「馬鹿。俺だって前に一人の女を雪の中三時間待った事だってあるぞ。そういう頑張りがあるからこそ、女だってグッとくるもんなんじゃねえの?」
「そ、そうだよな。わりーな…。俺、もうちょっと頑張るよ」
さっきまでの弱々しい声は嘘のようなぐらい、力の籠もった声だった。
時計を見ると十時五分前になっていた。先ほどの電話から約二時間経つ。
あれから電話ないところを見ると、今頃彼女とレストランで楽しく食事をしてるのだろう。
思えば苦節二十年。
やっと好きな人への想いが通じ、ゴリにも幸せが訪れそうなのだ。
俺は素直に祝福してあげたかった。
まだ付き合えるかどうかのハードルはあるにせよ……。
雪は止む気配もなく、辺り一面銀世界を作り上げていた。
こんな寒い日にあれだけ待ったんだから、ゴリの喜びは今までにない至福の幸せを感じているのではないだろうか。
そう考えると、何故か自分ごとのように嬉しかった。
「ボーン…。ボーン…。ボーン…。ボーン…。ボーン…。ボーン……」
十時になった合図の音を時計が奏でる。
音が十回鳴り終わる頃、まるでその音のあとを引き継ぐかのように電話が鳴り出した。
「はい…、もしもし岩上ですが……」
「さ…、さ…、む…、ぃ……」
「はあ?」
今の声はひょっとしてゴリの声だったのか……。
まさか……。
「おい、ゴリか? ゴリなのか?」
「さ…、さ…、む…、ぃ……」
何て事だろうか。
恐らく今までこの大雪の中、時間にして約四時間もゴリは電車で恋した女を待ち続けていたのだ。
「大丈夫かよ? おい…、おいっ」
「さ…、さみー…、よー……」
「今、田無の駅か? とりあえず近くの喫茶店にでも入ってろよ。すぐそっちに行くから。なっ? 分かったか? おいっ! ゴリ、返事しろよ!」
俺は電話を切って、大急ぎで外出する服に着替えた。
あのバカ野郎…、何だってこんな雪の中こんな時間まで待ってんだ。
今にも死にそうな声だったじゃねえか。
お湯を沸かし、ブルーマウンテンとキリマンジャロをブレンドさせ、暖かいコーヒーを淹れる。
魔法ビンにコーヒーを入れると、俺は外へ飛び出す。
フロントガラスに積もった雪を手で乱暴に掻き分け、車をすぐに発進させた。
田無の駅までいくら飛ばしても三十分は掛かってしまう。
この雪道で思うようにスピードを出せない。
駅に着き辺りを見回すと、電話ボックスの中で座り込んでいるゴリの姿が見えた。
俺は車から飛び出て、ゴリの元までダッシュで駆け寄る。
「大丈夫かよ、ゴリ!」
「おう、岩上。この中で温かい缶コーヒー飲んでたら幾分、温まった」
「とりあえず車に乗れよ」
「ああ……」
俺とゴリは車に乗っても、お互いしばらく無言だった。
所沢に着くまで、一言も口を開かなかった。
四時間もこの雪の中、待たされて裏切られたゴリの心情を考えると目頭が熱くなってくる。
「腹減ってないか?」
「い、いや…、頭がボーっとする……」
ゴリの額に手を当てると、すごい熱がありそうだった。
ずっと待ち続けろとアドバイスした自分を恨めしく思う。
「何か俺にできる事あるか?」
「とりあえず今日は帰って寝たい……」
「分かった、おまえの家まで送ればいいな?」
「ああ……」
「大丈夫か?」
「さ、さみぃー…。岩上、そういやあよ……」
「どうした?」
「ひ、一つおまえに嘘ついちまった」
「何を?」
「ほんとはずっと外で待ってたんじゃないんだ……」
「何の事?」
「途中であまりにも寒くて、近くのコーヒーショップに十五分だけ入ちゃったんだ……」
「馬鹿だなー。それでもおまえは四時間、彼女を駅で待ち続けたんだろ?」
「ああ……」
「それなら、そんな事恥じる必要はないさ」
その日はゴリを無事、家まで送り届け休ませる事にした。
家まで送る最中もゴリはずっと、『さみぃーさみぃー』と呪文のように繰り返し唱えていたのが、印象的だった。
これが『雪の振る中四時間待ちぼうけ事件』の前編である。
俺がここまで話すと、二ノ宮は興味津々に「続きはあるの?」と聞いてくる。
子供がお菓子をせがむようなキラキラした目で俺を見つめる二ノ宮。
「もちろん、ここまでじゃ伝説にならないだろ」
俺は笑いながら、続きを話す事にした。











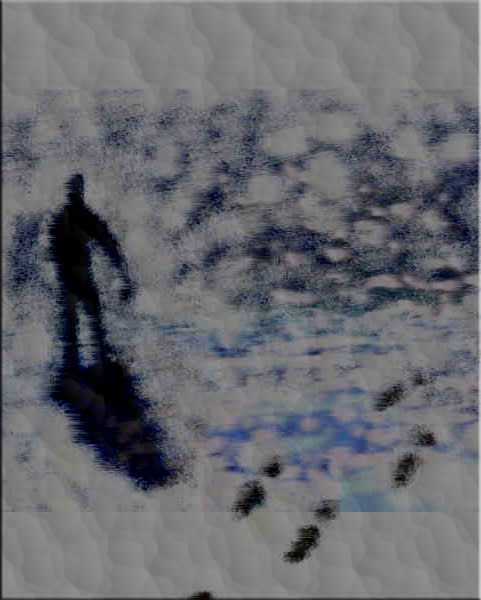






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます