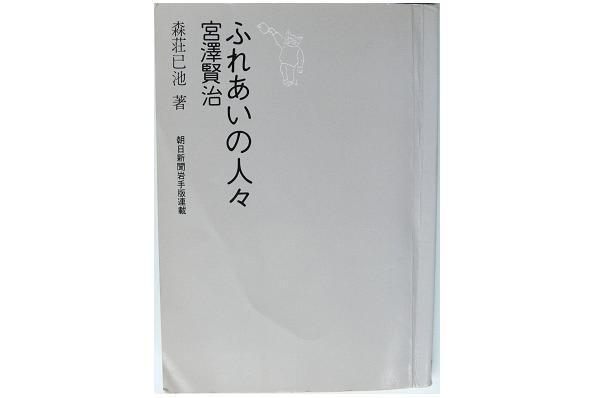
<1↑『ふれあいの人々』(森荘已池著、熊谷出版)>
前回のブログ”草野心平とはどんな人?”の中に、宮澤賢治を『中央で認めたのは佐藤惣之助と辻潤、心平の三人であった』とあったので、今回はその辻潤と佐藤惣之助について投稿したい。『宮澤賢治研究』の中にこの2人の小論があったから、その中から一部を拾ってみる。
1.辻潤について
『宮澤賢治研究』の中にダダイスト辻潤のしるした著した「惰眠洞妄語」という章がある。おそらくこれは大正13年7月23日付け読売新聞に掲載されたものとほぼ同一のものだと思う。
惰眠洞妄語
辻潤
宮澤賢治といふ人は何処の人だか、年がいくつなのだか、何をしてゐる人なのだか、私はまるで知らない。しかし、私は偶然にも近頃、その人の『春と修羅』といふ詩集を手にした。
近頃珍しい詩集だ―私は勿論詩人でもなければ、批評家でもないが―私の鑑賞眼程度は、若し諸君が私の言葉に促されてこの詩集を手にせられるなら直ちにわかる筈だ。
私は由来気まぐれで、甚だ好奇心に富んでゐる。しかし、本物とニセ物の区別位は出来る自信はある。私は今この詩集から沢山のコーテーションをやりたい欲望があるが、「わたくしといふ現象は、仮定された有機交流電燈の、ひとつの青い照明です(あらゆる透明な幽霊の複合体)―」といふのが文中の始まりの文句なのだが、この詩人はまつたく特異な個性の持ち主だ。
…(略)…
若し私がこの夏アルプスへでも出かけるなら私は『ツァラトゥストラ』を忘れても『春と修羅』を携えることを必ず忘れはしないだらう。
夏になると私は好んで華胥の国に散歩する。南華真経を枕として伯昏夢人や、列禦冠の輩と相往来して四次元の世界に避暑する。汽車賃もなんにも要らない。嘘だと思ふなら僕と一緒に遊びに行つて見給へ。
<『宮澤賢治研究』(草野心平編、十字屋書店)より>
<註> 華胥=昼寝、南華真経=荘子、伯昏夢人=伯昏無人?、列禦冠は列禦「寇」?、列禦寇=列子
さてこの人物、辻潤とは、『Yahoo!百科事典』によれば
辻潤(1884―1944)
東浅草生まれの翻訳家・評論家で、開成尋常中学校中退後、国民英学会等に学ぶ。小学校教師を経て上野女学校に勤務。そこで教え子伊藤野枝と恋愛、退職。その後、野枝が大杉栄のもとに走ってからは辻は放浪生活。世紀末文学・思潮を翻訳、ニヒリズムの傾向を深め、虚無的自我主義を打ち出す。高橋新吉を知ってダダイズムとアナキズムに接近。評論集『ですぺら』でダダの反逆精神を論じた。1932年頃から精神錯乱により入退院を繰り返し、35年『痴人の独語』、翌年『孑以前』刊行の後、全国行脚。昭和19年アパートの一室で餓死。
<『Yahoo!百科事典』による>
というような人のようだ。かなり破天荒で博覧強記、そしてなかなかの強者のようだ。
そして、
「若し私がこの夏アルプスへでも出かけるなら私は『ツァラトゥストラ』を忘れても『春と修羅』を携えることを必ず忘れはしないだらう」
という言い回しで宮澤賢治のことを褒めちぎっているが、”この夏アルプスへでも出かけるなら”と当時言うくらいだから、辻は毎年上高地に避暑に出かけるような身分や環境にあったに違いなく、おそらくかなりの上流家庭で育った人物に違いないと思った。
実際、たしかに辻の生家は初めの頃は裕福だったという。ところが、潤が開成中学に入学した頃から次第に没落し始めたという。多分それが故に同中学を退学せざるを得なかったのだろう。
たしかにダダイスト辻潤にすれば、賢治の心象スケッチ「春と修羅」は共鳴する点が多かったはずである。既成の権威・道徳・習俗・芸術形式の一切を否定する(<広辞苑より>)ダダイズムに近づいていった辻からみれば、心象スケッチ「春と修羅」はそれまでの詩と比較すれば極めて個性的・独創的だからその新鮮さや斬新さに魅惑され、圧倒されたに違いない。
2.佐藤惣之助について
まずは『Yahoo!百科を事典』を見てみる。おおよそ次のような人物であるようだ。
佐藤惣之助(さとうそうのすけ)(1890―1942)
神奈川県生まれの詩人。暁星中学附属仏語専修科に学び、佐藤紅緑に師事して俳句を詠んだ。千家元麿らと知り合い『白樺』的な人間主義から生命感と感覚性豊富な詩風に移り、晩年は戦争や時局に歩調をあわせた詩を書いた。詩集は『正義の兜』『わたつみの歌』など22冊があり、主宰した『詩之家』(1925.7創刊)から多くの新人を出した。晩年には古賀政男と組み、『赤城の子守唄』や『人生劇場』などの作詞もした。
<『Yahoo!百科事典』による>
前回触れたように、大正13年12月の「日本詩人」に佐藤惣之助氏が賢治の詩の言葉の特異性に注目して「奇犀冷徹その類を見ない。大正十三年度の最大の収穫である」と絶賛したということだったが、この佐藤は『宮澤賢治』というタイトルで次のような小論を書いている。
宮澤賢治
佐藤惣之助
宮澤賢治!の名は、草野心平君から紹介された。
草野君は、その他数人の詩人を紹介してくれた。友に私の嘱望の詩人である。
以上の人は、殆ど私の對蹠の人々である。それが為に私は熱心に読んだ。そして感心した。
ことに宮澤訓の場合、「春と修羅」は私を驚かした。私も且つて「華やかな散歩」を世に問ふ時に、従来の詩語詩藻に一切據るまいといふプライドをもつてした。ところが「春と修羅」の場合は、そんなものは頭から蹴飛ばしてゐた。
「詩語詩藻の一切なる詩集」これは珍しいものだ。さういつて私は一紹介文を書いた。そして云つた。((宮澤君のやうに新しく、宮澤君のやうにオリヂナリテーをもつて、君も詩を成したまへ。))
そこには、天文、地質、植物、化學の術語とアラベスクのやうな新語體の鎖が、盡くることなく廻轉してゐた。例へば「小岩井農場」の如き。
そこには私達の持たない峻烈な、雪線的氣芳があつた。蜒蜿たる龍骨があつた。そして、紫外、赤外線的、科學的風景が果てしなく把述されてゐた。
これは當時の詩壇の驚異であつたが、「春と修羅」は一般に読まれずに終つたらしい。特に私は人に奨めて、その寄贈本さへ、今は失ってしまつた。…
<『宮澤賢治研究』(草野心平編、十字屋書店)より>
<註>詩藻=詞藻(言葉のあや)?、氣芳=芳気?、蜒蜿=蜿蜒(延延)?
ついいままでは、辻潤も佐藤惣之助も共にそれぞれ独自に賢治の凄さを発見していたと思っていたのだが、佐藤の場合は辻とは異なり草野心平から紹介されて知ったということだったのだ。すると、草野の役割の方が遥かに佐藤よりも大きかったことがこのことからも知らされる。
3.森荘已池
そしてあれっと思ったのが、佐藤は一体誰から詩集『春と修羅』を寄贈されたのだろうか、もしかすると森荘已池だったりして…ということである。
というのは『ふれあいの人々』の中に森荘已池は次のようなことを書いているからである。
…大正十四年、私が上京したとき「春と修羅」は神田の古本屋でなくて夜店の古本屋に出ていた。
神楽坂、本郷、新宿、渋谷、神田のアセチレンの光の下に、二、三冊ずつ一冊十銭也でゾッキ本にまじって売られているのを見た。
…
私が「岩手詩人協会」をつくったとき、賢治は機関誌の「貌」の刊行費にと「春と修羅」「注文の多い料理店」を三十冊ずつくれた。私はどうすれば売れるのかを知らない中学生だった。賢治は「会員の皆様に買ってもらって『貌』の印刷費にすればいいでしょう」と、言ってくれたのだが―。…
私は上京するとき、「春と修羅」を売って「貌」の印刷費を作ろうと東京に運んだ。
だが、ケチネ氏が売り払った大量?の「春と修羅」が二十銭、三十銭で神田や本郷、新宿などの夜店の古本屋に、二、三ずつ出回っていたので、驚いてみな寄贈してしまった。何れ当時の有名無名の詩人たちに贈ったものと思うが、名簿もないので全く不明である。…
<『ふれあいの人々』(森荘已池著、熊谷出版)より>
<註>ここでいう『ケチネ氏』とは神田の古本屋関根書店の店主の関根喜太郎のことであり、当時は神田の書店組合長であったという。
前述の通り佐藤は『春と修羅』を買ったとは言っておらず寄贈を受けたということだから、森が”驚いて”寄贈した有名無名の詩人の中の一人に佐藤惣之助がいたのかも知れない。もしそうであったとしたならば、森の怪我の功名?だったということになろう。
それにしても、『春と修羅』は大正13年に関根書店から一冊2円40銭(かなり高価!)で発売され、発行部数は1,000冊だったということだが、1年ほどで「ゾッキ本」に混じって夜店で売られていたとは意外であった。
なお参考に、森が上京した年1925年(大正14年)の年齢を示せばそれぞれおおよそ
辻 潤(1884~1944)=41才(ダダイスト?)
佐藤惣之助(1890~1942)=35才(同人誌『詩之家』刊行等)
宮澤 賢治(1896~1933)=29才(花巻農学校教諭)
草野 心平(1903~1988)=22才(広東嶺南大学生)
黄 瀛(1906~2005)=19才(「朝の展望」が『日本詩人』第一席入選巻頭を飾る)
森 荘已池(1907~1999)=18才(盛岡中学学生)
である。辻と佐藤は賢治より年上、草野、黄、森はいずれも賢治より年下であった。
続き
 ””のTOPへ移る。
””のTOPへ移る。
前の
 ””のTOPに戻る
””のTOPに戻る
 ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。
”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。
 ”目次(続き)”へ移動する。
”目次(続き)”へ移動する。
 ”目次”へ移動する。
”目次”へ移動する。
前回のブログ”草野心平とはどんな人?”の中に、宮澤賢治を『中央で認めたのは佐藤惣之助と辻潤、心平の三人であった』とあったので、今回はその辻潤と佐藤惣之助について投稿したい。『宮澤賢治研究』の中にこの2人の小論があったから、その中から一部を拾ってみる。
1.辻潤について
『宮澤賢治研究』の中にダダイスト辻潤のしるした著した「惰眠洞妄語」という章がある。おそらくこれは大正13年7月23日付け読売新聞に掲載されたものとほぼ同一のものだと思う。
惰眠洞妄語
辻潤
宮澤賢治といふ人は何処の人だか、年がいくつなのだか、何をしてゐる人なのだか、私はまるで知らない。しかし、私は偶然にも近頃、その人の『春と修羅』といふ詩集を手にした。
近頃珍しい詩集だ―私は勿論詩人でもなければ、批評家でもないが―私の鑑賞眼程度は、若し諸君が私の言葉に促されてこの詩集を手にせられるなら直ちにわかる筈だ。
私は由来気まぐれで、甚だ好奇心に富んでゐる。しかし、本物とニセ物の区別位は出来る自信はある。私は今この詩集から沢山のコーテーションをやりたい欲望があるが、「わたくしといふ現象は、仮定された有機交流電燈の、ひとつの青い照明です(あらゆる透明な幽霊の複合体)―」といふのが文中の始まりの文句なのだが、この詩人はまつたく特異な個性の持ち主だ。
…(略)…
若し私がこの夏アルプスへでも出かけるなら私は『ツァラトゥストラ』を忘れても『春と修羅』を携えることを必ず忘れはしないだらう。
夏になると私は好んで華胥の国に散歩する。南華真経を枕として伯昏夢人や、列禦冠の輩と相往来して四次元の世界に避暑する。汽車賃もなんにも要らない。嘘だと思ふなら僕と一緒に遊びに行つて見給へ。
<『宮澤賢治研究』(草野心平編、十字屋書店)より>
<註> 華胥=昼寝、南華真経=荘子、伯昏夢人=伯昏無人?、列禦冠は列禦「寇」?、列禦寇=列子
さてこの人物、辻潤とは、『Yahoo!百科事典』によれば
辻潤(1884―1944)
東浅草生まれの翻訳家・評論家で、開成尋常中学校中退後、国民英学会等に学ぶ。小学校教師を経て上野女学校に勤務。そこで教え子伊藤野枝と恋愛、退職。その後、野枝が大杉栄のもとに走ってからは辻は放浪生活。世紀末文学・思潮を翻訳、ニヒリズムの傾向を深め、虚無的自我主義を打ち出す。高橋新吉を知ってダダイズムとアナキズムに接近。評論集『ですぺら』でダダの反逆精神を論じた。1932年頃から精神錯乱により入退院を繰り返し、35年『痴人の独語』、翌年『孑以前』刊行の後、全国行脚。昭和19年アパートの一室で餓死。
<『Yahoo!百科事典』による>
というような人のようだ。かなり破天荒で博覧強記、そしてなかなかの強者のようだ。
そして、
「若し私がこの夏アルプスへでも出かけるなら私は『ツァラトゥストラ』を忘れても『春と修羅』を携えることを必ず忘れはしないだらう」
という言い回しで宮澤賢治のことを褒めちぎっているが、”この夏アルプスへでも出かけるなら”と当時言うくらいだから、辻は毎年上高地に避暑に出かけるような身分や環境にあったに違いなく、おそらくかなりの上流家庭で育った人物に違いないと思った。
実際、たしかに辻の生家は初めの頃は裕福だったという。ところが、潤が開成中学に入学した頃から次第に没落し始めたという。多分それが故に同中学を退学せざるを得なかったのだろう。
たしかにダダイスト辻潤にすれば、賢治の心象スケッチ「春と修羅」は共鳴する点が多かったはずである。既成の権威・道徳・習俗・芸術形式の一切を否定する(<広辞苑より>)ダダイズムに近づいていった辻からみれば、心象スケッチ「春と修羅」はそれまでの詩と比較すれば極めて個性的・独創的だからその新鮮さや斬新さに魅惑され、圧倒されたに違いない。
2.佐藤惣之助について
まずは『Yahoo!百科を事典』を見てみる。おおよそ次のような人物であるようだ。
佐藤惣之助(さとうそうのすけ)(1890―1942)
神奈川県生まれの詩人。暁星中学附属仏語専修科に学び、佐藤紅緑に師事して俳句を詠んだ。千家元麿らと知り合い『白樺』的な人間主義から生命感と感覚性豊富な詩風に移り、晩年は戦争や時局に歩調をあわせた詩を書いた。詩集は『正義の兜』『わたつみの歌』など22冊があり、主宰した『詩之家』(1925.7創刊)から多くの新人を出した。晩年には古賀政男と組み、『赤城の子守唄』や『人生劇場』などの作詞もした。
<『Yahoo!百科事典』による>
前回触れたように、大正13年12月の「日本詩人」に佐藤惣之助氏が賢治の詩の言葉の特異性に注目して「奇犀冷徹その類を見ない。大正十三年度の最大の収穫である」と絶賛したということだったが、この佐藤は『宮澤賢治』というタイトルで次のような小論を書いている。
宮澤賢治
佐藤惣之助
宮澤賢治!の名は、草野心平君から紹介された。
草野君は、その他数人の詩人を紹介してくれた。友に私の嘱望の詩人である。
以上の人は、殆ど私の對蹠の人々である。それが為に私は熱心に読んだ。そして感心した。
ことに宮澤訓の場合、「春と修羅」は私を驚かした。私も且つて「華やかな散歩」を世に問ふ時に、従来の詩語詩藻に一切據るまいといふプライドをもつてした。ところが「春と修羅」の場合は、そんなものは頭から蹴飛ばしてゐた。
「詩語詩藻の一切なる詩集」これは珍しいものだ。さういつて私は一紹介文を書いた。そして云つた。((宮澤君のやうに新しく、宮澤君のやうにオリヂナリテーをもつて、君も詩を成したまへ。))
そこには、天文、地質、植物、化學の術語とアラベスクのやうな新語體の鎖が、盡くることなく廻轉してゐた。例へば「小岩井農場」の如き。
そこには私達の持たない峻烈な、雪線的氣芳があつた。蜒蜿たる龍骨があつた。そして、紫外、赤外線的、科學的風景が果てしなく把述されてゐた。
これは當時の詩壇の驚異であつたが、「春と修羅」は一般に読まれずに終つたらしい。特に私は人に奨めて、その寄贈本さへ、今は失ってしまつた。…
<『宮澤賢治研究』(草野心平編、十字屋書店)より>
<註>詩藻=詞藻(言葉のあや)?、氣芳=芳気?、蜒蜿=蜿蜒(延延)?
ついいままでは、辻潤も佐藤惣之助も共にそれぞれ独自に賢治の凄さを発見していたと思っていたのだが、佐藤の場合は辻とは異なり草野心平から紹介されて知ったということだったのだ。すると、草野の役割の方が遥かに佐藤よりも大きかったことがこのことからも知らされる。
3.森荘已池
そしてあれっと思ったのが、佐藤は一体誰から詩集『春と修羅』を寄贈されたのだろうか、もしかすると森荘已池だったりして…ということである。
というのは『ふれあいの人々』の中に森荘已池は次のようなことを書いているからである。
…大正十四年、私が上京したとき「春と修羅」は神田の古本屋でなくて夜店の古本屋に出ていた。
神楽坂、本郷、新宿、渋谷、神田のアセチレンの光の下に、二、三冊ずつ一冊十銭也でゾッキ本にまじって売られているのを見た。
…
私が「岩手詩人協会」をつくったとき、賢治は機関誌の「貌」の刊行費にと「春と修羅」「注文の多い料理店」を三十冊ずつくれた。私はどうすれば売れるのかを知らない中学生だった。賢治は「会員の皆様に買ってもらって『貌』の印刷費にすればいいでしょう」と、言ってくれたのだが―。…
私は上京するとき、「春と修羅」を売って「貌」の印刷費を作ろうと東京に運んだ。
だが、ケチネ氏が売り払った大量?の「春と修羅」が二十銭、三十銭で神田や本郷、新宿などの夜店の古本屋に、二、三ずつ出回っていたので、驚いてみな寄贈してしまった。何れ当時の有名無名の詩人たちに贈ったものと思うが、名簿もないので全く不明である。…
<『ふれあいの人々』(森荘已池著、熊谷出版)より>
<註>ここでいう『ケチネ氏』とは神田の古本屋関根書店の店主の関根喜太郎のことであり、当時は神田の書店組合長であったという。
前述の通り佐藤は『春と修羅』を買ったとは言っておらず寄贈を受けたということだから、森が”驚いて”寄贈した有名無名の詩人の中の一人に佐藤惣之助がいたのかも知れない。もしそうであったとしたならば、森の怪我の功名?だったということになろう。
それにしても、『春と修羅』は大正13年に関根書店から一冊2円40銭(かなり高価!)で発売され、発行部数は1,000冊だったということだが、1年ほどで「ゾッキ本」に混じって夜店で売られていたとは意外であった。
なお参考に、森が上京した年1925年(大正14年)の年齢を示せばそれぞれおおよそ
辻 潤(1884~1944)=41才(ダダイスト?)
佐藤惣之助(1890~1942)=35才(同人誌『詩之家』刊行等)
宮澤 賢治(1896~1933)=29才(花巻農学校教諭)
草野 心平(1903~1988)=22才(広東嶺南大学生)
黄 瀛(1906~2005)=19才(「朝の展望」が『日本詩人』第一席入選巻頭を飾る)
森 荘已池(1907~1999)=18才(盛岡中学学生)
である。辻と佐藤は賢治より年上、草野、黄、森はいずれも賢治より年下であった。
続き
 ””のTOPへ移る。
””のTOPへ移る。前の
 ””のTOPに戻る
””のTOPに戻る ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。
”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。 ”目次(続き)”へ移動する。
”目次(続き)”へ移動する。 ”目次”へ移動する。
”目次”へ移動する。

















先ごろ『「ヒドリ」か、「ヒデリ」か』と題したごく簡略な小著を上梓したばかりですので、ぜひ一本を献呈させていただき、ご笑覧に供したいと存じます。はがきにて、お名前・ご住所を教えて頂く訳にはまいりませんでしょうか。小生の住所は213-0015 川崎市高津区梶ケ谷 6 - 6 - 18でございます。
折角のお話ですので、厚かましくもお葉書にて住所等をご連絡いたしますのでよろしくお願いいたします。
ご返事と御礼おそくなって申し訳ございません。
ご教示ありがとうございました。
今後は、もう少し裏付けをとってから投稿したいと思います。
鈴木 守
古賀メロディーの一世風靡と賢治のあの有名な「雨ニモマケズ」が同時代とは。意外でした。
お早うございます。
コメントありがとうございました。
はい、私も菊池清麿氏の論考は、専門家から観た賢治を論じておりますので、その切り口は鋭く、かつ説得力が半端でないと思っております。賢治といえども時代を超えられるはずもなく、その時代から多大な影響を受けているのだということを私も教わりました。
鈴木 守