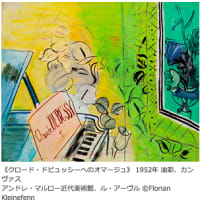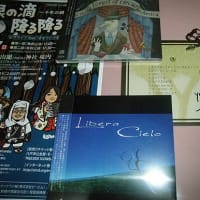必ず7641になる(茂木健一郎 クオリア日記)
で知って、興味を持ったので読んでみました。
『ウェブはバカと暇人のもの 現場からのネット敗北宣言』
アマゾンな罠(や、重宝しております)で下記もついで買い。
『僕が2ちゃんねるを捨てた理由』
こっちは前に書店で見て、時間ができたら読もうと思ってたので
送料調整もでき一石二鳥にて。表紙がかわゆいw
『ウェブはバカと暇人のもの 現場からのネット敗北宣言』
は、タイトルとはうらはらに硬直化しつつあるネットビジネスへの
警告および提言であり、
webマーケティング批判、という体裁をとったwebマーケティング本、
ウェブビジネスの落とし所伝授本、著者のビジネス視点&ノウハウ紹介本、
として面白く読めました。
オーマイニュースの撤退の経緯のような事例検証
×自らの体験情報を積み重ねた検証型で、
掘り下げ、噛み砕かれた文章で理解しやすい。
いまだ正体不明なweb2.0への意見は
それ自体がweb2.0の本質を探る内容になっているし、
ウェブを必要以上に敵視しているテレビ(業界人)への意見
(↑これは『僕が2ちゃんねるを捨てた理由』でも指摘されていたけれど)や
ウェブへの過度の期待を含めた勉強不足な企業やユーザーへの批判
(特に4章・5章)は、よくまとまっていて一読の価値ありかと。
・・・もちろん反論部分もありますが。
毒舌(ちょこっと恨み節風w)で、ちょっ上から目線ではありますが
それは表現として意図的なもの、として私にはOKレベルでありました。
てか、かえって著者のネットへの向きあい方の真摯さが伝わってきた。
(かつて惚れていた恋人への落胆について語ってるかのごとく)
まぁ、それ(バカと暇人)がテーマで、書籍化してるわけだから
イヤなら読まなければいいわけだし。
そう、イヤなら接触しないですむ/率が高い、というのが、
ウェブと紙媒体の違いでもある、ことは本書でも繰返し書かれています。
ハブ的なサイトやブログ(茂木さんのように)にアップされでもしない限り、
という条件付きだし、それを逆手に取ることもできるわけですが・・・
私もバカな暇人の1人なわけで、それには特に反論しません(本書の
定義に従えば正しいので)が、バカな暇人=マイナスではないとは思っている。
平和ボケがマイナス(だけ)でないのと同義で。
資産継承型の富裕層以外の人間に「(遊ぶ)暇ができた」というのが
資本主義×情報化社会の恩恵だとも思ってるので。
&「火」が一部の人間の特権であった時代(たとえば神とか)のほうが
よいのか悪いのか、今火を使ってる人間にはきっと判断しきれないように
誰でもが(といいつつ、まだまだ世界的には制限も多いけれど)
情報を発信できる時代が、マイナスだけだとは決して思えないので。
以下ドッグイヤーポイント
※個人的にマーキングしたいポイントです。
一部を抜粋しているので関心ある方は購読をお薦めします。
●集合愚(P17~18)
●匿名の個人として発信し、組織を背負っていないがゆえに、「絶対に勝てる競争」を高みから仕掛けてくる。クレームを受ける側は組織を背負っているため、逆ギレもできない。完全なるハンディキャップマッチに巻き込まれているのだ。(P40)
●かくして企業も個人もネット世論にびくつき、自由な発言ができなくなっていき、企業の公式サイトはますますつまらなくなっていく。(中略)テレビのコメンテーターは以前にもまして無害なことしか言わなくなった。(中略)強者を叩く発言をしておき、全面的に弱者をフォローしておけばとりあえずクレームは減る(P41)
●リアル世界によるネットへの介在は、「不当な書き込み」への抑止力を生むが、同時に「正しい書き込み」に対する抑止力も生む(P84)
●・ネットはプロの物書きや企業にとって、もっとも発言に自由度がない場所である。
・ネットが自由な発言の場だと考えられる人は、失うものがない人だけである(P90)
●ネットによって本来出会わなかったであろう人と人が交流できるようになったのは良いことだ!などとよく言われるが、おそらく、本来出会うはずがなかった人々が交流するようになったことで、摩擦のほうがより生まれたのではないだろうか。(P90)
●ネットでうけるネタ(P104)
●ネットでうまくいくための結論(P130)
●ネットはあくまでも自由な「雑談の場」。人々が居酒屋で交わす会話をコントロールできないのと同じで、ネット世論だって強引に変えることはできない(P207)
●その幻想が生まれる理由はただひとつ。
みんなネットのことをよくわかっていない
からである。(P220)
●そもそも「ネットによって人々の嗜好・生き方が細分化」されたというのはウソである。(P227)
●ヤフーを筆頭とするメガサイトの圧倒的集客力と、グーグルによる検索結果に従うことにより、ネットは人々をより均一化したのである(P229)
●細分化された興味・嗜好に対応する多種多様な情報はたしかにネット上に存在するが、その細分化されたなかで皆が知る情報は、ネットによって均一化されたのだ。(P230)
なんというか、スケールの問題は感じつつ。
(たとえば、 細分化と均一化の視点は興味深いけれど、ユーザーは結局は自分の
理解できる・行動できる範囲でしか理解しないし、行動しない・できない。
それは著者も把握しているような・・・。)
企業(及びユーザー)にネットヘの過度の期待や幻想を捨てよ、というのは
ひろゆき氏が「ネットはメディアではなくツールだ(=どう使うか、誰が使うかが重要)」と言ってるのと同義だな。
とはいえ、ネットをビジネスにする人間にとっては「ネットはとにかくすごいですよ!」「なんでもできちゃいます!」と煙に巻くことが(主に予算/経費を引きだす面での)メリットでもあり、そうした刷り込みが結果的にネットへの過信と落胆のギャップを生みだす。
そのあたりはネットビジネス従事者の今後の課題なんだろうなー、
と思いました。
で知って、興味を持ったので読んでみました。
『ウェブはバカと暇人のもの 現場からのネット敗北宣言』
アマゾンな罠(や、重宝しております)で下記もついで買い。
『僕が2ちゃんねるを捨てた理由』
こっちは前に書店で見て、時間ができたら読もうと思ってたので
送料調整もでき一石二鳥にて。表紙がかわゆいw
『ウェブはバカと暇人のもの 現場からのネット敗北宣言』
は、タイトルとはうらはらに硬直化しつつあるネットビジネスへの
警告および提言であり、
webマーケティング批判、という体裁をとったwebマーケティング本、
ウェブビジネスの落とし所伝授本、著者のビジネス視点&ノウハウ紹介本、
として面白く読めました。
オーマイニュースの撤退の経緯のような事例検証
×自らの体験情報を積み重ねた検証型で、
掘り下げ、噛み砕かれた文章で理解しやすい。
いまだ正体不明なweb2.0への意見は
それ自体がweb2.0の本質を探る内容になっているし、
ウェブを必要以上に敵視しているテレビ(業界人)への意見
(↑これは『僕が2ちゃんねるを捨てた理由』でも指摘されていたけれど)や
ウェブへの過度の期待を含めた勉強不足な企業やユーザーへの批判
(特に4章・5章)は、よくまとまっていて一読の価値ありかと。
・・・もちろん反論部分もありますが。
毒舌(ちょこっと恨み節風w)で、ちょっ上から目線ではありますが
それは表現として意図的なもの、として私にはOKレベルでありました。
てか、かえって著者のネットへの向きあい方の真摯さが伝わってきた。
(かつて惚れていた恋人への落胆について語ってるかのごとく)
まぁ、それ(バカと暇人)がテーマで、書籍化してるわけだから
イヤなら読まなければいいわけだし。
そう、イヤなら接触しないですむ/率が高い、というのが、
ウェブと紙媒体の違いでもある、ことは本書でも繰返し書かれています。
ハブ的なサイトやブログ(茂木さんのように)にアップされでもしない限り、
という条件付きだし、それを逆手に取ることもできるわけですが・・・
私もバカな暇人の1人なわけで、それには特に反論しません(本書の
定義に従えば正しいので)が、バカな暇人=マイナスではないとは思っている。
平和ボケがマイナス(だけ)でないのと同義で。
資産継承型の富裕層以外の人間に「(遊ぶ)暇ができた」というのが
資本主義×情報化社会の恩恵だとも思ってるので。
&「火」が一部の人間の特権であった時代(たとえば神とか)のほうが
よいのか悪いのか、今火を使ってる人間にはきっと判断しきれないように
誰でもが(といいつつ、まだまだ世界的には制限も多いけれど)
情報を発信できる時代が、マイナスだけだとは決して思えないので。
以下ドッグイヤーポイント
※個人的にマーキングしたいポイントです。
一部を抜粋しているので関心ある方は購読をお薦めします。
●集合愚(P17~18)
●匿名の個人として発信し、組織を背負っていないがゆえに、「絶対に勝てる競争」を高みから仕掛けてくる。クレームを受ける側は組織を背負っているため、逆ギレもできない。完全なるハンディキャップマッチに巻き込まれているのだ。(P40)
●かくして企業も個人もネット世論にびくつき、自由な発言ができなくなっていき、企業の公式サイトはますますつまらなくなっていく。(中略)テレビのコメンテーターは以前にもまして無害なことしか言わなくなった。(中略)強者を叩く発言をしておき、全面的に弱者をフォローしておけばとりあえずクレームは減る(P41)
●リアル世界によるネットへの介在は、「不当な書き込み」への抑止力を生むが、同時に「正しい書き込み」に対する抑止力も生む(P84)
●・ネットはプロの物書きや企業にとって、もっとも発言に自由度がない場所である。
・ネットが自由な発言の場だと考えられる人は、失うものがない人だけである(P90)
●ネットによって本来出会わなかったであろう人と人が交流できるようになったのは良いことだ!などとよく言われるが、おそらく、本来出会うはずがなかった人々が交流するようになったことで、摩擦のほうがより生まれたのではないだろうか。(P90)
●ネットでうけるネタ(P104)
●ネットでうまくいくための結論(P130)
●ネットはあくまでも自由な「雑談の場」。人々が居酒屋で交わす会話をコントロールできないのと同じで、ネット世論だって強引に変えることはできない(P207)
●その幻想が生まれる理由はただひとつ。
みんなネットのことをよくわかっていない
からである。(P220)
●そもそも「ネットによって人々の嗜好・生き方が細分化」されたというのはウソである。(P227)
●ヤフーを筆頭とするメガサイトの圧倒的集客力と、グーグルによる検索結果に従うことにより、ネットは人々をより均一化したのである(P229)
●細分化された興味・嗜好に対応する多種多様な情報はたしかにネット上に存在するが、その細分化されたなかで皆が知る情報は、ネットによって均一化されたのだ。(P230)
なんというか、スケールの問題は感じつつ。
(たとえば、 細分化と均一化の視点は興味深いけれど、ユーザーは結局は自分の
理解できる・行動できる範囲でしか理解しないし、行動しない・できない。
それは著者も把握しているような・・・。)
企業(及びユーザー)にネットヘの過度の期待や幻想を捨てよ、というのは
ひろゆき氏が「ネットはメディアではなくツールだ(=どう使うか、誰が使うかが重要)」と言ってるのと同義だな。
とはいえ、ネットをビジネスにする人間にとっては「ネットはとにかくすごいですよ!」「なんでもできちゃいます!」と煙に巻くことが(主に予算/経費を引きだす面での)メリットでもあり、そうした刷り込みが結果的にネットへの過信と落胆のギャップを生みだす。
そのあたりはネットビジネス従事者の今後の課題なんだろうなー、
と思いました。