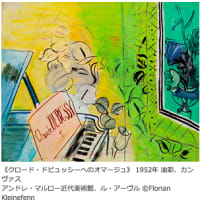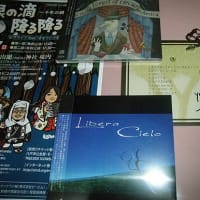1Q84(Wiki)
村上春樹さんの「1Q84」が100万部突破(読売新聞) - goo ニュース
「1Q84」が100万部突破(時事通信) - goo ニュース
村上春樹さん「1Q84」100万部 引用本にも波及
春樹新作爆発ヒット 「1Q84」 飢餓感あおり?1週間で96万部(産経新聞) - goo ニュース
というわけで、ある種の社会現象と化している『1Q84』。
まさに『空気さなぎ』のごとく。
まぁ、マイブームなので日々、時間があれば追っかけまくってるわけですが;
『1Q84』の書評はどんなものもすべて興味深い。
それぞれが村上春樹との関係を見つめ直し、“自分の物語”を語リ出す。
これこそ、空気さなぎ的物語ウイルス!!
この状態はパンデミックというにふさわしいのでは?
そしてそうした書評を読めば読むほど、
『1Q84』という本は巫女であり、ウイルスのキャリアであり、レシヴァでありまたパシヴァでもある、村上春樹氏自身の物語なのだな、と実感する。
世間の声と交わり、物語を生み出す。そしてそれはずたずたに自分を酷使する。
登場人物はすべて作者の分身(作品的に言えばドウタ)だというのは大前提だとして・・・
言葉を受け取って、傷つき苦しむリーダーは
村上春樹自身の創作の葛藤をイメージさせる。
物語を紡ぐ天吾もまた作者自身の影だとも思う。
『1Q84』は、まさに物語の形をとった“物語の物語”なのだと感じる。
その行為が、読み手の中の物語に共振し、新しい物語を作りだす。
遺伝子の書き換えのごとく。
それがどう結実するのかは本人にもわからない。
ただ、自分が主人公として物語を引き受け、
動かし結実させる意思を持つことが重要なのだ、・・・と
最後の天吾の決意を私はそう読み取りました。
「動的均衡」「生物と無生物のあいだ」の著者で
分子生物学者の福岡伸一氏の書評を発見!
先生も読んでおられましたかぁー、なんだか素敵だ♪
※過去記事:福岡伸一★できそこないの男たち
遺伝子支配に対抗する均衡 評:福岡伸一(よみうり堂)
遺伝子が利己的な支配者に見えるのは、私たちがその物語を信じ、身を委ねたいからである。そこに私たちがたやすく切り崩されてしまう契機が潜んでいる。それはかつて外側に存在していたビッグ・ブラザーを内側に求めることに等しい。リトル・ピープルに象徴されるこのような不可避的で、それでいて誘惑的な決定論に対抗するには、一つ一つの人生を自分の物語として自分で語り直すしかない。重要なのはその均衡であり、均衡は動的なものとして、可能性の在処(ありか)を示す。そう本書は宣言している。
私たちは時に合理性を無視し、利他的に行動しうる。その動因として私たちは自らの内部の核に、自らの複製ではない「さなぎ」をはぐくむことができる。本書の結末をそういう風に私は読んだ。
現時点での私的解釈として
●リトル・ピープル:ある種の媒介。ヴォイス(※下記信濃毎日新聞インタビュー参照)を運び空気さなぎを作る(作らせる)。組織ではないが、ある方向に(本人が無意識のうちに、あたかも本人の自主的意思のごとく)物事を押し流していく力。
それはマスコミだったり、それに反応する視聴者だったり、「国民」だったり、ネット世論だったりする。(参考ページ BOOK2/P279)
と思ってるので、福岡さんの「一つ一つの人生を自分の物語として自分で語り直すしかない」に共感します。
それにしても、第11章タイトルの「均衡そのものが善なのだ」はかなり深いテーマだと思うし、ある種「動的均衡」にも通じて興味深い。陰陽的でもあり、世界の成り立ち的でもあり。何かがものすごく圧倒的な力を持つ独裁的状況はやはりロクでもないだろうから。
月と太陽、月とペーパームーン、
渦とQ、善と悪のバランス。
陰陽のように、2つあるものの関わりが意味を持つ物語なのだとも思う。
(そういえば、登場人物は多いが、関わり方は見事なまでに1対1だなと今気づいた)
そういう視点で、村上春樹氏自身が『1Q84』のマザのような『空気さなぎ』を批評しているのは(その内容も含めて)とてつもなく興味深い。露骨に見えて実はとても巧妙な罠のような・・・。(なんてことをアレコレ思っていくのもまた呪術的魅力ですな)
以下、現時点で、個人的に参考にさせていただいているレビューをリンク。
(って、レビューも全部読むことができないのが悲しいっすね;
個人の数だけ物語はあるから・・・)
村上春樹『1Q84』感想 - 琥珀色の戯言
人称含め、多角的な視点で総括されていて、勉強になります。
※『モンキー・ビジネス』でのインタビューが紹介されています。
ROBARTious: 1Q84感想(2)~まだ温もりが残っているうちに
引用と読み込みの深さに何度も唸ってしまいました。特に下記。
誰にそんなことがわかる?
そう、誰にもわからない。これが現実なのか、物語なのか。
けれど、他人が語る物語を現実だと信じ込んだときに起こる暴力を『1Q84』は示している。それはオウム真理教であり、パレスチナをめぐる言説である。
イエーツは”In dreams begin the responsibilities.”と言った。
僕たちは現実か物語かわからない世界を生きている。指標はない。「こうであったかもしれない」過去が、その暗い鏡に浮かび上がらせるのは、「そうではなかったかも「しれない」現在の姿だ。
それでも、そうだとしても、僕たちは自分の物語を見つけ出し、創造し、生きていかなくてはならない。
あるいは、生きていくことができる。
2009年だろうと、200Q年であろうと。
レビューではありませんが、重要参考資料として。
af_blog: 物語は世界共通言語---村上春樹インタビュー
信濃毎日新聞の全文を写真でアップされているので読むことができました。
読んでる最中、平家物語を暗証するふかえりが浮かびました。
※一部抜粋/2008年3月30日付け信濃毎日新聞
「物語を書いていくことは、自分の魂の中に降りていく作業です。そこは真っ暗な世界。生と死も不確かで混沌としている。言葉もなければ、善悪の基準もない世界」
「でも魂の世界まで降りて行くと、そこは同じ世界なんですよ、それゆえに物語がいろいろな文化の差を超えて、理解し合えるのだと思う」
「物語というものは非常に有益なことでもあるのですが、一方でものすごく危険なことでもあるのです。このことを河合先生は本当によく分かっていた」
「あの人(オウム真理教の実行犯)たちは、どうしてあっちの方に行ってしまったのか。そのことはちゃんと解明しておかなくってはいけないことなんです。皆死刑にしておしまいというのではいけないことなんです」
「この人たち1人1人それぞれに弱いところもある。でもその六十何人もの普通の人たちの声が、1つのボイスになるとすごい説得力を持っていて、信頼してもいいような力を感じました(中略)だからこそ、そのボイスが戦争みたいなことに引きずりこまれないことを真剣に望んでいます」
「人というのは、そんなに上とか下とか、前とか後ろとかで決められるものではないんです。それぞれの人には物語があり、その物語の中で生きている。それが人を救うんです。僕の書きたいのはそういう物語。明るい物語ではないけれど、ある暗さの中で共振するものを見いだすことで、救われるような物語です」
「僕の考える総合小説はいろんな人のいろんな視線があって、いろんな物語があって、それが総合的な1つの場を作ってる小説です。そのためには三人称にならないと書けないですね」。
作品の重要なポイント「それは『恐怖』です。手応えはある。僕の重要な作品になるような気がする」
「1Q84」はやはりオウム真理教取材での1つのアンサーなんだろうな、と。
もしくはQ(問いかけ)?
こうしてみても、やはり今までの作品を読み返してみたくなる、
村上ワールドに降りていきたくなる、
そんな、世界が変わってしまった200Q、6月。
※もう少し時間がたったら、ちゃんとしたレビューを書きたいと思います。
今は空気を集めて糸を取りだしている状態。
村上春樹さんの「1Q84」が100万部突破(読売新聞) - goo ニュース
「1Q84」が100万部突破(時事通信) - goo ニュース
村上春樹さん「1Q84」100万部 引用本にも波及
春樹新作爆発ヒット 「1Q84」 飢餓感あおり?1週間で96万部(産経新聞) - goo ニュース
というわけで、ある種の社会現象と化している『1Q84』。
まさに『空気さなぎ』のごとく。
まぁ、マイブームなので日々、時間があれば追っかけまくってるわけですが;
『1Q84』の書評はどんなものもすべて興味深い。
それぞれが村上春樹との関係を見つめ直し、“自分の物語”を語リ出す。
これこそ、空気さなぎ的物語ウイルス!!
この状態はパンデミックというにふさわしいのでは?
そしてそうした書評を読めば読むほど、
『1Q84』という本は巫女であり、ウイルスのキャリアであり、レシヴァでありまたパシヴァでもある、村上春樹氏自身の物語なのだな、と実感する。
世間の声と交わり、物語を生み出す。そしてそれはずたずたに自分を酷使する。
登場人物はすべて作者の分身(作品的に言えばドウタ)だというのは大前提だとして・・・
言葉を受け取って、傷つき苦しむリーダーは
村上春樹自身の創作の葛藤をイメージさせる。
物語を紡ぐ天吾もまた作者自身の影だとも思う。
『1Q84』は、まさに物語の形をとった“物語の物語”なのだと感じる。
その行為が、読み手の中の物語に共振し、新しい物語を作りだす。
遺伝子の書き換えのごとく。
それがどう結実するのかは本人にもわからない。
ただ、自分が主人公として物語を引き受け、
動かし結実させる意思を持つことが重要なのだ、・・・と
最後の天吾の決意を私はそう読み取りました。
「動的均衡」「生物と無生物のあいだ」の著者で
分子生物学者の福岡伸一氏の書評を発見!
先生も読んでおられましたかぁー、なんだか素敵だ♪
※過去記事:福岡伸一★できそこないの男たち
遺伝子支配に対抗する均衡 評:福岡伸一(よみうり堂)
遺伝子が利己的な支配者に見えるのは、私たちがその物語を信じ、身を委ねたいからである。そこに私たちがたやすく切り崩されてしまう契機が潜んでいる。それはかつて外側に存在していたビッグ・ブラザーを内側に求めることに等しい。リトル・ピープルに象徴されるこのような不可避的で、それでいて誘惑的な決定論に対抗するには、一つ一つの人生を自分の物語として自分で語り直すしかない。重要なのはその均衡であり、均衡は動的なものとして、可能性の在処(ありか)を示す。そう本書は宣言している。
私たちは時に合理性を無視し、利他的に行動しうる。その動因として私たちは自らの内部の核に、自らの複製ではない「さなぎ」をはぐくむことができる。本書の結末をそういう風に私は読んだ。
現時点での私的解釈として
●リトル・ピープル:ある種の媒介。ヴォイス(※下記信濃毎日新聞インタビュー参照)を運び空気さなぎを作る(作らせる)。組織ではないが、ある方向に(本人が無意識のうちに、あたかも本人の自主的意思のごとく)物事を押し流していく力。
それはマスコミだったり、それに反応する視聴者だったり、「国民」だったり、ネット世論だったりする。(参考ページ BOOK2/P279)
と思ってるので、福岡さんの「一つ一つの人生を自分の物語として自分で語り直すしかない」に共感します。
それにしても、第11章タイトルの「均衡そのものが善なのだ」はかなり深いテーマだと思うし、ある種「動的均衡」にも通じて興味深い。陰陽的でもあり、世界の成り立ち的でもあり。何かがものすごく圧倒的な力を持つ独裁的状況はやはりロクでもないだろうから。
月と太陽、月とペーパームーン、
渦とQ、善と悪のバランス。
陰陽のように、2つあるものの関わりが意味を持つ物語なのだとも思う。
(そういえば、登場人物は多いが、関わり方は見事なまでに1対1だなと今気づいた)
そういう視点で、村上春樹氏自身が『1Q84』のマザのような『空気さなぎ』を批評しているのは(その内容も含めて)とてつもなく興味深い。露骨に見えて実はとても巧妙な罠のような・・・。(なんてことをアレコレ思っていくのもまた呪術的魅力ですな)
以下、現時点で、個人的に参考にさせていただいているレビューをリンク。
(って、レビューも全部読むことができないのが悲しいっすね;
個人の数だけ物語はあるから・・・)
村上春樹『1Q84』感想 - 琥珀色の戯言
人称含め、多角的な視点で総括されていて、勉強になります。
※『モンキー・ビジネス』でのインタビューが紹介されています。
ROBARTious: 1Q84感想(2)~まだ温もりが残っているうちに
引用と読み込みの深さに何度も唸ってしまいました。特に下記。
誰にそんなことがわかる?
そう、誰にもわからない。これが現実なのか、物語なのか。
けれど、他人が語る物語を現実だと信じ込んだときに起こる暴力を『1Q84』は示している。それはオウム真理教であり、パレスチナをめぐる言説である。
イエーツは”In dreams begin the responsibilities.”と言った。
僕たちは現実か物語かわからない世界を生きている。指標はない。「こうであったかもしれない」過去が、その暗い鏡に浮かび上がらせるのは、「そうではなかったかも「しれない」現在の姿だ。
それでも、そうだとしても、僕たちは自分の物語を見つけ出し、創造し、生きていかなくてはならない。
あるいは、生きていくことができる。
2009年だろうと、200Q年であろうと。
レビューではありませんが、重要参考資料として。
af_blog: 物語は世界共通言語---村上春樹インタビュー
信濃毎日新聞の全文を写真でアップされているので読むことができました。
読んでる最中、平家物語を暗証するふかえりが浮かびました。
※一部抜粋/2008年3月30日付け信濃毎日新聞
「物語を書いていくことは、自分の魂の中に降りていく作業です。そこは真っ暗な世界。生と死も不確かで混沌としている。言葉もなければ、善悪の基準もない世界」
「でも魂の世界まで降りて行くと、そこは同じ世界なんですよ、それゆえに物語がいろいろな文化の差を超えて、理解し合えるのだと思う」
「物語というものは非常に有益なことでもあるのですが、一方でものすごく危険なことでもあるのです。このことを河合先生は本当によく分かっていた」
「あの人(オウム真理教の実行犯)たちは、どうしてあっちの方に行ってしまったのか。そのことはちゃんと解明しておかなくってはいけないことなんです。皆死刑にしておしまいというのではいけないことなんです」
「この人たち1人1人それぞれに弱いところもある。でもその六十何人もの普通の人たちの声が、1つのボイスになるとすごい説得力を持っていて、信頼してもいいような力を感じました(中略)だからこそ、そのボイスが戦争みたいなことに引きずりこまれないことを真剣に望んでいます」
「人というのは、そんなに上とか下とか、前とか後ろとかで決められるものではないんです。それぞれの人には物語があり、その物語の中で生きている。それが人を救うんです。僕の書きたいのはそういう物語。明るい物語ではないけれど、ある暗さの中で共振するものを見いだすことで、救われるような物語です」
「僕の考える総合小説はいろんな人のいろんな視線があって、いろんな物語があって、それが総合的な1つの場を作ってる小説です。そのためには三人称にならないと書けないですね」。
作品の重要なポイント「それは『恐怖』です。手応えはある。僕の重要な作品になるような気がする」
「1Q84」はやはりオウム真理教取材での1つのアンサーなんだろうな、と。
もしくはQ(問いかけ)?
こうしてみても、やはり今までの作品を読み返してみたくなる、
村上ワールドに降りていきたくなる、
そんな、世界が変わってしまった200Q、6月。
※もう少し時間がたったら、ちゃんとしたレビューを書きたいと思います。
今は空気を集めて糸を取りだしている状態。