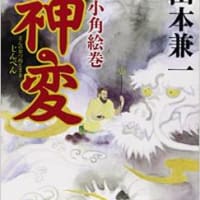WindowsXPマシンを利用中で、まだまだ使えるPCなのに、Windows7以降のシステムに乗り換えるには推奨されるマシンパワーには足りないというPCも多いだろう。OSが肥大し、マシンパワーが不足だ、などと考えている人は、多いだろうと思う。オレの経験から言えば、Windowsのバージョンアップはするけれども、Officeのバージョンアップは「まだ使えるから」という理由で、そのままと言う人も多い。
でも、Office文書やOutlookのメール経由でのウィルス罹患が多いし、Officeそのものも古いものほどセキュリティが甘い。古いアプリケーションの利用も、十分なセキュリティホールは存在する。
拙宅で使っていたWindows7のWindowsで不具合が生じ、結局再インストールするしか無いだろうと判断するに至った段階で、オレは実はWindowsを捨てた。Linuxに走ったのだ。
Linuxにも色々あって、Ubuntuで使われているデスクトップ環境のUnityは、以前に古いマシンに入れて、その反応のあまりの遅さに、唖然としてUbuntu直接ではなく、サブセットのXubuntuやlubuntuを使う事が多かった。Ubuntu13.10になって搭載されているUnityの時として「使い物にならない」ほどの速度は改善されている。それなりのパワーを持つ機種ならば、ubuntuでも良いだろうなぁと思うのである。
中古市場などには、XPマシンが流出しそうだが、再生して使うならLinuxしかない。OpenOfficeのサブセットであるLibraOfficeならば、VBAで細部まで作りこんだものならばまだしも、単なるスプレッドシートやら、文書とのリンクなどが埋められたMS-Officeドキュメント程度ならば、容易に読み込み編集できるし、古い形式のMS-Officeでの保存も可能だ。
WindowsXPで使っていても非力だと感じるマシンには、上記のUbuntu系列よりもより軽いPuppy LinuxだとかVine Linuxが存在する。市販のDVD再生が、コピーガードのために市長が困難だったりするなどの問題も残るし、それを解消するための手段がソースファイルからツールをビルドしてインストールしなければならない、などの制限はある。Ubuntu系列でも、ターミナルのウィンづを開いて、コマンド入力してコピーガード回のための方法を採らなければならない、などの厄介な部分はある。
しかし、それらの手間をかけても、それなりに比較的安定した挙動をLinuxでは確保できる。
そもそも、iOSクローンであるAndroidというシステムだって、Linux技術が基本となっている。iOSの基本技術がLinux同様にUnixクローンのFreeBSDであるという事実もある。Windowsのフォルダは、以前はディレクトリと称されていた。これはUnixから来ている。現在のiOSの元となっているMacOSX、それ以前のMacOSの見た目は、Unix上で動いていたX windowを元にしたものだ。つまりは、PCで主たるものとなったシステムの多くが、祖をUnixというシステムにあるわけだ。
コンピュータの使い方を学ぶという事は、つまり入力するデータと出力するデータ、その間の処理方法というものを学ぶ事である。XP終了後のPCを素材リサイクルなどに使うよりも、教育用としてlinuxやfreeBSDマシンに作り変えて、教育現場で利用するのはどうなんだろう。壊れたって元々廃棄物だったと考えれば気楽だし、壊れてからリサイクルに回せばいいだけの話だ。いくらでも再生し再利用の方法はあるのだが。