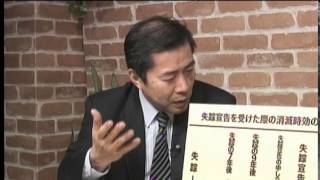我々は何を信じているのだろう。安心したいという思いが、安全バイアスに傾斜する心を生み出す。しかし、現実はそんなに安穏としたものではない。特に福島第一原発事故の発災以降、困ったことに安心できないほどの「安全とは言えない環境」になってしまった。
ここで最初に報告している土井淑平さんの、ちょっと背筋が寒くなるような話は、川内原発再稼働を図る人たちにとっては、世に知られてはイケない事のように見える。
被曝の影響は一様ではない。肉体的な影響だけではない。セシウムは筋電動性を持つという。筋電導ならば神経電導もありうる。多発する被災地での若年性の心筋梗塞による突然死。更には、気力の減退などの「鬱病」状の症状。後者は肥田舜太郎先生が発見し命名した「原爆ブラブラ病」と近似ではないか。
チェルノブイリの事象を見ると、例えば小児甲状腺癌の発症と、その「既存の知識では説明が出来ないほどの進行の速さ」をどう捉えるべきだろう。
北海道がんセンター名誉院長である西尾正道先生によると、甲状腺癌は「進行が遅い癌」の代名詞のようなものだという。それが数年で発症する。小児甲状腺癌の発症をスクリーニング効果だとしたい人がいる。しかし、甲状腺癌は十年単位で通常は進行するものだという。ヨウ素131による被曝だけでは癌の種しか生まれないと思える。それに前進に被曝が広がるセシウムが関与していないとは思えない。種を育てる肥料としての被曝だってあるのではないか。そうした人工的に生み出した放射性物質の相互作用は、実は知る限り誰も検証していない。
検証していない事は「分からない」のである。「分からない」という事は「安全」とは等価ではないし、検証する事すら忌避しているかのような放医研の、非科学的な態度を見るにつけ、放射能は安全だというワケノワカラヌ放射能安全神話でも作り出したいと考えているとしか思えない。











 Kazuhiro Tamai @tama_don
Kazuhiro Tamai @tama_don