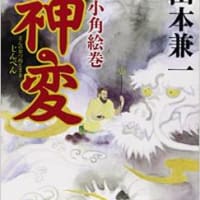日本の農業は、長い間農業従事者によって作られてきた。農業が「経営」が必要な「業」であるという自覚は、多分殆どの農民が持っていない常態が続いた。そうした経営的な思想は、戦前では一部の地主だけが持つものであったし、戦後の農地解放で土地を取得した旧小作農の多くは、単なる労働力を小作農時代と同様に使い、直接農業からの収入を得ることによって、幾許かの小作農時代よりも良い生活を行えるだけであった。
もちろん、旧小作農の多くは、農業を経営という視点で捉えることはなかったし、狭隘な土地からの収入だけでは生活が賄えないため、兼業農家という形態が増えたのである。
経営を知らぬ農家の代わりに経営を担ったのが、全国に展開する農協である。収穫への支払いと流通を握ることによって、農家の経営は農業機器の導入や肥料などの供給を含め、農協にお任せの時代が続いた。
その農協は、日本の農業政策を上意下達的に農家に伝える役割を果たしてもいる。収入は銀行業務を兼ねた農協を通じて農家に配布され、その運用益が高度経済成長時には高金利によって莫大なものとなり、農家の多くはその好景気から生まれる利得によって、海外団体観光ツアーなども満喫していた。日本の海外旅行の中心が「ノキョー」だった時代があったわけである。
こうした農協の、殆ど乱脈とも言える経理が、農業の政策転換、例えば減反政策などによって破綻する。経営実態の殆どを農協に頼っていた農家は、農協に「貯蓄」していたはずの金が、バブル崩壊やらリーマンショックなどによって単純に失われる羽目になる。更に、農政の転換による業態転換への支出などが、農家の体力を奪う。農家が頼っていた農協も、小さな地域農協が次々と破綻し、吸収合併などの合従連衡が起こり、身近な農協というものが縁遠い金融機関の農協として農家に対峙する。業としての農に見切りをつける離農者の増加や、後継者の離反による従事者の高齢化に伴い、耕作放棄地が増加する。
農業と言う産業をどう育てるかという政策がこの国にはなく、あるのは米が過剰生産されると減反する、などという継ぎ接ぎ膏薬のような形しかない。池田町はワインの町と言っているのだが、そうした付加価値をつけた製品なども、流行り廃りという風潮に流された結果、池田ワインなどが持て囃された時期が過ぎると、定番として消費者の中に浸透したとまではいかない。かって隆盛を誇った池田町も、思うような成長が続いていない。
責任の所在がハッキリしないまま、政策が行われ、結果に対する推測が誤った場合であっても、その変換は行われない。負けている太平洋戦争を「勝つまで続ける」と言い張った当時の政府の姿と似ている。
TPPとやらの絡みで、農業が脚光を浴びている。その浴び方は必ずしも嬉しい姿ではない。どうしてそのような姿を今晒すようになったのか、というのは、残念ながら農家の農政に対する当事者意識の低さとともに、殆ど流通業者が決めている「商品」としての農作物の「規格」の問題もある。胡瓜が曲がっていると嫌だとか、形の悪い人参は避けるという消費者の「見た目」による判断である。店頭で鮮度保持剤によって見た目の鮮度が保たれると、泥つきの葱などよりも鮮度保持剤まみれの商品の方が好まれる。土が付いていて汚い、という意識である。何やらお隣の韓国の「見た目が大事」だから美容整形が大流行、という話と似ている。美容整形農作物だけをスーパーマーケットで鮮度保持剤まみれのまま有難がって珍重する。何やら生産者の経営喪失の感覚と、消費者のモノを見る目の喪失が相俟って、日本の農業の未来は明るいものとは言えないようだなぁ。
もちろん、旧小作農の多くは、農業を経営という視点で捉えることはなかったし、狭隘な土地からの収入だけでは生活が賄えないため、兼業農家という形態が増えたのである。
経営を知らぬ農家の代わりに経営を担ったのが、全国に展開する農協である。収穫への支払いと流通を握ることによって、農家の経営は農業機器の導入や肥料などの供給を含め、農協にお任せの時代が続いた。
その農協は、日本の農業政策を上意下達的に農家に伝える役割を果たしてもいる。収入は銀行業務を兼ねた農協を通じて農家に配布され、その運用益が高度経済成長時には高金利によって莫大なものとなり、農家の多くはその好景気から生まれる利得によって、海外団体観光ツアーなども満喫していた。日本の海外旅行の中心が「ノキョー」だった時代があったわけである。
こうした農協の、殆ど乱脈とも言える経理が、農業の政策転換、例えば減反政策などによって破綻する。経営実態の殆どを農協に頼っていた農家は、農協に「貯蓄」していたはずの金が、バブル崩壊やらリーマンショックなどによって単純に失われる羽目になる。更に、農政の転換による業態転換への支出などが、農家の体力を奪う。農家が頼っていた農協も、小さな地域農協が次々と破綻し、吸収合併などの合従連衡が起こり、身近な農協というものが縁遠い金融機関の農協として農家に対峙する。業としての農に見切りをつける離農者の増加や、後継者の離反による従事者の高齢化に伴い、耕作放棄地が増加する。
農業と言う産業をどう育てるかという政策がこの国にはなく、あるのは米が過剰生産されると減反する、などという継ぎ接ぎ膏薬のような形しかない。池田町はワインの町と言っているのだが、そうした付加価値をつけた製品なども、流行り廃りという風潮に流された結果、池田ワインなどが持て囃された時期が過ぎると、定番として消費者の中に浸透したとまではいかない。かって隆盛を誇った池田町も、思うような成長が続いていない。
責任の所在がハッキリしないまま、政策が行われ、結果に対する推測が誤った場合であっても、その変換は行われない。負けている太平洋戦争を「勝つまで続ける」と言い張った当時の政府の姿と似ている。
TPPとやらの絡みで、農業が脚光を浴びている。その浴び方は必ずしも嬉しい姿ではない。どうしてそのような姿を今晒すようになったのか、というのは、残念ながら農家の農政に対する当事者意識の低さとともに、殆ど流通業者が決めている「商品」としての農作物の「規格」の問題もある。胡瓜が曲がっていると嫌だとか、形の悪い人参は避けるという消費者の「見た目」による判断である。店頭で鮮度保持剤によって見た目の鮮度が保たれると、泥つきの葱などよりも鮮度保持剤まみれの商品の方が好まれる。土が付いていて汚い、という意識である。何やらお隣の韓国の「見た目が大事」だから美容整形が大流行、という話と似ている。美容整形農作物だけをスーパーマーケットで鮮度保持剤まみれのまま有難がって珍重する。何やら生産者の経営喪失の感覚と、消費者のモノを見る目の喪失が相俟って、日本の農業の未来は明るいものとは言えないようだなぁ。