お仕事につながればと、一生懸命、書いています。
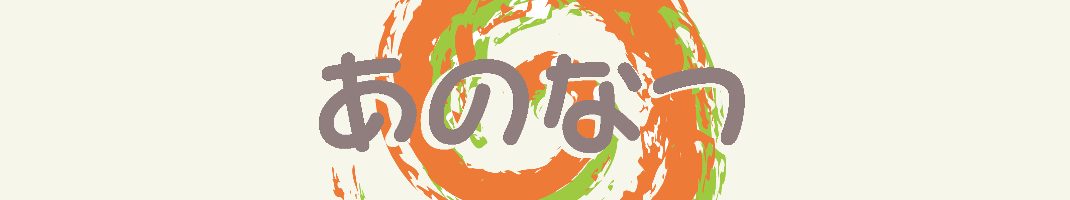
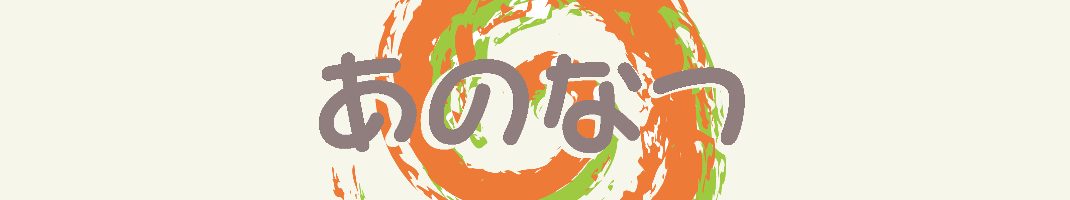
「10代で読んでいないと恥ずかしい必読書」なるものを2ちゃんねるで拾った。
ちゃんとツボを押さえている(笑)。
自分自身、文系と書いてあるところの半分ぐらい、理系なんかは4冊しか読んでないよ(理系なのに(ノД`))。
でも、今更読む気はしないかな。
「10代で読んでいないと・・・」じゃなくて、高校~大学のある時期に、こう言った小難しい本に傾倒する時期があるんだよなぁ。
ドロドロの純文学とか、小林秀雄とか、吉本隆明とか(笑)。
それで哲学的な台詞で頭を満たして、友達と議論したりしてヾ(-_-;) 。
「カミュ=サルトル論争」なんか、2晩も議論したけど、社会に出てから何の関係も無かったよなぁ┐( ̄~ ̄)┌。
そう言った時期にしか、この手の本を読もうとは思わないよ。
逆に言うと、その時期にどのくらい読んだかで、人生の総数が決まるね。
文系
プラトン『国家』
アリストテレス『ニコマコス倫理学』
ショーペンハウアー『意志と表象としての世界』
ヘーゲル『精神現象学』
デカルト『省察』
パスカル『パンセ』
ライプニッツ『単子論』
カント『純粋理性批判』
キェルケゴール『死に至る病』
バーク『フランス革命の省察』
ジェイムズ『宗教的経験の諸相』
ニーチェ『道徳の系譜』
ベーコン『ノヴム・オルガヌム』
フッサール『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』
メルロ=ポンティ『知覚の現象学』
ハイデッガー『存在と時間』
アーレント『精神の生活』
ヨナス『責任という原理』
サルトル『存在と無』
ベルグソン『時間と自由』
ミンコフスキー『生きられる時間』
レヴィナス『全体性と無限』
フロイト『快感原則の彼岸』
ヤマグチノボル『ゼロの使い魔』
ドゥルーズ=ガタリ『アンチ・オイディプス』
フォーダー『精神のモジュール形式』
ヤスパース『精神病理学総論』
エレンベルガー『無意識の発見』
ラカン『精神分析の四基本概念』
フーコー『言葉と物』
ソシュール『一般言語学講義』
ヴェイユ『重力と恩寵』
ディルタイ『精神科学序説』
ブーバー『我と汝・対話』
ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』
ミンスキー『心の社会』
ライル『心の概念』
バタイユ『エロティシズム』
アガンベン『ホモ・サケル』
ラッセル『西洋哲学史』
理系
高木貞治『解析概論』
ハイデガー『存在と時間』
コルモゴロフ『確率論の基礎概念』
デカルト『方法序説』
アインシュタイン『相対性理論』
ストロガッツ『SYNC』
アトキンス『エントロピーと秩序』
岡潔『春宵十話』
ゲーデル『不完全性定理』
ルネトム『構造安定性と形態形成』
ペンローズ『皇帝の新しい心』
フェルミ『熱力学』
シュライバー『無機化学』
ガウス『誤差論』
ヒルベルト『幾何学基礎論』
朝永振一郎『スピンはめぐる』
ブレジス『関数解析』
ポアンカレ『科学と方法』
シュレーディンガー『精神と物質』
プラトン『テアイテトス』
キャンベル『生物学』
ハイゼンベルク『部分と全体』
ニュートン『光学』
ライプニッツ『モナドロジー』
ケイン『スーパーシンメトリー』
デルコミン『ニューロンの生物学』
ユークリッド『ユークリッド原論』
カントル『超限集合論』
アトキンス『物理化学』
シャハレビッチ『整数論』
ニュートン『プリンシピア』
プリゴジン『確実性の終焉』
ローレンツ『ソロモンの指環』
ブルバキ『数学原論』
ポントリャーギン『連続群論』
ヴァイル『ソンメトリー』
ファインマン『統計力学』
シューム『「標準模型」の宇宙』
ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』
キースラー『無限小解析の基礎』
ウィーナー『サイバネティックス』
カドムツェフ『プラズマ中の集団現象』
アーノルド『古典力学の数学的方法』
ルベーグ『積分・長さおよび面積』
ディラック『量子力学』
ノボルヤマグチ『ゼロの使い魔』
バーンスタイン『リスク』
ケプラー『宇宙の調和』
ミチオカク『超弦理論とM理論』
アダマール『発明の心理』
ストライヤー『生化学』
セール『有限群の線型表現』
マスロフ『摂動論と漸近的方法』
倭の五王(わのごおう)とは、5世紀に、南朝の東晋や宋に朝貢して「倭国王」などに冊封された倭国の五人の王、讃、珍、済、興、武の事。
中国の文献(「宋書」倭国伝等々)に書かれている。
「日本書紀」の天皇系譜から「讃」→履中天皇、「珍」→反正天皇、「済」→允恭天皇、「興」→安康天皇、「武」→雄略天皇等の説がある。
このうち「済」「興」「武」については研究者間でほぼ一致を見ているが、「讃」と「珍」については「宋書」と「記紀」の伝承に食い違いがあるため未確定。
しかしながら、倭国の実態や、倭王と大和朝廷との関係性も未だ定説を見ないらしい。
最初に倭の五王と大和朝廷の関係性を否定したのは、本居宣長です。
江戸時代ともなると日本独自の文化が確立し、儒学者の中にも中国を軽視する傾向になっていったのでした。
そんな中に「古事記」を解読した本居宣長が、大和朝廷が朝貢外交をしていたなどとは、日本としてのプライドが許さなかったのかも知れないですね♪
現代でも、倭の五王が大和朝廷と関係ないとする主張は、この本居宣長の思想を受け継いでいるんだと思います。
朝貢していた卑弥呼と大和朝廷の関係性が曖昧なのも、まあ、同じ理由ですね。
歴史のどこかの時点で、日本は朝貢外交をしていなかった、となっていったんでしょう。
ただ、倭の五王と天皇系譜との一致は偶然とは言えないので、(中国の文献中の内容全て信憑性があるわけではないが)個人的には、概要は合っていると思っています。
2ちゃんねるで面白い説を展開している人がいたので、読み込んでしまいました。
便所の落書きと揶揄される掲示板ですが、アカデミー板とかは結構まともな議論が為されているので、たまに参考にしています。
彼曰く、「冊封(さくほう)と封国(ほうこく)は違う」という主張です。
「封国」は「冊封」とは違い、皇帝の親族か、初代皇帝と共に戦った将軍等、皇帝にとって遠ざけたい大物の勢力を、中央政権管理下の県としての地方ではなく藩として、遠方に政府直轄管理外の領土を与えて封じる時の言葉と言う訳です。
ネットや辞書で調べると、「冊封」と「封国」も同じ様な意味として扱われています。
しかしながら、「聖書を読み解く鍵は聖書にあり」と言うこともあり、実際の使用形態がどのように違うのかは、文献を当たって調べてみないと本当の意味はわかりません。
私自身も何冊か文献を当たったのですが、確かに彼の言うとおりで、朝鮮やベトナム等の蛮族(漢民族以外)出身の族長に対しては、封国とは絶対に使用していません。
全ておしはかった様に冊封を使用しています。
これに対して、倭の五王に関してだけは、封国と言う言葉を使用すること許しています。
他に封国を使用しているのは、皇帝の次男坊とかに土地を分割し属国とした場合にのみです。
中国の正式文書で、封国という言葉を使用しているのは、蛮族出身では倭王以外、歴史上一度もないと言うのは不思議です。
納得する理由としては、(この部分は明確に文言としては残っていないが、)皇帝の親族が倭王になったと言う解釈にならざるを得ません。
そう考えて「宋書倭国伝」を読むと、確かに「僕は地方の180の国を統合しましたよ」とか、子供が母親に自慢する様な女々しい文言が並んでいるのに気付きます。
子会社の(親会社からの)天下り社長が、業績を過大に報告し、何とか本社(親会社)に戻して貰おうとする姿に似ています。
現在の中国に、まともな漢民族は残っていないと思います。
全て他民族との混血か自称漢民族なのはもちろんですが、ここでは血統という意味ではありません。
漢民族の文化、風俗、風習などはことごとく破壊されて、微塵も残っていません。
易姓革命で漢民族から皇帝が生まれるかどうか?
生まれたとしても本当の漢民族王朝かどうか?
多分、中国という多民族混血国家があるだけで、群雄割拠する三国志時代の易姓革命は無いと思います。
もし倭の五王が皇帝の親族だとして、更に倭の五王が大和朝廷につながるのだとすると、(本家の漢民族が無くなったので)日本こそが漢民族の正当な継承者と言うことになり、歴史が根本的に変わってしまいますね。
面白いけど、どうなのかなぁ?( ̄△ ̄)
中学の頃、芥川龍之介の「杜子春」を読んで、「あの時もし声を出さなかったら、お前を殺していた。」と仙人が言う場面で萎えた。
極めて日本的なお涙頂戴の人情話に落ち着いていたからだ。
本場の中国はもっと違う話(道徳観)だろうと思った。
(実は後日、本場の中国の話を聞いて、更に驚いた。その話は、またの機会で。)
仙人になろうとする人間が、ちょっと情にほだされたぐらいで、声を上げるなんて。
仙人になるなら、親がどうなろうと心が動いてはいけないのではないか?
総理大臣が、母親を人質に取られて、国家の行く末を誤るか?
あそこで声を上げるなんてのは、杜子春は仙人の器ではなかっただけの話だよ。
当時その話を母親にした。
彼女もオレと同じ意見だった。
さらに彼女は、「男子が夢を実現させようとする時に、親の心配なんかしなくていい。子供の夢の為なら、親は喜んで犠牲になるモノだから。」と続けた。
「その程度の夢なら、男子一生の夢ではない。」とまで言い切った。
出来た母親だ。
喜んで犠牲にさせて貰おうと思った(笑)。
顧みて、今はどうだろう?
親に関しては今でも考えは変わらないけど、カミさんが鞭打たれたら?子供だったら?
子供が鞭打たれていたら、声を上げちゃうだろうなぁ。
と言うことは、守りに入ったのかなぁ?
いや、違う。
親になったんだ!
子供の夢を試す為に、畜生の姿で鞭打たれる側になったんだよな(ノД`)。
だとしたら、喜んで犠牲になれるよ。
あの時の母親の気持ちが理解できた。
だけど、ウチは2人とも女の子だからなぁ。
(¬ε¬)
思わず声を上げちゃうぐらいがいいのかな?
三軒茶屋のカレー屋さん「とんがらし」です。
おばあちゃん一人でやっているお店で、売れているんだか、売れていないんだか。
でも、江戸川からコッチに越してきた14年前から営業しているので、根強いファンがついているのかなぁ。
ちょっとサラッとしていて、水っぽいカレーです。
インド風を謳っていますが、インドっぽくないです。
ダシがキチンと利いているのがいいですね~。
実はインドカレーを色々と食べてみると解るのですが、インドカレーの弱点はダシです。
インド人はダシにそんなに気を使わない。
インド料理には、カレーとは別にスープもありますが、日本では馴染み無いでしょ?
あまり旨くないからです。
日本人の感覚からすると、ダシが利いていない。
と言うか、口直しに呑むちょっと酸っぱい感じのスープが多いです。
ここ、旨いです。
まあ、インパクトはあまりないですが、癖になりますよ。
一度行ってみて下さい。
最後に愛玉子(オーギョーチ)がデザートとしてついてきます。
これ口直しにちょうどいいです。
食べログ→ とんがらし