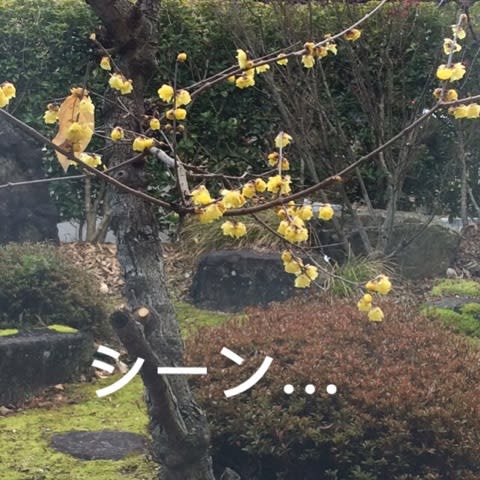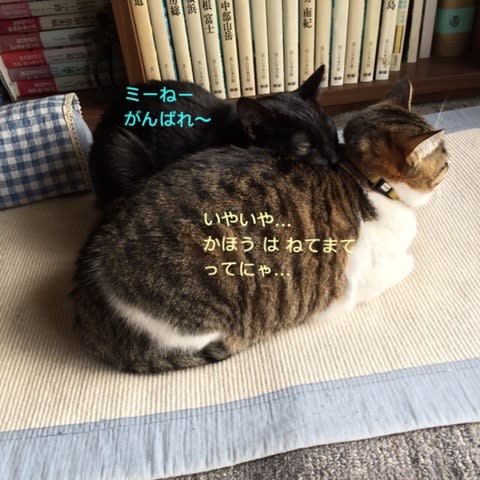どうろくじん の季節ですね。



どうろくじん…
どんど焼き、道祖神、などとも
呼ばれる、小正月に行われる火祭り。
成人の日が、
小正月でなくなってしまったので、
どうろくじん も 早めにやるところが
多いですね。
umeは
長野県の北の山村
 雪国で育ったので
雪国で育ったので子どものころの どうろくじん には
昔の名残りがありました。
大人に手伝ってもらいながら
子どもたちが
秋
 のうちに
のうちに柱になる木やカヤを切り出しておき
どうろくじん の前日に
地域
 をまわって、お正月飾りや豆がら
をまわって、お正月飾りや豆がらワラ、ダルマなどを集めてまわり
雪を踏み固めた田んぼの真ん中に
6メートルを超える円錐形の
どうろくじん を作り上げます。
柱を組んで立て、その周りにカヤなどを
巻き付けていくのは、息を合わせて
やらねばならない結構な大仕事です。
当日の夜は
火付け役の大人と
消し役の子どもの間で激しいバトルが
繰り広げられます。
子どもたちは
ワラでたたいたり、雪をおしつけたり
雪玉を投げつけたりして
火消しをしてまわったり
火付け役の邪魔したり、と
走り回り…。
大概、大人たちは酔っぱらってるので
すばやい子どもたちが優勢(^_^)
わたしが6年生のときは、
子どもたちの結束力がかたくて
火がつかなすぎ
待ってる大人や、見に来た大人たちも
待ちきれなくなって
火付けにまわってしまい
ついに付けられてしまった
 記憶が
記憶があります。
なつかしいなぁ。
火がついたら
書き初めを燃やし、
ものづくりのもちを焼きました。
書き初めは
高く上がっていくと字が上手になると
いわれ…
おもちは、食べると風邪をひかないと
いわれ…
ものづくり といわれる おもち は
ウチでは作らなかったのですが
姉の幼なじみの家に
わたしまでよんでもらって
いっしょに作らせてもらったのが
お正月の楽しみだったなぁ

そのおウチは、
家の中に小川が通っていて、水車が回り
だんごを作る米の粉をひいたりもしていました。
庭には、大きな だんごの木があって
もちを飾るのに ほどよい枝ぶりの木を
あれこれ言いながら
切り出してもらうのも
楽しみのひとつ(^^)
ずっと、だんごの木とよんでたけど
だんごの木、水木というらしいですね。
色を入れてこねてもらった米の粉を
見よう見まねで
まゆ玉、綿の花、俵、ナス、きゅうり
豆、柿 などに作ります。
ナスのヘタを、糸切りバサミで
ちょんちょんと切り出す工夫が
びっくりで、やらせてもらったり、、
オリジナルに好きなものも作らせてもらったり。
一番年下で不器用なので
みんなに「なにそれ?」といわれること
しばし(⌒-⌒; )
色とりどり、形さまざま な
見るも愉快な おだんご。
蒸して枝に刺すとき、だんごが
大きすぎて枝がしなってしまったりして
もう笑いっとおし。
おもちを蒸してる間には
みんなでそり遊びに出掛けたり
双六したり、トランプしたり
楽しかったなあ。
今思うと
貴重な体験をさせてもらいました。
父の時代には…
どうろくじん を作る前に
さえのかみ の くわぁんじん♪
♪こめ いっしょ に まめ ごんごう
(塞の神の勧進 米一升に豆五合)
と、
唄って各戸
 をめぐったらしい。
をめぐったらしい。父が覚えているのは集めたところまで。
豆ごはんむすびにして、
配られたりしたらしいですね。
火付けも、各地域対抗で
作ってから本番まで
夜番もして、他地域の人に燃やされないようにしたらしい。
母は、昼のうちに燃やされてしまった
どうろくじんを見たことがあるそう。
その地域はどうしたんでしょうね。
もう一回作ったんでしょうか。
さらに
亡くなった祖母は隣の市の出身でしたが
その祖母の時代には…
祖母から聞いた話では
どうろくじん のあった日の
真夜中過ぎから翌早朝の間に
♪どうろくじんさん、どうろくじんさん
どうろくじん というひとは♪
♪みちの はたに ねてた~♪
あずきのしる かけられて~♪
♪ふぎゃーふぎゃーとないた
と、年男の人たちが唄いながら
どうろくじん の燃えつきた柱を
引いてあるき
初めての男の子が産まれた家
 のかどに
のかどにこっそり置いていったそうな。
時代、地域によって様々ですね。
今は子どもも減り
火を使う行事は大変ですが
なるべく昔の形が残るといいなぁ