ひっじょーに面白かった。
良い文章とは、を書いた本に対して「ひっじょーに」とか言ってたら、
川端康成は草葉の陰で鼻を鳴らすだろう。
伊藤整の解説も含めて文庫112ページの本。非常に薄い。
しかもその中で最小限読むべきところは第3章までです。
いや、もちろん112ページしかないから全部読んでいいんだけど、
とりわけ感銘を受けるのは第3章まで。
第4章以降は同時代作家の実際の作品(文章)を比較・検討・分析している。
それはそれで面白いけれども、わたし程度は例に挙げられた有名作家
(泉鏡花や佐藤春夫、菊池寛や里見弴など多数)を各1冊くらいしか読んでないし、
引用部分も相当多いから、それをじっくり読むのは骨が折れる。
そもそも川端康成自身も2、3冊しか読んでない。
この部分は5割くらいの集中力で読みました。
しかし1章から3章までは本当にいいですよ!
まず「おお!」と思ったのは、川端康成が芸術活動を「芸術創作」と「芸術受用」とし、
作者と読者の双方の心理活動としている点。
創作活動は創作側だけが偉くて、読んでいる方は単に読んでるだけだと思っていたよ。
ノーベル賞作家にして読者が目に入っているとは。(偏見だが)目から鱗。
そして双方を結ぶ一本の橋は表現であるという。
どんな(善き)意図があっても、新しい手法を試みたとしても、「表現」の選択を
吟味しない限り、その内容は伝わらない。……と勝手に言葉を変えて言ってるけど、
だいたいこんなことを言ってるはずです。間違っていたらお詫びの上訂正する。
表現とは文章である。そして文章は小説の命であり枷である。
それぞれの国にその国の文章があり、時代ごとにも各々の文章がある。
坪内逍遥、二葉亭四迷の例が出て来る。たしかにこの頃は日本口語文の黎明期で
彼ら二人は相当に苦労していたはずだ。わたしが読んだ時もそう感じた。
ヨチヨチ歩き出したばかりの現代口語、という感じだったもの。
……こんな感じで続けていくと永遠に終わらないので、
感銘を受けた部分を書き抜く。
切り取りは悪意がなくても恣意的になりがちなので、文責はわたしにあります。
〇文章の第一条件は、この簡潔、平明ということであり、如何なる美文も、
若し人の理解を妨げたならば、卑俗な拙文にも劣るかもしれない。
〇「平家物語」や「太平記」はその当時にあっては確かに名文だったであろうが、
文章もまた星霜と共に変る。
〇単語の選択は、よき文章の第一歩で、ここに文章の生命もこもる。
〇音楽的効果についてもそうで、「耳できいて解る文章」とは、私の年来の祈りである。
〇世界各国共通語の文芸の夢もみる。
他に抜き書きが出来ないところで、芥川龍之介が「しゃべるように書く」よりむしろ
「書くようにしゃべりたい」と言っていた部分の引用とか、
漢文調が命脈を長く保ったのに、和文調の文章が早く廃れたといわれるのは本当かとか、
面白いところが数々ある。わたしが面白いと思ったものの他にも人によってはあるだろう。
そして何よりこれが、名文で書かれているというのが。
看板に偽りなしですねー。
「雪国」を読んだ時に思ったけれど、この人は本当に描写がきれい。
今回は描写ではなくて随筆ですが、明晰でちょっと湿度もあっていいですね。
文章家といえば川端康成というべきにやあらむ。中島敦もいいと思ったが。
文章の書き方について、川端康成は自分自身の問題として長年考え続けていたのだろう。
その結論を読者が一足飛びに教えてもらえるのは大変お得な気がする。
実はこれから大家の文章読本を続けて読もうと思っていて、まずは川端康成。
次が谷崎潤一郎。吉行淳之介。中村真一郎。三島由紀夫。井上ひさし。
丸谷才一は数年前に読んだ。「ちよつと気取って書け。」が印象的だった。
良い文章とは、を書いた本に対して「ひっじょーに」とか言ってたら、
川端康成は草葉の陰で鼻を鳴らすだろう。
伊藤整の解説も含めて文庫112ページの本。非常に薄い。
しかもその中で最小限読むべきところは第3章までです。
いや、もちろん112ページしかないから全部読んでいいんだけど、
とりわけ感銘を受けるのは第3章まで。
第4章以降は同時代作家の実際の作品(文章)を比較・検討・分析している。
それはそれで面白いけれども、わたし程度は例に挙げられた有名作家
(泉鏡花や佐藤春夫、菊池寛や里見弴など多数)を各1冊くらいしか読んでないし、
引用部分も相当多いから、それをじっくり読むのは骨が折れる。
そもそも川端康成自身も2、3冊しか読んでない。
この部分は5割くらいの集中力で読みました。
しかし1章から3章までは本当にいいですよ!
まず「おお!」と思ったのは、川端康成が芸術活動を「芸術創作」と「芸術受用」とし、
作者と読者の双方の心理活動としている点。
創作活動は創作側だけが偉くて、読んでいる方は単に読んでるだけだと思っていたよ。
ノーベル賞作家にして読者が目に入っているとは。(偏見だが)目から鱗。
そして双方を結ぶ一本の橋は表現であるという。
どんな(善き)意図があっても、新しい手法を試みたとしても、「表現」の選択を
吟味しない限り、その内容は伝わらない。……と勝手に言葉を変えて言ってるけど、
だいたいこんなことを言ってるはずです。間違っていたらお詫びの上訂正する。
表現とは文章である。そして文章は小説の命であり枷である。
それぞれの国にその国の文章があり、時代ごとにも各々の文章がある。
坪内逍遥、二葉亭四迷の例が出て来る。たしかにこの頃は日本口語文の黎明期で
彼ら二人は相当に苦労していたはずだ。わたしが読んだ時もそう感じた。
ヨチヨチ歩き出したばかりの現代口語、という感じだったもの。
……こんな感じで続けていくと永遠に終わらないので、
感銘を受けた部分を書き抜く。
切り取りは悪意がなくても恣意的になりがちなので、文責はわたしにあります。
〇文章の第一条件は、この簡潔、平明ということであり、如何なる美文も、
若し人の理解を妨げたならば、卑俗な拙文にも劣るかもしれない。
〇「平家物語」や「太平記」はその当時にあっては確かに名文だったであろうが、
文章もまた星霜と共に変る。
〇単語の選択は、よき文章の第一歩で、ここに文章の生命もこもる。
〇音楽的効果についてもそうで、「耳できいて解る文章」とは、私の年来の祈りである。
〇世界各国共通語の文芸の夢もみる。
他に抜き書きが出来ないところで、芥川龍之介が「しゃべるように書く」よりむしろ
「書くようにしゃべりたい」と言っていた部分の引用とか、
漢文調が命脈を長く保ったのに、和文調の文章が早く廃れたといわれるのは本当かとか、
面白いところが数々ある。わたしが面白いと思ったものの他にも人によってはあるだろう。
そして何よりこれが、名文で書かれているというのが。
看板に偽りなしですねー。
「雪国」を読んだ時に思ったけれど、この人は本当に描写がきれい。
今回は描写ではなくて随筆ですが、明晰でちょっと湿度もあっていいですね。
文章家といえば川端康成というべきにやあらむ。中島敦もいいと思ったが。
文章の書き方について、川端康成は自分自身の問題として長年考え続けていたのだろう。
その結論を読者が一足飛びに教えてもらえるのは大変お得な気がする。
実はこれから大家の文章読本を続けて読もうと思っていて、まずは川端康成。
次が谷崎潤一郎。吉行淳之介。中村真一郎。三島由紀夫。井上ひさし。
丸谷才一は数年前に読んだ。「ちよつと気取って書け。」が印象的だった。










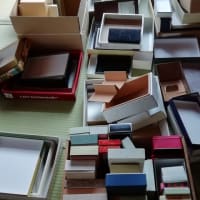














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます