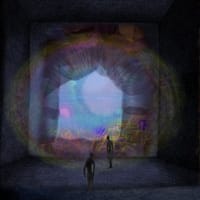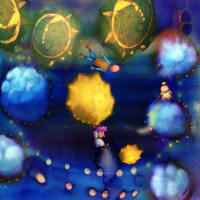ロボサムライ駆ける■第七章 血闘場(5)
■ロボサムライ駆ける■第七章 血闘場(5)
作 飛鳥京香(C)飛鳥京香・山田企画事務所
http://www.yama-kikaku.com/
http://ameblo.jp/yamadabook/ (5)
主水は過去を思い出していた。三年前、主水は大帝の前に膝を屈していた。
「そちが早乙女主水か。日本からの留学ロボットか」
ルドルフが尋ねた。
「さようでございます」
側には心配そうな顔をした、マリアが佇んでいた。
「本来ならば、黄色いロボットなど会いたくはないのだがのう」
ルドルフ大帝は主水を見下すようにしゃべった。ルドルフは黄金のいすに座っている。ここはベルリン、ルドルフの宮殿、謁見の間である。
霊戦争後、ヨーロッパの大国となったのは、ルドルフ大帝率いる神聖ゲルマン帝国である。このルドルフの宮殿は、ヨーロッパ各国から贈られた美術工芸品で一杯だという。美的センスにおいてはヨーロッパ一だと思われていて、本人にもそう思っている耽美王である。財宝には眼がないのだ。
「おまけに、そちはこのリヒテンシュタイン卿の娘マリア=リヒテンシュタインを嫁に迎えたいというのか」
黙って膝を曲げているだけの主水である。「これ主水とやら、返事をせぬか」
宮殿の誰かが声を掛けた。
「さようでございます、殿下。ぜひともマリア=リヒテンシュタイン嬢を我が嫁に」
「が、貴公知っておろう。マリアはビスマルク公の息子ザムザと婚約しておるのだぞ」
主水はルドルフを見上げた。
「それも充分承知しております」
主水はキッとして答える。
「ほほう、充分だと。どれくらい充分なのかな。では、マリアを掛けて、ザムザ=ビスマルクと対決するかな」
ルドルフは主水の胸を内を探るように尋ねた。
「……」
「どうじゃ。返事をせい」
その時、宮殿に急ぎ走り込んできたロボットがある。
「大帝、こやつが何と言おうと決闘させて下さい」
金髪で、力強い顎、冷徹な青い眼、鷲鼻、おまけに二メートル二〇はある巨身。ザムザ=ビスマルクである。
「この東洋の黄色い猿ロボットに、むざむざ婚約者を盗まれたとあっては我が家の名誉にかかわります。大帝、どうか決闘をお許し下さい」
息せききって言うザムザであった。
「どうじゃな、主水。もし、この決闘の申し出を受けなければ、東洋の卑怯者として貴公の名は長く残るであろうよ」
ルドルフはひじ掛けに手を当て、足を組み、ゆっくりと言った。主水をけしかけているのだ。
「主水、決闘だ」
「主水、どうか、私のために決闘しないで。卑怯者と言われてもいいではないの。あなたがいなくなることが恐い」
側にたたずんているマリアが嘆いていた。「決闘しないというならば、私がマリアを殺すぞ」
ザムザがマリアを抱き抱えていた。ゆっくりと剣を抜く。
「これ、ザムザ。大帝の前であるぞ。何をしでかすザムザ。恋の嫉妬に目が眩んだか」
「いえ大帝、失礼をお許し下さい。ヨーロッパロボットが、この東洋ロボットに辱めを受けたこと、許しがたいのです」
「決闘せざるをえないな、ザムザ」
主水がザムザの方をキッとにらみつけ、ゆっくり言った。
決闘場所は、ベルリンから離れた田舎の都市、ハイデルベルグである。決闘の町として有名であった。
決闘場には、多数の観客が詰め掛けていた。スタジアムの真ん中で二人は対峙しているのである。正式な決闘のため、ルドルフ大帝が役人を遣わしていた。
東洋のロボットを見ようと、人々は詰め掛けていたのである。二人の一挙一動にスタジアムから歓声が上がっている。空は決闘日和に、雲ひとつなく晴れ上がり、マイン川からの澄み切った風が二人の体をなでていた。
二人は長い間睨み合っている。
「主水、容赦はしないぞ」
「ご同様だ。ザムザ」
叫ぶやいなや両者は中央に躍り出た。
最初のひとたちが、主水の額を切った。
「おおっ…」
という叫び声が観客から上がる。
「ふん、口ほどにもないのう、主水」
「あっ」
マリアが眼をつぶってしまった。
「マリア、眼をつぶるな、お前の愛しい主水が我輩の手で倒れるのを見ろ」
勝ち誇るザムザ。瞬間、ザムザにすきが生じる。それを見逃す主水ではない。
「と-つ」
その慢心の笑みの顔真ん中を主水のムラマサは突き抜いていた。
「うわっ…」
観客のさざめきが主水の耳にも届いた。スタジアムは総立ちである。その時、スタジアムに何かが侵入してきた。
「ザムザ君」
大きな悲鳴が、主水の後から聞こえた。
「この黄色いロボットめが、私の愛しいザムザを…」
主水は、剣を、ザムザの顔から引き抜き、声の主の方へ振り返った。
白馬に乗ったやさ男が、にくしみの青い目で、主水を睨んでいる。怒りのオーラがそのあたりに満ち満ちていた。男はゆっくりと馬から降り、ザムザの体を抱き上げ、ほおずりした。
「ザムザ、さぞつらかったろう」
そして、再び、主水の方を向いた。
「主水とやら、今度は私が相手だ」
まわりの観衆から、宮廷人々が止めに入った。
「お止めください、ロセンデール様。これは正式の決闘なのです」
「いや、ならん。この黄色いロボットに一太刀打ち付けねば…」
「存分にされよ。受けて立ちましょう」
「何をほざく」
それが初めての出会いであった。
◆
「リキュール、何をしておるのじゃ」
怒りの声が女に飛んでいる。
リヒテンシュタイン博士は、自分の実験室で資料をまさぐっている我が娘を発見していた。リヒテンシュタイン研究所は、博士がロボットでありながら、新しいタイプのロボットを研究していることで、世界でも有名であった。
「ま、まさか、お前、私の発見をロセンデールに…」
少し考えていたリヒテンシュタイン博士だが言う。
「わかったぞ、今までロセンデールに情報を流しておったのは、お前だったのか。我が娘だとは気付かなかった」
「今頃、気が付いたのですか、お父様。まあ頭の古いタイプのロボットのお父様としては仕方がないですわね」
「何を言う…」
階下での二人の大声の、ののしりあいを聞き付けて、登場するのはリキュールと双子ロボットであるマリアであった。
「いったい何があったの」
研究室で睨み合っている二人のロボットに気付く。
「お父様。まあ、リキュールお姉様もどういうことなの」
「マリア、このお前の姉は裏切り者なんじゃ。ロセンデールに秘密を漏らしておったのじゃ」 博士は怒りにまかせて、リキュールを非難する。
「どうして、お姉様」
マリアはリキュールに目を向けた。
「どうしてですかって、マリア、お前はあの主水とかいう東洋のロボットにううつを抜かしてしまって目が見えなくなってしまったのですか。今の世界をご覧なさい。早く世界を統一しなきゃあ、大変なことになってしまうのですよ」
妹のマリアの方を向いてリキュールは毒ついた。
「それとロセンデールに秘密をしゃべることは関係があるのですか」
「この娘はロセンデールにたぶらかされおって。よし、今からロセンデールの家に行こう、お前は留守番だ、マリア」
「でも、私もいったほうが…」
「いい」
それが、マリアが生きている二人を見た最後だった。二人は邸から出て行く。悲劇はこの後おこった。
二人の遺体がロセンデール家から送り返されてきた。
『当家に侵入しょうとして殺された』との添え書きつきで。
ロセンデールが、リキュールとリヒテンシュタイン博士を殺したのか。それははっきりとはわからない。
マリアは博士とリキュールの遺体を前に復讐を誓う。
「お姉様。いい、あなたの記憶を私の電子頭脳の一部に移植するわ。だから、私は今日からマリア=リキュール=リヒテンシュタインとなるわ。ロセンデール卿、覚えてらっしゃい。きっと父の恨み晴らして見せるわ」
「マリアどうした。なぜそんなに嘆き悲しんでいるんだ」
主水がリヒテンシュタイン博士の屋敷を訪れていた。
「主水…、もっと早くきてくれれば……」
主水の胸元で泣き崩れるマリアでった。
「お父様とお姉様が…、ロセンデールに滅ぼされたの」
「が、リキュール殿はロセンデール卿の…」「そう、姉はロセンデールの愛人ロボットだった。でもこの状態よ」
「ルドルフ殿下に訴えれば…」
「だめよ。証拠がない。それに、ロセンデールはルドルフ殿下のお気に入りだもの」
「おのれ、ロセンデールめ、この恨みはらさいでか」
「復讐は、ロセンデールが他の国にいるときでないと…」
が、主水とマリアは、とうとうロセンデールの屋敷まできてしまっていた。ロセンデールの館は中世の城を模して作られている。回りに堀が巡らされている。
「ロセンデール、姿を見せろ」
主水は長い間叫んでいた。やがて、ロセンデールが城壁の上から姿を見せた。
「おや、これはこれは私の愛しいザムザを滅ぼした黄色いロボットではありませんか。それに黄色いロボットにくっついた裏切り者では…」
ロセンデールの嘲りの言葉に、急にマリアが珍しく、癇癪を爆発させていた。
「ロセンデール、降りてらっしゃい。父と姉の敵…」
「おやおや、麗人マリア、どうかしたのですか。そんな怒りは体によくありませんよ。私があなたの博士と姉を殺したですと…。間違ってもらっては困ります。二人は、私のこの屋敷に不法侵入しようとしたのです。それ故、自動装置が働き、二人を焼き殺してしまったのです。事故ですよ。事故」
「ロセンデール、覚えていなさい。この敵、必ず打って見せます」
「おやおや、マリア。恐ろしい表情ですね。あなたの姉リキュールはいくら怒ったって、このようなお顔は見せませんでしたよ」
「止めなさい。私の姉を嘲るのは」
「主水よろしいですか。愛しい者を失ったものの痛みがわかったでしょう」
ロセンデールの青い目に冷たい光が宿っていた。騒ぎを聞き付けてルドルフの親衛隊が駆けつけ、とりあえず収まったのであるが。ロセンデールは次々と刺客を二人の身を襲わせた。それ故、二人は神聖ゲルマン帝国より逃れたのである。
(続く)
■ロボサムライ駆ける■第七章 血闘場(5)
作 飛鳥京香(C)飛鳥京香・山田企画事務所
http://www.yama-kikaku.com/
http://ameblo.jp/yamadabook/
■ロボサムライ駆ける■第七章 血闘場(5)
作 飛鳥京香(C)飛鳥京香・山田企画事務所
http://www.yama-kikaku.com/
http://ameblo.jp/yamadabook/ (5)
主水は過去を思い出していた。三年前、主水は大帝の前に膝を屈していた。
「そちが早乙女主水か。日本からの留学ロボットか」
ルドルフが尋ねた。
「さようでございます」
側には心配そうな顔をした、マリアが佇んでいた。
「本来ならば、黄色いロボットなど会いたくはないのだがのう」
ルドルフ大帝は主水を見下すようにしゃべった。ルドルフは黄金のいすに座っている。ここはベルリン、ルドルフの宮殿、謁見の間である。
霊戦争後、ヨーロッパの大国となったのは、ルドルフ大帝率いる神聖ゲルマン帝国である。このルドルフの宮殿は、ヨーロッパ各国から贈られた美術工芸品で一杯だという。美的センスにおいてはヨーロッパ一だと思われていて、本人にもそう思っている耽美王である。財宝には眼がないのだ。
「おまけに、そちはこのリヒテンシュタイン卿の娘マリア=リヒテンシュタインを嫁に迎えたいというのか」
黙って膝を曲げているだけの主水である。「これ主水とやら、返事をせぬか」
宮殿の誰かが声を掛けた。
「さようでございます、殿下。ぜひともマリア=リヒテンシュタイン嬢を我が嫁に」
「が、貴公知っておろう。マリアはビスマルク公の息子ザムザと婚約しておるのだぞ」
主水はルドルフを見上げた。
「それも充分承知しております」
主水はキッとして答える。
「ほほう、充分だと。どれくらい充分なのかな。では、マリアを掛けて、ザムザ=ビスマルクと対決するかな」
ルドルフは主水の胸を内を探るように尋ねた。
「……」
「どうじゃ。返事をせい」
その時、宮殿に急ぎ走り込んできたロボットがある。
「大帝、こやつが何と言おうと決闘させて下さい」
金髪で、力強い顎、冷徹な青い眼、鷲鼻、おまけに二メートル二〇はある巨身。ザムザ=ビスマルクである。
「この東洋の黄色い猿ロボットに、むざむざ婚約者を盗まれたとあっては我が家の名誉にかかわります。大帝、どうか決闘をお許し下さい」
息せききって言うザムザであった。
「どうじゃな、主水。もし、この決闘の申し出を受けなければ、東洋の卑怯者として貴公の名は長く残るであろうよ」
ルドルフはひじ掛けに手を当て、足を組み、ゆっくりと言った。主水をけしかけているのだ。
「主水、決闘だ」
「主水、どうか、私のために決闘しないで。卑怯者と言われてもいいではないの。あなたがいなくなることが恐い」
側にたたずんているマリアが嘆いていた。「決闘しないというならば、私がマリアを殺すぞ」
ザムザがマリアを抱き抱えていた。ゆっくりと剣を抜く。
「これ、ザムザ。大帝の前であるぞ。何をしでかすザムザ。恋の嫉妬に目が眩んだか」
「いえ大帝、失礼をお許し下さい。ヨーロッパロボットが、この東洋ロボットに辱めを受けたこと、許しがたいのです」
「決闘せざるをえないな、ザムザ」
主水がザムザの方をキッとにらみつけ、ゆっくり言った。
決闘場所は、ベルリンから離れた田舎の都市、ハイデルベルグである。決闘の町として有名であった。
決闘場には、多数の観客が詰め掛けていた。スタジアムの真ん中で二人は対峙しているのである。正式な決闘のため、ルドルフ大帝が役人を遣わしていた。
東洋のロボットを見ようと、人々は詰め掛けていたのである。二人の一挙一動にスタジアムから歓声が上がっている。空は決闘日和に、雲ひとつなく晴れ上がり、マイン川からの澄み切った風が二人の体をなでていた。
二人は長い間睨み合っている。
「主水、容赦はしないぞ」
「ご同様だ。ザムザ」
叫ぶやいなや両者は中央に躍り出た。
最初のひとたちが、主水の額を切った。
「おおっ…」
という叫び声が観客から上がる。
「ふん、口ほどにもないのう、主水」
「あっ」
マリアが眼をつぶってしまった。
「マリア、眼をつぶるな、お前の愛しい主水が我輩の手で倒れるのを見ろ」
勝ち誇るザムザ。瞬間、ザムザにすきが生じる。それを見逃す主水ではない。
「と-つ」
その慢心の笑みの顔真ん中を主水のムラマサは突き抜いていた。
「うわっ…」
観客のさざめきが主水の耳にも届いた。スタジアムは総立ちである。その時、スタジアムに何かが侵入してきた。
「ザムザ君」
大きな悲鳴が、主水の後から聞こえた。
「この黄色いロボットめが、私の愛しいザムザを…」
主水は、剣を、ザムザの顔から引き抜き、声の主の方へ振り返った。
白馬に乗ったやさ男が、にくしみの青い目で、主水を睨んでいる。怒りのオーラがそのあたりに満ち満ちていた。男はゆっくりと馬から降り、ザムザの体を抱き上げ、ほおずりした。
「ザムザ、さぞつらかったろう」
そして、再び、主水の方を向いた。
「主水とやら、今度は私が相手だ」
まわりの観衆から、宮廷人々が止めに入った。
「お止めください、ロセンデール様。これは正式の決闘なのです」
「いや、ならん。この黄色いロボットに一太刀打ち付けねば…」
「存分にされよ。受けて立ちましょう」
「何をほざく」
それが初めての出会いであった。
◆
「リキュール、何をしておるのじゃ」
怒りの声が女に飛んでいる。
リヒテンシュタイン博士は、自分の実験室で資料をまさぐっている我が娘を発見していた。リヒテンシュタイン研究所は、博士がロボットでありながら、新しいタイプのロボットを研究していることで、世界でも有名であった。
「ま、まさか、お前、私の発見をロセンデールに…」
少し考えていたリヒテンシュタイン博士だが言う。
「わかったぞ、今までロセンデールに情報を流しておったのは、お前だったのか。我が娘だとは気付かなかった」
「今頃、気が付いたのですか、お父様。まあ頭の古いタイプのロボットのお父様としては仕方がないですわね」
「何を言う…」
階下での二人の大声の、ののしりあいを聞き付けて、登場するのはリキュールと双子ロボットであるマリアであった。
「いったい何があったの」
研究室で睨み合っている二人のロボットに気付く。
「お父様。まあ、リキュールお姉様もどういうことなの」
「マリア、このお前の姉は裏切り者なんじゃ。ロセンデールに秘密を漏らしておったのじゃ」 博士は怒りにまかせて、リキュールを非難する。
「どうして、お姉様」
マリアはリキュールに目を向けた。
「どうしてですかって、マリア、お前はあの主水とかいう東洋のロボットにううつを抜かしてしまって目が見えなくなってしまったのですか。今の世界をご覧なさい。早く世界を統一しなきゃあ、大変なことになってしまうのですよ」
妹のマリアの方を向いてリキュールは毒ついた。
「それとロセンデールに秘密をしゃべることは関係があるのですか」
「この娘はロセンデールにたぶらかされおって。よし、今からロセンデールの家に行こう、お前は留守番だ、マリア」
「でも、私もいったほうが…」
「いい」
それが、マリアが生きている二人を見た最後だった。二人は邸から出て行く。悲劇はこの後おこった。
二人の遺体がロセンデール家から送り返されてきた。
『当家に侵入しょうとして殺された』との添え書きつきで。
ロセンデールが、リキュールとリヒテンシュタイン博士を殺したのか。それははっきりとはわからない。
マリアは博士とリキュールの遺体を前に復讐を誓う。
「お姉様。いい、あなたの記憶を私の電子頭脳の一部に移植するわ。だから、私は今日からマリア=リキュール=リヒテンシュタインとなるわ。ロセンデール卿、覚えてらっしゃい。きっと父の恨み晴らして見せるわ」
「マリアどうした。なぜそんなに嘆き悲しんでいるんだ」
主水がリヒテンシュタイン博士の屋敷を訪れていた。
「主水…、もっと早くきてくれれば……」
主水の胸元で泣き崩れるマリアでった。
「お父様とお姉様が…、ロセンデールに滅ぼされたの」
「が、リキュール殿はロセンデール卿の…」「そう、姉はロセンデールの愛人ロボットだった。でもこの状態よ」
「ルドルフ殿下に訴えれば…」
「だめよ。証拠がない。それに、ロセンデールはルドルフ殿下のお気に入りだもの」
「おのれ、ロセンデールめ、この恨みはらさいでか」
「復讐は、ロセンデールが他の国にいるときでないと…」
が、主水とマリアは、とうとうロセンデールの屋敷まできてしまっていた。ロセンデールの館は中世の城を模して作られている。回りに堀が巡らされている。
「ロセンデール、姿を見せろ」
主水は長い間叫んでいた。やがて、ロセンデールが城壁の上から姿を見せた。
「おや、これはこれは私の愛しいザムザを滅ぼした黄色いロボットではありませんか。それに黄色いロボットにくっついた裏切り者では…」
ロセンデールの嘲りの言葉に、急にマリアが珍しく、癇癪を爆発させていた。
「ロセンデール、降りてらっしゃい。父と姉の敵…」
「おやおや、麗人マリア、どうかしたのですか。そんな怒りは体によくありませんよ。私があなたの博士と姉を殺したですと…。間違ってもらっては困ります。二人は、私のこの屋敷に不法侵入しようとしたのです。それ故、自動装置が働き、二人を焼き殺してしまったのです。事故ですよ。事故」
「ロセンデール、覚えていなさい。この敵、必ず打って見せます」
「おやおや、マリア。恐ろしい表情ですね。あなたの姉リキュールはいくら怒ったって、このようなお顔は見せませんでしたよ」
「止めなさい。私の姉を嘲るのは」
「主水よろしいですか。愛しい者を失ったものの痛みがわかったでしょう」
ロセンデールの青い目に冷たい光が宿っていた。騒ぎを聞き付けてルドルフの親衛隊が駆けつけ、とりあえず収まったのであるが。ロセンデールは次々と刺客を二人の身を襲わせた。それ故、二人は神聖ゲルマン帝国より逃れたのである。
(続く)
■ロボサムライ駆ける■第七章 血闘場(5)
作 飛鳥京香(C)飛鳥京香・山田企画事務所
http://www.yama-kikaku.com/
http://ameblo.jp/yamadabook/