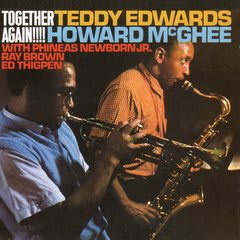まつきり三郎 & スイングバイ・ブラザース
ミュージシャンにとってレコーディングというのは一つの目標であり、活動の節目であろう。その昔はレコードを発売してくれるレーベルがまずありき。プロであっても新人のみならず、ベテランといえどもレコード会社にまずは認められないことには、アルバムを作ることもできなかった。
演奏が一度アルバムになれば、それなりに告知もされファンの間で話題になり、人気が出ることも。ファンにとっては実際のライブ演奏は聴いた事が無くとも、まずはレコードを聴いてファンになるのが普通であった。
ミュージシャンにとっても活動歴の中のひとつのステップとして、自分の参加したアルバムを紹介することもできた。ジャズのように、日々変化をしている中で「その時の演奏の記録」としての意味は大きいと思う。過去の偉大なミュージシャンも録音が無いと単なる伝説の人でしかない。
今の時代、レコード会社が企画して作られるジャズのアルバムというのは何枚あるのだろうか?自分は昨今の業界事情にはまったく疎いので、もしかしたらそれなりに発売されているのかもしれない。少なくとも自分はそのような新譜アルバムを最近買い求めたことは無い。
ライブに行った時に紹介されるアルバムというは、大部分が自主制作のアルバム。なかなか普段接することもないので聴く事はおろか、存在自体を知らない。昔は新しいアルバムが出ると雑誌で紹介され、ジャズ喫茶にも入荷し、ラジオで聴くことも多かったが、今はそれらを知ること自体が大変だ。
今思い返せば、ジャズを聴き始めた頃はラジオを良く聴いた。受験生の友であった深夜放送はもちろんだが、ジャズのよくかかる番組を探して欠かさず聴いていたものだ。ラジオで聴くと途中でDJの語りや解説も入って、知らず知らずのうちにミュージシャン・曲やアルバムの説明を受けることになる。それが自然と記憶の片隅に、ジャズを知るのはそんなパターンであった。
今は自主制作が当たり前の時代、誰でも作る気になればなれるのだが。しかし、せっかく作ったアルバムをどうやって世に知らしめ、ファンの手元に届けるか?何でもネットでできる時代になったとはいえ、実際にはなかなか難しい問題だ。
アルバムを作るにはそれなりのコストもかかる。道楽で作るのなら別だが、プロであればそれなりの儲けも出るくらい捌かなければならないし。プロモートや販売を全部自分でやるのも大変だ。
このところ、定期的に活動をしている「まつりき三郎とスイングブラザース」も初めてCDを録音したという話をしばらく前に聞いた。やっと発売にこぎつけたとのことで、久々に新CDの入手を兼ねてライブに出掛けてみた。場所は、高田馬場のサニーサイド。このバンドにはお似合いの、家庭的な雰囲気のライブハウスだ。
当日のライブの最初の曲はTo You。以前に聴いた時(その時、記事を書いた記憶がある)はラストの曲だったが、自分が好きな曲だ。
CDではこの曲が一曲目。スインギーなアップテンポな曲ではなくこの曲を選んだというのもユニークだが、このバンドの拘りを感じる。その後も、CDに収められている曲が続く。テナーの渡邊恭一の大ブローが聴けるMistyもライブではアルバム以上の大熱演。締めはベイシーナンバーで有名なシャイニーストッキングス。相変わらず、レパートリーの豊富さと多様さを楽しめるプログラムであった。
「このバンドはスイングジャズをやるバンド」とリーダーの松木氏はいうが、従来の常識のスイングバンドではない。
このバンドの良さを一口でいうのは難しい。メンバーがビッグバンド好き、ドラムレスとか、アレンジ重視とか、曲は何でもとか付け加えていっても、果たしてどこまでイメージできるか。
どんなバンドかというのは、百聞は一見にしかず。ライブを一度聴いて貰うのが一番だが、まずはこのCDを聴いてみるのがいい。
というのも、このCDは50分の収録時間があるが、曲は全部で8曲30分のミニCD。残りはというと曲間にDJが収められている。実は、このCDはジングルも含めて全体がラジオ番組仕立てされている。曲だけでなくDJを含めてこのCDを通して聴くと、このバンドのプロファイルやコンセプトも良く分かるという仕掛けになっていた。
初アルバムといって、意欲だけが空回りして面白くないアルバムも多い。
その点、このCDは自分達のやりたいことのプロモーションと、自分達の技のプレゼンテーションとしては完璧だ。これを聴いて実際にライブを聴いてみようと思う人は多いと思う。自分はこのCDを聴いて、こんな形で新しいグループを知り、次第にジャズ好きになっていった昔のラジオ番組を思い出した。
スイングジャズと銘打ったライブは、大体年寄りが自分達の青春時代を懐かしみ、昔懐かしいサウンドを聴きに集まるものが多い。ところが、今回のライブは若者、ミドル、女性でほぼ満席。自分のような年寄りは反対に肩身が狭かった。きっと今までのスイングジャズのファンだけでなく、このCDを聴いて新たなファンも増えていくと思う。常識破りのスイングジャズで、今後の益々の活躍を期待したいものだ。
1. To You
2. Royal Garden Blues
3. Cantina Band
4. Misty
5. Last Train Home
6. Diarrhea Diary Rag
7. Aren’t You MOSAKU?
8. Shinny Stockings
まつきり三郎 & Swing-by Brothers
MATSUKI Risabro 松木 理三郎 (tp)
WATANABE Kyoichi 渡邊 恭一 (ts cl)
ENOMOTO Yusuke 榎本 裕介 (tb)
KAWANURA Ken 河村 健(p)
KAJI Yuta 加治 雄太 (g)
KIKUTA Shigenobu 菊田 茂伸 (b)
Arranged by 松木理三郎
Produced by Matsuki Risabro & Swing-by Brothers
Recorded at Pastoral Sound, Setagaya, Tokyo on June 19 2015
ミュージシャンにとってレコーディングというのは一つの目標であり、活動の節目であろう。その昔はレコードを発売してくれるレーベルがまずありき。プロであっても新人のみならず、ベテランといえどもレコード会社にまずは認められないことには、アルバムを作ることもできなかった。
演奏が一度アルバムになれば、それなりに告知もされファンの間で話題になり、人気が出ることも。ファンにとっては実際のライブ演奏は聴いた事が無くとも、まずはレコードを聴いてファンになるのが普通であった。
ミュージシャンにとっても活動歴の中のひとつのステップとして、自分の参加したアルバムを紹介することもできた。ジャズのように、日々変化をしている中で「その時の演奏の記録」としての意味は大きいと思う。過去の偉大なミュージシャンも録音が無いと単なる伝説の人でしかない。
今の時代、レコード会社が企画して作られるジャズのアルバムというのは何枚あるのだろうか?自分は昨今の業界事情にはまったく疎いので、もしかしたらそれなりに発売されているのかもしれない。少なくとも自分はそのような新譜アルバムを最近買い求めたことは無い。
ライブに行った時に紹介されるアルバムというは、大部分が自主制作のアルバム。なかなか普段接することもないので聴く事はおろか、存在自体を知らない。昔は新しいアルバムが出ると雑誌で紹介され、ジャズ喫茶にも入荷し、ラジオで聴くことも多かったが、今はそれらを知ること自体が大変だ。
今思い返せば、ジャズを聴き始めた頃はラジオを良く聴いた。受験生の友であった深夜放送はもちろんだが、ジャズのよくかかる番組を探して欠かさず聴いていたものだ。ラジオで聴くと途中でDJの語りや解説も入って、知らず知らずのうちにミュージシャン・曲やアルバムの説明を受けることになる。それが自然と記憶の片隅に、ジャズを知るのはそんなパターンであった。
今は自主制作が当たり前の時代、誰でも作る気になればなれるのだが。しかし、せっかく作ったアルバムをどうやって世に知らしめ、ファンの手元に届けるか?何でもネットでできる時代になったとはいえ、実際にはなかなか難しい問題だ。
アルバムを作るにはそれなりのコストもかかる。道楽で作るのなら別だが、プロであればそれなりの儲けも出るくらい捌かなければならないし。プロモートや販売を全部自分でやるのも大変だ。
このところ、定期的に活動をしている「まつりき三郎とスイングブラザース」も初めてCDを録音したという話をしばらく前に聞いた。やっと発売にこぎつけたとのことで、久々に新CDの入手を兼ねてライブに出掛けてみた。場所は、高田馬場のサニーサイド。このバンドにはお似合いの、家庭的な雰囲気のライブハウスだ。
当日のライブの最初の曲はTo You。以前に聴いた時(その時、記事を書いた記憶がある)はラストの曲だったが、自分が好きな曲だ。
CDではこの曲が一曲目。スインギーなアップテンポな曲ではなくこの曲を選んだというのもユニークだが、このバンドの拘りを感じる。その後も、CDに収められている曲が続く。テナーの渡邊恭一の大ブローが聴けるMistyもライブではアルバム以上の大熱演。締めはベイシーナンバーで有名なシャイニーストッキングス。相変わらず、レパートリーの豊富さと多様さを楽しめるプログラムであった。
「このバンドはスイングジャズをやるバンド」とリーダーの松木氏はいうが、従来の常識のスイングバンドではない。
このバンドの良さを一口でいうのは難しい。メンバーがビッグバンド好き、ドラムレスとか、アレンジ重視とか、曲は何でもとか付け加えていっても、果たしてどこまでイメージできるか。
どんなバンドかというのは、百聞は一見にしかず。ライブを一度聴いて貰うのが一番だが、まずはこのCDを聴いてみるのがいい。
というのも、このCDは50分の収録時間があるが、曲は全部で8曲30分のミニCD。残りはというと曲間にDJが収められている。実は、このCDはジングルも含めて全体がラジオ番組仕立てされている。曲だけでなくDJを含めてこのCDを通して聴くと、このバンドのプロファイルやコンセプトも良く分かるという仕掛けになっていた。
初アルバムといって、意欲だけが空回りして面白くないアルバムも多い。
その点、このCDは自分達のやりたいことのプロモーションと、自分達の技のプレゼンテーションとしては完璧だ。これを聴いて実際にライブを聴いてみようと思う人は多いと思う。自分はこのCDを聴いて、こんな形で新しいグループを知り、次第にジャズ好きになっていった昔のラジオ番組を思い出した。
スイングジャズと銘打ったライブは、大体年寄りが自分達の青春時代を懐かしみ、昔懐かしいサウンドを聴きに集まるものが多い。ところが、今回のライブは若者、ミドル、女性でほぼ満席。自分のような年寄りは反対に肩身が狭かった。きっと今までのスイングジャズのファンだけでなく、このCDを聴いて新たなファンも増えていくと思う。常識破りのスイングジャズで、今後の益々の活躍を期待したいものだ。
1. To You
2. Royal Garden Blues
3. Cantina Band
4. Misty
5. Last Train Home
6. Diarrhea Diary Rag
7. Aren’t You MOSAKU?
8. Shinny Stockings
まつきり三郎 & Swing-by Brothers
MATSUKI Risabro 松木 理三郎 (tp)
WATANABE Kyoichi 渡邊 恭一 (ts cl)
ENOMOTO Yusuke 榎本 裕介 (tb)
KAWANURA Ken 河村 健(p)
KAJI Yuta 加治 雄太 (g)
KIKUTA Shigenobu 菊田 茂伸 (b)
Arranged by 松木理三郎
Produced by Matsuki Risabro & Swing-by Brothers
Recorded at Pastoral Sound, Setagaya, Tokyo on June 19 2015