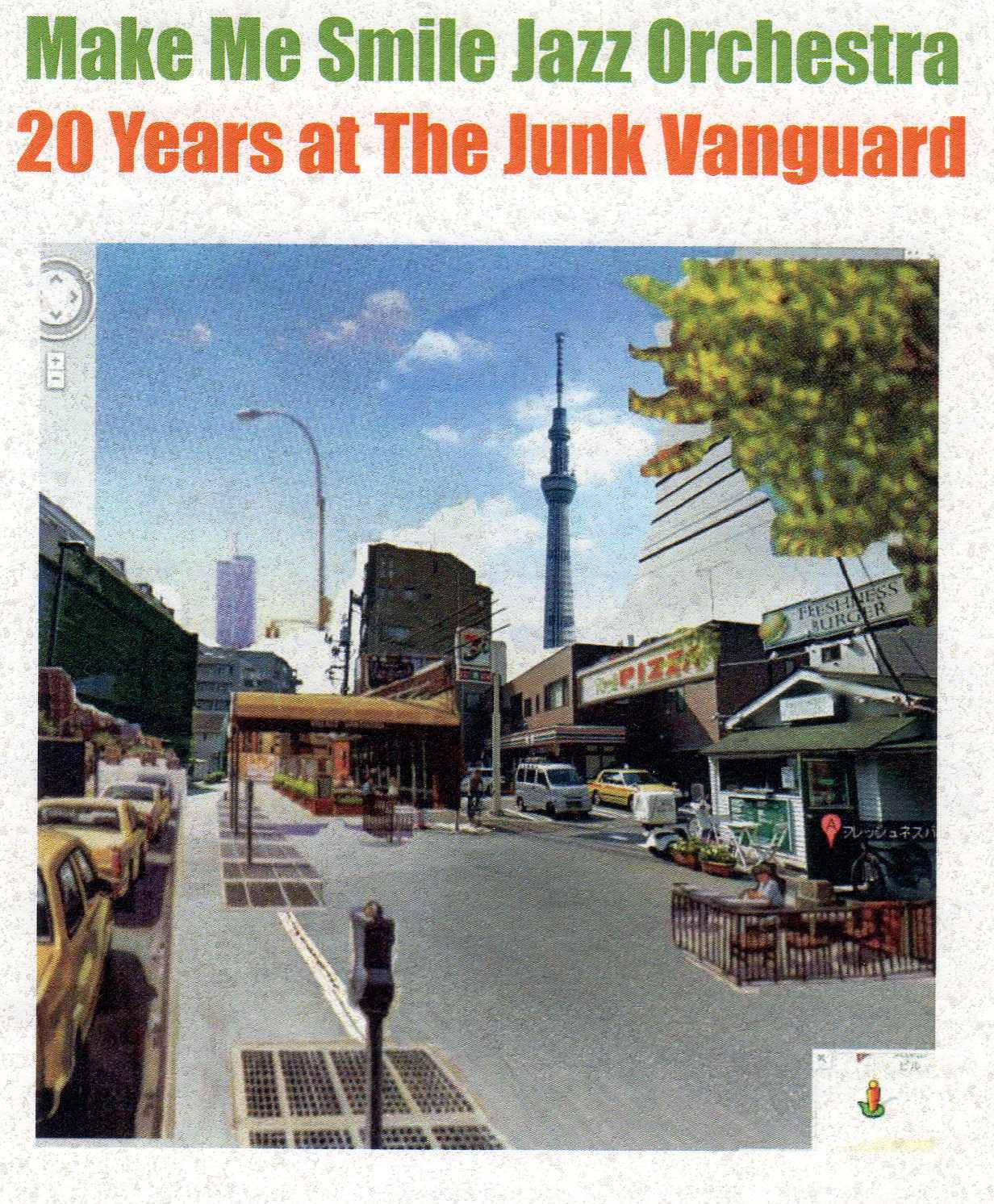James Williams Meets The Saxophone Masters
ジャズメッセンジャーズに加わってメジャーデビューしたミュージシャンは昔から多かった。アートブレーキーのリクルート能力のなせる業であろう。
コンコルドレーベルからアルバムを出していた70年代後半のメッセンジャーズ出身の出世頭はウィントンマルサリスだろう。オーディションにやってきたマルサリスを、ブレイキーに強く勧めたのは当時メンバーであったジェームスウィリアムスであったという。少し前に加わった先輩とはいえ当時のウィリアムスはまだ20代。彼自身がまだデビューしたばかりの時であった。そんなウィリアムスがマルサリスの可能性を感じ取り、親分のブレイキーに自信を持って推薦したとは。ピアニストとしてだけでなく、教育者やプロデューサーとしても活躍したウィリアムスの本物を見極める「眼力」も生まれつきの才能であったのかもしれない。
ジャズメッセンジャーズを辞めた後はニューヨークで、ガレスピーなどの大物ミュージシャンとも共演を重ね、自らのグループでも演奏する。そして、再びブレイキーとレイブラウンと一緒にマジカルトリオを作る。このアルバムは児山紀芳氏のプロデュースであった、大物先輩達に気に入られる「爺殺し」であり、日本人好みのピアニストとして育っていった。
それから10年、すでに40歳を超えピアニストとして確固たる地位を得ていたウィリアムスがプロデュースしたアルバムがこのアルバムになる。
ピアノと一緒に半分顔を出しているジャケットが印象的だが、このアルバムでは確かにピアニストとしてのウィリアムスの役割は半分かもしれない。リーダーアルバムといっても、アルバムタイトルにあるように3人のテナーとの共演アルバムである。
3人のテナーは、真ん中に重鎮ジョーヘンダーソンを据え、左にブレイキー時代一緒にプレーしたビルピアース、右には同じメンフィス出身のジョージコールマンといった布陣。
内容はというとウィリアムスのバックを務めるためのアンサンブル主体でなく、反対に3人のソロの競演を楽しむいわゆるバトル物だ。もちろんウィリアムスのピアノも登場するが、けっして主役というわけではない。ウィリアムス自身、このアルバムのリーダーは自分一人ではなく3人のテナーも一緒だといっているように。
3人並べて聴くと、それぞれの音色、スタイルの違いが良く分かるが、自分の好みというとこの中ではやはりジョーヘンダーソンだ。
このアルバムも日本のレーベルの作品、テナーバトルの企画自体が日本人好みの味付けがされている感じがするが、果たしてジェームスウィリアムスが日本人好みのプレーヤーだったのか、日本人好みのプロデュースを要請されるようになったのか?
1. Fourplay James Williams 9:54
2. Lo Joe G.C. Coleman 6:56
3. Centerpiece Harry "Sweets" Edison 11:08
4. Calgary Traditional 10:16
5. The Song Is You Oscar Hammerstein II / Jerome Kern 9:44
6. Old Folks Dedette Lee Hill / Willard Robison 13:39
Joe Henderson (ts)
George Coleman (ts)
Bill Pierce (ts)
James Williams (p)
James Genus (b)
Tony Reedus (ds)
Produced by James Williams & Kazunori Sugiyama
Engineer : Jim Anderson
Recorded at The Power Station, NYC, on September 23 1991
ジャズメッセンジャーズに加わってメジャーデビューしたミュージシャンは昔から多かった。アートブレーキーのリクルート能力のなせる業であろう。
コンコルドレーベルからアルバムを出していた70年代後半のメッセンジャーズ出身の出世頭はウィントンマルサリスだろう。オーディションにやってきたマルサリスを、ブレイキーに強く勧めたのは当時メンバーであったジェームスウィリアムスであったという。少し前に加わった先輩とはいえ当時のウィリアムスはまだ20代。彼自身がまだデビューしたばかりの時であった。そんなウィリアムスがマルサリスの可能性を感じ取り、親分のブレイキーに自信を持って推薦したとは。ピアニストとしてだけでなく、教育者やプロデューサーとしても活躍したウィリアムスの本物を見極める「眼力」も生まれつきの才能であったのかもしれない。
ジャズメッセンジャーズを辞めた後はニューヨークで、ガレスピーなどの大物ミュージシャンとも共演を重ね、自らのグループでも演奏する。そして、再びブレイキーとレイブラウンと一緒にマジカルトリオを作る。このアルバムは児山紀芳氏のプロデュースであった、大物先輩達に気に入られる「爺殺し」であり、日本人好みのピアニストとして育っていった。
それから10年、すでに40歳を超えピアニストとして確固たる地位を得ていたウィリアムスがプロデュースしたアルバムがこのアルバムになる。
ピアノと一緒に半分顔を出しているジャケットが印象的だが、このアルバムでは確かにピアニストとしてのウィリアムスの役割は半分かもしれない。リーダーアルバムといっても、アルバムタイトルにあるように3人のテナーとの共演アルバムである。
3人のテナーは、真ん中に重鎮ジョーヘンダーソンを据え、左にブレイキー時代一緒にプレーしたビルピアース、右には同じメンフィス出身のジョージコールマンといった布陣。
内容はというとウィリアムスのバックを務めるためのアンサンブル主体でなく、反対に3人のソロの競演を楽しむいわゆるバトル物だ。もちろんウィリアムスのピアノも登場するが、けっして主役というわけではない。ウィリアムス自身、このアルバムのリーダーは自分一人ではなく3人のテナーも一緒だといっているように。
3人並べて聴くと、それぞれの音色、スタイルの違いが良く分かるが、自分の好みというとこの中ではやはりジョーヘンダーソンだ。
このアルバムも日本のレーベルの作品、テナーバトルの企画自体が日本人好みの味付けがされている感じがするが、果たしてジェームスウィリアムスが日本人好みのプレーヤーだったのか、日本人好みのプロデュースを要請されるようになったのか?
1. Fourplay James Williams 9:54
2. Lo Joe G.C. Coleman 6:56
3. Centerpiece Harry "Sweets" Edison 11:08
4. Calgary Traditional 10:16
5. The Song Is You Oscar Hammerstein II / Jerome Kern 9:44
6. Old Folks Dedette Lee Hill / Willard Robison 13:39
Joe Henderson (ts)
George Coleman (ts)
Bill Pierce (ts)
James Williams (p)
James Genus (b)
Tony Reedus (ds)
Produced by James Williams & Kazunori Sugiyama
Engineer : Jim Anderson
Recorded at The Power Station, NYC, on September 23 1991
 | Meets the Saxophone Masters |
| クリエーター情報なし | |
| Sony |