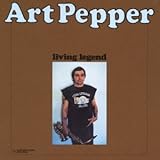Big Band Jazz From The Summit / Louis Bellson
最近あまり行われないがマイクプライスのビッグバンドのライブを聴きに行くとエリントンの曲に加え西海岸のアレンジャーの作品を取り上げることが多い。彼が若い頃過ごしたバディーリッチやスタンケントンオーケストラは西海岸のアレンジャーの作品が多かった。日本に来る前には、西海岸で活動していたので地元の知り合いも多いようだ。
西海岸のアレンジャーというと、ビルホルマン、サムニスティコなどが有名だが、最近ではゴードングッドウィンなどもオーケストラを含めて人気があるようだ。
西海岸のアレンジャーが活躍し始めたのは、映画音楽の興隆と合わせて、ウェストコーストジャズの全盛期50年代に遡るが、ビルホルマンなどの長老達はそこの当時から活躍を続ける第一人者。当時は、他にもマティーペイチ、ショーティーロジャースなどスタンケントンやウディハーマンオーケストラ出身者がプレーだけでなくアレンジャーとしても大活躍していた。
ビッグバンドドラマーというとバディーリッチがすぐに思い浮かぶが、もう一方の雄はルイベルソンだと思う。歯切れの良いドラミングはビッグバンドだけでなく、コンボでの演奏でもメリハリの効いた絶妙なタイム感を持っている。好きなドラマーの一人だ。
このベルソンというと、エリントンオーケストラでのスキンディープが有名だ、他にもベイシーを始めとした有名オーケストラにも在籍したことがあるがいずれも看板にはなっても長続きはしなかったようだ。
やはり、根っからのビッグバンド好きで、自分のイメージもあったのだろう、自らのビッグバンドもよく編成していた。レコーディングだけでなく地元のクラブでのライブ演奏も積極的に行っていた。その時の様子は自分でレコーディングを手配することもあり、後になって世に出たものも多い。コンコルドレーベルにもベルソンのビッグバンドのアルバムは何枚かあるが、その中にもプライベートで作ったアルバムが再び陽の目を見たものがある。
ケニークラーク&フランシーボランがヨーロッパで新たなビッグバンドを立ち上げたのが61年、この時、本家アメリカのビッグバンド事情は冬の時代を迎え、レギュラーオーケストラを維持していくのは名門といえども難しくなっていた。まして、新しいビッグバンドの登場も殆どなかった頃だ。
そんな状況の1962年、ルイベルソンはビッグバンド編成で、地元ロスのクラブ「ザ・サミット」に出演した。編成は、標準的なビッグバンド編成に加えてフレンチホルンとチューバが加わっているのが特徴だが、アレンジでもこれらが上手く使われている。
その時の演奏がライブレコーディングされルーレットレーベルからリリースされた。このバンドにはロスで活躍していたスタジオミュージシャンが参加し、コンテカンドリやジョーマイニといった実力あるソリストも加わっている。しかし、演奏自体はどちらかというと当時の西海岸で活躍して新進気鋭のアレンジャーの作品のお披露目の場といってもいいかもしれない。レコーディングエンジニアは、ライブ録音が得意なWally Heider、いい音とバランスで収録されている。
アルト奏者としても有名なベニーカーターもこの頃はアレンジャーとしての仕事も多かった。このカーターのアレンジが7曲、他にもマティーペイチ、ショーティーロジャース、ボブフローレンスなどの編曲が並ぶ。曲もウェストサイドストーリーからのクールを除けば、スタンダード曲ではなくオリジナル曲が並ぶ。とはいっても大作ではなく、どれもスインギーなベルソンのバンドにはお似合いの曲。短いソロを挟みながら、どれもアレンジャーの腕比べといった感じだ。最後の曲はベルソンのオリジナル曲だが、ベルソンはドラマーであっても作曲も得意だったようだが、ここではベルソンのドラムもフィーチャーされる。
所有盤はフレッシュサウンドのCDだが、この盤にはこのライブの余韻が残っている直後に行われたスタジオ録音の曲が8曲追加されている。それもお蔵入りしていた未発表録音。フレッシュサウンドのアルバムはこのようなファンの心理をくすぐる様な編集が多い。
こちらの編成は9人編成の大型コンボ。ライブの時のメンバーとの重複が多いが、トロンボーンのフランクソロリーノも参加して、ソリストが一段と充実している。編成だけでなく選曲も当時のジャズのヒット曲が並び、少し趣が違っていて面白い。
バディーリッチなど新しいビッグバンドが登場してくるのは60年代の後半。ビッグバンドの火を消さないように頑張っていた時代の演奏だ。
連休中は東京TUCと新宿SOMEDAYで連日ビッグバンドのライブが続く。晴天が続くようだがゴルフは休みにしてライブ通いをしてみようと思う。
1. Who's Who
2. Cool
3. Amoroso
4. Prelude
5. Gumshoe
6. Blitzen
7. St. Louie
8. Moon Is Low
9. Doozy
10. Lou's Blues
11. With Bells On
12. The Diplomat Speak
13. Chop Chop Waltz
14. The Dipsy Doodle
15. Blowing The Blues
16. Opus De Funk
17. Cotton Tail
18. Walkin'
19. Moanin'
20. Don'cha Go ‘Way Mad - incomplete
#1〜12
John Andino ,Conte Candoli, Frank Huggins, Jimmie Zito, , Ray Triseari(1stnight), Uan Rasey(2nd night), Al Parcino(3rd night) (tp)
Mike Barone, Nick Di Mario (tb)
Ernie Tack (btb)
Bill Perkins, Carrington Visor (ts)
Joe Maini, Willie Green (as)
Teddy Lee (bs)
Art Maebe (fhr)
Red Callender (tuba)
Lou Levy (p)
Gene Estes (vibe,boo bams)
Tony Rizzi (g)
Jimmy Bond (b)
Louis Bellson (ds)
Arranged by
Benny Carter (#1,3,5,6,8,9 &10)
Mart Paich (#2,7)
George Williams (#4)
Shorty Rogers (#11)
Bob Frlorence (#12)
Produced by Teddy Reig
Recorded Live at The Summit, 6507 Sunset Blvd. Hollywood, Ca. January 22, 23 & 24 , 1962
#13〜20
Donte Candori (tp)
Jimmy Rito (tb)
Frank Rosolino (tb)
Joe Maini (as)
Carrington Visor (ts)
Bill Perkins (bs)
Lou Levy (p)
Jimmy Bond (b)
Louie Bellson (ds)
Arranged by Marty Paich
Recorded at United Recorders Studio, Hollywood, January 25 & 26, 1962
最近あまり行われないがマイクプライスのビッグバンドのライブを聴きに行くとエリントンの曲に加え西海岸のアレンジャーの作品を取り上げることが多い。彼が若い頃過ごしたバディーリッチやスタンケントンオーケストラは西海岸のアレンジャーの作品が多かった。日本に来る前には、西海岸で活動していたので地元の知り合いも多いようだ。
西海岸のアレンジャーというと、ビルホルマン、サムニスティコなどが有名だが、最近ではゴードングッドウィンなどもオーケストラを含めて人気があるようだ。
西海岸のアレンジャーが活躍し始めたのは、映画音楽の興隆と合わせて、ウェストコーストジャズの全盛期50年代に遡るが、ビルホルマンなどの長老達はそこの当時から活躍を続ける第一人者。当時は、他にもマティーペイチ、ショーティーロジャースなどスタンケントンやウディハーマンオーケストラ出身者がプレーだけでなくアレンジャーとしても大活躍していた。
ビッグバンドドラマーというとバディーリッチがすぐに思い浮かぶが、もう一方の雄はルイベルソンだと思う。歯切れの良いドラミングはビッグバンドだけでなく、コンボでの演奏でもメリハリの効いた絶妙なタイム感を持っている。好きなドラマーの一人だ。
このベルソンというと、エリントンオーケストラでのスキンディープが有名だ、他にもベイシーを始めとした有名オーケストラにも在籍したことがあるがいずれも看板にはなっても長続きはしなかったようだ。
やはり、根っからのビッグバンド好きで、自分のイメージもあったのだろう、自らのビッグバンドもよく編成していた。レコーディングだけでなく地元のクラブでのライブ演奏も積極的に行っていた。その時の様子は自分でレコーディングを手配することもあり、後になって世に出たものも多い。コンコルドレーベルにもベルソンのビッグバンドのアルバムは何枚かあるが、その中にもプライベートで作ったアルバムが再び陽の目を見たものがある。
ケニークラーク&フランシーボランがヨーロッパで新たなビッグバンドを立ち上げたのが61年、この時、本家アメリカのビッグバンド事情は冬の時代を迎え、レギュラーオーケストラを維持していくのは名門といえども難しくなっていた。まして、新しいビッグバンドの登場も殆どなかった頃だ。
そんな状況の1962年、ルイベルソンはビッグバンド編成で、地元ロスのクラブ「ザ・サミット」に出演した。編成は、標準的なビッグバンド編成に加えてフレンチホルンとチューバが加わっているのが特徴だが、アレンジでもこれらが上手く使われている。
その時の演奏がライブレコーディングされルーレットレーベルからリリースされた。このバンドにはロスで活躍していたスタジオミュージシャンが参加し、コンテカンドリやジョーマイニといった実力あるソリストも加わっている。しかし、演奏自体はどちらかというと当時の西海岸で活躍して新進気鋭のアレンジャーの作品のお披露目の場といってもいいかもしれない。レコーディングエンジニアは、ライブ録音が得意なWally Heider、いい音とバランスで収録されている。
アルト奏者としても有名なベニーカーターもこの頃はアレンジャーとしての仕事も多かった。このカーターのアレンジが7曲、他にもマティーペイチ、ショーティーロジャース、ボブフローレンスなどの編曲が並ぶ。曲もウェストサイドストーリーからのクールを除けば、スタンダード曲ではなくオリジナル曲が並ぶ。とはいっても大作ではなく、どれもスインギーなベルソンのバンドにはお似合いの曲。短いソロを挟みながら、どれもアレンジャーの腕比べといった感じだ。最後の曲はベルソンのオリジナル曲だが、ベルソンはドラマーであっても作曲も得意だったようだが、ここではベルソンのドラムもフィーチャーされる。
所有盤はフレッシュサウンドのCDだが、この盤にはこのライブの余韻が残っている直後に行われたスタジオ録音の曲が8曲追加されている。それもお蔵入りしていた未発表録音。フレッシュサウンドのアルバムはこのようなファンの心理をくすぐる様な編集が多い。
こちらの編成は9人編成の大型コンボ。ライブの時のメンバーとの重複が多いが、トロンボーンのフランクソロリーノも参加して、ソリストが一段と充実している。編成だけでなく選曲も当時のジャズのヒット曲が並び、少し趣が違っていて面白い。
バディーリッチなど新しいビッグバンドが登場してくるのは60年代の後半。ビッグバンドの火を消さないように頑張っていた時代の演奏だ。
連休中は東京TUCと新宿SOMEDAYで連日ビッグバンドのライブが続く。晴天が続くようだがゴルフは休みにしてライブ通いをしてみようと思う。
1. Who's Who
2. Cool
3. Amoroso
4. Prelude
5. Gumshoe
6. Blitzen
7. St. Louie
8. Moon Is Low
9. Doozy
10. Lou's Blues
11. With Bells On
12. The Diplomat Speak
13. Chop Chop Waltz
14. The Dipsy Doodle
15. Blowing The Blues
16. Opus De Funk
17. Cotton Tail
18. Walkin'
19. Moanin'
20. Don'cha Go ‘Way Mad - incomplete
#1〜12
John Andino ,Conte Candoli, Frank Huggins, Jimmie Zito, , Ray Triseari(1stnight), Uan Rasey(2nd night), Al Parcino(3rd night) (tp)
Mike Barone, Nick Di Mario (tb)
Ernie Tack (btb)
Bill Perkins, Carrington Visor (ts)
Joe Maini, Willie Green (as)
Teddy Lee (bs)
Art Maebe (fhr)
Red Callender (tuba)
Lou Levy (p)
Gene Estes (vibe,boo bams)
Tony Rizzi (g)
Jimmy Bond (b)
Louis Bellson (ds)
Arranged by
Benny Carter (#1,3,5,6,8,9 &10)
Mart Paich (#2,7)
George Williams (#4)
Shorty Rogers (#11)
Bob Frlorence (#12)
Produced by Teddy Reig
Recorded Live at The Summit, 6507 Sunset Blvd. Hollywood, Ca. January 22, 23 & 24 , 1962
#13〜20
Donte Candori (tp)
Jimmy Rito (tb)
Frank Rosolino (tb)
Joe Maini (as)
Carrington Visor (ts)
Bill Perkins (bs)
Lou Levy (p)
Jimmy Bond (b)
Louie Bellson (ds)
Arranged by Marty Paich
Recorded at United Recorders Studio, Hollywood, January 25 & 26, 1962