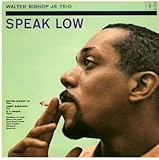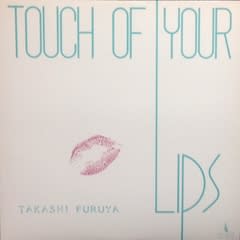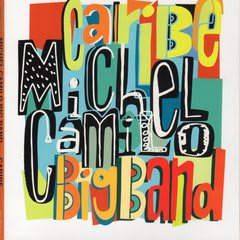The Roar of ’74 / Buddy Rich Big Band
先日久しぶりに稲垣貴庸ビッグバンドのライブに行った。最近は他のバンドでの演奏を聴く機会が多いので、稲垣BBも良く聴いていると思ったが一年ぶりくらいだった。
稲垣貴庸BBというとやはりバディーリッチ。
ビッグバンドファンには、バディーリッチ好きも多いが、リッチの曲を聴くにはこの稲垣BBが一番いい。この日も常連さんを含めて多くのお客が集まっていた。メンバーもお客さんもそれを目当てに集まるので、自分のオーケストラでバディーリッチを演奏する時の稲垣さんのドラムは一層軽快になる。

アップテンポの曲が多いのでドラムは大変だと思ったが、ホーンセクションも目いっぱい吹き続けることが多く、曲間に一息入れないとしんどいらしい。確かにミディアムテンポが多いベイシーとは大違いで、リッチの曲をこなすにはテクニックに併せて体力勝負のような気がする。
お馴染みのリッチの曲が続いたが、久々にウェスサイドストーリーメドレーの大作も聴けた。
そして、締めはナットビル。リズミックなメロディーも馴染み易いが、この曲はアップテンポで一段とドライブがかかる。ビッグバンドでのショーケースとしてもうってつけの曲なのだろう。
この曲は、何故か他のバンドでも取り上げることが多いホレスシルバーの名曲だ。
さて、この曲が入っているリッチのアルバムはというとこのアルバム。
レーシングスーツに身を包んだ写真が印象的で、一度見れば忘れないジャケットデザインだ。デザインどおりスピード感溢れる曲が並ぶ。
久しぶりにじっくりアルバムを眺めてみたが、ライナーノーツには曲とメンバーだけで何も書かれていない。
このスピード感を増すためか、リズム隊が補強されパーカッションが加わっている。サムウッドヤードとあるが、あのエリントンオーケストラのドラムのサムウッドヤードか?
そして、ギターにジェフベック。
これだけで結構雰囲気が変る、エイトビートでなくとも躍動感が増す。同じ4ビートでも、リッチのドラミングはドライブ感が違う。それにこのリズム隊が加わるとターボ付きのパワーとなる。それがオーケストラ全体をドライブするので、並のビッグバンドとは異次元のサウンドとなる。
リッチのアルバムで、このアルバムを推す人も多いが、このドライブ感がたまらないのだろう。自分はジャズロック風の演奏が多くなってきてからのアルバムよりも初期のアルバムを聴く事が多いが、このアルバムのナットビルとタイムチェックはどちらも好きな曲だ。
リッチのオーケストラもデビューした時のパシフィックジャズからRCAにレーベルが変っていたが、このアルバムはというと、グルーブマーチャントへとまた変わっている。
グルーブマーチャントというと、サドメルの初アルバムを作ったソリッドステートレーベルを作ったプロデューサー、ソニーレスターのレーベルだ。
グルーブマーチャントというと同名の曲がサドメルのレパートリーにもあった。ジェロームリチャードソンのグルービーな曲で、好きな曲のひとつだが、そうしてもこの曲のイメージを持ってしまうが。時代が変われば、同じグルービーといってもカッコよさは変化する物。
ソニーレスターが一段とパワーを増したバディーリッチのオーケストラから、また新たな「カッコよさ」を引き出したアルバムといえよう。
次回の稲垣ビッグバンドのライブは、5月6日@新宿Someday
バディリッチファンの方は是非一度お試しください。
1. Nutville (Horace Silver) 4:47
2. Kilimanjaro Cookout (Manny Albam) 6:14
3. Big Mac (Ernie Wilkins) 5:54
4. Backwoods Sideman (John La Barbera) 4:29
4. Time Check (Don Menza) 3:45
5. Prelude to a Kiss (Duke Ellington, Mack Gordon, Irving Mills) 3:32
6. Waltz of the Mushroom Hunters (Greg Hopkins) 7:16
7. Senator Sam (Wilkins) 4:40
Buddy Rich (ds)
Charley Davis (tp)
Larry Hall (tp)
Greg Hopkins (tp)
Pat La Barbera (ts,ss)
Bob Crea (ts)
John Laws (bs)
Alan Kaplan (tb)
Keith O'Quinn (tb)
John Leys (btb)
Buddy Budson (p)
Joe Beck (g)
Tony Levin (b)
Jimmy Maeulen (cong)
Sam Woodyard (per)
Produced by Sonny Lester
Recorded on October 6 & 13, 1973
先日久しぶりに稲垣貴庸ビッグバンドのライブに行った。最近は他のバンドでの演奏を聴く機会が多いので、稲垣BBも良く聴いていると思ったが一年ぶりくらいだった。
稲垣貴庸BBというとやはりバディーリッチ。
ビッグバンドファンには、バディーリッチ好きも多いが、リッチの曲を聴くにはこの稲垣BBが一番いい。この日も常連さんを含めて多くのお客が集まっていた。メンバーもお客さんもそれを目当てに集まるので、自分のオーケストラでバディーリッチを演奏する時の稲垣さんのドラムは一層軽快になる。

アップテンポの曲が多いのでドラムは大変だと思ったが、ホーンセクションも目いっぱい吹き続けることが多く、曲間に一息入れないとしんどいらしい。確かにミディアムテンポが多いベイシーとは大違いで、リッチの曲をこなすにはテクニックに併せて体力勝負のような気がする。
お馴染みのリッチの曲が続いたが、久々にウェスサイドストーリーメドレーの大作も聴けた。
そして、締めはナットビル。リズミックなメロディーも馴染み易いが、この曲はアップテンポで一段とドライブがかかる。ビッグバンドでのショーケースとしてもうってつけの曲なのだろう。
この曲は、何故か他のバンドでも取り上げることが多いホレスシルバーの名曲だ。
さて、この曲が入っているリッチのアルバムはというとこのアルバム。
レーシングスーツに身を包んだ写真が印象的で、一度見れば忘れないジャケットデザインだ。デザインどおりスピード感溢れる曲が並ぶ。
久しぶりにじっくりアルバムを眺めてみたが、ライナーノーツには曲とメンバーだけで何も書かれていない。
このスピード感を増すためか、リズム隊が補強されパーカッションが加わっている。サムウッドヤードとあるが、あのエリントンオーケストラのドラムのサムウッドヤードか?
そして、ギターにジェフベック。
これだけで結構雰囲気が変る、エイトビートでなくとも躍動感が増す。同じ4ビートでも、リッチのドラミングはドライブ感が違う。それにこのリズム隊が加わるとターボ付きのパワーとなる。それがオーケストラ全体をドライブするので、並のビッグバンドとは異次元のサウンドとなる。
リッチのアルバムで、このアルバムを推す人も多いが、このドライブ感がたまらないのだろう。自分はジャズロック風の演奏が多くなってきてからのアルバムよりも初期のアルバムを聴く事が多いが、このアルバムのナットビルとタイムチェックはどちらも好きな曲だ。
リッチのオーケストラもデビューした時のパシフィックジャズからRCAにレーベルが変っていたが、このアルバムはというと、グルーブマーチャントへとまた変わっている。
グルーブマーチャントというと、サドメルの初アルバムを作ったソリッドステートレーベルを作ったプロデューサー、ソニーレスターのレーベルだ。
グルーブマーチャントというと同名の曲がサドメルのレパートリーにもあった。ジェロームリチャードソンのグルービーな曲で、好きな曲のひとつだが、そうしてもこの曲のイメージを持ってしまうが。時代が変われば、同じグルービーといってもカッコよさは変化する物。
ソニーレスターが一段とパワーを増したバディーリッチのオーケストラから、また新たな「カッコよさ」を引き出したアルバムといえよう。
次回の稲垣ビッグバンドのライブは、5月6日@新宿Someday
バディリッチファンの方は是非一度お試しください。
1. Nutville (Horace Silver) 4:47
2. Kilimanjaro Cookout (Manny Albam) 6:14
3. Big Mac (Ernie Wilkins) 5:54
4. Backwoods Sideman (John La Barbera) 4:29
4. Time Check (Don Menza) 3:45
5. Prelude to a Kiss (Duke Ellington, Mack Gordon, Irving Mills) 3:32
6. Waltz of the Mushroom Hunters (Greg Hopkins) 7:16
7. Senator Sam (Wilkins) 4:40
Buddy Rich (ds)
Charley Davis (tp)
Larry Hall (tp)
Greg Hopkins (tp)
Pat La Barbera (ts,ss)
Bob Crea (ts)
John Laws (bs)
Alan Kaplan (tb)
Keith O'Quinn (tb)
John Leys (btb)
Buddy Budson (p)
Joe Beck (g)
Tony Levin (b)
Jimmy Maeulen (cong)
Sam Woodyard (per)
Produced by Sonny Lester
Recorded on October 6 & 13, 1973
 | Roar of 74 |
| クリエーター情報なし | |
| Lrc Ltd |