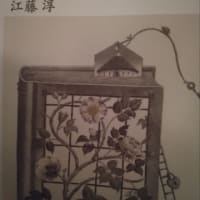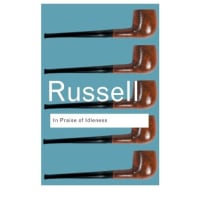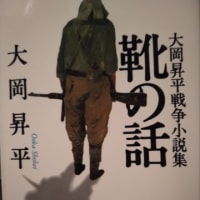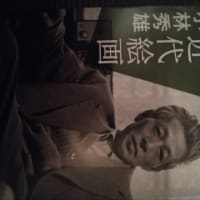サンクト・ペテルブルクにコレラが蔓延していた1893年、10月のある朝、
ピョートル・チャイコフスキー(1840~1893年)は、不機嫌な表情で朝食の席に着いていた。
かねてから、彼の様子をみていた作家であり、医者であり、友人であるアントン・チェーホフは
「ピョートル、君はただ単にペシミズムの発作を(また)起こしているだけさ。
君が第5交響曲で語ったように、僕たちは、生きなければならないのだよ。
それがどんなに悲惨でもね。」
などと言ってチャイコフスキーを慰めていたようである。
チャイコフスキーは、かつて、冬のヴォルガ川に身体を浸し、肺炎にかかるか、「賭け」をしたことがあった。
ロシア正教の教えと同性愛者であったチャイコフスキーの考えは齟齬をきたしており、チャイコフスキーの裡でも、つらい問題となっていたようである。
だからこそ、チャイコフスキーは、もしも神がロシア正教の教え通り、ソドムを滅ぼした同性愛を憎む神であるならば、必ず自分を肺炎にかからしめ、地獄の業火で身を滅ぼすはずである、と考えたのであった。
しかし、彼は「賭け」に勝ったことがあり、その勝利を第4交響曲、そして第5交響曲で謳い上げたのである。
しかし、やはりチャイコフスキーは、同性愛者についてまわる当時の社会の醜聞におびえることに苦しんでいた。
そこで、チャイコフスキーは、それらの記憶をすべて、第6交響曲に投影しようと考え、自分の人生のすべてを楽譜に表現したのである。
それが、よく(日本では)『悲愴』と呼ばれるチャイコフスキーの交響曲第6番ロ長調である。
いわゆるチャイコフスキーの『悲愴』は、
1楽章が幼年時代における音楽への漠然とした欲求を、
第2楽章が青春時代における上流社会の楽しいような生活を、
第3楽章はさまざまな意味での生活との闘いとさまざまな意味での名声の獲得を、
そして、最終楽章には、
「深淵より」そのような自分の人生から見つめたことを表現したのである。
自分の人生のすべてを作曲したかもしれないと考えたチャイコフスキーは、ある意味では、自分のすべてとも言うこともできるこの交響曲に、『悲愴』という標題を与えるまで、悩みに悩んだようである。
彼が言っていた「人生について」が、いつ『悲愴』に変わったのかは定かではないが、
彼が何気なく目をとめたシェークスピアのソネットの
「私は自分の書いたもので恥をさらした。
つまらぬものを愛すると、君もそうなるだろう」
と一節を見て、彼のいつもの不機嫌な感情がはじまり、『悲愴』になった、とする説もあるようである。
さて、標題が『悲愴』に決まり、訳もなく楽しい気分になったチャイコフスキーは、「また」あの「賭け」をしてみたくなったようであり、周囲に
「私は、欲望以外のすべてを神に委ねてきた。
今一度、神に問おう。
私は、生きるべきか、死ぬべきか」
と言っていたようである。
しかし、1893年11月6日、その「賭け」をする前に、ピョートル・チャイコフスキーは当時、サンクト・ペテルブルクで蔓延していたコレラにかかり、亡くなったのである。
ところで、
1945年にやっと、日本で女性が投票権を得た、ある意味、女性の公民権を日本にもたらしたアメリカでも、女性が公民権を得たのは、1920年であるのは驚きである。
1940年代のアメリカにおいて、多くの州とアメリカ陸軍では、厳しい人種差別が行われ、一部の州や自治体では、異人種間の結婚・同棲や同性愛は犯罪とされ、すべての州・自治体では恥ずべき行為と見なされていたのである。
現在の法律では、女性と男性は平等、黒人と白人も平等であり、性的指向および性自認は、市民としての権利にまったく影響しない、とされている。
しかし、ごく最近まで、権利を主張する戦いは続いていたのである。
いつでも、また世界のどこでも、すべての人間は法の下で平等、ではなく、
また、法の下での平等が保証されるまでの歩みは遅く不安定かつ不完全であり、さらに不平等なことも多く、ほぼいつも混乱を生んでいた。
日本でも先日、同性婚をめぐる現行法の規定についての動きがあったように、公民権をはじめさまざまな権利の、法的認定を求める戦いは続くのであろうが、世界において、19世紀には大敗北であった権利に関する戦いは、20世紀から21世紀にかけては成果を上げていると言っても良いようにも思う。
勿論、法的地位を獲得した成果が現れるのは、現実の世界よりも法律上の記載であることが、あまりに多いのであるが、それでも前進を否定すべきではない、と、私は思う。
現に、世界で見れば、100年前では、それも比較的最近まで考えられなかった法的地位を、女性、人種的少数派、LGBTの人々が、獲得したのである。
私の想像だが、チャイコフスキーならば、
「やるべきことはまだ多く残されてはいるが、すでに多くのことが成し遂げられているのも事実だ」
と今の世界を褒めてくれるかもしれない、とも、思う。
チャイコフスキーが気に病んだ世間の目、それはひとつの怪物ではなく、ひとりひとりの目の集合体であり、世論と言い換えられるのかもしれない。
世論というものは、固まって見えることが多いが、実は気まぐれで、世論こそ、いろいろと影響を受けやすいものかもしれないと、私は、思う。
正義と寛容さを保証することに関して、政治家や判事は世論を先導するよりも、世論に従うことがずっと多いようである。
かねてより、公民権を推進する個々の戦術は、時代や争点、政治状況、経済状況、人口動態、推進する人々のパーソナリティに応じて変わってきた。
しかし、そのもとになる戦略は常によく似ている。
メディア、一般大衆、法律家の注意を
差別の不当さ、差別されている側の基本的な人間性、差別をする側の基本的な非人間性に向けさせるのである。
認識や政策の変化を促す上で、言葉と行動はそうじょうこうかをもたらす。
それは、同じくらい重要で、切っても切れない関係にある。
公民権法の成立に向けて転機となったのは、レイシズムを終わらせようという、マーティン・ルーサー・キングの人々の心を奮い立たせる訴えだった。
リンカーン記念堂の階段で行われた彼の演説で
「私には夢がある。
それは、いつかこの国が起ちあがり、『すべての人間が平等に造られているということは、自明の真実であると考える』というこの国の信条を、本当の意味で実現することである」
と述べ、2万5000人の聴衆に加え、数千万人のテレビ視聴者の心を震わせた演説に、私も、また、触れるたびに感動を禁じ得ない人間のうちのひとりである、と思うのである。
ここまで、読んで下さり、ありがとうございます。
最近、日中は暖かくなってきましたね( ^_^)
春の足音がきこえてくるようですね(*^^*)
今日も、頑張りすぎず、頑張りたいですね。
では、また、次回。