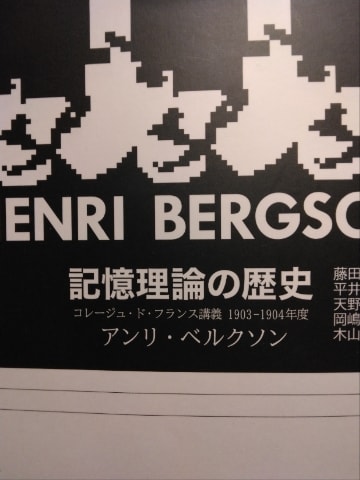なんと鋭い唯物論理解なのだろうか。
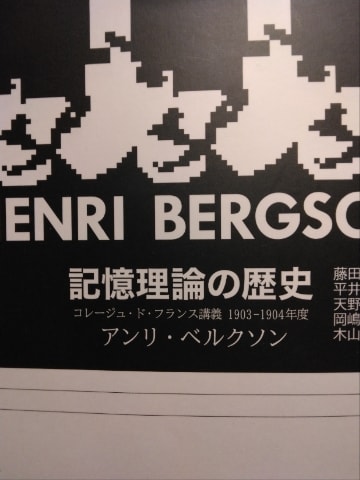
マルクスの唯物史観における「物」が、いわゆる物質としての「物」ではないという小林秀雄のマルクス理解は、昭和4年という時代的背景を、忘れさせる。
小林秀雄は、『様々なる意匠』のなかで
「脳細胞から意識引き出す唯物論も、精神から存在を引き出す観念論も等しく否定したマルクスの唯物史観に於ける『物』とは、飄々たる精神ではないことは勿論だが、又固定した物質でもない」
と述べているのである。
それから、かなりの時間が経過しても、マルクスの唯物史観における「物」とは物質としての物であると思い込んでいる人も少なくないようである。
たとえば、「唯物論」に対して「唯幻論」を唱えた心理学者の岸田秀は、唯物論の「物」を近代物理学的な意味での物質と理解した上で、そのような意味の唯物論に反対する立場として「唯幻論」を主張したのだ、と柄谷行人との対談『フェティシズムについて』のなかで述べているが、もし、マルクス的唯物論が、小林秀雄的に理解されたような意味での唯物論であったならば、岸田秀の唯幻論は、「唯幻論」ということばを用いずとも、唯物論ということばで十分だったはずではないだろうか。
しかし、岸田秀は、「唯物論」の物は、いわゆる近代物理学的な意味での「物」であることを疑わなかったようである。
このような誤解は、岸田秀だけのものではなく、多くの人がそのように考えていたようである。
小林秀雄は、「物」的な物理学から、「場」的な物理学への転換を知っていたため、その誤解を免れることが出来たようであり、小林秀雄独自のマルクス解釈はここから始まっているといってよいのかもしれない。
小林秀雄、吉本隆明、柄谷行人といった文芸評論家たちによって理解されたマルクスは、いわゆるマルクス主義者やマルクス研究者たちによって理解されたようなマルクスとは違い、小林秀雄という文芸評論家の手によるマルクス理解から始まるのではないだろうか。
吉本隆明も、柄谷行人も、小林秀雄に理解されたマルクスを前提にして、そのマルクス論を展開しているようである。
柄谷行人は、このことについて『マルクスその可能性の中心』のあとがきのなかで、
「明らかに、小林秀雄は、マルクスのいう商品が、物でもなく観念でもなく、いわば言葉であること、しかもそれらの『魔力』をとってしまえば、物や観念すなわち「影」しかみあたらないことを語っている。
この省察は、今日においても光っている」
と述べている。
大正末期から昭和初期にかけて襲ってきた「マルクス主義」という台風は、文芸評論家小林秀雄を「思想家」たらしめたような、言語化などできないような次元での影響を及ぼしたようである。
皮肉にも、小林秀雄は、マルクス主義と対決する過程で、最も深くマルクス主義の思想的核心部に触れることができたのだろう。
そして、それは、マルクスを理論家として読むのではなくて、思想家としてのマルクスを読むことであったのではないだろうか。
小林秀雄は、マルクス主義と全面的に対決せざるを得ない奇妙なめぐり合わせによって、最も深い部分で、マルクスの影響を受けたのかもしれない。
彼自身、単なる哲学者でも、政治学者でも、そして経済学者でもなくて、ひとりの思想家であったマルクスが、ひとりの文芸評論家を思想家に鍛え上げたのではないだろうか。
吉本隆明や柄谷行人がどれほど激しく小林秀雄を批判しても、彼らの思考そのものが、小林秀雄とマルクスの接触によって作り出された小林秀雄的パラダイムのなかで、なされていることは、否定できないだろう。
吉本隆明や柄谷行人の思考もまた、マルクスの影、そして、小林秀雄の影に覆われているようである。
吉本隆明は、小林秀雄のマルクス解釈について『小林秀雄-その方法』のなかで、
「初期の小林秀雄は、本多秋五も指摘しているように、マルクスもエンゲルスもレーニンもよく読んでいて、きわめて適切に引用していることがわかる。
たとえば『マルクスの悟達』や『文芸批評の科学性に関する論争』などの批評文は、現在よんでみても、ただ、いやおうなく小林秀雄的な色彩でエンゲルスやレーニンの言葉がよまれているということを除いては、けっしておかしなものではない」
と述べている。
吉本隆明は、躊躇いを持ちながらも、小林秀雄のマルクス解釈の正当性を認めているのではないだろうか。
吉本は、小林のマルクス解釈が、
「いやおうなく小林秀雄的な色彩で」染められている、と言っており、
ここに、吉本隆明の小林秀雄批判の根拠があるのだが、
小林秀雄のマルクス解釈の正当性の根拠は、むしろそこにあり、それを除いたらば、小林秀雄のマルクス解釈は、はじめからあり得なかったはずであろう。
小林秀雄の小林秀雄たる所以は、「小林秀雄的な色彩」のなかにあるのであり、私たちが、問題にしなければならないのは、
小林秀雄的な色彩とは何か、という問題なのではないだろうか。
なぜ小林秀雄の認識が、今も有効で在り続けているのか、ということこそ問題であり、私たちが、問うのも、その問題であろう。
吉本隆明の小林秀雄批判には、なぜ、小林のマルクス解釈が正確であったのかという問題の追求が欠けているようである。
小林秀雄は、マルクス主義者でも、マルクスの研究者でも、マルクスを特別に思想家として敬愛していたわけでもないにもかかわらず、小林のマルクス解釈は正確であり、吉本隆明や柄谷行人にまで影響を与えるような、独自のマルクス読解を達成できたが、それは、小林秀雄が「批評家」であったからではないだろうか。
小林秀雄は、マルクスが直面したであろう思想的な危機を共有出来るような、そのような思想的極限を生きた批評家であり、小林秀雄は、マルクスのテキストのなかに、自分自身の問題を発見し、それを解釈したに過ぎないのかもしれない。
小林秀雄にとって、マルクスもまた、すぐれた批評家のひとりであり、マルクスを読むことは容易であったのかもしれない。
そして、小林秀雄にとっては、マルクスを読むことは、ただ、批評家という、自分の感受性に忠実であるだけで、可能だったことなのかもしれない。
文芸評論家が「文芸」だけしか語らないとすれば、文芸評論家という存在は、その存在意義を失ってしまうように、私には、思われる。
たとえば、小林秀雄と中村光夫を比較するとき、同じように文芸評論家と言われるふたりであるにもかかわらず、これほどまでに、「批評」の向かう方向が異なるのか、と驚いてしまう。
小林秀雄の批評の進行方向には、「哲学」や「思想」とでも呼ぶべきものがあり、小林秀雄の評論はいつも原理的な問題へ向かう。
言ってしまえば、小林秀雄の思考は、物事の本質をきわめようとするような垂直的な思考である。
これに対して、中村光夫の批評の進行方向にあるのは、「文学」や「文学史」のみであり、言ってしまえば、批評の原理と方々を固定化して、その批評の原理と方々を様々な分野に応用しているのみではないだろうか。
近代文学や現代文学の研究、解釈に限っていえば、小林秀雄よりも、中村光夫の方が、はるかに優れた文芸評論家であり、その影響も、中村光夫の方が圧倒的に強いものを持っているかもしれない。
しかし、中村光夫という文芸評論家には、原理論的思索が欠如しているが、それに代わり、文学史的、実証的な探求が在るのかもしれない。
昭和10年夏、中村光夫は、小林秀雄、大岡昇平らと、霧ヶ峰を訪れ、暫くそこに滞在しているのだが、そのとき、中村は、小林が「物理学」に対して示した関心を、まったくと言ってよいほど共有していなかったようである。
また、中村光夫は、ベルクソンやデカルトや、ニーチェなどについても、ほとんど関心を向けていないようである。
このことは、小林秀雄の近くにいた中村光夫が、ほとんど小林秀雄の影響を受けておらず、小林秀雄とはまったく違ったタイプの批評家であったことを示しているだろう。
小林秀雄の批評は、原理論的であり、ある意味では、抽象的ですらあるのに対して、中村光夫の批評は、極めて具体的であり、また実践的であった。
しかし、中村光夫的批評の具体性や実践性は、なにか根本的な問題を無視することによって成立した具体性や実践性であるようにも、私には、思われ、そのことが、中村光夫に、原理論的な思索が欠如しているように感じさせるのかもしれない。
やはり、私は、中村光夫的な批評よりも、小林秀雄的な批評に興味を持つのであるが、やはり、小林秀雄的批評の系譜には、吉本隆明と柄谷行人が、いる。
ふたりとも小林秀雄の影響を受けたことを告白しており、ふたりとも、小林秀雄からの圧倒的な影響の下に、その批評活動をはじめており、ふたりとも、極めて激しく、小林秀雄を批判し、否定しようとしている。
しかし、ふたりが、小林秀雄を批判し、否定すればするほど、吉本隆明も柄谷行人も、さらに小林秀雄的になってゆくように、見える。
たとえば、柄谷行人が、マルクスを論じ、数学や物理学、あるいは論理学の問題を追及してゆけばゆくほど、その批評の方向が、さらに小林秀雄の方に傾いているように思う。
また、吉本隆明も、その言語論をはじめ、国家論や身心論が小林秀雄とまったく違う場所でなされていると思えないのである。
それらは、いずれも、小林秀雄的パラダイムの中に在るといってよいのではないだろうか。
無論、ふたりは、小林秀雄が踏みこもうとしなかった領域に踏みこもうとし、そうすることによって、小林秀雄を超えようとしているのだが、ふたりの試みが小林秀雄的批評に対して、根本的な変換をもたらしてはいないように、思われる。
むしろ、私には、このことが、小林秀雄的批評を乗り越えることの困難さを示しているように、見えるのである。
ここまで、読んで下さり、ありがとうございます。
今日からまた、定期更新を再開いたしますので、また、よろしくお願いいたします😊
今日も、頑張りすぎず、頑張りたいですね。
では、また、次回。
*見出し画像は
ベルクソンの「記憶理論の歴史」-コレージュ・ド・フランス講義 1903-1904年度-からです