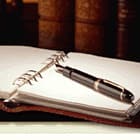
私の高校時代の恩師で、作家デヴューなさった方がいます。
退職後に自費出版した自伝的小説が65歳以上限定の文芸賞を受賞したとかで。私もその人が来るべき印税生活のために退職金をつぎ込んで購入したリゾートホテルに呼び出され、あやうく、その本を購入させられそうになりました(笑)。恩師は生活のために仕方なく国語教師になんぞなったけれど、作家が長年の夢。この処女作で狙っているのは、シニア向け文芸賞ではなく、芥川賞だと宣言していました。それからすでに五年ぐらい経っていますが、恩師がその後、次回作の小説を発表したとも、それが受賞したとも聞いていません。でも、ど素人の私がそのとき疑問に思ったのは、芥川賞って、新人の若い作家さんが対象じゃなかったっけ? でした。
文学の世界で毎年話題になるのは、芥川賞および直木賞。
候補者が発表され、正式な決定が下るまでは、候補者本人も、その周囲も、そのファンすらもやきもきしてしまうことでしょう。今年は、かなり高齢の女性で海外在住という異色の経歴者が受賞したとかで話題になった芥川賞。いっぽう、直木賞は、実力派の中堅作家がめでたく受賞。とくに異論がなかった展開だったように思います。
ここから、作家さんの御芳名を出します。
悪口のつもりはないですが、エゴサーチされている作家さん本人、もしくは、そのファンの方は気分を害するかもしれませんので、スルー推奨です。はい、忠告しました。
読者の皆さんにお聞きしたいです。
この芥川賞および直木賞、選書の参考にしますか?
今年の直木賞は、門井慶喜さんの『銀河鉄道の父』。なんとあの宮沢賢治の父親の視点から、童話作家を目指して家業を継がなかった長男への想いをつづった小説。私、この本、昨年末に興味があって図書館で見かけたんですが、借りずじまい。ところが直木賞受賞が決定するや否や、予約殺到なので半年先になりますとのこと。しかし、ゆきつけの大型チェーン書店では、大河ドラマ関連の西郷隆盛本はプッシュして独立に陳列展示されていますが、今回の芥川賞・直木賞ふくめて特別扱いはされていませんでした。
こんなことを書くとこの作家さんを貶めているようですから、補記しておきます。
この門井さんの前作『家康、江戸を建てる』は題材が面白かったし、この人は美術ミステリーも手掛けられているので、何作か読んだことがあります。直木賞を受賞するにふさわしい作家さんだと思っています。ただし、私はこの方の本は二度読みしたいとはあまり思わないので、やはり図書館で済ませてしまいます。今回の宮沢賢治の父の話もそうです。作家になりたくて長男の責務を放棄して、家業の質屋を継がなかった男。商売は汚い、文学は尊いと言い張って現実逃避しつづけ、聖人君子のように生きて夭折した男。彼は月給取りとして働きながら、原稿を書き続け、死後に日本の文学史に名を遺す文士となりました。私もその詩文に涙した一人です。でも、(読んでもいないのに批判するのはナンセンスですが)道楽のために家族を泣かした男の話を、私はお金を払ってまで読みたくはありません。この宮沢賢治の姿は、作家さん本人の生き方と重なる部分があるようで、真実味があり、文壇の評価も高かったのでしょう。でも、作家さんが本人の自伝的側面を投入したこの傑作、もし、若かりし頃に書かれていればそこで評価されたでしょうが、その後の作家生活はなかったのではないでしょうか。ご本人も、作家としてキャリアを積むまでは形にしたくなったテーマだったと語っています。感慨深いですね。
この直木賞受賞作と対極的な一作があります。
下町の工場を継いだ二代目と社員たちの奮闘を爽やかに描き切った、池井戸潤さんの『下町ロケット』ですね。池井戸さんの文章は失礼ですが、文学的表現力としては高くなく、高校生の作文程度です。でも、かえって読みやすいし、サラリーマンや経営者の苦悩に共感できます。書店などでも売れ行きがいいのか、池井戸さんの文庫本はかならず目立つ場所に展示されていますよね。
現在、売れている本が百年のちも名作として読み継がれるとは限りません。
私が子供の頃、赤川次郎さんの三毛猫探偵シリーズなどがバカ売れしましたけれど、いまは書店で見かけなくなりましたし。本にもブームというものがあります。
芥川賞・直木賞は、その作家さんの業績を箔付けするものに違いありません。
それまで売れ行きが芳しくなかった過去作まで注目されます。作品名よりも作家のネームバリューで販売数が変わるわけです。でも、直木賞はともかくとして、近作の芥川賞受賞作は、私には合わないものが多いです。たとえば、数年前に朝吹なんとかさんという女性の受賞作がありまして、借りて読んだのですが、文体は流麗で美しいけれど、なにを訴えているのか、わからないんです。私の想像力が貧困すぎるせいでしょうが、情景が浮かび上がってこない。文字の羅列をたどっているうちに、いつのまにか、よくわからない場面転換していたりする。でも、一流の文学者にとっては、それが「文学的・芸術的価値が高い」作品なのでしょう。
今回、その実力が折り紙付きと言われたある歴史作家さんがいたのですが、惜しくも受賞を逃しました。その人の作品は新聞連載になっていたのでよく読んでいますが、受賞するにはするなりの基準があるんでしょうね。でも、芥川賞を獲ってマスコミで話題になったけれど、いま、どうしているのか音沙汰無しとか、下手したら廃業してしまった作家さんもいるそうです。書き続けている作家さんにとっては、今度こそという思いがあったのでしょう。最近、人気作家だった恩田陸さんがやっと直木賞受賞されましたが、この人は正直、もっと前に受賞してしかるべき力量のある人だったと思います。
権威ある文壇や大御所作家がお墨付きを与えた名作が、大衆読者のこころに響くとは限らない。ただし、有名な受賞作は、賞を狙う者にとっては傾向を練りやすい参考材料になるかもしれないですね。でも、芥川賞って、なんで一般受けしなそうなものばかり選びたがるのか、不思議です(笑)。村上春樹さんみたいな無冠の、ノーベル文学賞候補もいますし。
私がいちばん参考にするのは、やはり本屋さん大賞ですね。
書店員さんが売りたい本というのは、やはり読者のニーズをよく掴んでいるんです。お気に入りの本は、陳列の仕方も違ってきますし。書店員さんは仕事柄、いろいろなジャンルの本に触れていますから、特定分野のマニアックな知識に偏りがある作家さんよりは、選書の幅が広いです。私の良く通う大型チェーン店の書店員さんは、地域の広報誌にお気に入り本紹介のエッセイを載せているので参考にしています。作家さん同士があとがきなどで身内の褒めあいのように書かれる書評よりも嘘がないですし。最近はネット上の評価レヴューですぐ価値づけされていますから、下手な本をいいと勧めるのも勇気がいりますよね。
有名な受賞作は、たしかに名作選びの参考にはなります。
しかし、自分に合わないと、なんでこんなんが受賞作なのか! 選者の目は節穴か! と怒りたくもります。 ひとの好みは千差万別、蓼食う虫も好き好き。
受賞作が書き手の、読み手のあなたの傑作とは限らない。しかし、一冊の本は誰かの人生を変えることはありえます。受賞に至らなかった作品であっても、誰かが大事に大切にしてくれる作品はかならずあります。
読書の秋だからといって、本が好きだと思うなよ(目次)
本が売れないという叫びがある。しかし、本は買いたくないという抵抗勢力もある。
読者と著者とは、いつも平行線です。悲しいですね。





























