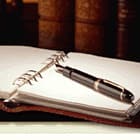
かつて私は、国立大学の学生として、芸術作品の研究論文を執筆していました。
社会学や科学系ならば実験かフィールドワークが素材集めになりましょうが、文化教養系学問の研究は、まずは資料集め。本を読んでなんぼの世界です。美術作品ならば、もちろん現物も鑑賞しますけどね。
私がM2(修士の二回生)のときのこと。
お隣の研究室所属の二学年後輩が訪ねてきて、自分は都市デザインの研究をしたいが、参考文献をどれにしたら分からないので選んでほしいというのです。自分の指導教官に聞いてみたけれど、わからなかったから、という泣きそうな顔で。
理系と違って、文系の、とくに文化表現の研究では、たいがい研究室の所属教官のテーマと同じでなくていいので、学生は好き勝手に卒業研究のテーマにします。下手したらアニメだとか、ポップミュージックだとか。そして、参考文献が本でなくて、URLだらけになります。ネットから情報引っ張れば、剽窃もしやすくなりますし。ところが、その当時の教官はガチガチの洋の東西の美術史だか、美学だかを学んできた研究者なので、そんな最新のサブカルチャーの参考資料なんぞ知るわけがないんです。これは極端な例ですが、研究者というものは、自分の専門をすこしでも離れるとど素人以下です。知らないものを知る必要はない。
卒業論文や修士論文の締め切りは年度末ですが、たいがい、その半年前ぐらいかに中間発表会があります。学生はレジュメと参考文献リストを用意して発表。教官は自分が不案内なテーマだと露骨に嫌な顔したり、とんちんかんな参考文献を提示したり、のストレスをかけてきます。私も自分の研究テーマは、その大学は蓄積のないものだったので、イチから参考文献を集め、足で稼いで作品も数をこなしてみてきましたが、こっぴどくこき下ろされました。いまから思えば、学会の異質さに慣れるように、わざと意地悪に演じたのでしょう。ところが、いざ執筆してみると高評価。むしろ、中間発表会で教官の言いなりになって資料集めしたりテーマを決めたりした学生は主体性がありませんから、出来が悪いものでした。ただし、卒論や修論が書けなくても、就職さえちゃんとできればいいわけです。教授に下手に可愛がられたら、大学から出られなくなりますし(笑)
はい、自慢話うっとおしいですね。おっしゃるとおりです。読み直している自分も、苦笑。
ブログ読者さまに石を投げられそうなので、本題に戻りましょう。
困り切った後輩にしたアドバイスは、自分のテーマに近い信頼のおける先行研究者の著書や論文はもちろん、それらの最後にある参考文献リストも参考にする、というもの。ガイド的な本は参考文献にしてはいけない。また日頃から、研究室で買っている英字の美術雑誌でめぼしい記事があればコピーしておく。私もその後輩のテーマを気にかけていて、バックナンバーを漁っているときに、ついでにコピーして渡したことがあります。図書を管理する人間というのは、じつは、レファレンスに応じる、すなわち読者が求めたい本にアクセスする手助けをする役目があります。研究として価値があるのはもちろん、先行の参考文献にはない資料を自分で探してくることです。
作家さんもそうでしょうが、文章を書く訓練をしていると、構成力が身に着きますので、本の目次やはしがき、そして巻末の参考文献リストをちら読みしただけで、読むべき本かそうでないかわかるようになります。
しっかりと書かれている本は、かならず、はしがきを読んだだけで本の主旨がわかるようになっています。欧米の研究書では、前書きで章の構成とその要約になっていますから、忙しい時は前書きだけさっと読んで、利用できそうな章だけ深く読み込んでおけばいいのです。参考文献リストもきっちり記載されていますから、探しやすくなります。
なお、日本の小説家でたまに参考文献リストに、本の出版年を書いていないことがありますが、これは致命的ではありませんか。同じ文豪の小説であっても、版によって文体が異なり、下手したら結末も微妙に違うことがあります。これは、大人気ラノベの『ビブリオ古書堂の事件手帖』シリーズでも触れられていましたが、同じ著作でもエディションが違う可能性はまともな大学で卒業論文を書けば、かならず指導されるはずの基本です。電子書籍と違って、出版技術が年代によって変わってくるからこその本だけの特質です。本を書いているプロなのに書誌学を知らないのは、文士として恥ずかしいのではないでしょうか。参考文献の出版年を書いていない作家の、とくに小説はたいがい面白くないことが多く、買う気がしませんね。出版社の編集者も気が付かないのかと言いたくなります。
いつもいつもの毒舌が長くなってきましたので、本日はこのへんで。
読書の秋だからといって、本が好きだと思うなよ(目次)
本が売れないという叫びがある。しかし、本は買いたくないという抵抗勢力もある。
読者と著者とは、いつも平行線です。悲しいですね。





























